
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
サンクスカードは感謝の気持ちを伝えるための有効なツールとして多くの企業で活用されていますが、その一方で「気持ち悪い」と感じる人も少なくありません。
その原因は形式的な運用や過剰な表現、運用の手間などにあります。
本記事では、サンクスカードに対するネガティブな印象の原因を明らかにし、より自然で効果的な運用方法を提案します。

サンクスカードへの反発は、実は運用方法に問題があることが多いんです
形式的・義務的な運用による弊害

確かに、毎週必ず5枚は出すようにと言われると、気持ちより義務感が先に立ちますよね
サンクスカードが義務化されると、従業員は感謝の気持ちを強制的に表現しなければならなくなります。これにより、感謝の言葉が形式的になり、本来の意味を失ってしまいます。
サンクスカード義務化による具体的な問題点は、次のようになります。
- 毎週一定数のカード送付を強制される
- 内容が薄くなり、形式的な感謝表現となる
- 受け手が送り手の真意を疑うようになる
- 従業員のモチベーション低下を招く
- 組織内の信頼関係が希薄化する
このような運用は、本来の感謝の気持ちを伝えるという目的から逸脱し、逆効果となる可能性があります。

感謝は自然に湧き上がる感情ですから、制度で強制すると本末転倒になってしまうんです
過剰な表現や偽善的な印象

「あなたは神です!」みたいなカードを受け取った時は、正直戸惑いました
サンクスカードにおいて、過度な賛辞や誇張された表現が使われると、受け手に違和感や不信感を与えることがあります。例えば、「あなたは神です!」や「あなたがいてくれるだけで十分です!」といった表現は、本心からの感謝には見えず、逆に偽善的に感じられることがあります。
サンクスカードの問題点と印象、そして改善のポイントは次のようになります。
| 問題のある表現例 | 与える印象 | 改善のポイント |
| 「あなたは神です!」 | 大げさで不自然 | 具体的な行動への感謝 |
| 「あなたがいてくれるだけで十分です!」 | 偽善的 | 素直で自然な表現 |
| 「完璧すぎます!」 | 現実的でない | 実際の貢献内容を明記 |
このような表現は、感謝の気持ちを伝えるどころか、逆効果となる可能性があるため、注意が必要です。

感謝の表現は、シンプルで具体的な方が相手の心に響くものです
運用の手間や負担感

紙のカードの回収や集計作業って、想像以上に時間がかかるんですよね
サンクスカードの作成や集計が手間となり、業務負担が増加することがあります。特に紙ベースでの運用では、カードの配布や回収、内容の確認など、多くの時間と労力が必要となります。
サンクスカードの運用における負担は、次のようのものがあります。
- カードの配布と回収作業
- 内容の確認と集計作業
- データの管理と保存
- 定期的な報告書作成
- システムメンテナンス
これにより、従業員は本来の業務に集中できなくなり、ストレスを感じることもあります。また、運用担当者にとっても、集計作業や管理が大きな負担となるため、効率的な運用方法の検討が求められます。

運用の負担が感謝の気持ちを上回ってしまっては本末転倒ですね
マンネリ化や形骸化

同じような内容のカードばかり見ていると、だんだん慣れてしまって感動が薄れてきます
サンクスカードの運用が継続される中で、内容がマンネリ化し、形だけのものとなってしまうことがあります。例えば、毎回同じような内容のカードが送られると、受け手はその価値を感じなくなり、カード自体の意味が薄れてしまいます。
また、送る側も義務感からカードを作成するようになり、感謝の気持ちが込められなくなります。このような状況を防ぐためには、運用方法の見直しや工夫が必要です。

制度を整えるだけでは、人は動きません。鍵は内発的動機づけです
サンクスカード運用の見直しポイント

どうすれば自然で効果的なサンクスカード運用ができるのか、具体的に教えてください
自発的な感謝の促進

まずは感謝を伝えることへの心理的ハードルを下げることから始めましょう
サンクスカードの効果を最大限に引き出すためには、従業員が自発的に感謝の気持ちを伝えることが重要です。そのためには、感謝の文化を醸成し、従業員同士が自然に感謝を伝え合う環境を整えることが求められます。
感謝文化の醸成には、次のような方法が有効です。
- 感謝表現の大切さを共有するワークショップの開催
- 日常的に感謝の言葉を交わす習慣の促進
- 管理職による感謝表現の模範的な実践
- 感謝のエピソードを共有する場の設置
- 感謝を伝えることへの心理的ハードルの軽減
例えば、感謝の気持ちを表現することの大切さを共有するワークショップを開催したり、日常的に感謝の言葉を交わす習慣を促進することで、自然な感謝のやり取りが生まれやすくなります。

上司の方が率先して感謝を表現してくれると、部下も真似しやすくなりますね
表現の自由度を高める

定型文ではなく、自分の言葉で感謝を伝えることが大切です
サンクスカードの内容に制限を設けず、従業員が自由に感謝の気持ちを表現できるようにすることが重要です。定型文やテンプレートに頼らず、自分の言葉で感謝を伝えることで、受け手にとってもその気持ちが伝わりやすくなります。
サンクスカードの「制限的な運用」と「自由度の高い運用」は、次のような例が挙げられます。
| 制限的な運用 | 自由度の高い運用 |
| 定型文の使用を強制 | 自分の言葉での表現を推奨 |
| 文字数や形式の厳格な指定 | 柔軟な表現形式を許可 |
| 感謝対象の限定 | 幅広い感謝対象を受け入れ |
| 頻度の強制 | 自然なタイミングでの感謝 |
また、感謝の対象や内容も多様であるべきであり、小さなことでも感謝を伝えることが推奨されます。これにより、サンクスカードがより意味のあるものとなり、従業員同士の信頼関係の構築にも寄与します。

小さなことでも感謝を伝えられる雰囲気があると、自然に感謝の輪が広がりそうです
運用の簡素化とデジタル化

デジタル化により、感謝を伝える負担を大幅に軽減できます
サンクスカードの運用を効率化するためには、デジタル化が有効です。専用のアプリやツールを導入することで、カードの作成や送信、集計が簡単に行えるようになります。
サンクスカードのデジタル化には、次のようなメリットがあります。
- カード作成・送信の簡素化
- 自動集計による作業効率の向上
- 送受信履歴の一元管理
- リアルタイムでの効果測定
- ペーパーレス化によるコスト削減
これにより、従業員の手間が軽減され、運用担当者の負担も減少します。また、デジタル化により、カードの内容や送受信履歴の管理が容易になり、運用の透明性や効果測定も可能となります。

スマートフォンから気軽に送れるようになれば、もっと自然に感謝を伝えられそうですね
定期的なフィードバックと改善

数字も大事ですが、面談時の表情の変化を見逃さないようにしてください
サンクスカードの運用が効果的であるためには、定期的なフィードバックと改善が欠かせません。従業員からの意見や感想を収集し、運用方法や内容の見直しを行うことで、制度の形骸化やマンネリ化を防ぐことができます。
サンクスカードの効果的に運用するための施策は、次のようなものがあります。
- 従業員アンケートの実施
- 運用データの分析と評価
- 課題の特定と改善策の検討
- 新しい運用方法の試行
- 効果測定と次回改善への反映
また、運用の成果や課題を共有し、全員で改善に取り組む姿勢を持つことで、サンクスカードの価値を高め、組織全体のエンゲージメント向上につなげることができます。

変化を起こすって、まずは気づくことからなんですね
まとめ:感謝の気持ちを自然に伝えるために

人を育てるって、育てようと思った瞬間から始まるんですよね
サンクスカードは、従業員同士の感謝の気持ちを可視化し、組織内のコミュニケーションを活性化する有効なツールです。しかし、形式的な運用や過剰な表現、運用の手間などが原因で、「気持ち悪い」と感じられることもあります。
そのため、サンクスカードの導入や運用においては、従業員の自発性を尊重し、表現の自由度を高め、運用の効率化を図ることが重要です。また、定期的なフィードバックと改善を通じて、より自然で効果的な感謝の文化を育むことが求められます。

まだ分からないことだらけですが、まずは現場の声をちゃんと拾うことから始めたいと思ってます


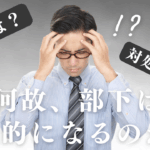
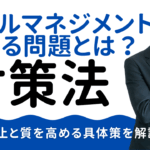
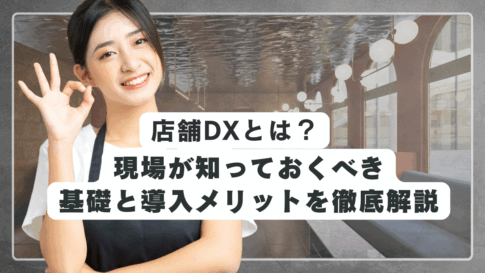
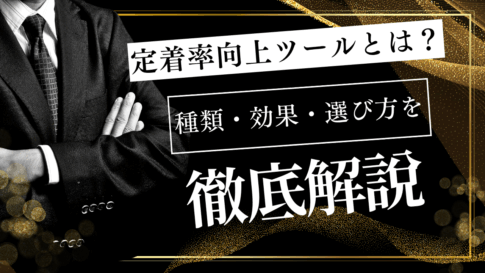
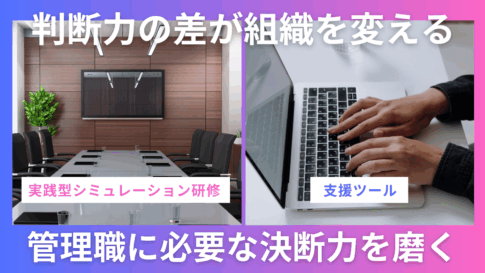
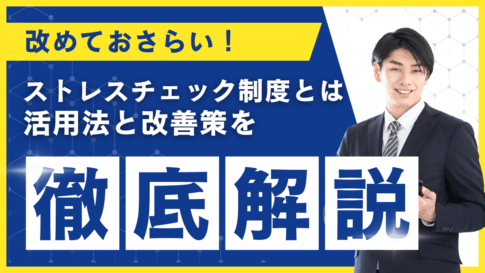
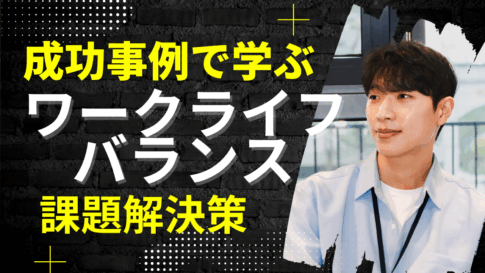

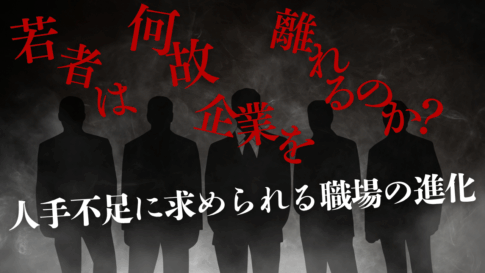
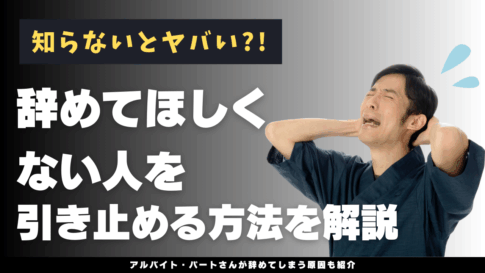



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。