
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「働きアリの法則」という言葉を聞いて、「働かない2割は不要」と思ったことはありませんか?実はその解釈、間違っているかもしれません。
本記事では、誤解されやすいこの法則の正しい意味を解説するとともに、組織運営にどう活かすべきかを解説します。マネジメントに悩む方必見の内容です。
働きアリの法則とは?その基本をおさらい

働きアリの法則について、まずは基本を整理してみましょう。この法則は単純な「優劣」を表すものではないんです。
働きアリの法則とは、アリの集団において2割がよく働き、6割が普通に働き、残り2割はほとんど働かないという観察結果に基づいた法則です。この法則は生物学的に自然な役割分担の一形態であり、全体のパフォーマンスを最適化する仕組みとされています。
働きアリの法則を表にすると、次のようになります
| 働き方の分類 | 割合 | 特徴 |
| よく働く | 2割 | 高いパフォーマンスを発揮 |
| 普通に働く | 6割 | 標準的な働きぶり |
| ほとんど働かない | 2割 | 活動量が少ない |

この比率って、働かない2割を取り除いても、また同じ割合が生まれるんですよね?それってなぜなんでしょうか?

まさにその通りです。これは単なる能力差ではなく、集団全体が長期的に安定して機能するためのバランスなんです。
興味深いのは、働かない2割を取り除いても、残った集団の中で再び同様の割合が生まれることです。この現象は単なる能力差というより、集団全体が長期的に安定して機能するためのバランスだと考えられています。
「働かない2割は切り捨て」?よくある誤解

効率を考えると、働かない2割は邪魔に思えてしまうんですが、これって間違いなんですね。
働きアリの法則においてよくある誤解が、「働かない2割は無駄だから切り捨てればいい」という考え方です。しかし、これは本来の意図とは異なります。むしろ、その2割がいることで、集団全体に余裕が生まれ、突発的な事態への対応力や柔軟性が高まるとされています。
働きアリの法則について、誤解を招く考え方は次のようなものがあります。
- 働かない2割は組織の負担
- 効率性のために排除すべき
- 成果主義で一律に評価すべき

常に全員がフル稼働していると、組織は疲弊しやすくなります。余裕があるからこそ、緊急時に対応できるんです。
また、常に全員がフル稼働している状態では、組織は疲弊しやすくなります。人間社会では、「今は目立たないが後に力を発揮する」存在も多く、短期的な効率だけで判断することは危険です。
人間社会や組織にそのまま当てはめてよいのか?

アリと人間では、やっぱり全然違いますよね。人間の方が複雑な要因がたくさんありそうです。
働きアリの法則を人間の組織運営にそのまま適用するのは慎重に行うべきです。アリと違い、人間には個人差、心理状態、モチベーション、家庭環境など、行動に影響する多くの要素が存在します。
アリと人間の組織運営について、具体的な違いは次の通りです。
| アリの特徴 | 人間の特徴 |
| 本能による行動 | 複雑な心理状態 |
| 固定的な役割 | 変化する能力・状況 |
| 単純な環境要因 | 多様な背景・環境 |

人間の場合、環境や支援によって能力を発揮できるようになることも多いですからね。表面的な成果だけで判断するのは危険です。
また、ある人が常に「非効率な2割」に属しているとは限らず、環境や支援によって能力を発揮できるようになることもあります。よって、表面的な成果や効率だけで人を分類するのではなく、背景にある要因を含めて多角的に見る視点が大切です。
働きアリの法則を組織マネジメントに活かす方法

それでは、この法則を実際のマネジメントにどう活かせばいいんでしょうか?
この法則をマネジメントに活かすには、「余白」の存在を前向きに捉える姿勢が求められます。組織における”働かない2割”が、リスク対応や新たな挑戦に力を発揮するケースも多く、彼らの潜在力を見逃すのは損失です。
働きアリの法則を組織マネジメントに活用するには、次のような方法があります。
- メンバーの状態や強みを正しく把握する
- 役割に応じた支援や配置を行う
- 多様な価値を認める組織文化を構築する
- 短期的成果だけでなく長期的視点を持つ

リーダーはメンバーの状態や強みを正しく把握することが重要です。均一な成果主義ではなく、多様な価値を認める組織文化が大切ですね。
リーダーはメンバーの状態や強みを正しく把握し、役割に応じた支援や配置を行うことが大切です。また、均一な成果主義ではなく、多様な価値を認める組織文化が、長期的に健全な成長を促進します。
みんなのマネージャで実現する健全な組織運営

村上さんがよく紹介されている「みんなのマネージャ」って、こういった課題にどう役立つんですか?
「みんなのマネージャ」は、従業員の状態を可視化し、マネージャーが適切に支援するための仕組みを提供します。AIにより最適化されたペースで配信されるサーベイは、モチベーションやコンディションの変化を即座に察知し、フィードバックの質を高めます。
みんなのマネージャについて、具体的には次のような機能があります。
| 機能 | 効果 |
| 週次サーベイ | モチベーション・コンディションの変化を察知 |
| 状態可視化 | 従業員の状況を客観的に把握 |
| AI分析 | データに基づく適切なアプローチを提案 |

従来の属人的なマネジメントでは見落とされがちな部分も、データで可視化できるのが強みです。全員が自分らしく働ける環境づくりに役立ちますよ。
従来の属人的なマネジメントでは見落とされがちな”働かない2割”にも、最適なアプローチが可能となります。全員が自分らしく働ける環境を整え、組織全体の力を最大限に引き出すサポートを行います。
※みんなのマネージャの口コミ記事への内部リンクを制作後に実装
まとめ:誤解せずに活用すれば、組織はもっと強くなる

働きアリの法則って、よく誤解されがちですが、正しく理解すれば組織運営に役立つんですね。
働きアリの法則は、誤って解釈されやすい一方で、正しく理解すれば組織運営における貴重なヒントになります。重要なのは、常に「成果」で人を評価するのではなく、潜在力や役割のバランスを考慮したマネジメントです。
働きアリの法則を正しく活用するためには、次のポイントを覚えておくことが重要です。
- 短期的成果だけでなく長期的視点を持つ
- 個々の特性や背景を理解する
- 多様性を活かした組織作りを心がける
- 適切なツールを活用して可視化を行う

誤解を解き、正しく活用することで、組織はより柔軟で強固なものへと変わっていくでしょう。
「みんなのマネージャ」のような可視化ツールを活用することで、個々の特性を見極め、効果的に支援することが可能になります。誤解を解き、正しく活用することで、組織はより柔軟で強固なものへと変わっていくでしょう。

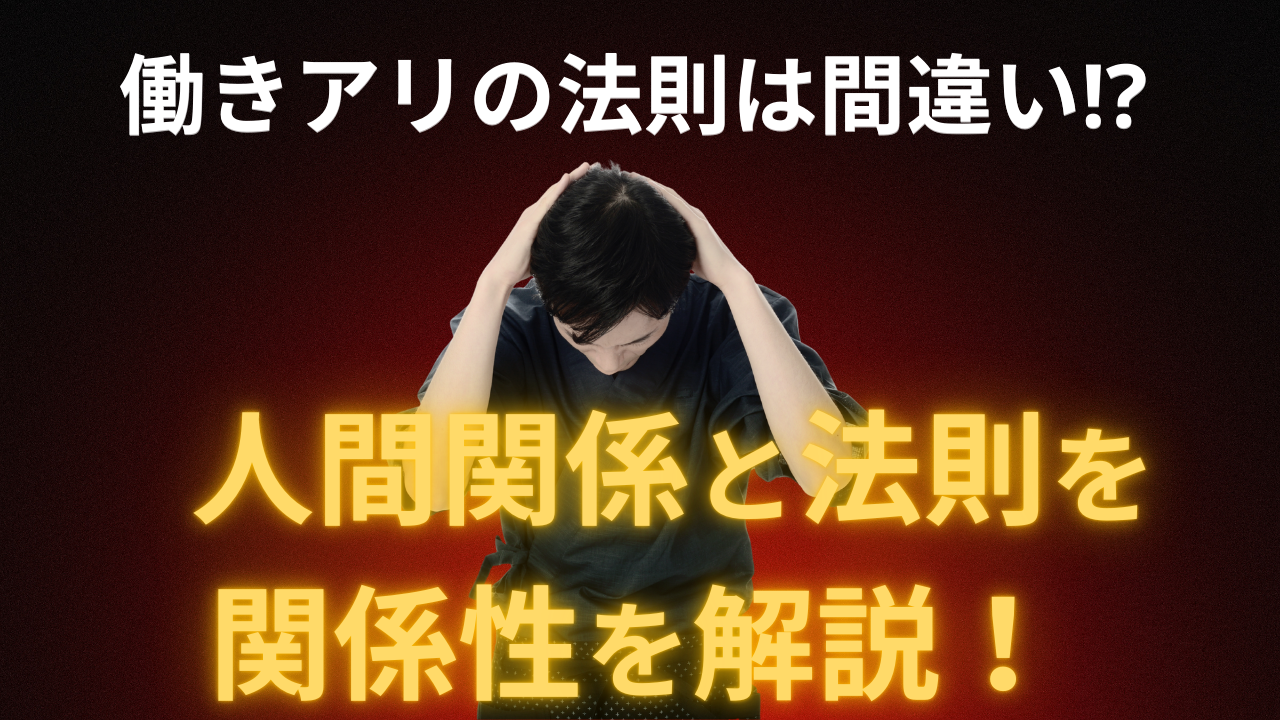
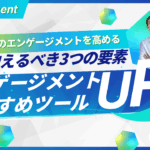
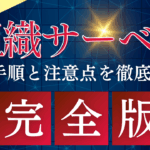
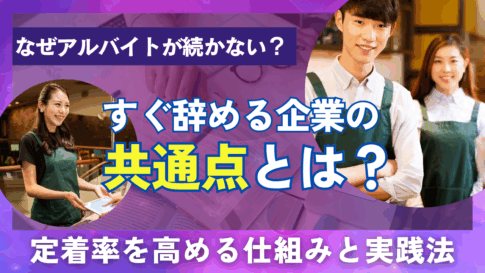
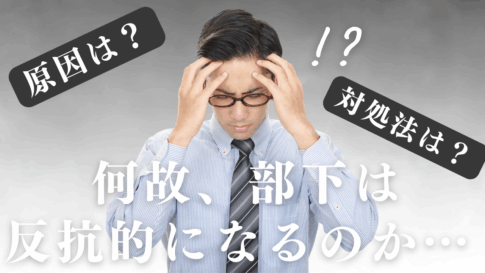
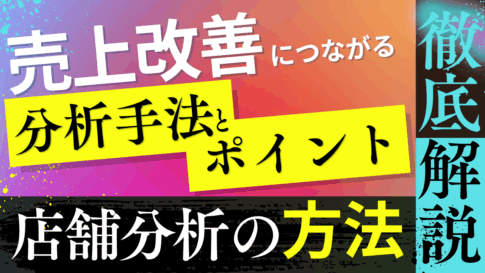
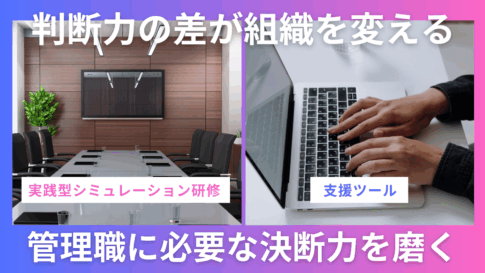
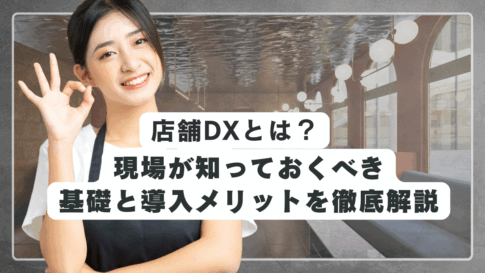
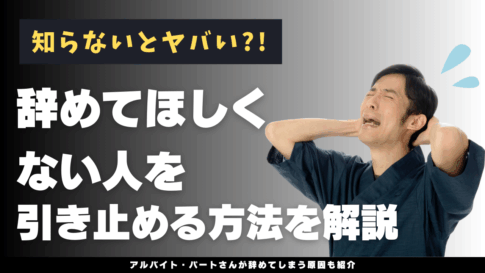
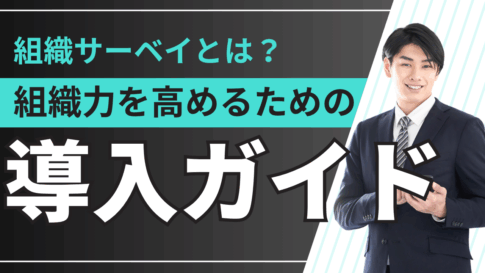
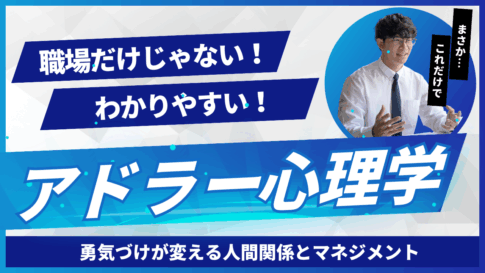



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。