
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
エンゲージメントサーベイは、従業員のモチベーションや職場環境を把握するために欠かせない施策です。
本記事では、効果的なサーベイを実施するための「質問項目」にフォーカスし、分類別の例や設計のポイントをご紹介します。

エンゲージメントサーベイって、従業員の本当の気持ちを知るための重要なツールなんですよね。でも、質問の作り方次第で結果が大きく変わってしまうんです。
エンゲージメントサーベイとは
エンゲージメントサーベイとは、従業員の仕事に対する熱意や組織への愛着心を測定するための調査です。企業が従業員のモチベーションや満足度を把握し、組織の課題を明確にするために活用されます。
定期的に実施することで、従業員の心理的状態や職場環境の変化をタイムリーに把握し、離職防止や生産性向上につなげることが可能です。
エンゲージメントサーベイの主な構成要素としては、次のようなものが挙げられます。
| 要素 | 内容 |
| 組織への信頼 | 経営陣への信頼度、会社のビジョンへの共感 |
| 人間関係 | 上司・同僚との関係性、チームワーク |
| 働きがい | 業務に対する満足感、達成感 |
| 自己成長 | キャリア形成への支援、成長機会の提供 |
サーベイは一般的に、複数の質問項目に対して従業員が回答する形式で行われます。これらの質問を通じて、従業員のエンゲージメントレベルを数値化し、組織の強みや課題を可視化することができます。
その結果をもとに、具体的な改善策を立案し、実施することで、より良い職場環境の構築が期待されます。

質問項目の設計って、思っている以上に奥が深いんですね。従業員の皆さんが答えやすくて、でも本音を引き出せるような質問を作るのは難しそうです。
質問項目の重要性
エンゲージメントサーベイにおける質問項目は、従業員の本音や職場に対する感情を引き出す鍵となります。適切な質問項目を設定することで、従業員の満足度や課題を正確に把握し、組織の改善点を明確にすることが可能です。
例えば、組織への信頼や人間関係、働きがい、自己成長に関する質問を通じて、従業員がどのように感じているかを具体的に知ることができます。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
また、質問項目の内容や表現によって、従業員の回答の質や率直さが大きく変わるため、慎重な設計が求められます。質問項目を適切に設計することで、従業員の声を正確に反映したデータを収集し、効果的な組織改善に役立てることができます。

質問項目は大きく4つのカテゴリーに分けて考えると整理しやすいですよ。それぞれの特徴を理解して、バランス良く質問を配置することが大切です。
質問項目の分類と例

組織への信頼って、従業員のエンゲージメントの基盤になる部分ですよね。ここがしっかりしていないと、他の施策も効果が薄れてしまいそうです。
組織への信頼に関する質問
組織への信頼に関する質問は、従業員が会社や経営陣に対してどれだけ信頼を寄せているかを測定します。例えば、「経営陣は明確なビジョンを持っており、それをあなたに対しても伝えていますか?」や「この会社の理念や目標を理解していますか?」といった質問が挙げられます。
他にも、組織への信頼を測る質問事項には、次のような例も挙げられます。
これらの質問を通じて、従業員が組織の方向性や価値観に共感しているかを把握し、組織の一体感や帰属意識の強さを評価することが可能です。
信頼関係が強い組織では、従業員のモチベーションやパフォーマンスが向上し、離職率の低下にもつながります。したがって、組織への信頼に関する質問は、エンゲージメントサーベイにおいて重要な役割を果たします。

人間関係の質問では、上司との関係だけでなく、同僚やチーム全体との協力体制も重要なポイントになります。心理的安全性も測定できる内容にしたいですね。
人間関係に関する質問
人間関係に関する質問は、職場内での同僚や上司との関係性を評価するために用いられます。例えば、「上司は自身の意見や考えを尊重してくれていると感じますか?」や「チームメンバーと協力体制が整っていると感じますか?」といった質問が該当します。
他にも、人間関係に関する質問事項には、次のような例が挙げられます。
| 関係性の種類 | 質問例 |
| 上司との関係 | 上司は自身の意見や考えを尊重してくれていると感じますか? |
| 同僚との関係 | チームメンバーと協力体制が整っていると感じますか? |
| コミュニケーション | 職場でのコミュニケーションは円滑ですか? |
| サポート体制 | 困った時に相談できる人がいますか? |
これらの質問を通じて、職場のコミュニケーションの質やチームワークの状態を把握し、必要に応じて改善策を講じることが可能です。
良好な人間関係は、従業員の満足度やエンゲージメントの向上に直結し、組織全体の生産性や業績にも良い影響を与えます。そのため、人間関係に関する質問は、エンゲージメントサーベイにおいて欠かせない要素となっています。

働きがいって、人それぞれ感じ方が違いそうですね。業務の内容だけでなく、成果への評価や成長実感も大切な要素になりそうです。
働きがい・やりがいに関する質問
働きがい・やりがいに関する質問は、従業員が日々の業務に対してどれだけ満足感や達成感を感じているかを測定します。例えば、「日々の業務にやりがいを感じていますか?」や「仕事を通じて自分の成長を実感できていますか?」といった質問が挙げられます。
他にも、働きがい・やりがいに関する質問事項には、次のようなものも挙げられます。
これらの質問を通じて、従業員のモチベーションや仕事への熱意を把握し、必要に応じて業務内容や職務設計の見直しを行うことが可能です。
働きがいややりがいを感じる職場は、従業員のエンゲージメントが高まり、組織の成果や業績向上にも寄与します。したがって、働きがい・やりがいに関する質問は、エンゲージメントサーベイにおいて重要な指標となります。

キャリア支援に関する質問は、特に若手社員のエンゲージメントに直結しますね。将来への希望が見えるかどうかで、定着率も大きく変わってきます。
自己成長・キャリアに関する質問
自己成長・キャリアに関する質問は、従業員が自身の成長やキャリア形成に対してどれだけ前向きに取り組んでいるかを評価します。例えば、「いまの会社では自分が成長できる機会が用意されていると感じますか?」や「上司や会社はあなたのキャリア形成をサポートしていますか?」といった質問が該当します。
他にも、自己成長・キャリアに関する質問項目には、次のような例も挙げられます。
| 項目 | 質問例 |
| 成長機会 | いまの会社では自分が成長できる機会が用意されていると感じますか? |
| キャリアサポート | 上司や会社はあなたのキャリア形成をサポートしていますか? |
| スキル向上 | 新しいスキルを身につける機会がありますか? |
| 将来性 | この会社で長期的にキャリアを築いていけると思いますか? |
これらの質問により、従業員が自身の将来に対してどれほど希望を持っているか、また企業側がその希望をどのようにサポートしているかを把握できます。
キャリアへの支援が明確であればあるほど、従業員のロイヤルティは高まり、離職防止にもつながります。企業としても人材を育成しやすくなるため、自己成長・キャリアに関する項目は重要な評価基準となるのです。

質問を作る時のポイントって、実際にやってみると難しそうですね。従業員の方が答えやすくて、でも必要な情報はしっかり取れるバランスが大切ですね。
質問項目設計のポイント

質問文はシンプルが一番です。専門用語を使ったり、複雑な文章にすると、回答者が混乱してしまい、正確なデータが取れなくなってしまいます。
シンプルでわかりやすい質問文にする
エンゲージメントサーベイの質問は、従業員が直感的に理解できるシンプルな表現にすることが重要です。専門用語や曖昧な言い回しは避け、誰もが同じ意味で捉えられるように設計する必要があります。
また、長文の質問や複雑な構文は、回答者にとってストレスとなり、正確な情報を得られなくなるリスクもあります。
質問文を作成するときのポイントをまとめると、次のようになります。
簡潔かつ具体的な文面にすることで、従業員は答えやすくなり、信頼性の高いデータが収集できます。回答率の向上にもつながるため、質問文の設計は非常に重要な工程です。

質問数って、多すぎても少なすぎても良くないんですね。従業員の負担を考えながら、必要な情報はしっかり集められるバランスを見つけるのが大切ですね。
回答の負担にならない質問数を設定する
エンゲージメントサーベイの効果を高めるには、質問数のバランスが重要です。多すぎる質問は回答者の負担となり、回答離脱や精度低下の原因となります。逆に少なすぎると、必要な情報が収集できず、分析の精度が下がってしまいます。
エンゲージメントサーベイの実施頻度・推奨質問数・目的には、次のような関係があります。
| 実施頻度 | 推奨質問数 | 目的 |
| 週次 | 3~5問 | タイムリーな状況把握 |
| 月次 | 5~10問 | 定期的なエンゲージメント測定 |
| 四半期 | 10~15問 | 詳細な分析と改善策検討 |
理想は1回のサーベイで5~10問程度が目安とされており、特に週次で実施する場合は3~5問に抑えるのが一般的です。継続的な運用を前提にすることで、蓄積データの分析やタイムリーな改善が可能になります。

目的がはっきりしていないサーベイは、結果が出ても活用しづらいんです。何のために調査するのかを明確にしてから質問を選ぶことが重要ですね。
目的に沿った質問項目を選定する
エンゲージメントサーベイは目的に応じて質問項目を選定することが重要です。例えば、離職率の改善を目指す場合は心理的安全性や職場の人間関係に関する質問、組織力の強化が目的であれば組織への信頼や目標の共有に関する質問が効果的です。
具体的な目的と質問内容は、次のようになっています。
目的を明確にすることで、回答結果に基づいた具体的なアクションプランを策定しやすくなります。また、目的と質問内容の一貫性があることで、従業員にも調査の意図が伝わりやすく、より信頼性の高いデータ収集につながります。

エンゲージメントサーベイって、ただ実施するだけじゃなくて、その後の改善アクションまで考えて設計することが大切なんですね。従業員の声を活かせる仕組みづくりが重要ですね。
まとめ
エンゲージメントサーベイの質問項目は、組織の課題や従業員の心理状態を把握するための重要な手段です。目的に応じて適切な質問を設計することで、従業員の本音を引き出し、組織改善に活かすことができます。
質問内容はシンプルかつ具体的に、負担にならない数に留め、定期的に運用することが大切です。
効果的なエンゲージメントサーベイのポイント
✓ 組織への信頼・人間関係・働きがい・自己成長の4つの分野をバランス良く含める
✓ 質問文はシンプルで理解しやすい表現にする
✓ 回答負担を考慮して適切な質問数に調整する
✓ 調査目的を明確にして質問項目を選定する
※CTAを追加して「みんなのマネージャ」への導線を設定する予定※

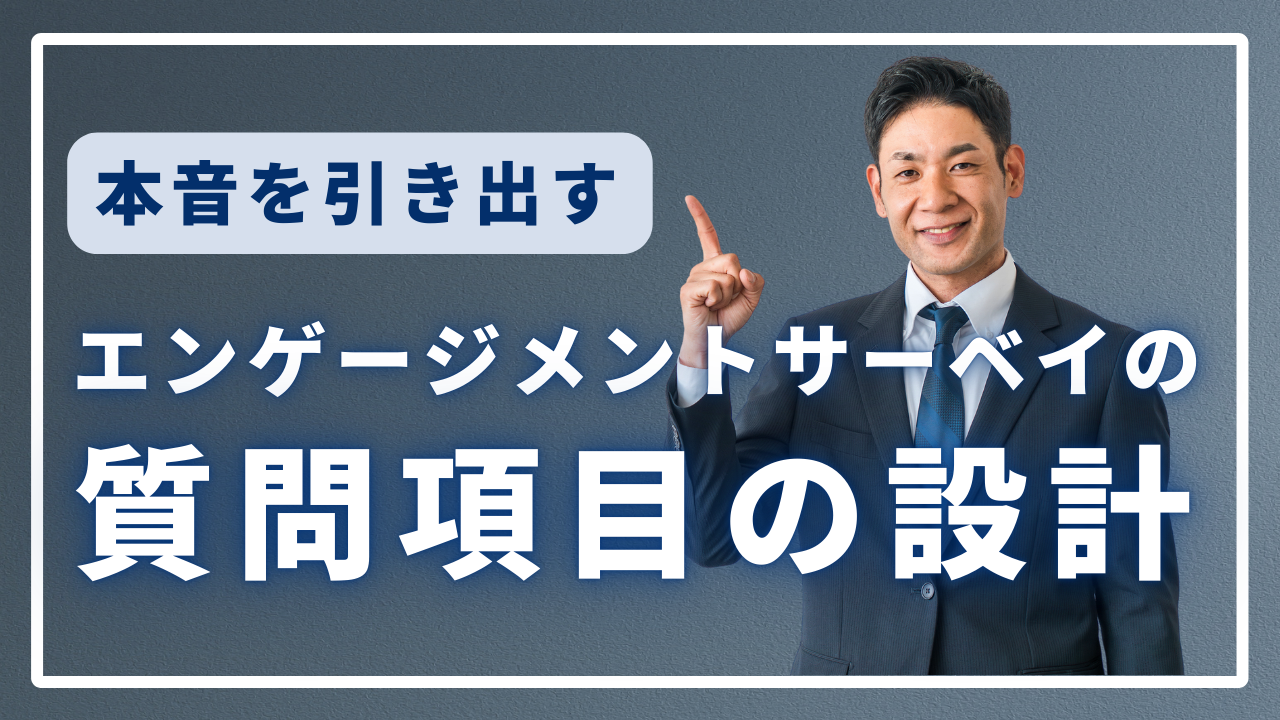
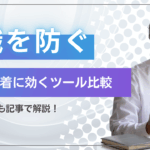

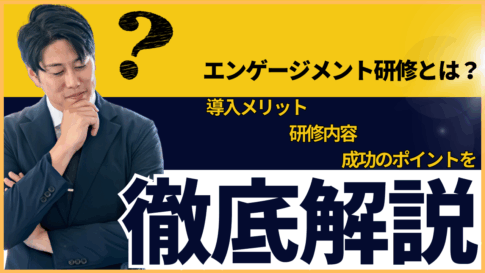
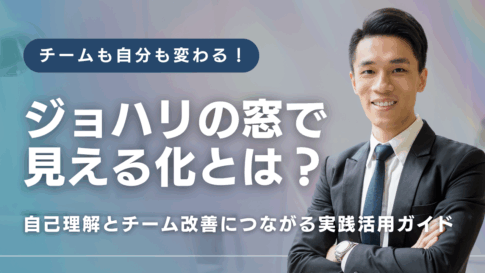
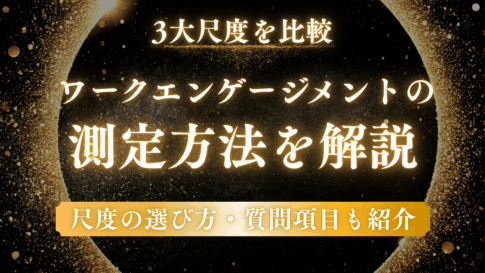



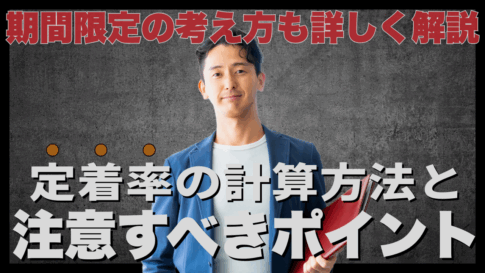




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。