
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
従業員の声を活かして組織をより良くしたいと考える企業にとって、組織サーベイは重要な手段です。
しかし、実施方法や注意点を知らなければ、効果を最大化することはできません。
本記事では、組織サーベイの基本から具体的な実施手順、注意点、おすすめツールまで、わかりやすく解説します。

組織サーベイの導入を検討される企業が増えていますが、単に実施するだけでは意味がありません。従業員の本音を引き出し、それを確実に改善につなげることが重要です。
組織サーベイとは?その目的と重要性

組織サーベイって、どんなことを調査するんですか?実際に現場でどのような効果が期待できるのでしょうか?
組織サーベイとは、企業が従業員の意識や職場環境に関する情報を収集し、組織の現状や課題を把握するための調査手法です。その目的は、従業員の満足度やエンゲージメントの向上、組織風土の改善、退職率の低下など、多岐にわたります。
| 組織サーベイの主な目的 | 期待される効果 |
| 従業員満足度の向上 | モチベーション向上、生産性の向上 |
| エンゲージメントの強化 | 組織への愛着増加、定着率向上 |
| 組織風土の改善 | コミュニケーション活性化、チームワーク強化 |
| 退職率の低下 | 人材確保、採用コスト削減 |
| 職場環境の最適化 | 働きやすさ向上、ワークライフバランス改善 |
組織サーベイを実施することで、経営層や人事担当者は、従業員の声を客観的なデータとして把握し、的確な施策を講じることが可能になります。また、従業員にとっても、自身の意見が組織運営に反映されることで、モチベーションの向上や職場への信頼感が高まる効果が期待できます。このように、組織サーベイは、企業と従業員の双方にとって重要なコミュニケーション手段となっています。

制度を整えるだけでは、人は動きません。鍵は”内発的動機づけ”です。組織サーベイは、従業員一人ひとりの声を聞き、その動機を引き出すための第一歩なんです。
組織サーベイの実施手順

初めて組織サーベイを実施する場合、どんな手順で進めればいいのでしょうか?失敗しないためのポイントも知りたいです。
ステップ1:目的の明確化
組織サーベイを実施する際には、まずその目的を明確にすることが重要です。例えば、従業員満足度の向上、職場環境の改善、エンゲージメントの強化など、何を達成したいのかを具体的に設定します。
目的を明確にするためには、次のステップが有効です。
- 明確な目標設定:従業員満足度向上、職場環境改善、エンゲージメント強化など具体的な目標を定める
- 調査項目の最適化:目的に応じた適切な質問項目と分析方法を設計する
- 結果活用の計画:得られたデータをどのように活用するかを事前に計画する
- 従業員への説明:調査の目的と意義を従業員に共有し、理解と協力を促進する
目的が明確であれば、調査項目や分析方法も適切に設計でき、得られた結果を有効に活用することができます。また、目的を従業員に共有することで、調査への理解と協力を得やすくなります。

この人事施策、現場の”納得感”まで落とし込めていますか?目的が曖昧だと、従業員にとって「なぜこの調査をするのか」が分からず、形式的な回答しか得られなくなってしまいます。
ステップ2:設問の設計
目的に沿って、適切な設問を設計します。設問は、従業員の意識や行動、職場環境などを測定する内容とし、回答しやすい形式にすることが望ましいです。
設問を設計するためには、次のステップが有効です。
- 回答負担の軽減:設問数を適切に調整し、回答時間が過度に長くならないよう配慮する
- 中立的な表現:偏りのない中立的な言い回しで設問を作成する
- 測定可能な内容:従業員の意識、行動、職場環境を具体的に測定できる設問にする
- 回答形式の工夫:選択式、評価尺度など回答しやすい形式を採用する
また、設問数は多すぎず、回答時間が長くならないよう配慮することが重要です。設問の内容や表現にも注意を払い、偏りのない中立的な言い回しを心がけましょう。

まだ分からないことだらけですが、まずは”現場の声”をちゃんと拾うことから始めたいと思ってます。質問の作り方って、本当に回答の質に影響するんですね。
ステップ3:調査の実施と回収
設問が完成したら、調査を実施します。調査方法は、オンラインアンケートや紙ベースの調査など、従業員の状況に応じて選択します。
次の表は、各調査の特徴とメリット・デメリットをまとめた表になっています。
| 調査方法 | メリット | デメリット | 適用場面 |
| オンラインアンケート | 効率的、集計が容易、匿名性確保 | デジタル環境が必要 | ITリテラシーが高い組織 |
| 紙ベースの調査 | 全従業員が参加可能、親しみやすい | 集計に時間がかかる | ITインフラが限定的な環境 |
| 対面インタビュー | 詳細な意見収集、深掘り可能 | 時間とコストがかかる | 少人数組織、質的調査 |
調査期間中は、回答のリマインドやサポートを行い、回答率の向上を図ります。また、回答の匿名性を確保することで、従業員が率直な意見を述べやすくなります。
ステップ4:結果の分析とフィードバック
回収したデータを分析し、組織の現状や課題を把握します。分析結果は、経営層や各部門の責任者に共有し、必要に応じて従業員にもフィードバックを行います。
効果的なフィードバックの要素としては、次のようなものがります。
- 透明性の確保:調査結果を従業員に適切に共有し、信頼関係を構築する
- 課題の明確化:データから読み取れる組織の強みと改善点を明確に示す
- 改善への道筋:具体的な改善計画と実行スケジュールを提示する
- 従業員の声の反映:意見が組織運営にどう活かされるかを具体的に説明する
フィードバックは、調査結果の透明性を高め、従業員の信頼感を醸成する効果があります。また、フィードバックを通じて、従業員の意見が組織運営に反映されることを実感させることが重要です。

数字も大事ですが、面談時の”表情の変化”を見逃さないようにしてください。データの背景にある従業員の感情を読み取ることが、真の改善につながるのです。
ステップ5:改善策の立案と実行
分析結果を基に、組織の課題に対する改善策を立案し、実行に移します。改善策は、具体的かつ実行可能な内容とし、優先順位をつけて取り組むことが効果的です。
改善策の立案と実行の具体的なステップは、次のようになっています。
- 具体的な改善計画:課題に対する明確で実行可能な解決策を策定する
- 優先順位の設定:影響度と緊急度を考慮して改善項目の優先順位を決定する
- 進捗管理:改善策の実行状況を定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を行う
- PDCAサイクルの実践:計画、実行、評価、改善のサイクルを継続的に回す
また、改善策の進捗状況や成果を定期的に確認し、必要に応じて見直しを行います。このように、組織サーベイの結果を活用してPDCAサイクルを回すことで、継続的な組織改善が可能になります。

変化を起こすって、まずは”気づくこと”からなんですね。プロジェクトの中で、この実感が本当に大切だということを学びました。
組織サーベイ実施時の注意点

組織サーベイの実施では、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておくことで、より効果的な調査が実現できるでしょう。
従業員の負担軽減と参加促進
組織サーベイを実施する際には、従業員の負担を軽減し、参加を促進する工夫が必要です。例えば、調査の所要時間を短縮する、回答しやすい設問形式を採用する、調査の目的や意義を明確に伝えるなどの対策が考えられます。
参加促進のための工夫には、次のようなものがあります。
- 時間短縮:回答時間を10-15分程度に抑えて負担を軽減する
- 設問形式の最適化:選択式やスケール評価など回答しやすい形式を採用する
- 目的の明確化:調査の意義と従業員にとってのメリットを丁寧に説明する
- 結果活用の約束:調査結果をどのように組織改善に活かすかを事前に示す
また、調査結果がどのように活用されるのかを説明し、従業員の協力を得ることが重要です。

この案、まだ粗いんですけど……従業員の皆さんが前向きに参加してもらえるような仕組みづくりが大切ですよね。
データの正確性と信頼性の確保
調査データの正確性と信頼性を確保するためには、設問の設計や調査方法に注意を払う必要があります。例えば、設問の表現が曖昧であったり、質問が誘導的である場合、正確な回答が得られなくなる可能性があります。
次の表は、信頼性を確保するために気を付けるポイントについてまとめたものになります。
| 信頼性確保の要素 | 具体的な対策 |
| 設問の明確性 | 曖昧な表現を避け、具体的で理解しやすい質問を作成する |
| 中立性の維持 | 誘導的な質問を排除し、客観的な回答を促す |
| 匿名性の保証 | 回答者が特定されないシステムを構築する |
| データ処理の正確性 | 集計ミスや解釈の偏りを防ぐチェック体制を整備する |
また、匿名性を保証することで、従業員が本音で回答しやすくなり、信頼性の高いデータが集まります。さらに、調査後のデータ処理や集計にも注意を払い、集計ミスや解釈の偏りがないようにしましょう。
結果の活用と継続的な改善
組織サーベイは、実施して終わりではありません。調査結果を分析してフィードバックし、具体的な改善策につなげていくことが不可欠です。
結果の活用と継続的な改善方法には、次のようなものが挙げられます。
- 結果の分析と共有:データを適切に分析し、経営層から現場まで必要な情報を共有する
- 改善策の実行:分析結果に基づいた具体的な改善アクションを実施する
- 効果の検証:改善施策の有効性を定期的に確認し、必要に応じて見直しを行う
- 継続的な取り組み:次回のサーベイに向けて学びを活かし、調査の質を向上させる
さらに、その後の改善施策が有効かどうかを定期的に確認し、次回のサーベイに活かしていくという継続的な取り組みが、組織の成長につながります。このように、結果を活用して改善を繰り返す姿勢が、従業員からの信頼を得るポイントでもあります。

人を育てるって、”育てよう”と思った瞬間から始まるんですよね。継続的な改善も同じで、意識を持ち続けることが何より大切です。
組織サーベイの成功事例と効果

あ、今のすごく大事な観点ですね。実際にどんな成果が得られるのか、具体的な事例があると説得力がありますよね。
実際に組織サーベイを導入した企業では、従業員のモチベーション向上や退職率の改善など、さまざまな成果が報告されています。例えば「みんなのマネージャ」では、週次のサーベイとフィードバック支援により、退職率を67%改善したという実績があります。
次の表は、組織サーベイの成功事例と効果をまとめたものになります。
| 成果指標 | 改善効果 | 具体的な変化 |
| 退職率 | 67%改善 | 人材の定着率向上、採用コスト削減 |
| 昇格者の適応力 | 大幅向上 | 新任管理職の早期戦力化 |
| 組織の育成力 | 均一化達成 | 部門間の育成格差解消 |
| マネジメント品質 | 標準化実現 | 属人的運用からの脱却 |
また、昇格者の現場適応力が向上し、組織全体の育成力が均一化されるといった効果も見られます。このように、データに基づいたマネジメントは、属人的な運用から脱却し、組織のパフォーマンスを高めることにつながります。継続的なサーベイ実施と適切なフィードバックの仕組みを整えることが、成功の鍵といえるでしょう。
組織サーベイにおすすめのツール紹介

“みんなのマネージャ”のフィードバック機能、現場の心理的安全性づくりにかなり効きますよ。実際に顧客企業で導入いただいた際の効果を実感しています。
組織サーベイを効果的に実施するには、適切なツールの活用が重要です。中でも「みんなのマネージャ」は、パルスサーベイ機能、AIによるアクション提案、エンゲージメント分析、1on1支援などが一体化されたツールで、調査から改善までを一貫してサポートします。
「みんなのマネージャ」の主要機能は、次のようになっています。
- 高頻度パルスサーベイ:週1回の定期的なアンケートでリアルタイムな状況把握を実現
- ダッシュボード:各従業員のコンデイションを一目で確認
- 離職予防機能:早期警告システムによる離職リスクの事前察知
- AIアクションリスト機能:サーベイ結果に基づきAIがマネジメントの行動提案
- 多彩な評価機能:スキル評価、360度評価、カスタマイズ可能な設問設定
特に、週1回の高頻度なアンケートとAIによる個別最適化により、リアルタイムで従業員の状態を把握でき、離職予防やマネジメントの質向上に寄与します。導入から活用まで伴走支援が整っているため、初めての組織サーベイ導入にも適しています。さらに、スキル評価や360度評価、カスタマイズ可能な設問設定など、現場に即した多彩な機能も魅力です。

最近では「みんなのマネージャ」の活用プロジェクトでAIからのフィードバックを参考にコミニケションを取るなど、実際に使ってみるとフィードバックから新たな気付きを得られて驚きます。
※みんなのマネージャの口コミ記事への内部リンクを制作後に実装
まとめ:組織サーベイで実現する持続的な組織改善

組織サーベイは単なる調査ではなく、従業員との対話の始まりです。継続的な改善サイクルを回すことで、真の組織成長が実現できるのです。
組織サーベイは、従業員の声を組織運営に活かし、持続的な成長を実現するための重要な手段です。適切な実施手順と継続的な改善により、従業員満足度の向上、退職率の低下、組織パフォーマンスの向上といった具体的な成果を得ることができます。

この前の1on1、ちゃんと”聞く”って奥が深いんだなって実感しました。組織サーベイも同じで、従業員の声を真摯に受け止める姿勢が何より大切ですね。


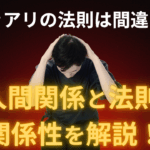

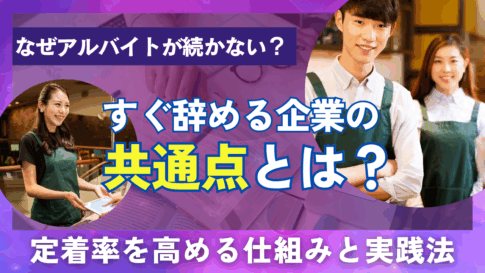
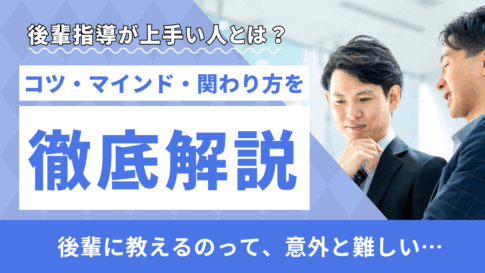
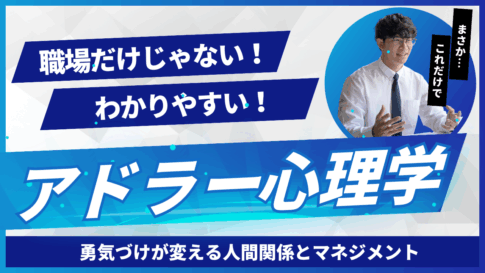
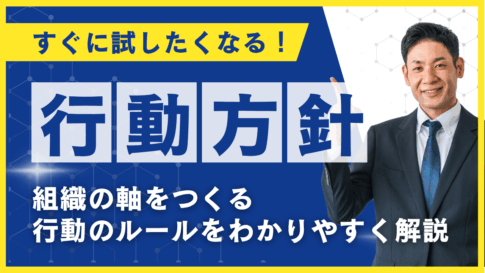
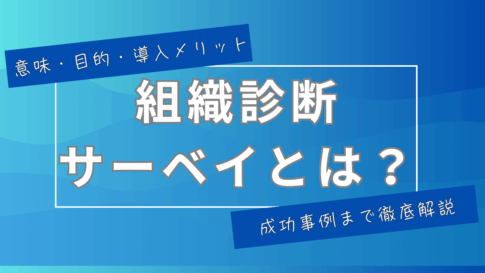

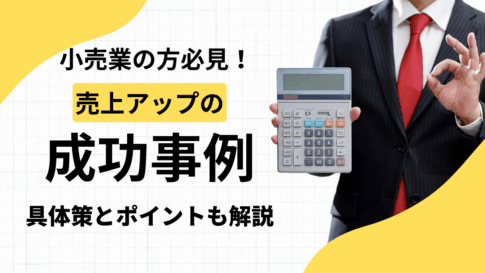
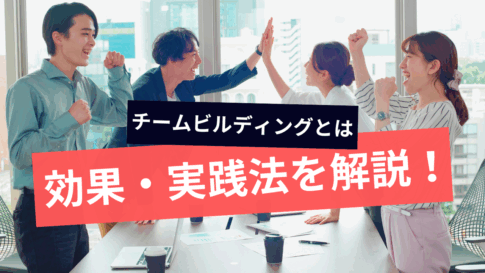



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。