
飲食店向け経営・DXコンサルタント(ジュニアアソシエイト)
新卒で大手IT企業に入社し、飲食店の業務システム開発に携わる。当時から佐藤をメンターとして仰ぎ、その「現場ファースト」の姿勢に強く感銘を受ける。その後、佐藤のコンサルティング会社設立に際し、自身のデジタルスキルと現場への情熱を活かしたいと志願し、創業メンバーとして参画。
「終業時間を過ぎても仕事が終わらないのは仕方ない」「誰も帰らないから自分も帰れない」そのようなサービス残業が当たり前という空気、あなたの職場にもありませんか?
日本では長らく美徳とされてきた働きすぎ文化ですが、近年は価値観の変化や働き方改革の流れを受け、「ただ働き」の実態に疑問の声が高まりつつあります。
この記事では、なぜサービス残業が当たり前になってしまったのか、その背景を探るとともに、今すぐできる個人の対策や会社が取るべき対応について解説します。
「サービス残業は当たり前」を「変えられる」に変えるヒントを、ぜひ見つけてください。
- サービス残業とは
- サービス残業を防ぐポイント
- なぜサービス残業が起きてしまうのか

今日は、まだまだ多くの職場で問題になっている「サービス残業」について詳しく見ていきましょう。
サービス残業とは

サービス残業って、よく耳にはしますが、具体的にはどういうものなんでしょうか?
「サービス残業」という言葉を耳にしたことがある方も多いかもしれません。これは、本来支払われるべき残業代が支給されないまま、法定の労働時間を超えて働くことを意味します。
労働基準法では、1日につき8時間、もしくは週に40時間を超える労働については、会社が割増賃金を支払う義務があると定められています。つまり、こうした時間外労働には正当に残業代が発生するのが原則です。
しかし現実には、こうした規定が守られない「サービス残業」が多くの職場で見られます。

法律で定められた当然の権利が守られていない、これが現在の日本の労働現場の実情なんですね。
サービス残業の実情

実際にはどれくらいの人がサービス残業を経験しているんでしょうか?
現在の日本において、サービス残業は特別な例ではなく、むしろ多くの企業で日常的に行われています。
日本労働組合総連合会が行った「労働時間に関する調査(2015年)」では、実に42.6%もの人が、サービス残業を経験したことがあると答えています。
特に、役職が上がるにつれて残業が増える傾向にあり、一般社員よりも課長職の方がより多く残業している実態が浮かび上がっています。
また、この調査では「どのような対策を取れば残業を減らせるか」という質問に対し、「人員を適切に配置すること」と答えた人が過半数を超えており、恒常的な人手不足が残業の原因のひとつであることがうかがえます。

約半数の人が経験しているということは、これは個人の問題ではなく、社会全体の構造的な問題ですね。
サービス残業が起こる背景

なぜこんなに多くの企業でサービス残業が起きてしまうんでしょうか?
では、なぜ違法ともいえるサービス残業が職場に根付いてしまうのでしょうか。ここでは、その主な理由を5つに分けて解説していきます。
- 理由1:人件費を抑えたい企業側の思惑
- 理由2:断りづらい職場の空気
- 理由3:労働時間の管理がずさん
- 理由4:経営層の労働法知識が不十分
- 理由5:業務量に対する人手不足
理由1:人件費を抑えたい企業側の思惑
調査結果にもあるように、社員の多くは「人を増やせば残業は減る」と感じています。しかし、企業側としては、人件費の増加は経営を圧迫するため、抑えたいという意識が強いのが現実です。
結果として、正当な残業代を支払わずに労働を求める、いわゆる「サービス残業」がまかり通る状況が生まれてしまうのです。
理由2:断りづらい職場の空気
本来であれば、会社が残業を命じた場合は、きちんとその分の手当を支払わなければなりません。また、タイムカードなどで就労時間を適切に記録することも必要です。
ところが、一部の企業では残業代なしの残業が常識のようになっており、社員が声を上げにくい空気が存在します。上司や同僚が当然のように長時間働いている環境では、自分だけが定時で帰ることに罪悪感を覚えてしまい、黙って残業をしてしまう人も少なくありません。
理由3:労働時間の管理がずさん
残業が発生した場合、その時間を管理するのは本来会社の責任です。
しかし、サービス残業が常態化しているような企業では、労働時間そのものの把握がずさんになっているケースが多いです。こういった企業では、残業が日常化しており、時間管理という発想すら欠如していることもあります。
理由4:経営層の労働法知識が不十分
サービス残業が起こるもう一つの要因として、経営者や管理職側の労働法に対する理解不足が挙げられます。
例えば、どのタイミングで割増賃金が必要になるかを正確に理解していない企業も存在し、そのために意図せず違法状態に陥っているケースもあるのです。
理由5:業務量に対する人手不足
会社が抱える業務に対して人手が足りていない場合、どうしても社員一人ひとりの業務量が増え、結果として残業が発生しやすくなります。
本来であれば、人員の補充や業務の効率化などで対応すべきです。しかし、対応が行われないまま仕事だけが増えると、社員がサービス残業せざるを得ない状況になります。
具体例として、「システムエンジニアは激務だ」と言われる背景には、「予想外の業務が発生して工数が膨れ上がる」などの問題が指摘されています。
このように、現場の実態に即した業務配分がなされていないことも、サービス残業の大きな原因のひとつです。
さらに、労働基準法では残業時間に上限があります。上限を超えないように「帳簿上だけ残業を隠す」などの行為が行われ、結果としてサービス残業が発生する企業も見受けられます。

このように複数の要因が絡み合っているからこそ、サービス残業の問題は簡単には解決できないんですね。しかし、だからといって放置していいわけではありません。
サービス残業には法的に違法・罰則も規定されている

法的な面から見ると、サービス残業はどのような扱いになるんでしょうか?
残業に対する賃金の支払いを行わないケースは、「サービス残業」として明確に法律違反となります。労働基準法第37条第1項では、所定の労働時間を超える勤務や休日出勤、深夜労働に対して、割増賃金の支払いが企業に義務づけられています。
労働時間の延長や休日出勤が発生した場合には、通常の賃金に加えて25%~50%の範囲内で、政令に定められた割増率以上で残業代を支払わなければならない。
(出典:e-Gov「労働基準法」)
この条文に違反した事業者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される可能性があります。
サービス残業はどこから違法なのか

「自主的な残業」と「違法な残業」の境界線を明確にしておくことが大切ですね。
一見すると「本人が自主的に残って働いているだけ」と思われがちなケースでも、内容によっては違法と判断される場合があります。以下に、違法とみなされるケースとそうでないケースを整理します。
| 違法とされる例 | 違法ではない例 |
|---|---|
| 自主的とはいえ、業務量や雰囲気によって残らざるを得なかった場合 | 完全に自己判断によるスキルアップ学習 |
| 上司や会社が黙認していた場合 | 業務とは無関係な自主学習・訓練 |
| 能力不足を理由に会社から残業を求められた場合 | 語学などの個人的な勉強 |
自主的な残業でも違法になるケースがある
労働者が「自分から進んで」業務を延長していた場合でも、企業側がその行為を知りながら放置していた場合は、黙認とみなされて違法になります。たとえ上司が直接命令していなかったとしても、会社が業務を把握していれば、賃金の支払い義務が発生するのです。
また、「社員の能力が足りなかったから、終わらなかった業務の分は残業代なし」という対応も法的に許されません。成果の大小にかかわらず、労働時間に対しては正当な対価を支払う必要があります。
テレワークにも注意が必要
リモートワークの普及によって、オフィス外での勤務時間が見えづらくなっています。しかし、勤務時間外に社員が作業していることを会社が把握していた場合には、当然ながら残業代の支払いが求められます。
「会社にいないから残業じゃない」という理屈は通用しません。労働者の働いた実態がある限り、場所を問わず賃金の支払い義務が発生します。
能力不足が原因での残業の不払いは違法
業務が終わらない理由が「その社員の仕事の遅さ」にあったとしても、それを理由に賃金を支払わないのは法的に認められません。すべての労働時間に対して、会社は正規の賃金を支払う義務があります。
例えば「同じ作業を他の社員なら時間内に終えられる」などの場合でも、残業代の不支給は違法となる可能性が高いのです。
自発的なスキルアップのための残業は労働時間に含まれない
本人が自らの成長のために取り組む勉強やトレーニングについては、勤務時間とは見なされません。
例えば、業務時間外に英語や資格の勉強をするなど、会社からの指示がない自主的な取り組みであれば、サービス残業とは区別されます。

境界線が明確になると、何が問題で何が問題でないかがよく分かりますね。
サービス残業が当たり前になっている場合の対応策

では、実際にサービス残業が当たり前になっている職場にいる場合、どのような対策を取ることができるでしょうか?
現在でも多くの企業で「サービス残業」が当たり前のように行われていますが、これは明らかに法律に違反した行為です。
それでは、従業員側がこのような不正行為を行っている企業に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。ここでは、有効とされる3つの対処法をご紹介します。
- 不当なサービス残業を通報する
- 会社を辞めて、新たな環境を選ぶ
- 未払いの残業代を請求する
1.不当なサービス残業を通報する
まず考えられるのが、違法な労働実態を外部に知らせる、つまり「告発」する方法です。社内の相談部署に訴えるのも一つの手ですが、より確実な対処を求めるなら、労働基準監督署に申告するという選択肢もあります。
また、法的な観点からアドバイスがほしい場合には、弁護士に相談することも検討すべきでしょう。
2.会社を辞めて、新たな環境を選ぶ
どうしても状況が改善されず、心身ともに疲弊してしまっている場合は、思い切って退職・転職することも有効な手段です。
日本にはさまざまな業種がありますが、中でも運送業や郵便業、情報通信業、電気・ガス・水道などのインフラ関連の職種は、長時間の残業が慢性化しやすい傾向にあると指摘されています。
こうした業種から離れるためには、転職支援サービスを利用して、より健全な職場環境への転職を目指すのもよいでしょう。
3.未払いの残業代を請求する
もしも長期間にわたって残業代が支払われていない場合、法的に認められた期間内に請求することが大切です。未払い残業代の請求には「3年」という時効があります。
請求の手続きを有利に進めるためにも、なるべく早い段階で弁護士に相談しておくことをおすすめします。専門家のサポートを受ければ、スムーズな解決へとつながるでしょう。

3つの対策があるんですね。状況に応じて、自分に合った方法を選ぶことが重要ですね。
サービス残業がなかなか解消されない理由

これだけ問題になっているのに、なぜサービス残業はなくならないのでしょうか?
サービス残業が社会問題として長く取り上げられているにもかかわらず、完全に根絶されることはありません。
その背景には、企業が抱える構造的な課題が関係しています。ここでは、サービス残業がなくならない主な理由を3つに分けてご紹介します。
- 業務量が多く常に忙しい職場環境
- 無言の圧力となる職場の空気
- 経営層による理解の欠如
1.業務量が多く常に忙しい職場環境
従業員一人ひとりに対して割り当てられる業務量が過剰で、結果的に定時内で終わらせるのが困難な状態が続くと、自然と残業が発生してしまいます。
また、業務が立て込んでいるにもかかわらず、新たな人材の採用や業務の効率化などが行われていない場合、負担は既存の社員に集中します。このような状況では、残業そのものが日常的になり、サービス残業が常態化する一因となるのです。
業務の見直しや人員の補充などの具体的な対策を取らなければ、このサイクルはなかなか断ち切れません。職場の「忙しさ」が当たり前になると、残業が前提の働き方となってしまい、それに見合った対価が支払われないケースも増えていきます。
2. 無言の圧力となる職場の空気
職場内に「サービス残業は当然」などの雰囲気が漂っていると、従業員が自らの意思で断ることが難しくなります。とくに上司や先輩社員が率先して長時間残っている場合、部下や若手社員もその姿勢に合わせざるを得ないと感じてしまうでしょう。
「評価に響くのではないか」「空気を乱したくない」などの心理的なプレッシャーが働くことで、たとえ業務が終わっていたとしても帰宅しづらくなることがあります。
このような文化が根づいている企業では、従業員が自発的に行動を起こすことが難しく、サービス残業の根絶には時間がかかります。
3. 経営層による理解の欠如
経営者自身が「サービス残業は違法である」という意識を十分に持っていない場合、その問題が表面化しにくくなります。「社員が自発的にやっていることだから問題ない」と誤解しているケースも少なくありません。
しかし、たとえ命令していなかったとしても、企業がその労働実態を把握し、対策を取っていなければ、労働基準法違反に問われる可能性があります。
経営層が労働生産性の向上を求める一方で、環境整備を後回しにしてしまうと、結果的に社員の疲弊を招きます。こうした状況が続けば、企業全体の生産性にも影響が及び、サービス残業はより深刻な問題となっていくでしょう。

この3つの理由が重なり合うと、確かに根深い問題になりそうですね。企業全体での意識改革が必要ということでしょうか。
サービス残業を放置するリスク

企業がサービス残業を放置し続けると、どのようなリスクがあるのでしょうか?
サービス残業は、単に「無給で働いている」という問題にとどまりません。これを放置することによって、企業側にも深刻なリスクが降りかかります。
ここでは、具体的に考えられる3つのリスクについて見ていきましょう。
- 法的な罰則を受けるリスク
- 情報漏えいのリスクが高まる
- 正しい人事評価が困難になる
1. 法的な罰則を受けるリスク
労働基準法では、法定労働時間を超えて労働を行わせた場合、企業側は必ず割増賃金を支払うよう義務づけられています。これに違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があり、違反企業として社名が公表されることもあります。
企業名が公開されることで社会的な信用が低下し、採用活動や取引先との関係にも悪影響を及ぼすことも。実際に、ブラック企業と見なされることで人材確保が困難になり、結果的に業績悪化につながることもあるのです。
2. 情報漏えいのリスクが高まる
自宅やカフェなど、オフィス以外の場所で仕事を続けることで、情報漏えいの危険が高まります。例えば、個人所有の端末で業務データを扱う場合、セキュリティ対策が不十分である可能性があります。
また、公共の場でパソコンを操作している際、画面をのぞき見されたり、Wi-Fi経由での情報流出が起きる危険もあるでしょう。
上記のような環境での作業により、顧客情報や企業の機密事項が外部に漏れると、企業は信用を失うだけでなく、法的責任を問われる可能性も出てきます。この場合の社会的な損失は計り知れません。
3. 正しい人事評価が困難になる
サービス残業が横行している職場では、正確な労働時間の把握が困難になります。実際にどれだけ働いたのかが明確でないと、評価の基準が曖昧になり、正しく業績を反映できません。
例えば、定時内に成果を上げている社員と、長時間働いている社員との区別がつかなくなると、評価が不公平になりかねません。この不公平感が蓄積すると、優秀な人材が離職する原因にもつながります。
また、育成計画の設計がずれ込み、組織全体のパフォーマンスにも悪影響を及ぼします。

企業側にとっても、サービス残業を放置することは大きなリスクなんですね。短期的な人件費削減どころか、長期的には大きな損失につながりそうです。
サービス残業は当たり前ではない

最後に、これまでの内容を踏まえて、大切なポイントをまとめておきましょう。
「みんなやっているから」「慣例になっているから」などの理由で、サービス残業を容認する考え方は、もはや通用しません。労働者には、正当な労働に対して報酬を受け取る権利がありますし、企業側にもその義務があります。
特に、自主的な残業であっても、会社側がそれを把握しながら何の対処もしていない場合は、黙認による違法行為と見なされる可能性があります。
また、「能力不足を理由に残業代を出さない」などの対応も、法的に認められない処置であることを理解しておきましょう。
一方で、社員が自分の意思でスキルアップのために行う学習や訓練などは、業務とは見なされないため、残業時間には含まれません。例えば、自宅で語学の勉強をしたり、業務に関する資格取得を自主的に目指す行動などは、あくまで個人の取り組みとされます。
サービス残業が当たり前とされてきた時代は、少しずつ終わりを迎えつつあります。
働く側の意識が変わり、企業側にも健全な労務管理が求められる今、声を上げることや正しい知識を持つことが、未来を変える第一歩です。

確かに、正しい知識を持って行動することで、働く環境は変えられるものなんですね。一人ひとりの意識から変えていくことが大切だと感じました。

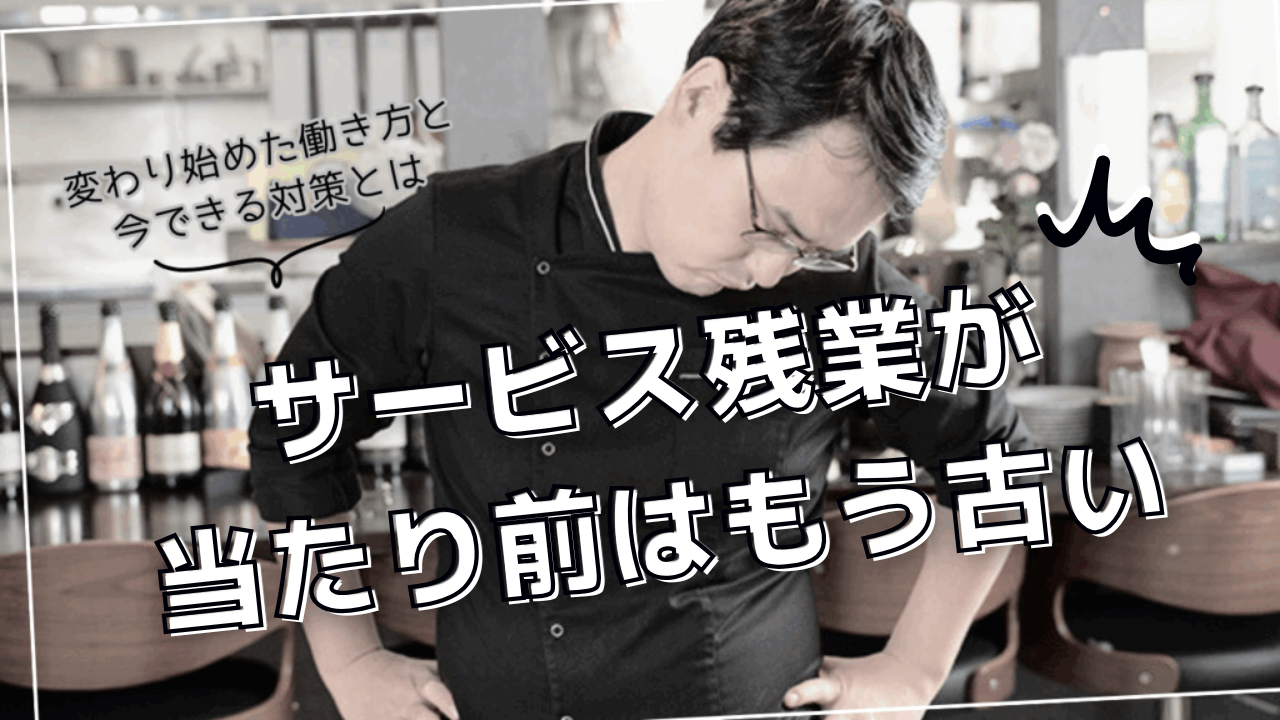

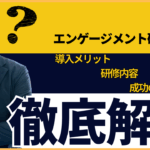
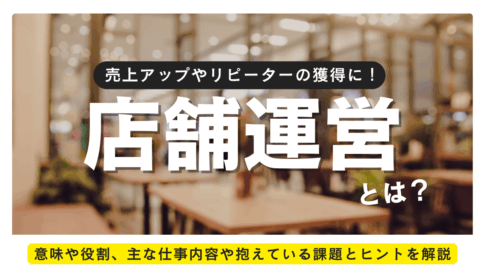
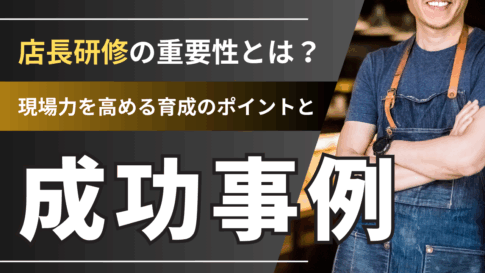
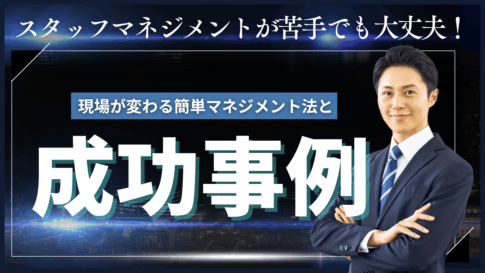

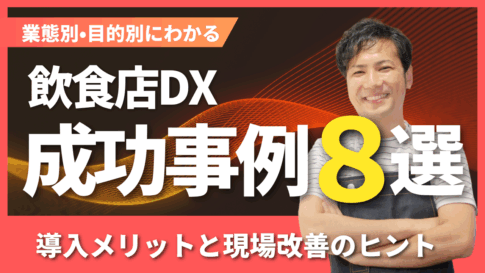


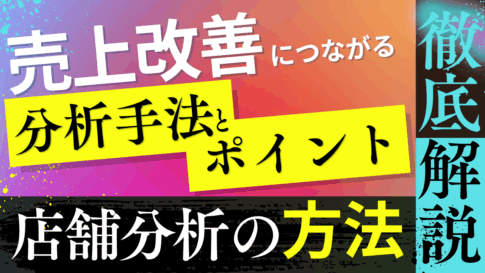



飲食店向け経営・DXコンサルタント
大手IT企業で飲食業界向けシステムの開発に携わった後、ITと現場のギャップを埋めるべく独立。現在は、個人店から多店舗展
開の企業まで、幅広い飲食店のDX推進をサポート。デジタル技術を駆使して、バックヤードの非効率な業務をなくし、従業員がより楽しく働ける環境を創り出すこと。そして、その結果として、お客様に最高の体験を提供できる店が増えることをミッションに活動中。