
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
ワークエンゲージメントを正しく測定することは、組織の生産性向上や離職率の低下に直結する重要な取り組みです。しかし「どの尺度を使えばよいのか?」「測定って実際どうやるの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、代表的な3つの尺度(UWES、MBI-GS、OLBI)の特徴や違いを徹底比較し、それぞれの質問項目や評価方法もわかりやすく解説します。自社の目的に合った最適な測定方法を選ぶための参考にしてください。

西野さん、最近多くの企業がワークエンゲージメントの測定に関心を持っていますが、どの尺度を選べばいいのか迷う声をよく聞きますね。

そうですね。満足度調査とは違って、従業員の意欲の深さを可視化する必要があるので、適切な測定方法を選ぶことが重要ですよね。
ワークエンゲージメントとは?測定が必要な理由

まずは基本から確認しましょう。ワークエンゲージメントが組織にとってどれほど重要な指標なのか、データとともに見ていきましょう。
ワークエンゲージメントとは、仕事に対して熱意や活力を感じ、没頭して取り組んでいる心理状態を指します。これは従業員のモチベーションや組織への愛着度を表す指標として、近年多くの企業が注目しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 離職率 | エンゲージメントが高い従業員は離職率が低い |
| 生産性 | エンゲージメントが高い従業員は生産性も高い |
| 組織パフォーマンス | 組織全体のパフォーマンス向上に直結 |
| 測定の意義 | 従来の満足度調査では把握できない「意欲の深さ」を可視化 |
従来の満足度調査では把握できない”意欲の深さ”を可視化する手段として、エンゲージメントの定期的な測定が不可欠になっています。
代表的な3つの測定尺度を比較

測定尺度って複数あるんですね。それぞれどんな特徴があるんですか?
ワークエンゲージメントを測定する際には、いくつかの信頼性の高い尺度が利用されています。代表的なものとして、「UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)」「MBI-GS(Maslach Burnout Inventory – General Survey)」「OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)」の3つがあります。
これらはそれぞれ測定項目や評価の観点が異なり、企業が測定目的に応じて選択する必要があります。
UWES(ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)とは

UWESは最も一般的に使われている尺度ですね。活力、熱意、没頭という3つの要素から、従業員のポジティブな状態を測定できます。
UWESは、最も一般的に使用されているエンゲージメント測定尺度です。「活力」「熱意」「没頭」という3つの側面から構成されており、従業員がどの程度エネルギッシュに働いているかを評価します。質問数は17問、9問、3問と用途に応じて選べる構成になっており、7段階評価でスコアを算出します。心理的なポジティブ要素に焦点を当てているため、従業員の”良い状態”を把握したい企業に向いています。
MBI-GS(Maslach Burnout Inventory – General Survey)とは

バーンアウトの測定尺度なのに、エンゲージメントも測れるんですね。逆説的な考え方が興味深いです。
MBI-GSは、元々はバーンアウト(燃え尽き症候群)を測定するために開発された尺度です。しかし、疲労感やシニシズム(冷笑)、職務効力感の3要素を含むことで、逆説的にエンゲージメントの状態も把握できます。評価は「まったくない」から「毎日ある」までの頻度で行い、スコアが低いほどエンゲージメントが高いと判断されます。エンゲージメントの低下リスクを早期に把握したい場合に有効です。
OLBI(Oldenburg Burnout Inventory)とは

OLBIは疲弊と離脱に着目した尺度です。問題の早期発見や課題の抽出を重視する組織に適しています。
OLBIは、「疲弊」と「離脱」という2つの側面から、仕事に対するネガティブな傾向を測定する尺度です。計16問で構成され、4段階評価でスコアを算出します。MBI同様に、スコアが低いほどエンゲージメントが高いとされ、心理的疲労や仕事からの心理的距離を測ることができます。ポジティブな側面よりも、問題点や課題の抽出に適しています。
測定手順と質問項目の具体例

実際の測定って、どんな手順で進めればいいんですか?質問項目の具体例も知りたいです。
ワークエンゲージメントの測定は、単に質問項目に回答させるだけでは不十分です。正確かつ継続的に実施することで、組織の実態が明確になります。まず、使用する尺度を選び、その質問票を用意し、従業員に匿名で回答してもらうのが基本的な流れです。
| 測定手順 | 詳細 |
|---|---|
| 1. 尺度の選定 | UWES、MBI-GS、OLBIから目的に応じて選択 |
| 2. 質問票の準備 | 選定した尺度の質問項目を用意 |
| 3. 回答の実施 | 従業員に匿名で回答してもらう |
| 4. 結果の集計 | 自動集計により平均点や分布を分析 |
| 5. 傾向の分析 | 組織全体や個人ごとのエンゲージメント傾向を把握 |
回答結果は自動集計され、平均点や分布によって組織全体や個人ごとのエンゲージメント傾向を分析できます。質問例としては「仕事に没頭していると感じる」「職場に貢献できていると実感する」など、主観的な感情や行動に関するものが中心です。
回答方法と評価スケール

評価スケールの違いは重要なポイントです。データの解像度や変化の追跡精度に直結しますからね。
各尺度によって評価スケールには違いがあります。UWESでは「まったくそう思わない(0点)」から「とてもそう思う(6点)」までの7段階、OLBIは4段階、MBI-GSは頻度ベース(例:月に数回~毎日)です。スケールの選定によって、データの解像度や変化の追跡精度が異なるため、目的に応じて選びましょう。また、組織内での導入においては、質問項目の説明や目的の共有が重要で、信頼できる回答を得るためには心理的安全性の確保が求められます。
スコアの解釈と改善アクションへのつなげ方

測定して終わりじゃなくて、そこからどう改善につなげるかが肝心ですよね。
測定後のスコアは、単なる数値ではなく「改善への出発点」として活用することが重要です。例えばUWESで平均スコアが4.0未満の場合、エンゲージメントが低いと判断され、チーム全体のモチベーション対策が求められるかもしれません。スコアはチームごと・個人ごとに分解して分析することで、優先的にフォローすべき対象を特定できます。改善策としては、1on1面談の実施や業務負荷の見直し、キャリア面談などが有効です。
目的に応じた尺度の選び方

目的が明確になれば、尺度の選定もスムーズになります。何を知りたいのかを整理することから始めましょう。
ワークエンゲージメント測定の目的が明確であれば、最適な尺度の選定もスムーズになります。たとえば、「従業員のポジティブな感情を可視化し、モチベーション向上につなげたい」場合はUWESが最適です。一方、「離職予兆や心理的疲労を早期に発見したい」ならMBI-GSやOLBIが効果的です。
また、スコアの定量分析だけでなく、定性的なフィードバックを得る場合には、サーベイ後の1on1や面談とセットで運用するのが望ましいです。組織の文化や人材戦略との親和性を考慮して、柔軟に選択・運用することが求められます。
効果的な測定には「みんなのマネージャ」の活用も

数ヶ月に一度の測定だと、変化の兆しを見逃しそうですね。もっと高頻度で測定できる方法があるんでしょうか?
従来のエンゲージメント尺度では、数ヶ月に一度の測定が主流で、変化の兆しを見逃しやすいという課題がありました。その点、「みんなのマネージャ」は、週1回のパルスサーベイをベースに、AIが回答状況から最適な頻度や質問内容を調整します。
| 機能 | 特徴 |
|---|---|
| パルスサーベイ | 週1回の高頻度測定で変化の兆しを早期発見 |
| AI調整機能 | 回答状況から最適な頻度や質問内容を自動調整 |
| 専門家監修 | メンタルヘルスとマネジメントの専門家による行動提案 |
| 属人化の回避 | フィードバックや支援が属人化せず、マネージャー育成にも貢献 |
| リアルタイム把握 | 組織全体のエンゲージメント状況をリアルタイムに把握 |

みんなのマネージャのフィードバック機能は、現場の心理的安全性づくりにかなり効きますよ。専門家監修の行動提案で属人化も避けられます。
さらに、メンタルヘルスとマネジメントの専門家監修による行動提案機能により、フィードバックや支援が属人化せず、店長やマネージャーの育成にも役立ちます。組織全体のエンゲージメント状況をリアルタイムに把握できるダッシュボード機能もあり、実行可能な施策につなげやすいのが大きな特長です。
まとめ

測定って、まずは”現場の声”をちゃんと拾うことから始まるんですね。そして継続的に改善していくことが大切だとよく分かりました。
ワークエンゲージメントは、単なる一時的な感情ではなく、組織の健全性を反映する重要な指標です。適切な尺度を選び、継続的に測定・改善を行うことで、従業員の定着率や生産性の向上につながります。目的に応じてUWES・MBI-GS・OLBIを比較し、自社に最適な方法を選択しましょう。もし「属人化せず、手軽かつ高頻度で測定したい」と感じたら、「みんなのマネージャ」のような支援ツールの活用もぜひ検討してみてください。

人を育てるって、”育てよう”と思った瞬間から始まるんですよね。エンゲージメント測定も、従業員一人ひとりの内発的動機づけを引き出すきっかけとして活用していただければと思います。

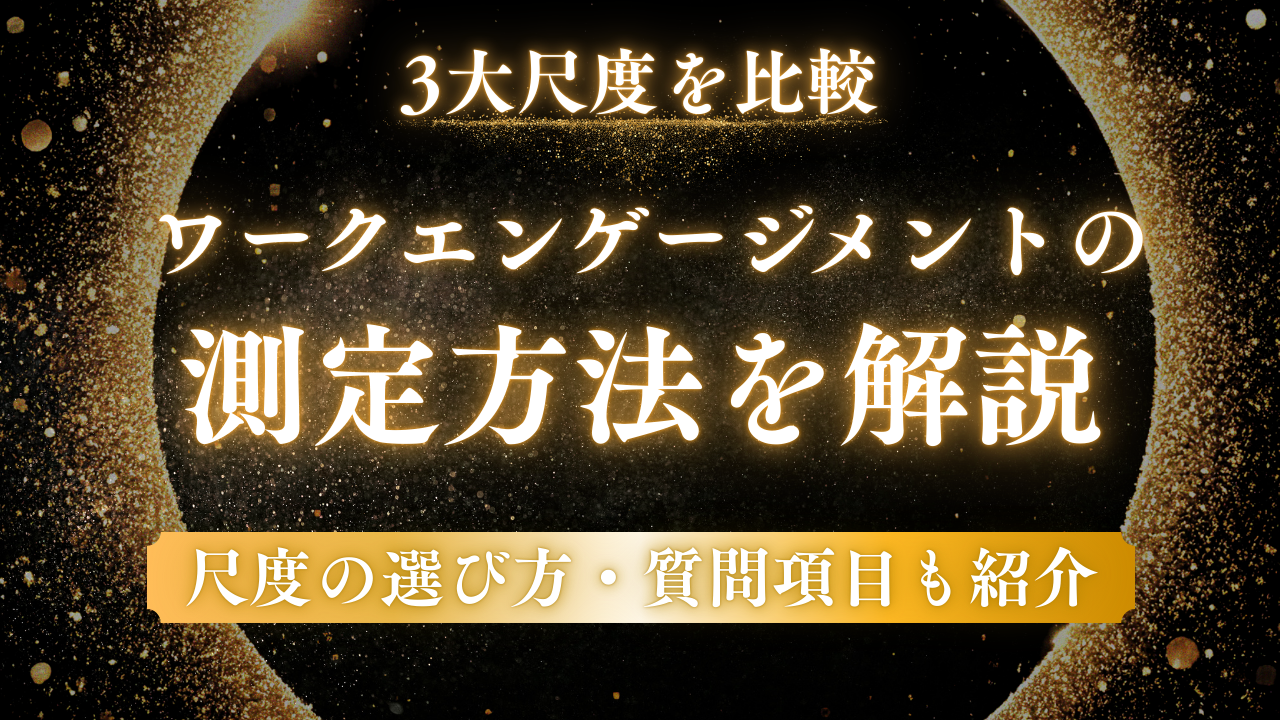
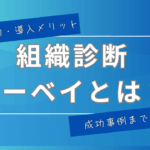
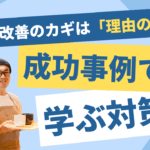
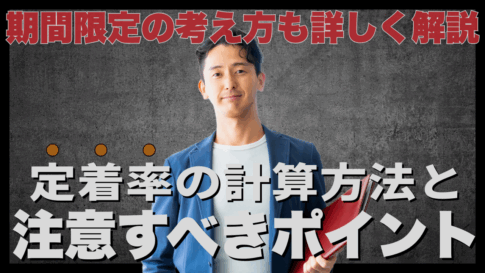

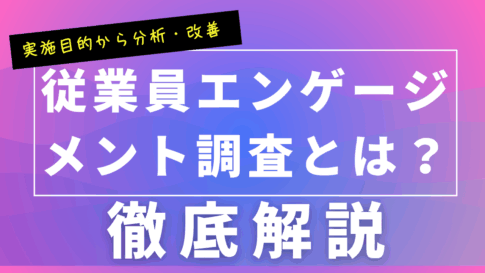

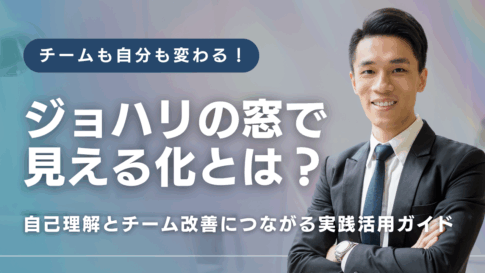


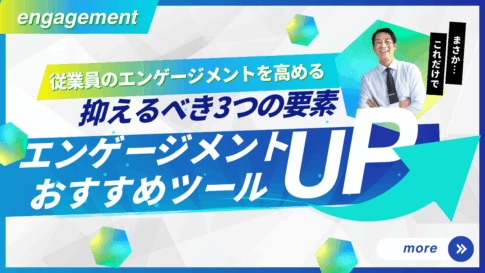



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。