
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
近年、多くの企業で「従業員エンゲージメント」の重要性が叫ばれています。その中でも特に注目されているのが「帰属意識」との関係性です。
帰属意識とは、従業員が「この組織の一員である」と実感し、組織の目標に対して主体的に貢献したいと感じる心理的なつながりのことです。帰属意識が高まることで、エンゲージメントも自然と向上し、離職率の低下や生産性の向上などの好循環が生まれます。
本記事では、帰属意識とエンゲージメントの関係性に焦点を当て、具体的な向上施策をご紹介します。
- 帰属意識とエンゲージメントの関係性
- 「従業員エンゲージメント」の重要性が叫ばれている理由
- 帰属意識を高める具体的な施策
帰属意識とは

西野さん、最近「帰属意識」について質問されることが多いのですが、まずは基本から整理してみましょうか。

はい、お願いします。帰属意識って言葉はよく聞くんですが、具体的にはどういうものなんでしょうか?
帰属意識とは、自分が特定の集団に属しており、その構成員であるという自覚や意識を意味します。この言葉は企業に限らず、国、学校、民族、スポーツチームなど、さまざまな組織やコミュニティに対して使用されるのが特徴です。
英語では「sense of belonging」と表現され、単なる物理的な所属以上に、心理的なつながりや一体感があることが含まれています。
帰属意識が高まると、人はその集団に対して愛着や関心を持つようになり、「ここが自分の居場所だ」という認識が強まります。そして「この集団の一員であり続けたい」と願う感情が生まれるのです。
なぜ帰属意識が重要視されているのか?

昔と比べて、なぜ今こんなに帰属意識が注目されるようになったんでしょう?

それは日本の雇用慣行の変化が大きく影響しているんです。終身雇用制度が変化した影響ですね。
近年、企業において「帰属意識」が注目されるようになった背景には、日本社会での終身雇用制度の変化があります。
高度経済成長期には、一つの会社で長期間働き続けることが一般的なキャリアパスとされており、この雇用慣行が日本経済を支える土台ともなっていました。
しかし、現在では経済のグローバル化が進み、労働市場も流動的になっています。それに加えて多様な働き方が広がり、転職が一般化したことで、一つの企業に生涯勤め続ける人の割合は減少傾向にあります。
企業側の課題
企業側にとって、社員の離職は深刻な課題です。新たな人材を採用し、戦力化するまでには多大なコストと時間がかかります。また、離職者が増えることで、社内に蓄積されたノウハウやスキルの継承が難しくなるリスクもあります。
このような状況の中、社員の帰属意識を高めることで、自社に愛着を持ち、長く働き続けてくれる人材の育成が重視されるようになってきました。
帰属意識を持つことで得られる利点

帰属意識が高まると、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか?

企業にとっても、働く人にとっても、どちらにもメリットがありそうですね。
社員が会社への帰属意識を高めることで、企業側にも社員自身にも多くの良い影響がもたらされます。主なメリットは以下の通りです。
まず、会社への愛着が芽生えた社員は、今の職場で長く働きたいという気持ちが強まります。さらに、帰属意識を持つことで「この組織の一員として役割を果たそう」という責任感が生まれ、業務にも主体的に取り組むようになります。
社員の定着が進めば、時間とともにその人が身につけたスキルや知識が組織内に蓄積され、全体として生産性が向上していくでしょう。
経営面でのメリット
また、人材が安定していれば、新たに採用活動や社員教育に費やすコストも削減でき、経営資源を他の重要なプロジェクトに回せるのもメリットです。
帰属意識が低下する原因とリスク

逆に、帰属意識が下がってしまう原因って何があるんでしょうか?

これは重要なポイントですね。原因を知ることで、予防策も立てられますから。
反対に、社員の帰属意識が希薄になると、次第に離職率が上がり、仕事への意欲も低下してしまいます。社内の人間関係がぎくしゃくしたり、業務ミスが増えるなどの悪影響も避けられません。では、どうして帰属意識が下がるのでしょうか。主な理由は以下の通りです。
まず、給与や待遇、評価制度に不満があると、社員の会社に対する満足度が下がりやすくなります。「努力しても正当に評価されない」「報酬が見合っていない」と感じることで、仕事への愛着やモチベーションが薄れ、転職を考えるきっかけになることも少なくありません。
また、社内でのコミュニケーションが不足している場合も、帰属意識は低下しがちです。特に最近ではリモートワークの普及によって、社員同士のちょっとした雑談や気軽な相談の場が減り、個々のつながりが希薄になっている企業も見受けられます。
理念共有の重要性
さらに、経営層と社員との間にビジョンや理念の共有がない場合も、社員が自分の仕事に意味を見出せず、「自分は何のために働いているのか」と疑問を抱くようになります。その結果、会社への一体感を持てず、自ら居場所を探して転職する社員が増える恐れがあるのです。
帰属意識を高めるための具体的な施策

では、具体的にどんな施策が効果的なのか見ていきましょう。

実際にクライアント企業で導入できそうな施策があると良いですね。
帰属意識の低下にはさまざまなリスクがあるため、企業側としては積極的に対策を取る必要があります。部署単位であれ、会社全体であれ、リーダー層が中心となって継続的に取り組むことが大切です。以下に有効な方法をご紹介します。
待遇や評価制度の見直し
給与や勤務条件に課題がある場合、可能な範囲で改善を検討しましょう。例えば、賃金の引き上げが難しい場合でも、フレックス勤務や短時間労働制度の導入、福利厚生の拡充など、社員が働きやすい環境を整える工夫はできます。
また、評価に関しては誰もが納得できる透明性のある基準を設けることが重要です。客観的な評価制度を導入すれば、たとえ結果が芳しくなくても社員は評価に対して理解しやすくなります。
次回への課題として前向きに受け止め、仕事へのモチベーションを高めることも期待できます。
社内コミュニケーションの促進
社員同士や社員と経営層との間で、日頃からコミュニケーションの機会を増やすことも、帰属意識向上には欠かせません。
そのための方法としては、チャットツールや社内SNSの導入が有効です。リアルタイムで情報交換や相談ができる環境を整えれば、自然と会話量も増えていきます。
フリーアドレス制を取り入れて席の固定をなくす
社員が気軽に集まれる「マグネットスペース」を社内に設ける
また、フリーアドレス制を取り入れて席の固定をなくすことや、社員が気軽に集まれる「マグネットスペース」を社内に設けるなど、オフィスレイアウトの工夫も効果が期待できます。
さらに、普段接点の少ない社員同士が交流できる社内イベントの開催や、1on1ミーティング、メンター制度の導入なども有効です。こうした取り組みにより、上下や横のつながりが強化され、組織としての一体感が生まれます。
インナーブランディングの推進

インナーブランディングって、具体的にはどのような取り組みなんでしょうか?

社内向けのブランディング活動ですね。企業理念やビジョンを社員に浸透させる取り組みです。
インナーブランディングとは、企業理念やブランド価値を社員に深く浸透させる社内向けの取り組みです。この活動を通して、社員は会社への理解や共感を深めていきます。
経営陣が自らビジョンや理念を積極的に発信し、全社的に共有することで、経営層と社員との意識のズレを解消し、全員が同じゴールに向かって進める環境が整います。
社員が企業の目標や価値観に共感すれば、「自分もこの会社で頑張りたい」という気持ちが自然と芽生えるでしょう。
エンゲージメントとの違い

ここで、帰属意識と混同されがちな「エンゲージメント」についても整理しておきましょう。

確かに、よく似た概念だと思っていました。違いがあるんですね?
従業員エンゲージメントとは、社員が自ら会社に対して貢献しようとする意欲や、主体的に業務へ取り組む姿勢のことです。「エンゲージメント(Engagement)」の言葉自体は、英語で「約束」「誓約」「関与」「没頭」などの意味を持っています。
日本ではこの言葉が、マーケティング分野と人事・組織開発分野でそれぞれ異なる使われ方をしています。
顧客が企業、ブランド、サービス、または商品に対して抱く愛着心や、その愛着が行動として現れることを「エンゲージメント」と呼ぶのが特徴です。例えば、SNSでは「いいね」やコメント、シェアといったアクションがその代表例です。
まずマーケティングの文脈では、顧客が企業、ブランド、サービス、または商品に対して抱く愛着心や、その愛着が行動として現れることを「エンゲージメント」と呼ぶのが特徴です。例えば、SNSでは「いいね」やコメント、シェアといったアクションがその代表例です。Webサイト運営でも、閲覧数や滞在時間などが顧客エンゲージメントを示す指標となります。
一方で、人事領域で使われる「従業員エンゲージメント」は、企業と社員の心理的なつながりや、仕事への前向きな姿勢、会社への愛着度などを表す言葉です。組織の活性化や生産性向上などの観点から、経営層や人事担当者の間で重視されるようになっています。
なぜ今「エンゲージメント」が注目されているのか?

エンゲージメントが注目される背景も、帰属意識と似ているんでしょうか?

そうですね。特に2つの大きな社会的変化が影響しています。
近年、日本国内において「従業員エンゲージメント」が強く注目されるようになった背景には、いくつかの社会的変化があります。とくに次の2つが大きな要因とされています。
人的資源の重要性が急激に高まっている
日本の総人口は長期的に減少傾向にあり、将来的には1億人を下回る予測まで出ています。この流れに伴い、労働力人口も減り続けており、企業にとって「人材の確保と維持」が喫緊の課題となっています。
さらに、転職市場の活発化により人材の流動性がかつてないほど高まっていることも無視できません。従来の終身雇用制度が崩れつつある中、優秀な人材をいかにして流出させないか、また採用した社員が長く戦力として活躍できるようにするかが、企業経営で大きなテーマとなっています。
上記の背景から、社員一人ひとりの会社への愛着や貢献意欲を数値化・可視化する「従業員エンゲージメント」の重要性がますます高まってきているのです。
働き方の多様化と主体性の必要性

働き方の変化も大きな要因なんですね。具体的にはどのような変化でしょうか?

社会全体がダイバーシティを重視するようになったことで、従来のマネジメントスタイルでは対応しきれなくなったんです。
もう一つの大きな理由は「働き方の変化」です。
社会全体がダイバーシティを重視する方向へ進む中、企業も多様な価値観やライフスタイルに対応することが求められています。情報量の爆発的増加、テクノロジーの進化、グローバル化など、社会構造そのものが以前とは大きく様変わりしました。
これにより、従来のような「上司が指示を出し、部下がそれに従う」という一方向のマネジメントスタイルでは、企業の競争力を維持できなくなっています。状況に応じて柔軟に動ける組織づくりが求められる中で、社員一人ひとりの「自発的な行動力」や「主体性」が重要視されるようになってきました。
そのため、企業は社員が自社の理念や目標に共感し、主体的に業務に取り組める環境づくりに力を入れているのです。
エンゲージメントを高めるための具体的な施策

では、実際にエンゲージメントを高めるための施策を見ていきましょう。

帰属意識向上の施策とは、どこが違うのでしょうか?
ここでは、エンゲージメントを高めるための具体的な施策をみていきましょう。
現状課題の分析と施策の検討
組織として取り組むべき改善ポイントが特定できたら、次は具体的なアクションプランに落とし込みます。例えば、従業員が「自身の評価に納得できない」「仕事へのやりがいを感じづらい」などの課題がある場合は、評価制度の見直しや、成果を称える仕組みとして「ピアボーナス制度」などの新制度導入が効果的です。
また、「企業理念やビジョンに共感できない」の声が多い場合には、理念浸透のための研修や、社員参加型のビジョンワークショップを開催することも有効です。
公正で納得感のある評価制度
従業員が主体的に行動しても、それが正当に評価されなければ、次第に意欲は低下していきます。社員の努力や成果がきちんと認められる評価制度の構築は、エンゲージメント向上の基本です。
特に、自発的な行動や挑戦が評価対象となるような評価項目を設けることで、社員のモチベーションを維持しやすくなります。
経営理念とビジョンの社内浸透
エンゲージメント向上には、経営理念や企業ビジョンの共有が欠かせません。従業員が「自分の仕事が企業全体の目標達成にどうつながっているのか」を明確に理解できることが、エンゲージメント向上の大きなカギとなります。
さらに、組織が目指すゴールと従業員一人ひとりのキャリア目標や価値観が重なる部分が見つかれば、より強い共感が生まれます。
マネジメントスタイルの見直し

マネジメントの見直しというのは、具体的にはどのような点を変えるべきでしょうか?

指示・命令型から、部下の自主性を重視するスタイルへの転換が重要ですね。
従業員が自主的に動きたい意欲を持っていても、管理職側のマネジメントがそれを阻んでいては意味がありません。もちろん、業務指示や報告・連絡・相談の徹底は必要ですが、同時に、部下が自分で考え、行動できる裁量や環境を与えるマネジメント手法が求められます。
適切なフォローと信頼関係のバランスが大切です。
チームとしての結束力を強める
企業の目標は、個人の力だけでは達成できないことがほとんどです。そのため、メンバー間の協力体制は不可欠です。
チームビルディングを通して、目的意識を共有し、それぞれの役割を明確にすることで、一人ひとりが自分の仕事に対して価値を感じられるようになります。
職場内コミュニケーションの活性化
従業員エンゲージメントを高めるには、職場の人間関係も大きな影響を与えます。良好な人間関係は、働く上での安心感や信頼感につながり、従業員が積極的に発言し行動できる環境づくりの土台となります。
風通しの良い職場環境を作ることで、社員一人ひとりが主体性を発揮しやすくなるでしょう。
キャリア成長の仕組みづくり
従業員の理想とするキャリアパスが、現在の業務の延長線上にしっかり描けるかどうかも、エンゲージメントに大きく関わります。転職が一般化した今、「この会社で働き続けることで自分がどのように成長できるのか」を明確に示すことが重要です。
社内でのステップアップの道筋を可視化し、キャリアに関する情報をオープンにすることで、社員の安心感や将来への期待感が高まります。
従業員の満足度を上げることが帰属意識を高めるポイント

最後に、帰属意識とエンゲージメントの関係性についてまとめてみましょう。

この2つは密接に関係しているということですね。どちらも従業員満足度が基盤になっている気がします。
従業員のエンゲージメントを高めるためには、「帰属意識」の向上が欠かせません。理念浸透や職場のコミュニケーション活性化、公正な評価制度など、日々の取り組みがその土台をつくります。
従業員一人ひとりが「この会社で働いて良かった」と実感できる環境づくりが、結果として企業全体の成長につながります。ぜひ、自社に合った施策を見つけ、帰属意識とエンゲージメントの向上を目指していきましょう。

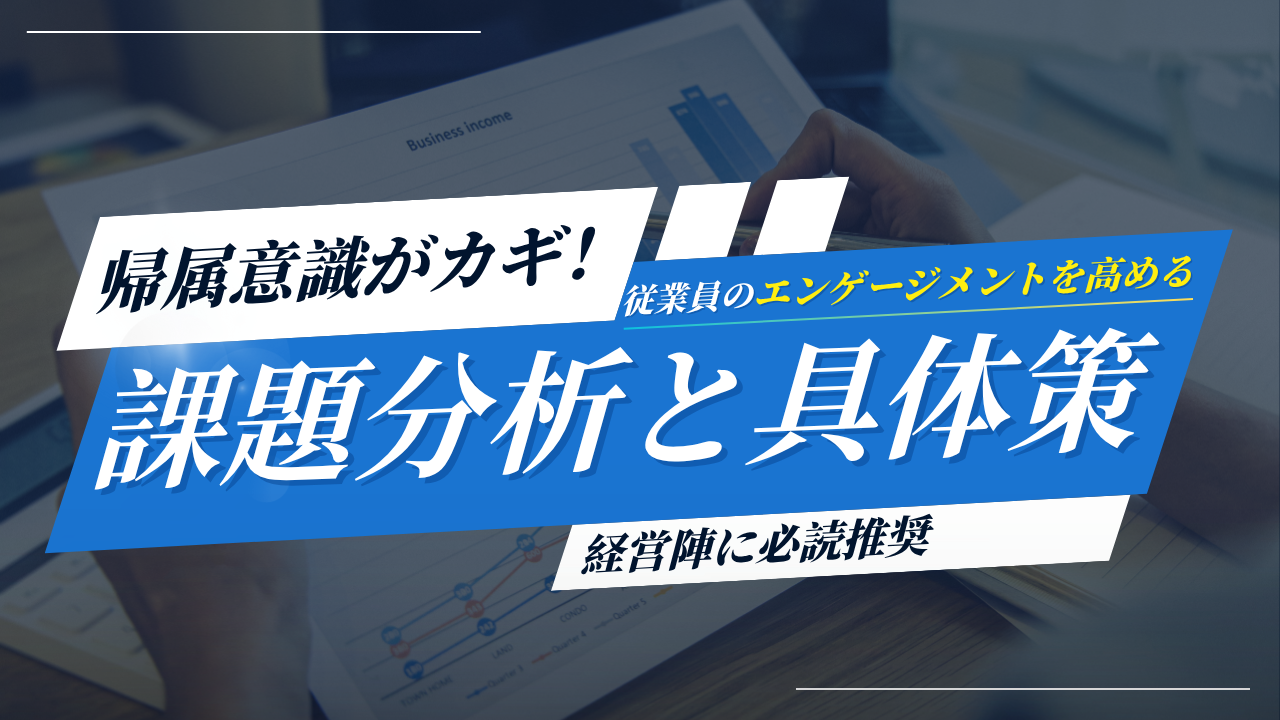
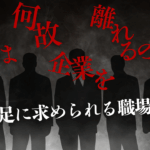
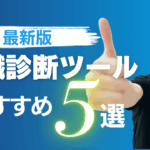

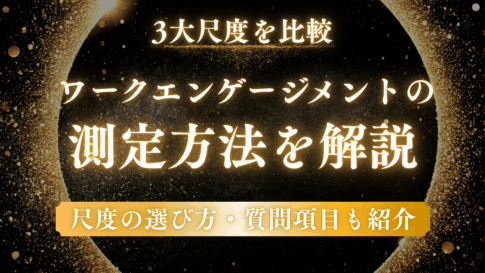



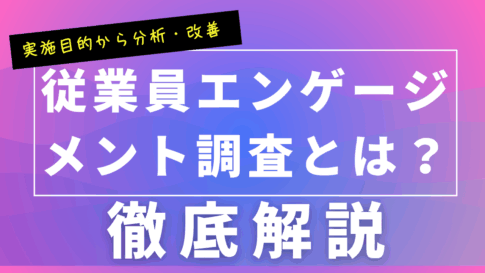

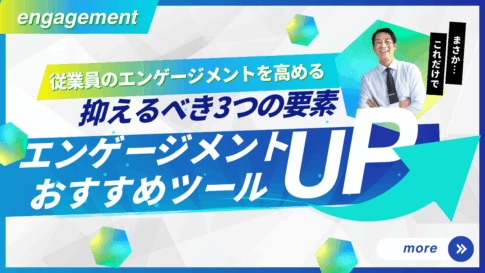



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。