
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
従業員のモチベーションや定着率に深く関係する「エンゲージメント」。この目に見えにくい組織の健康状態を把握する手段として、多くの企業が取り組み始めているのが「従業員エンゲージメント調査」です。 しかし、「どのように実施すればいいのか分からない」「結果をどう活かせばよいのか悩んでいる」という声も少なくありません。本記事では、日本企業におけるエンゲージメントの現状から、具体的な調査方法、分析・活用のポイント、そして形骸化を防ぐための最新ツール「みんなのマネージャ」の事例までを分かりやすく解説します。
従業員エンゲージメントとは?調査の前に知っておきたい基本知識

エンゲージメントというと、何だか難しく聞こえるかもしれませんが、要は「社員がどれだけ会社を愛し、熱意を持って働いているか」を測る指標なんです。

単なる満足度とは違って、「もっと貢献したい」という気持ちが大切なんですね。それを調査で把握するのが今回のテーマですね。
従業員エンゲージメントとは、社員が自社に対してどれだけの愛着や熱意を持ち、主体的に業務へ取り組んでいるかを示す概念です。単なる満足度や働きやすさとは異なり、「組織に貢献したい」という自発的な姿勢を測るのがポイントです。
このエンゲージメントが高いと、離職率が下がるだけでなく、生産性や顧客満足度の向上にもつながります。最近では、エンゲージメントの状態を把握し、組織課題を可視化するための「調査」が多くの企業で注目されています。調査を通じて現場の声を拾い上げ、改善の起点とすることが、組織の持続的な成長において非常に重要になっています。
エンゲージメントの定義とビジネスへの影響

エンゲージメントが高い企業では、業績や顧客満足度が明らかに向上します。データを見ると一目瞭然ですよ。
エンゲージメントは、社員が「この会社で働き続けたい」「もっと役に立ちたい」と感じる心理的な結びつきです。近年の研究では、エンゲージメントの高い企業ほど、業績や顧客満足度が高く、離職率が低いという傾向が明らかになっています。
| 項目 | エンゲージメント高い企業 | エンゲージメント低い企業 |
| 業績 | 向上傾向 | 低迷傾向 |
| 顧客満足度 | 高水準 | 低水準 |
| 離職率 | 低い | 高い |
| チーム協力体制 | 強化される | 弱い |
| 目標達成率 | 高い | 低い |
たとえば、エンゲージメントスコアが高い部署では、チームの協力体制が強化され、目標達成率も高まるという結果が多く報告されています。つまり、組織全体の成果を高めるためには、従業員のエンゲージメント状態を把握し、適切なアクションをとることが欠かせません。
なぜ今「調査」が必要とされているのか

テレワークが普及して、マネージャーが現場の状況を把握するのが本当に難しくなりましたよね。だからこそ調査が重要なんですね。
テレワークの普及や価値観の多様化により、従業員の働き方や職場への期待も大きく変化しています。その結果、マネジメント層が現場の状況を把握しきれず、離職やパフォーマンス低下の兆候を見逃すケースが増えています。
現代の職場環境の変化要因
こうした背景から、従業員の状態を定期的に可視化する「エンゲージメント調査」のニーズが急速に高まっています。特に、早期の課題発見と適切なフォローを実現するためには、調査結果をリアルタイムに活用できる体制が重要です。
日本企業におけるエンゲージメントの現状とは

日本のエンゲージメント水準は、国際的に見ると残念ながら非常に低いのが現実です。これは我々コンサルタントとしても重要な課題だと認識しています。
日本では従業員エンゲージメントの重要性が徐々に認知されてきているものの、国際的に見るとその水準は依然として低い傾向にあります。特に、指示待ち型の労働文化や、年功序列による評価制度が根強く残る企業では、主体的に働く環境が整っていないことが一因です。
日本企業の課題要因
• 指示待ち型の労働文化の定着
• 年功序列による評価制度の根強い残存
• 主体的に働く環境の不整備
• マネジメント層の関与不足
また、マネジメント層の関与が不足していることも、社員の心理的なつながりを弱めている要因です。エンゲージメント調査を通じて、これらの課題を可視化し、どのような施策が有効なのかを分析することが、日本企業にとって今後の組織強化に欠かせません。
国内調査データから読み解く日本のエンゲージメント水準

6~10%という数字は本当に衝撃的ですね。グローバル平均の3分の1以下って、改善の余地が大きいということでもありますが…
国内で実施された大規模なエンゲージメント調査によると、日本の従業員のうち「エンゲージメントが高い」とされる人の割合は、おおよそ6~10%程度とされています。これはグローバル平均の3分の1以下にあたり、極めて低い水準です。
| 地域 | エンゲージメント高い従業員の割合 |
| 日本 | 6~10% |
| グローバル平均 | 約30% |
| アメリカ | 約30% |
特に若年層では、キャリア成長や職場の人間関係に不満を感じやすく、エンゲージメントの低下が顕著です。こうした傾向を把握し、改善に向けた打ち手を検討するためにも、定期的なエンゲージメント調査の実施が求められています。
欧米との比較で見える日本の課題

欧米では1on1ミーティングが当たり前に行われていますが、日本ではまだまだ普及していない。この差が如実に表れているんです。
欧米諸国と比較すると、日本のエンゲージメントの低さは際立っています。たとえばアメリカでは、従業員の約30%が高いエンゲージメントを示しているのに対し、日本は10%を下回るケースが一般的です。
この背景には、業務に対する自律性の不足や、経営層との対話の機会が少ないことなどが挙げられます。欧米では1on1ミーティングやパルスサーベイの活用が進んでおり、こうした仕組みを取り入れることで、エンゲージメント向上に成功している企業が増えています。
従業員エンゲージメント調査の実施方法

調査手法ってたくさんあるんですね。企業によって最適な方法が違うというのは興味深いです。
エンゲージメントの状態を正確に把握するためには、調査の設計と運用方法が極めて重要です。一般的にエンゲージメント調査には、定期的に短時間で回答できる「パルスサーベイ」や、年次で実施する大規模なサーベイなどがあります。
| 調査手法 | 実施頻度 | 設問数 | 特徴 |
| パルスサーベイ | 週次・月次 | 少ない | 短時間・高頻度・タイムリー |
| 年次サーベイ | 年1回 | 多い | 網羅的・詳細分析・長期視点 |
企業の目的や組織規模によって適した手法は異なるため、自社の課題や文化に合った形式を選定することが大切です。また、調査は実施するだけでなく、集計・分析、フィードバックまでをセットで考えることで、改善施策への落とし込みが可能になります。
代表的な調査手法(パルスサーベイ、年次サーベイなど)

パルスサーベイの魅力は、何といってもタイムリー性です。変化にすぐ気づけるのが大きなメリットですね。
パルスサーベイは、週次や月次といった高頻度で実施されるアンケート形式の調査です。少ない設問数で短時間に回答できるため、従業員の負担が少なく、タイムリーなデータ取得が可能です。
各調査手法の特徴比較
一方、年次サーベイは設問数が多く、網羅的に組織全体の状態を把握するのに適していますが、変化への即時対応には向きません。近年では、両者を組み合わせて活用する企業が増えており、定点観測と詳細分析の両方を実現しています。
設問設計のポイントと回答率を上げる工夫

設問を具体的な行動に基づいて作るのは重要ですね。曖昧だと回答者も困ってしまいますし、データの信頼性も下がってしまいます。
エンゲージメント調査の効果を高めるには、設問の質と回答率がカギとなります。まず、設問は曖昧な表現を避け、従業員が直感的に理解しやすい内容にすることが重要です。
効果的な設問設計のポイント
• 曖昧な表現を避ける
• 具体的な行動に基づいた設問にする
• 直感的に理解しやすい内容にする
• 回答者の心理的負担を軽減する
たとえば、「上司との関係に満足している」ではなく、「上司は私の意見を尊重してくれる」のように、具体的な行動に基づいた設問が有効です。また、匿名性の確保やフィードバックの約束、結果の透明性を担保することで、従業員の信頼を得て、回答率を高める工夫が求められます。
調査結果の活用法と改善へのつなげ方

調査は実施するだけでは意味がありません。結果をどう分析し、具体的な改善行動に落とし込むかが、調査を成功させる鍵です。
エンゲージメント調査は実施するだけでは意味がありません。得られた結果をいかに分析し、具体的な改善行動へと落とし込むかが、調査を成功させる鍵です。調査結果を正しく読み解くことで、組織の中で何が問題となっているのかを特定し、優先的に対応すべき課題を見つけ出せます。
結果の分析と課題の特定
優先度の高い課題の選定
具体的な改善施策の設計
実行とフォローアップ
そして、それを基に適切な打ち手を設計・実行していくことが、従業員エンゲージメント向上への第一歩となります。
課題の特定と打ち手の考え方

多角的に分析するのが大切なんですね。部門ごとや職種ごとに違いがあるというのは、現場で実感することがあります。
調査結果の分析では、単にスコアの高低を見るだけでなく、部門間や職種間のギャップ、時系列での推移など多角的に把握することが重要です。
| 分析視点 | 確認内容 | 期待効果 |
| 部門間比較 | 部署ごとのスコア差 | 課題部署の特定 |
| 職種間比較 | 職種ごとの傾向 | 職種特有の課題発見 |
| 時系列推移 | 経年変化の確認 | 改善効果の測定 |
| 属性別分析 | 年齢・性別・勤続年数別 | セグメント課題の把握 |
たとえば、「職場の心理的安全性が低い」といったスコアが出た場合、その原因が上司とのコミュニケーション不足なのか、評価制度への不満なのかを掘り下げることで、打ち手が明確になります。その際、現場の声を尊重し、関係者とともに施策を設計することで、実効性の高い改善につながります。
継続的な改善サイクルをどう構築するか

継続的な改善サイクルが根づくことで、エンゲージメントの高い組織文化が形成されていくんです。これが理想的な状態ですね。
調査は1回限りではなく、継続的な実施とフィードバックのサイクルを構築することで効果を発揮します。たとえば、四半期ごとにサーベイを行い、改善施策を実施→効果測定→再度サーベイという流れを繰り返すことで、組織は着実に変化していきます。
特に、調査結果を全社員にフィードバックし、改善に向けた取り組みの進捗を可視化することで、従業員の参加意識も高まります。このようなサイクルが根づくことで、エンゲージメントの高い組織文化が形成されていきます。
調査の形骸化を防ぐ「みんなのマネージャ」の活用事例

調査の形骸化って本当によく聞く課題ですね。せっかく時間をかけてアンケートに答えても、何も変わらないとがっかりしてしまいます。
従業員エンゲージメント調査は、ただ実施するだけでは意味がありません。課題の一つは「形骸化」です。定期的にアンケートを配信していても、結果を活用できていない、改善につながらない、従業員が本音を言わなくなる——こうした事態を防ぐためには、仕組みと運用の両面での工夫が必要です。
調査の形骸化を防ぐ要素
• 結果の適切な活用
• 改善施策への確実な落とし込み
• 従業員の本音を引き出す仕組み
• 継続的な運用体制の構築
そこで注目されているのが、サーベイの実施から分析・改善支援まで一貫してサポートする「みんなのマネージャ」です。高頻度かつ個別最適化された調査機能や、マネージャー向けの行動提案機能を通じて、形骸化を防ぎ、エンゲージメント改善を実現します。
AIによる個別最適化で調査精度を向上

みんなのマネージャのAI機能は、個別最適化がポイントです。従業員一人ひとりに合わせたアプローチができるのが魅力ですね。
「みんなのマネージャ」は、AIを活用して従業員一人ひとりの状態に応じてアンケートの頻度や内容を調整できるのが特徴です。
| 機能 | 内容 |
| 個別最適化 | 従業員の状態に応じた設問調整 |
| 高頻度実施 | 週1回のサーベイ実施 |
| 早期察知 | メンタル状態の変化を迅速に把握 |
| リアルタイム対応 | 即座の状況把握と対応 |
例えば、メンタルの状態に問題が見られる従業員には、設問を増やしたり、サーベイ頻度を高めることで早期の異変察知が可能になります。また、週1回という高頻度での実施により、従業員のちょっとした変化にも迅速に対応できます。これにより、従来の「数か月に1回」のサーベイでは拾えなかった重要な兆候を見逃さずに済み、組織全体のエンゲージメント向上へとつながります。
サーベイ結果を「行動」に落とし込む支援機能とは

結果を見ても何をすればいいか分からないって、管理職の方からよく聞きます。具体的な行動提案があるのは心強いですね。
調査の結果を見ても「で、何をすればいいのか分からない」という悩みは、管理職にとって非常に多いものです。「みんなのマネージャ」では、専門家監修によるAIアクションリストを搭載しており、各従業員に対して取るべきアクションを明示してくれます。
行動支援機能の特徴
さらに、フィードバックの伝え方や言葉の選び方までアドバイスされるため、フィードバックスキルに不安のあるマネージャーでも迷わず対応できます。こうした一貫した支援により、調査が「現場で実行される行動」に変わり、形骸化することなく改善サイクルが回るのです。
まとめ

エンゲージメント調査は、単に実施することが目的ではありません。社員一人ひとりの声を拾い上げ、組織全体の改善に役立てることが本質なんです。
従業員エンゲージメントの調査は、単に「実施すること」が目的ではありません。社員一人ひとりの声を拾い上げ、現場の状態を可視化し、組織全体の改善に役立てることが本質です。
特に日本企業では、エンゲージメントの水準が国際的に見て低いため、調査による実態把握と継続的な改善活動が強く求められています。そのためには、調査手法の選定、設問設計、そして結果の具体的な活用まで、一貫した運用が重要になります。

みんなのマネージャのようなツールがあると、調査が形骸化せずに本当に組織改善につながりそうですね。これからが楽しみです。
「みんなのマネージャ」のように、AIを活用して調査精度を高め、マネージャーへの行動提案までを自動で支援する仕組みを取り入れることで、調査の形骸化を防ぎ、効果的な改善が可能になります。単なるアンケートに終わらせない、エンゲージメント向上のための実践的なツールとして、今後ますますその存在が注目されていくでしょう。

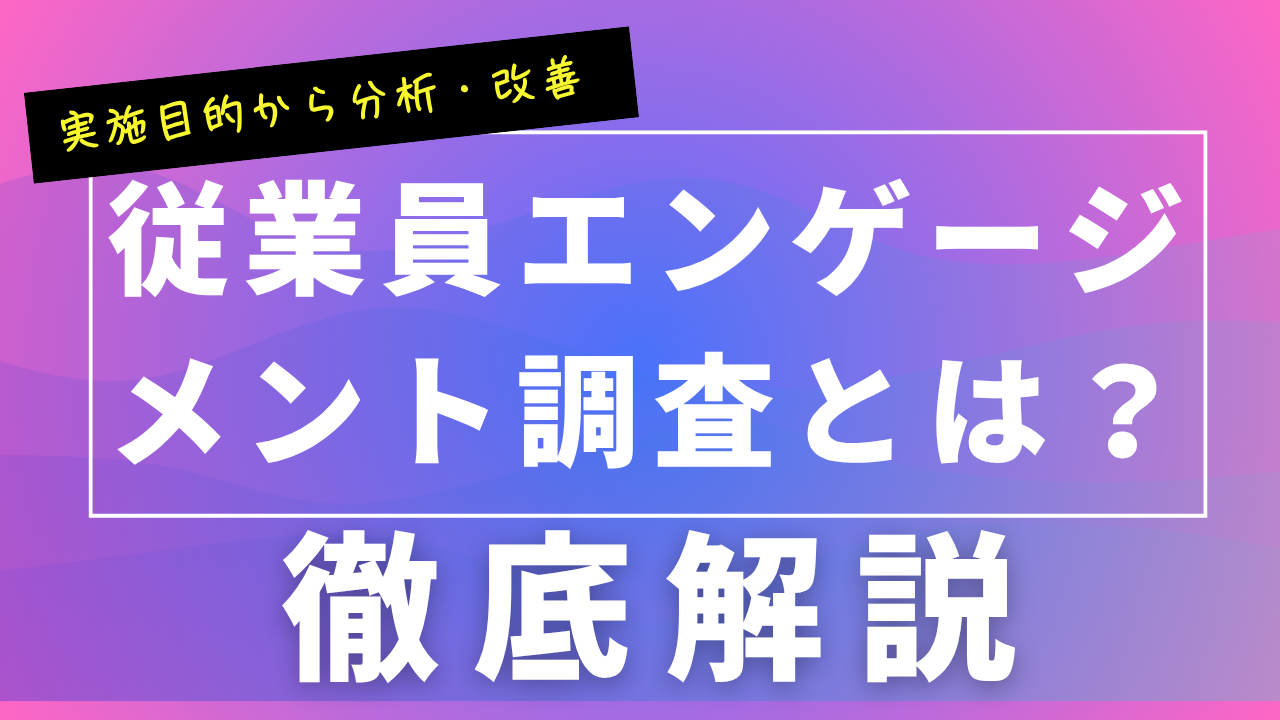
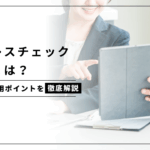
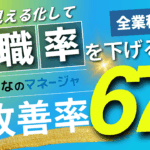





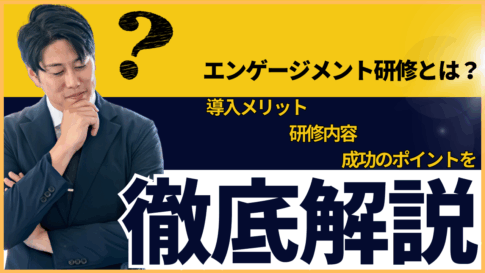

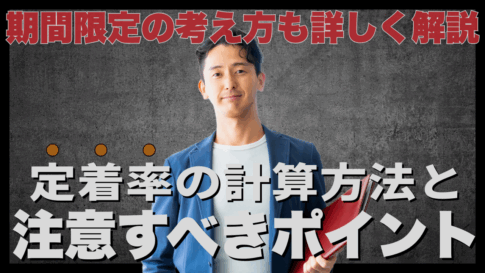



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。