
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「せっかく採用しても、すぐに辞めてしまう…」
そんなお悩みを抱えていませんか?社員の定着率の低下は、人材不足や採用コストの増大だけでなく、職場の生産性や士気にも深刻な影響を与えます。
この記事では、定着率が下がる原因を明らかにし、そのうえで改善に効果的な7つの具体的施策をわかりやすく紹介します。実際の成功ポイントや、最新のマネジメント支援ツール「みんなのマネージャ(みんまね)」の活用方法まで解説しているので、自社の人材定着に向けた取り組みをすぐに始めたい方に必見の内容です。
- なぜ定着率が低いと問題なのか
- 改善するための施策
- 定着率の改善に役立つツールとその理由
定着率の改善が急務な理由とは?
人材の定着率は、企業の安定的な成長を支える基盤のひとつです。
採用にかかるコストや育成に要する時間は膨大で、定着率が低いとそれらが何度も繰り返される非効率な状況になります。定着率の低さは職場の雰囲気やモチベーション低下にも繋がり、残された従業員への負荷も増大します。

制度だけでなく、社員一人ひとりの“内発的動機づけ”を引き出す仕組みが必要なんです。定着率の改善は、単なる人事施策ではなく“経営戦略”と捉えてください。
反対に、定着率が高い企業は人材が育ちやすく、業務の効率化やイノベーションの創出にもつながります。定着率を改善する取り組みは、単なる人事課題にとどまらず、経営全体にとって極めて重要な戦略的テーマと言えるのです。
企業の生産性・業績に直結する
定着率が高くなれば何がいいのでしょうか? 人が辞めないのであれば、知識や経験は蓄積され続けていきます。つまり以下のような点が考えられるのです。
- 教育コストが抑えられ、業務の質が安定する
- 経験者がノウハウを伝えることで、チーム全体のスキルが向上する
- クオリティの高い業務成果によって顧客からの信頼感が増し、満足度の向上につながる

この前のインタビューでも、“同じチームで3年以上働いている人がいると、お客様との信頼関係もスムーズに築ける”って言われてました!人が続けてくれることって、外からの印象にもすごく影響してるんですね。
知識・経験が豊富な人材が増えれば業績向上につながり、ひいては会社全体の利益の底上げにもなります。
このように、定着率の改善は業績向上への投資としても非常に効果的です。たかが定着率と考えてしまいがちですが、人が辞めるのは想像以上の損失なのです。
離職コストの増大と人材確保難の背景
近年の採用難の中、離職コストは企業にとって重い負担です。
中途採用や新卒採用にかかる費用は年々増加しており、育成期間を経て定着しない場合、そのコストは未回収になってしまいます。

その人事施策、現場の“納得感”まで落とし込めていますか? 採用に力を入れるだけでは不十分で、入社後の環境と支援が整っていないと“投資が無駄”になる可能性も高いのです。
さらに人材が定着しない職場は、「辞めやすい」印象を持たれ、人材募集が困難になることも。こうした悪循環を断ち切るためには、定着率改善のための根本的な対策が必要です。
定着率が低下する主な原因
定着率が低下する背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
表面的には待遇や給与の不満が理由とされがちですが、実際には「職場環境」「人間関係」「成長実感の欠如」など、働く人の心理や体験に深く関わる要素が多く挙げられます。特に近年は、働き方の多様化により従来のマネジメントや支援方法が機能しづらくなり、従業員一人ひとりに寄り添った環境整備が求められます。
まずは、こうした要因を正しく把握することが、改善への第一歩です。

私も転職してきたとき、“給与”よりも“人間関係”とか“働きやすさ”のほうがずっと気になってました。やっぱり、毎日顔を合わせる環境ってすごく大事ですよね。
職場環境や人間関係の悪化
社員が退職を考えるきっかけとして最も多いのが「人間関係のストレス」です。
上司や同僚とのコミュニケーションが不足し、孤立感や不安を感じることでモチベーションが下がり、離職につながってしまいます。また、職場の雰囲気が悪くなることで心理的安全性が失われ、本音を言いにくい環境が形成されます。

数字も大事ですが、面談時の“表情の変化”を見逃さないようにしてください。言葉にされないサインこそが、離職の兆候であることが多いんです。
このような環境では、小さな不満も蓄積されやすく、結果として高い離職率につながるのです。ですから、風通しの良い職場を作ることが、定着率改善の土台となります。
不透明な評価制度とキャリアパスの不在
自分の努力がどう評価されるのかが見えにくい職場では、やりがいや将来の展望が持てず、離職を考えやすくなります。
また、昇進や成長のための明確な道筋がないと、働く意味を見失ってしまう人も少なくありません。評価制度が属人的であったり、基準が曖昧な場合には特に注意が必要です。

この前、“自分がどこを目指せばいいのか分からない”って話してた社員さんがいて…。キャリアの地図がないまま頑張るのって、やっぱり不安なんですよね。
公平で納得感のある評価体制とキャリア支援の仕組みを整えることで、社員のモチベーションと定着率の両方を高めることが可能になります。
育成体制やコミュニケーションの不足
新人や若手社員に対する教育・育成が不十分だと、「放置されている」と感じてしまい、早期退職の要因になります。
また、日常的な対話や相談の機会が少ないと、悩みを抱え込んでしまうケースも増えます。こうした問題は特に現場任せの運営がされている職場で起こりやすく、意図しない離職を招いてしまいます。

人を育てるって、“育てよう”と思った瞬間から始まるんですよね。現場任せではなく、組織としての“育成の意思表示”が必要です。
継続的な1on1やフィードバックの機会を設けることで、信頼関係の構築と早期離職の防止が期待できます。
定着率を改善する7つの施策
定着率を向上させるには、単なる給与アップや福利厚生の見直しだけでは十分とは言えません。
働く環境や組織文化、評価制度、コミュニケーションのあり方など、包括的な改善が求められます。以下に挙げる7つの改善点は特に効果が高いと言われるものです。
それぞれの施策をバランスよく取り入れることで、社員が安心して長く働ける職場づくりの実現につながります。
1. 働きやすい環境の整備(柔軟な働き方・休暇制度など)
リモートワークの導入やフレックスタイム制の活用、年次有給休暇の取得推進など、柔軟な働き方の選択肢を増やすことは、社員の満足度向上につながります。家庭との両立やプライベートの充実が図れることで、働き続ける意欲が高まります。

制度を整えるだけでは、人は動きません。鍵は“内発的動機づけ”です。柔軟な制度は、“自分に合った働き方ができる”という安心感を生みます。
オフィスは多くの時間を過ごす場所ですから、環境を改善すると業務中の従業員のストレスも減少させられます。社員が安心して働ける物理的・心理的な環境を整ええるのは、定着率改善の大前提となります。
リモートワークはインターネットなどを使って会社以外の場所で働く仕組みのこと。以前はテレワークと呼ばれていましたが、現在ではリモートワークの呼称が定着しています。フレックスタイム制は労働者が自分で勤務時間を決められる制度のこと。
もちろん、定められた総労働時間を守る必要があり、さらに必ず勤務しなくてはならないコアタイムもありますが、時間の融通が利きやすくなります。
2. 公正な評価とフィードバックの仕組み
社員の努力や成果が正しく評価される環境は、モチベーションの維持に不可欠です。
透明性のある評価制度を整えることで、不満や不信感の蓄積を防ぎます。また、定期的なフィードバックを行うことで、成長の方向性が明確になり、自己効力感も高まります。

この前の1on1、ちゃんと“聞く”って奥が深いんだなって実感しました。評価って、数字だけじゃなくて、どう伝えるかが本当に大事なんですね。
特に1on1面談や多面評価の導入など、個人と組織の期待をすり合わせる仕組みが効果的です。
3. 明確なキャリアパスと成長支援体制
「この会社で成長できる」と実感できることは、社員が長く働く理由の一つです。
キャリアプランを可視化し、スキルアップの機会を提供することは、定着率向上に直結します。研修制度や資格取得支援、メンター制度などを整えることで、社員の成長意欲を後押しすることができます。個人の将来像に合わせた育成計画を提供することが重要です。

“成長できる実感”があるかどうか。それが“定着”と“離職”の分かれ道になります。制度としての育成ではなく、個々のキャリアに向き合う支援が求められます。
先輩社員や上司が指導するOJT制度とは違って、メンターが制で重視されるのは精神的なケアやサポートです。また、直接的な部署の上司や先輩ではなく、少し離れた部署から呼ばれることが多くなっています。
4. 定期的な1on1や対話の機会の設置
上司と部下の定期的な1on1ミーティングは、社員の心の声をくみ取り、早期に課題を発見する貴重な場です。
業務の進捗確認だけでなく、悩みや不安、キャリアの希望などを共有することで、信頼関係の構築にもつながります。単なる形式的な面談ではなく、「話しやすい」「聞いてもらえる」と感じてもらえば、コミュニケーションの質も高まり、離職予防と定着促進のカギになります。

まだ分からないことだらけですが、まずは“現場の声”をちゃんと拾うことから始めたいと思ってます。1on1って、信頼を積み重ねる場所なんですね。
5. メンタルヘルスケアや心理的安全性の確保
ストレス社会といわれる現代において、心の健康を守る取り組みは定着率改善の重要な要素です。
従業員が安心して本音を話せる心理的安全性のある職場では、不安や孤独感が軽減されます。メンタルヘルス研修や社内カウンセリング体制の整備、日々のコンディションチェックなどを取り入れることで、従業員の健康管理と組織の信頼関係が同時に強化されます。

“みんなのマネージャ”のフィードバック機能、現場の心理的安全性づくりにかなり効きますよ。安心して話せる環境が、定着の第一歩です。
6. 社内コミュニケーションの活性化
部署間の壁を越えた交流や、オープンな情報共有の仕組みは、エンゲージメントを高め、チームワークを促進します。社内SNSや感謝の言葉を伝え合う制度、カジュアルな交流イベントなども有効です。また、現場と経営層の双方向のコミュニケーションを意識することで、組織全体の一体感が生まれ、社員の帰属意識が高まります。

この前のプロジェクトで、“他部署の人とも気軽に話せたのがすごくよかった”って言われて…。やっぱり、普段からのつながりって、大事ですね。
現代ではほとんどの人がSNSを利用していますが、この利用者を社内に限定したものが社内SNSです。若い人が慣れ親しんだタイムライン的なコミュニケーションによって、カジュアルなやり取りが可能になり、部署を超えた情報共有もやりやすくなります。
7. 採用段階からのミスマッチ防止
定着率の改善は、採用時から始まっています。仕事内容や社風を正しく伝え、期待値をすり合わせることが、入社後のギャップを防ぐのです。
この場合は適性検査や面接評価の工夫によって、自社と相性の良い人材を見極めることができます。リアルな職場体験やオープンなコミュニケーションを通じて、「ここで働きたい」と感じてもらう採用設計が求められます。

採用は“入り口”であり“約束”でもあります。入社後に『思っていたのと違う』とならないよう、誠実な情報提供と期待値のすり合わせが欠かせません。
施策を成功に導くためのポイント
どれだけ優れた施策を導入しても、それを実行する組織の姿勢や運用体制が整っていなければ、効果は限定的です。
定着率改善を真に成功させるには、現場だけでなく経営層も巻き込んだ全社的な取り組みが必要です。属人的な対応に頼らず、数値に基づいた分析と改善サイクルを回すことが重要であり、そのために施策を「実行し続ける」ための3つのポイントを解説します。
経営層からの本気の関与
人材の定着は経営課題であり、経営層が明確に関与することで、全社的な優先順位が高まります。トップがメッセージを発信し、定着に関するKPIや施策実行状況を把握する姿勢を示すことで、現場の実行力も向上します。
経営ビジョンと社員の成長支援がつながっているというメッセージは、働く意欲を大きく高める要因となります。

この人事施策、現場の“納得感”まで落とし込めていますか? 経営層の関与が本気であるほど、現場も“これは本気なんだ”と動きやすくなるんです。
KPIは日本語に直すと重要業績評価指標となります。目標達成に向けての進捗を数字化したものです。具体的例を挙げると商談数や受注率となり、どのくらいの数字を達成すればいいのかが一目瞭然になります。
データに基づく定着率の可視化と分析
属人的な感覚ではなく、実際の数値で定着状況を把握することが重要です。
離職者の傾向や退職理由、在籍者のエンゲージメントレベルなどを可視化することで、改善すべきポイントが明確になります。
さらに施策実行後にどう数値が変化したかを検証することで、継続・中止・改善の判断ができ、施策が「形骸化」するのを防ぎます。
属人化、つまり担当者しか物事を把握できない状態になっていると、担当者がいない場合の対応が遅れてしまいます。さらに評価や業務内容がブラックボックス化してしまい、担当者の負担増まで招いてしまうのです。

“感覚”じゃなくて“数字”で見るって、最初は難しく感じたんですけど…今では“ちゃんと見える化”することで、次の一手も考えやすくなりました!
現場マネージャーの役割とスキル強化
現場のマネージャーは、日々のコミュニケーションや評価・育成において大きな影響力を持ちます。
彼らのマネジメントスキルやフィードバックの質が、定着率に直結するといっても過言ではありません。マネージャーの役割を明確にし、定期的な研修や支援体制を設けることで、全体のマネジメント力が底上げされ、定着施策の実効性が高まります。
マネージャーの担当はプロジェクトの管理・調整。業務内容が多岐にわたるので、何でも屋になってしまいがちですが、プロジェクトの全体を見渡せるポジションです。

“育てよう”と思った瞬間から、マネジメントは始まります。スキルと同時に、“関心”を持てるかが問われているんです。
「みんなのマネージャ」でできる定着率改善施策とは?
定着率の改善には、日常的なコミュニケーションの質向上と、マネジメントの標準化が重要です。
「みんなのマネージャ」は、従業員のエンゲージメントを高め、現場のマネジメント力を底上げするクラウド型支援サービスです。
AIによる状態分析から、具体的なフィードバック支援、スキル管理まで、定着率向上に必要な機能をワンストップで提供します。ここでは、みんまねが持つ具体的な機能とその効果を紹介します。

私も実際に使用して見ましたが、現場の方が“これなら使えそう”って前向きになってくれたのが印象的でした。道具があるだけじゃなく、“どう活かすか”を一緒に考えるのが大事なんですね。
週次サーベイによる状態把握とAI最適化
みんまねでは、従業員のモチベーションや心理状態を把握するために、週に1回のパルスサーベイを実施します。短時間で回答できる設計で、日常的なコンディション変化を見逃しません。
それだけではなく、AIが従業員の回答傾向を学習し、必要に応じてアンケート頻度を調整。メンタル状態が不安定な人には頻度を増やすなど、個別最適化が行われます。これにより、早期のフォローアップが可能になり、離職のリスクを未然に防げます。
パルスサーベイは短時間で回答できる質問を周期的に繰り返す調査です。短期間で繰り返すことで従業員の変化を把握しやすくなり、マネジメント業務に役立ちます。
フィードバック支援とマネジメント標準化
サーベイ結果に基づいて、AIがマネージャーに最適なフィードバック方法を提案します。
例えば、どんな言葉で話すべきか、どう伝えればよいかなど、具体的なアドバイスが自動で提示されるため、マネジメントの質にばらつきが生まれにくくなります。特にマネージャー経験が浅い人にとっては、効果的な対話のナビゲーションツールとして機能し、従業員との信頼関係構築を支援します。

相談を受けるときにはまず状況をよく聞き、心情に共感する必要があります。上から「指導」する姿勢ではなく、焦らないことが重要です。
スキル管理で成長支援と報酬制度を連携
みんまねには、業務ごとのスキルを定量的に管理できる機能も搭載されています。
自己評価と他者評価を数値化し、スキルごとに可視化することで、育成の進捗や課題を明確にします。また、一定のスコアに到達した際に時給アップや報酬制度と連動させる設計も可能で、成長意欲を高めながら、定着率アップにも寄与します。
こうした「見える化」と「ご褒美設計」は、現場での実効性が非常に高い施策となります。
「見える化」によって業務の内容や状態が確認しやすくなると、相談への対応や評価もしやすくなります。また、人間は現金なものです。「ご褒美」を設定してあげることでやる気を引き出し、業務への取り組み姿勢の改善も見込めます。

スキルの“見える化”が進むと、評価の納得感が増すだけでなく、“あと一歩で手が届く”という達成感にもつながる。報酬とつなげることで、現場のやる気も自然と引き出せます。
まとめ
定着率の改善は、採用活動だけでなく、組織全体の活力と成長性を支える重要な取り組みです。
職場環境の整備や評価制度の透明化、マネージャーの育成など、多角的なアプローチが必要となります。今回ご紹介した7つの施策は、それぞれが独立しているわけではなく、組み合わせて運用することで相乗効果が生まれます。

“変化を起こす”って、まずは“気づくこと”からなんですね。この記事を通して、その“気づき”をちゃんと行動に変えていきたいと思いました。
その中でも、日常的な対話の質を高め、個々の状態を見える化する仕組みは、定着率向上において極めて効果的です。「みんなのマネージャ」は、こうした施策を効率よく実現するための強力なツールとして、多くの現場で活用されています。
定着率の低下に悩んでいる企業こそ、今こそ仕組みと支援の見直しを図り、組織が自走できる土台を築くことが求められています。人が辞めず、育ち続ける組織づくりを目指し、ぜひ一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。


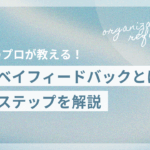
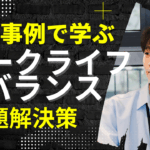

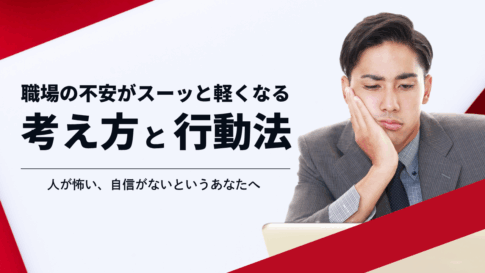
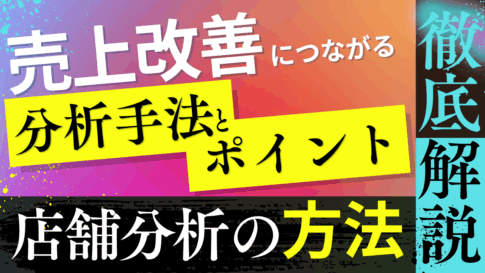
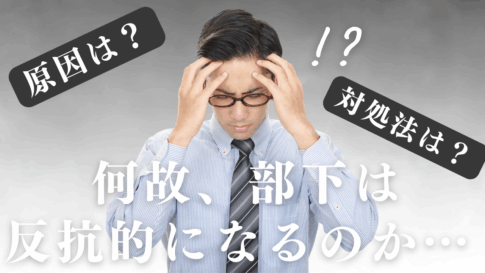
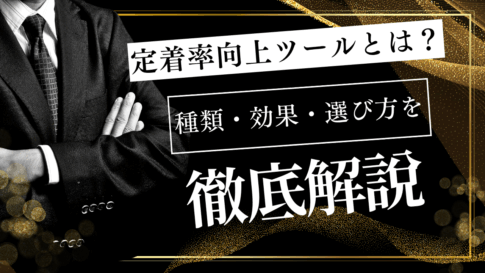
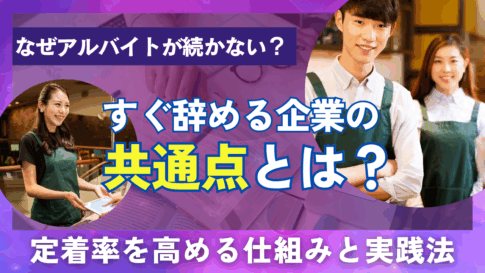
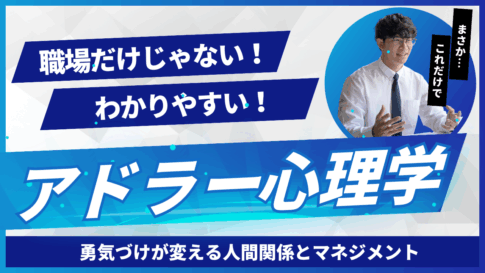
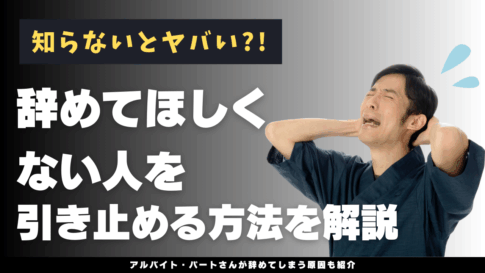



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。