
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
近年、多くの企業が人手不足に悩む中、「若者はどこへ行ったのか?」という疑問が増えています。ただ人がいないのではなく、働くことへの価値観や職場への期待が大きく変化しているのです。
本記事では、若者と職場とのミスマッチが生じる理由や、多様化する働き方の選択肢、そして企業がいま見直すべきポイントについて解説します。若手人材の離職防止と定着率向上のヒントを探っていきましょう。
- 若者が企業を離れる本当の理由
- 多様な働き方に対する若者の価値観と行動
- 企業が導入すべきマネジメント支援の具体策
なぜ若者は企業から離れていくのか?

最近の人手不足の問題について相談を受けることが多いのですが、単純に人がいないという問題ではないことが多いんです。

確かに、求人を出しても応募がないとか、入社してもすぐに辞めてしまうという話をよく聞きますね。
近年、若者の企業離れが進んでいます。ただ単に仕事がないからではなく、そこには価値観や働き方に対する深い意識の変化が影響しています。
では、なぜ今の若者たちは企業から離れていくのでしょうか。その背景を、主な3つのポイントに分けて見ていきましょう。
- 価値観の変化:「やりがい」や「自己成長」「働きやすさ」を重視する傾向が強まっている。
- 働き方への意識の変化:リモートワークやフレキシブルな働き方が広がっている。
- 企業風土への不満:意見が尊重されない、風通しが悪い環境では退職・転職を選ぶ傾向がある。
こうした変化を企業が理解せず、従来の価値観で人材マネジメントを行っていては、若者の離職は止まりません。企業側の理解と対応が急務となっています。
若者が感じる「働きにくさ」とは

現代の若者が感じる「働きにくさ」は、実は給与や福利厚生の問題だけではないんです。
現代の若者が感じる「働きにくさ」は、給与や福利厚生の問題だけではありません。
これらの結果、「自分はこの会社に合わない」「成長できない」と感じ、職場に違和感を覚えた若者が離職に至るのです。企業側は働く環境やマネジメント方法を見直し、個人に寄り添った制度設計を行うことが求められます。
「働きがい」「成長実感」への欲求

若い方と話していると、お金だけじゃなくて「成長できているか」を気にする人が多いと感じます。
若者が仕事に求めるのは、単なる労働対価ではなく「働きがい」や「自己成長の実感」です。例えば、単調な作業ばかりで自分の成長が見えない職場では、長く続けたいというモチベーションは生まれません。
また、成果が評価されず、どれだけ努力しても認められないと感じる職場では、成長意欲も萎えてしまいます。
こうした不満はやがて「この会社で働く意味がない」という感情につながり、退職という選択に結びつきます。企業は個人の目標やキャリアビジョンを尊重し、段階的な成長を支援する仕組みを整えることが重要です。
ミスマッチの背景にある企業の古い価値観

企業側の「昭和的」な価値観がそのまま残っていることが、ミスマッチの大きな要因となっていますね。
多くの職場で若者とのミスマッチが生まれている原因の一つに、企業側の「昭和的」な価値観のままの運用があります。
年功序列、上意下達、長時間労働の美徳など、現在の若者には受け入れがたい文化がいまだに残っている企業も少なくありません。また、「若者は指示に従うべき」という一方的なマネジメントもミスマッチを助長します。
価値観のすれ違いは、早期離職を引き起こす大きな要因です。企業は過去の常識にとらわれず、若年層の価値観やニーズを理解し、組織文化をアップデートしていく必要があります。
多様な働き方が広がる中での若者の選択肢

最近は「企業に所属する」という働き方以外にも、いろんな選択肢がありますよね。
近年、若者たちは「企業に所属して働く」という常識から離れ、さまざまな働き方を選ぶようになっています。では具体的に若者の働き方に対してどのような考えがあるのでしょうか。
- フリーランスや副業:会社に縛られず、自分のスキルを活かして自由に働く
- 非正規雇用・短時間労働:かつての不安定なイメージから自分に合った働き方へ
- 「安定」よりも「自由」:若者にとっての成功は「自分らしく生きること」
フリーランスや副業志向の増加

正社員として一つの会社に縛られるのではなく、自分のスキルを主体にキャリアを築きたいという声をよく聞きますね。
正社員としてひとつの会社に縛られるのではなく、複数の仕事を掛け持ちしたり、自分のスキルを活かして自由に働くフリーランスという選択肢が注目されています。
| 傾向・背景 | 詳細 |
| 複数のキャリア志向 | フリーランスや副業で多様な働き方を希望する |
| 自己価値を重視 | 会社に依存せず、自分のスキルを主体にキャリアを構築したい |
| 副業解禁の流れ | スキル向上・人脈形成の機会として副業を積極的に活用 |
これらの傾向・背景により、従来のキャリア形成の枠組みは崩れつつあります。
非正規雇用・短時間労働を選ぶ理由

非正規雇用って、今は「自分に合った働き方」として前向きに選ばれているんですね。
非正規雇用や短時間勤務を選ぶ若者も増えています。かつては不安定な働き方と見なされていた非正規ですが、今は「自分に合った働き方」として前向きに選ばれるようになっています。そこにはどのような理由が含まれているのでしょうか。
- 生活を優先:家族や趣味など仕事以外の時間を優先し生活を充実させるため。
- 精神的なゆとり:ストレスの少ない働き方で自身のメンタルを安定させるため。
- 柔軟な働き方への志向:固定的な業務体制ではなく、自分のペースに合った働き方を選ぶため。
企業側としては、こうした多様な雇用形態を積極的に受け入れる体制を整えることが求められます。
「安定」より「自由」を求める価値観の変化

今の若者にとっての成功は「自分らしく生きること」に変わってきていますね。
かつては安定した大企業に入ることが「成功」の象徴とされていましたが、今の若者にとっての成功は「自分らしく生きること」に変わっています。
そのため、安定よりも「自分の時間が持てるか」「好きなことができるか」といった自由や柔軟性を重視する傾向があります。この価値観の変化は、働き方だけでなく人生全体の設計にも影響を与えています。
企業にとっては、従来の「福利厚生の充実」だけでは若者を惹きつけられなくなってきており、自由度の高い働き方や、働く目的を自分で選べる職場設計が重要になっています。
人手不足に悩む企業が見直すべきポイント

企業が人手不足を解決するには、単に人を採用するだけじゃなくて、根本的な見直しが必要なんですね。
人手不足に直面している企業は、単に「人がいない」と嘆くのではなく、自社の組織文化やマネジメントの在り方を根本から見直す必要があります。
今、必要なのは若者の価値観を理解し、それに応じた柔軟な働き方や評価制度を構築することです。また、働きがいを感じられる職場づくり、メンタル面での支援、風通しの良いコミュニケーション体制など、職場環境全体の改善が不可欠です。
以下では、企業が取り組むべき具体的なポイントを整理して解説します。
若者視点の職場づくりが急務

今の若者は「自社が若者にとってどんな価値を提供できるか」を明確にすることが重要ですね。
今の若者は、ただ働くだけでなく、自分がその職場でどう成長できるか、どんな意味を見出せるかを重視します。そのため企業は、「自社が若者にとってどんな価値を提供できるか」を明確にする必要があります。では、若者は職場にどのような要素を求めているのか考えましょう。
| 若者が求める要素 | 詳細 |
| 自己成長の支援 | 学びや挑戦の機会がある、成長を実感できる仕組み |
| 信頼関係がある職場 | 上司・同僚との信頼関係、安心して意見が言える雰囲気 |
| 柔軟な働き方の提供 | リモートワーク、時差出勤、副業容認など自由度の高い働き方 |
形式的な制度だけでなく、日々のコミュニケーションや職場の雰囲気が大きな影響を与えるため、現場レベルでの改善が求められます。若者が「ここで働きたい」と感じられる職場こそ、今後の人手不足時代に強い企業といえるでしょう。
画一的な評価・育成制度の限界

一人ひとりの成長スピードや関心に合わせた指導って、確かに大切ですよね。
従来の評価制度は、年齢や勤続年数、形式的な成果だけを重視してきましたが、これでは多様な働き方を求める若者のやる気を引き出すことはできません。
今求められているのは、個々のスキルや貢献度を柔軟に評価し、それに応じた育成を行う制度です。一人ひとりの成長スピードや関心に合わせた指導を行い、納得感のある評価を通じてモチベーションを高める必要があります。
画一的な枠にはまらない評価制度を導入することで、若者が長く働きたいと思える環境を整えることが可能になります。
「みんなのマネージャ」が提供する本音を引き出す仕組みとは

従業員の本音を早期に把握することが、人手不足解決の鍵になりますね。「みんなのマネージャ」はその点で非常に効果的なツールです。
人手不足や若年層の離職に悩む企業にとって、今求められるのは「従業員の本音を早期に把握し、対話と信頼関係を軸にしたマネジメント」です。
そのための革新的ツールが、「みんなのマネージャ」。従来の制度や面談だけでは見えなかったミスマッチや違和感を可視化し、リアルタイム・個別最適・エビデンスベースで職場改善を支援します。
「みんなのマネージャ」の具体的な機能と効果をまとめてみました。
| 機能・仕組み | 概要・効果 |
| パルスサーベイ(個別最適) | 状態に応じた質問を定期配信。本音や変化を早期に把握 |
| AI提案型フィードバック支援 | 最適な声かけ・接し方・タイミングをAIが提案。信頼構築を支援 |
| エンゲージメントスコアの可視化 | モチベーションを可視化し、離職リスクの高い人材を早期特定 |
| マネジメント支援ダッシュボード | 現場マネージャー向けに状況を一目で把握できるツールを提供 |

従業員の本音や不満を定量的に把握できるって、すごく画期的ですね!
従来のように一方的な評価や、定期的な面談だけでは把握できなかった従業員の本音や不満を、定量的に可視化する仕組みを提供しています。
特に若年層の離職が多い業種や店舗ビジネスにおいて、若者の「違和感」をいち早く察知するためには、リアルタイムかつ個別最適なフィードバック体制が必要です。
「みんなのマネージャ」は、現場のマネージャーが心理的安全性の高い対話を通じて従業員をサポートできるよう、AIによる行動提案やダッシュボード機能を駆使しながら、組織全体の人材育成を支援します。
まとめ

若者の価値観の変化を理解して、それに応じた柔軟な働き方を支援することが何より重要ですね。
若者が企業を離れていく背景には、価値観の多様化と、それに伴う働き方の変化があります。「安定」より「自由」や「自己成長」を求める若者に対し、従来型の企業文化やマネジメント手法は適合しなくなってきました。また、職場に対する心理的な違和感や働きにくさが、ミスマッチや早期離職の原因にもなっています。
こうした中で企業に求められるのは、若者の視点を理解し、柔軟で多様性に富んだ働き方を支援する環境の整備です。

「みんなのマネージャ」みたいなツールがあると、若者の本音を引き出しやすくなりそうですね。
「みんなのマネージャ」は、そんな時代の変化に即したマネジメント支援ツールです。個別最適化されたサーベイ、AIによるフィードバック支援、エンゲージメントの可視化などにより、若者の本音を引き出し、対話を通じて信頼関係を築ける環境づくりを支援します。
これにより、人手不足という課題に対しても、根本からアプローチすることが可能になります。今後の人材戦略において、若者とのギャップを埋めるためのツールとして、「みんなのマネージャ」の活用が大きな鍵となるでしょう。

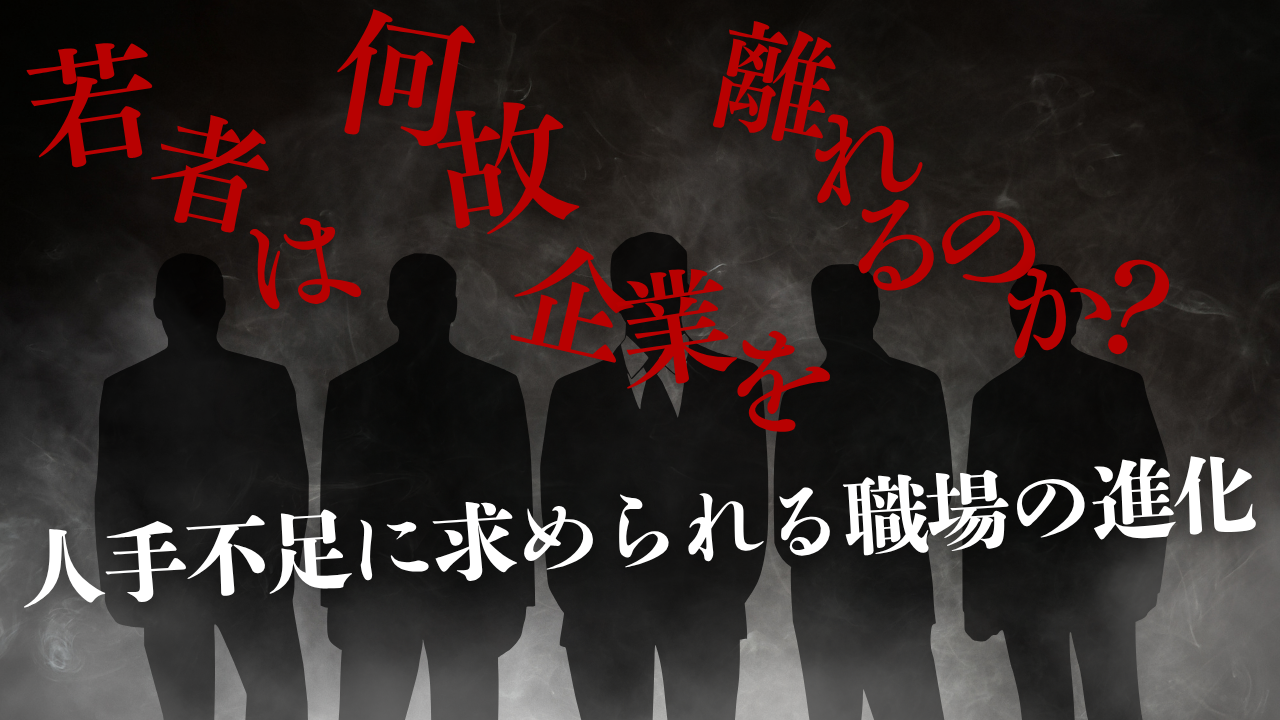
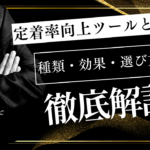
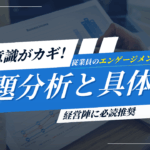

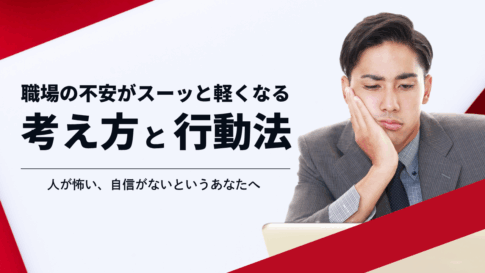
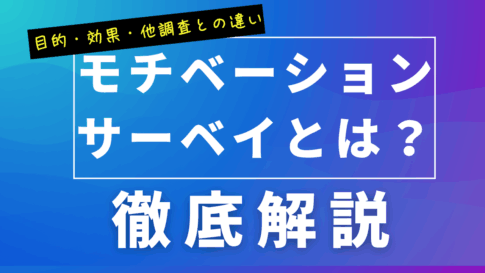
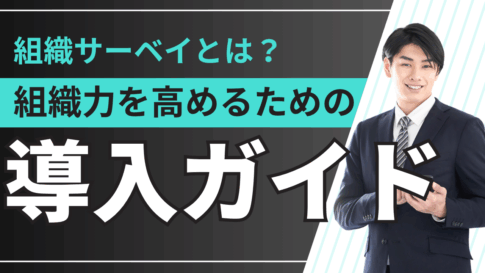
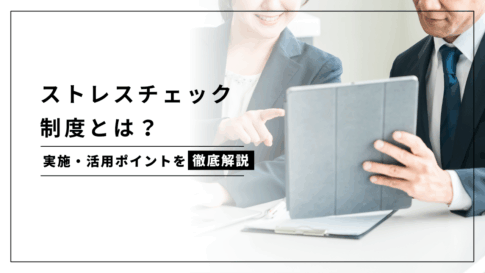
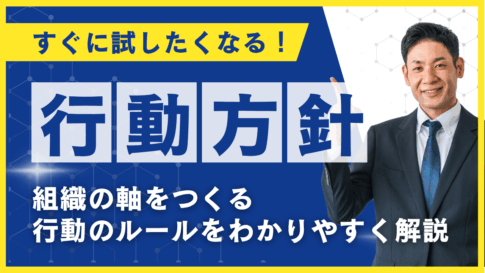

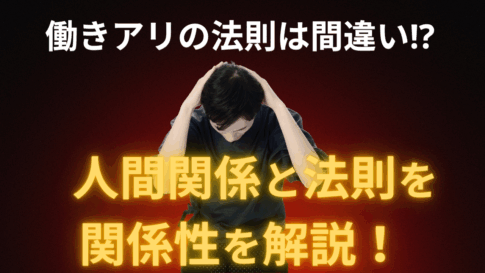



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。