
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「最近、従業員の離職が続いていて困っている」「職場の雰囲気がなんとなく悪い気がする」──そんな悩みを抱える経営者・人事担当者の間で注目されているのが「エンゲージメントサーベイ」です。
しかし、調査頻度や機能、使いやすさなど、サービスごとに特徴が異なるため、どれを選べばよいか迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特に「離職防止」に強いエンゲージメントサーベイを厳選して比較。中でも、従業員の心理変化をリアルタイムで察知し、具体的な改善アクションにつなげられる「みんなのマネージャ」の特長にも焦点を当て、現場で本当に役立つサーベイツールを紹介します。
エンゲージメントサーベイとは?離職防止との関係を解説

従業員のモチベーションや職場への満足度を測るエンゲージメントサーベイは、離職予防の強力なツールになります。数字で見える化することで、問題を早期に発見できるんです。

なるほど!従業員の本音を聞き出すのって難しいですが、定期的なサーベイなら安心して答えられそうですね。
エンゲージメントサーベイとは、従業員の仕事や職場に対する心理的なつながりや意欲を測定する調査のことです。企業がこのサーベイを導入する主な目的として以下のような効果が期待されています。
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 離職防止 | エンゲージメントが高い従業員ほど職場への満足度が増し、離職リスクが低下 |
| 早期課題発見 | 従業員の不調や不満を早期に把握し、対策を講じることが可能 |
| 改善アクション | 定期的なサーベイを通じて従業員の状態を可視化し、具体的な改善につなげる |
特に飲食やサービス業などの人材流動が激しい業界では、従業員の状態を継続的に把握する仕組みの重要性が高まっています。
離職防止に強いエンゲージメントサーベイの特徴

離職を防ぐためのサーベイには、いくつかの共通した特徴があります。年に一度の調査だけでは、従業員の心の変化を見逃してしまうのが現実です。
離職を防ぐために有効なエンゲージメントサーベイには、いくつかの共通した特徴があります。従業員の本音を見逃さないためには、単に年に一度の調査では不十分です。ここでは、離職防止に効果的なサーベイの特徴を解説します。
高頻度のパルスサーベイで心理状態を可視化

パルスサーベイって初めて聞きました!週1回とか短いスパンで実施するんですね。確かに月1回だと、変化に気づくのが遅れそうです。
離職の兆候は、日々の小さな変化に現れます。週1回や月数回といった高頻度で行う「パルスサーベイ」は、従業員のコンディションをリアルタイムに捉えるために最適です。
これにより、従業員の心理状態の変化を継続的に把握することができます。
アラート機能によるリスク検知の仕組み
従業員の回答結果をもとに、エンゲージメントの低下を自動で検知し、管理者に通知する「アラート機能」も重要です。離職やモチベーション低下が懸念される従業員を早期に特定し、必要なフォローを迅速に行うことが可能になります。
特に多拠点やフランチャイズ展開をしている企業では、現場から離れた管理者でも従業員の状況を把握できる点が大きなメリットとなります。
フィードバック支援機能の有無

サーベイは「見て終わり」になりがちですが、結果をどう活用するかが一番重要です。適切なフィードバックができなければ、せっかくのデータが無駄になってしまいます。
サーベイの結果を「見て終わり」にしないためには、管理者が適切なフィードバックを行える体制が必要です。近年では、サーベイ結果をもとにAIがフィードバック内容や話し方のアドバイスを提供するサービスも登場しています。
これにより、フィードバックの質を標準化し、属人性を排除した運用が可能になります。
離職防止におすすめのエンゲージメントサーベイツール比較

たくさんのツールがあるんですね!それぞれの特徴を比較して、自分たちの会社に合うものを選ぶのが大切ですね。
現在、多くの企業が離職防止を目的としてエンゲージメントサーベイを導入していますが、サービスごとに機能や特徴には違いがあります。ここでは、離職対策に有効とされる代表的なツールの特長を紹介します。
| ツール名 | 実施頻度 | 主な特徴 | 離職防止への適用度 |
|---|---|---|---|
| Geppo | 月1回 | 3問程度の簡単な質問、全社的な負担が少ない | 入り口としては有効だが急激な変化の察知は困難 |
| ラフールサーベイ | 定期実施 | ストレスチェックと連動、心理学に基づいた質問設計 | メンタルケアとの相乗効果が期待できる |
| みんなのマネージャ | 週1回 | AI対応の高頻度サーベイ、フィードバック支援機能 | 心理的安全性を確保し本音が表出しやすい |
それぞれのツールには異なる強みがあり、企業の規模や業界特性に応じて選択することが重要です。
Geppo:低頻度型ながら簡単に実施できる
Geppoは、月1回の低頻度サーベイを特徴とするサービスです。3問程度の簡単な質問で構成され、全社的な負担が少ない点が評価されています。
従業員の満足度やストレス度を簡易的に可視化でき、マネジメント層が状況を把握するための入り口としては有効です。ただし、頻度が少ないため、急激な心理変化や離職リスクの早期察知にはやや不向きとなります。
ラフールサーベイ:ストレスチェックと連動
ラフールサーベイは、法定のストレスチェックと連動させてエンゲージメントを測定できるツールです。心理学に基づいた質問設計と組織診断が特徴で、メンタルケアとの相乗効果が期待できます。
また、全体傾向だけでなく個人単位のデータも確認できるため、早期離職予防や現場改善に役立てることができます。
みんなのマネージャ:AI対応の高頻度サーベイで心理的安全性を確保

みんなのマネージャのAI機能は現場の心理的安全性づくりにかなり効きますよ。実名制でありながら、従業員が安心して本音を話せる環境を整えているのが特徴です。
「みんなのマネージャ」は、週1回の高頻度サーベイを基本に、AIが従業員のメンタル状況に応じて出題頻度を自動調整する先進的な仕組みが特徴です。
さらに、店長やマネージャーに対しては、フィードバックの方法や話し方までをAIが具体的に支援します。従業員が実名制かつ個別アカウントで参加するため、心理的安全性も確保され、本音が表出しやすい環境を整えています。
「みんなのマネージャ」が離職防止に適している理由

みんなのマネージャは単なるアンケートツールじゃないんですね。従業員の状態を把握してから、実際の行動まで支援してくれるのがすごいです!
「みんなのマネージャ」は、離職防止を強く意識した設計がなされているエンゲージメントサーベイツールです。多くの競合と異なり、単なるアンケート実施だけでなく、従業員の本音を引き出し、現場で具体的な行動に落とし込むまでの一連の仕組みが整っています。
これらの機能により、従業員の心理状態の変化を見逃すことなく、適切な対応を実現できます。
週1回の高頻度サーベイで本音を見逃さない
「みんなのマネージャ」のサーベイは、基本的に週1回という高頻度で実施されます。これにより、従業員の感情の変化や小さな違和感もタイムリーに捉えることが可能です。
多くの企業が月次や四半期単位での実施にとどまる中、離職リスクの早期察知という観点では大きなアドバンテージとなります。
AIがリスクのある従業員に頻度を最適化

AIが個別最適化してくれるのは画期的ですね。一律のアプローチではなく、それぞれの従業員に応じたケアができるのが重要です。
従業員のサーベイ回答データをもとに、AIがリスク度を自動で分析し、必要に応じてアンケートの頻度を調整します。たとえば、不安やストレスを感じている傾向が見られる従業員には、頻度を上げて継続的にフォローを行う仕組みです。
これにより、画一的な運用ではカバーできない個別最適なケアが実現できます。
店長向けのフィードバック支援で早期対応が可能
「みんなのマネージャ」では、サーベイ結果を受けて店長や上司がどう対応すべきかも明示されます。単に「問題がある」と通知するだけでなく、「どのように声をかけるか」「どんな伝え方が有効か」といった具体的なフィードバック方法を提案します。
これにより、マネジメント経験が浅い現場責任者でも質の高い対応が可能になり、対応のばらつきを防ぐことができます。
まとめ

離職防止という課題に本気で向き合うなら、行動につながる仕組みを持つツールを選ぶことが成果への近道となります。

エンゲージメントサーベイの選び方がよく分かりました!ただアンケートを取るだけじゃなく、その後のアクションまで考えることが大切なんですね。
エンゲージメントサーベイは、従業員の心の状態や職場への関与度を可視化し、離職の兆候をいち早く察知するための重要な手段です。特に離職防止を目的とする企業にとっては、高頻度かつ柔軟なサーベイ体制が求められます。
その中で「みんなのマネージャ」は、週1回のパルスサーベイに加え、AIによる最適化、フィードバック支援など、現場で実際にアクションを起こすための機能が豊富に備わっています。
また、実名制アカウントによる透明性や、店長・従業員双方へのサポート体制も整っており、従業員が安心して本音を伝えられる環境が整っています。
離職防止という課題に本気で向き合うなら、行動につながる仕組みを持つツールを選ぶことが、成果への近道となるでしょう。

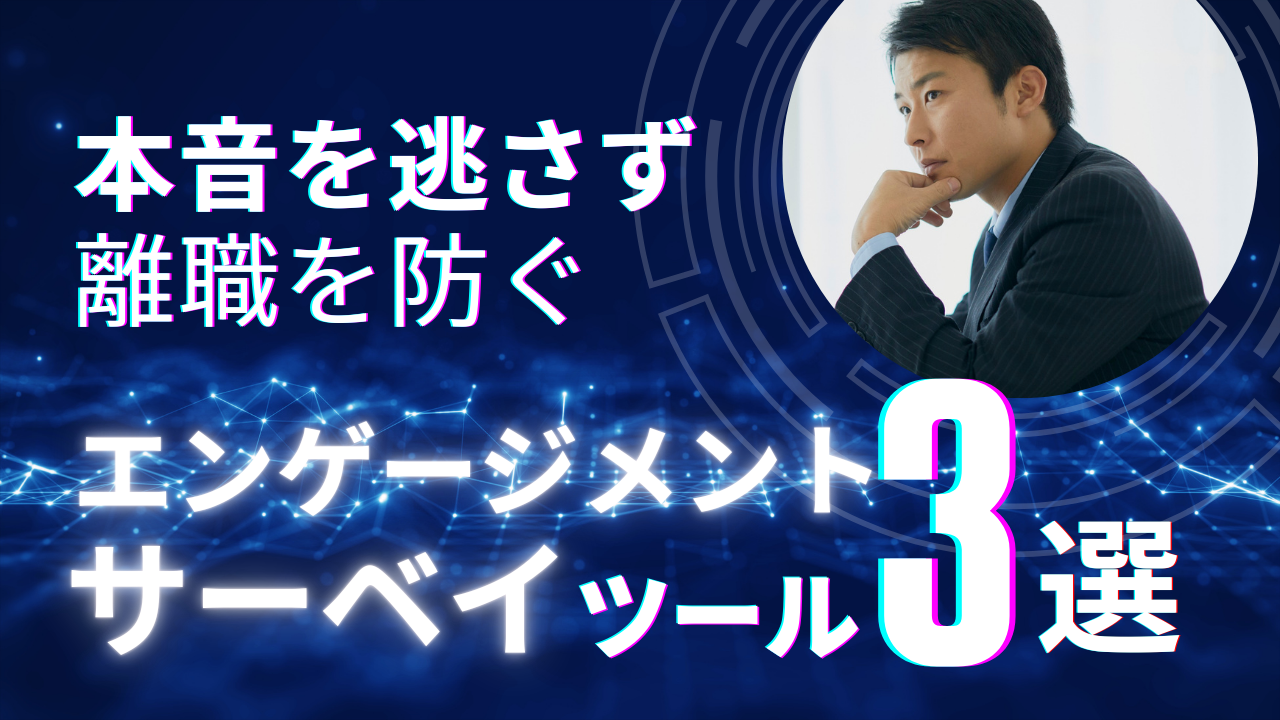
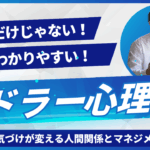
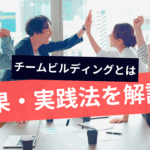

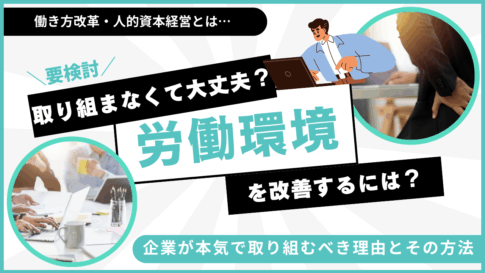
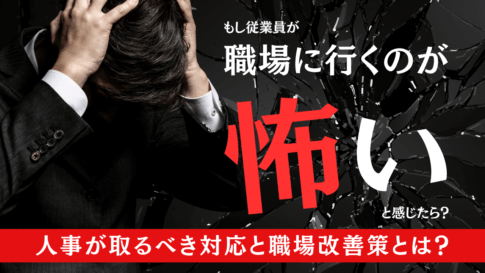


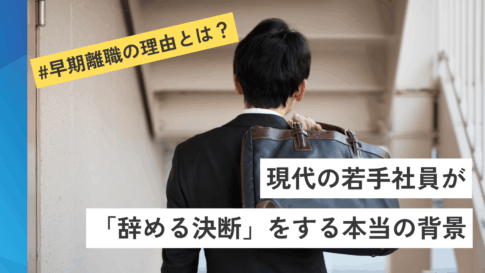
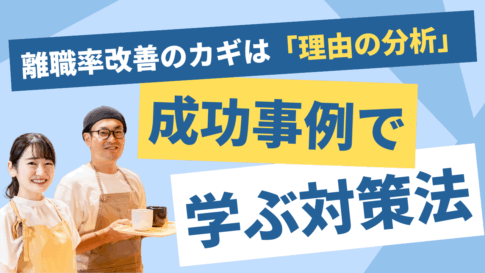
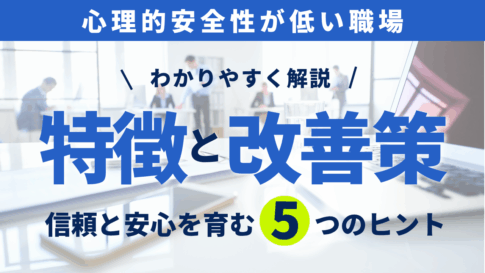



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。