
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
近年、採用市場の激化や労働人口の減少により、「辞めさせない仕組みづくり」が企業の最優先課題になっています。中でも「離職率改善」は、経営の健全性と採用コストの削減、社員エンゲージメントの向上に直結する重要なテーマです。
本記事では、「離職理由の可視化を起点にした離職率改善の方法」とあわせて、具体的な事例を交えてご紹介します。
【大前提】企業はなぜ離職率改善を図るべきか?

まずは離職率改善の重要性について考えてみましょう。企業にとって、これは単なる人事施策ではなく、経営戦略そのものなんです。
企業にとって離職率の高さとは、単に「人が辞めていく」という問題にとどまりません。以下のような明確なリスクを伴いうため、離職率の改善が必要だと考えられます。

確かに、人が辞めるたびに採用や研修に時間とお金がかかりますし、チーム力も下がってしまいますね。予想以上に影響が大きいです。
つまり離職率の改善は、「採用活動の効率化」「現場の安定」「企業価値の向上」に直結する、包括的な経営対策といえるのです。
離職率改善のための3つのステップ

離職率改善は闇雲に取り組んでも効果は期待できません。体系的なアプローチが重要です。
離職率改善の取り組みを行うために活用したい情報や対策を、実際の事例をもとに当記事では3つご紹介します。要となるのは、社員や従業員の離職理由を正確に把握し、課題に対して適切な対策を講じることです。
①離職理由の現状把握

まずは現状把握ですね。でも、辞める人って本当の理由をなかなか話してくれないイメージがあります…
最初に取り組むべきは、「なぜ社員・従業員が辞めていくのか?」を把握することです。
以下のような方法で離職の理由を視覚化しましょう。
一般的な企業におけるありがちな離職理由としては、次のようなものが挙げられます。

離職面談は「引き止めるため」ではなく「組織改善のため」という姿勢が大切ですね。そうすれば本音を話してもらいやすくなります。
まずはありがちな離職理由を抱かせてしまわないよう職場環境を整え、離職や社内トラブルをできる限り防止しましょう。
そのほか社員や退職希望者とのコミュニケーションは欠かせません。離職面談は「引き止めるため」ではなく「職場環境の改善のため」であることを説明し、社員に寄り添った取り組みのための対話とできるよう心がけましょう。圧力をかけるのではなく、離職理由を教えてもらうという姿勢が重要です。
②離職理由の傾向を洗う

個別のケースではなく、傾向として分析するんですね。データ分析の考え方ですね!
集まった情報を「社員個別のケース」として処理するのではなく、傾向として整理していきます。その離職理由が発生しやすい部署と社員の属性や傾向を分析すると、よりよい離職率低下のための対策が見えてくるでしょう。
「社員が離職理由として挙げがちなこと」を例にすると、以下のような分類ができます。
| 離職理由 | 発生部署 | 社員・従業員の年代と属性 |
|---|---|---|
| 評価制度の不信感 | 営業部 | 20代後半の自己成長派 |
| キャリアの不透明さ | 開発部 | 若手〜中堅、出世意欲が強い |
| 人間関係の悪化 | 店舗部 | アルバイト、20~30代 |
会社のサービスや理念、社員の層により異なる「自社ならではの分析結果」を見出すことができれば、離職率改善のための大き一歩となります。
③PDCAサイクルを回す

改善活動は継続が命。一度きりの施策では根本的な解決にはなりません。
改善活動は「一度きり」では意味がありません。継続的に、より多くの社員のための職場環境改善を目指しましょう。
このサイクルを継続することが、離職率改善の最短ルートです。実際に離職率を改善している企業の多くでは、離職理由をもとに社員とコミュニケーションをとり、さまざまな対策を導入している事例が多いです。
業種別、離職の事例

業種によって離職の理由や傾向って違うんですね。具体的な事例があると参考になります。
離職の事例としては、次のようなものが考えられます。
離職事例①宿泊業
宿泊業では、勤務時間が長くなりがちで、シフト制による不規則な勤務形態も多く見られます。そのため、業務には高い体力が求められ、十分な休息を確保しづらい環境に置かれることが少なくありません。加えて、深夜勤務や連勤による生活リズムの乱れから、スタッフ自身の体調管理が他業種に比べて難しくなる傾向があります。
こうした状況が続くと、特に年齢を重ねたスタッフにとっては、体力的・精神的負担が大きくなり、将来的な健康への不安も高まります。その結果、長期的な就業継続が困難だと感じ、離職を選択するケースが多く見られます。また、ワークライフバランスを重視する価値観の変化も、離職の一因となっています。
②飲食チェーン店
飲食店では、時間帯により混雑度合いのばらつきが生じ、業務の偏りが見られやすいです。しかし一般には、深夜帯を除き、ランチタイムとアイドルタイムは給与が変わらないことが多いため、スタッフが疑問を持ちやすい傾向にあります。
飲食チェーンの離職事例を踏まえると、時間帯ごとに適切なラインを確保し、スタッフの負担が偏らない店舗環境を作り必要があるでしょう。
改善のために!社員とのコミュニケーションを大切にしよう

制度や仕組みを整えることも重要ですが、やはり人と人とのコミュニケーションが基盤になります。
制度や仕組みのほか、社員との日常的なコミュニケーションも離職率の改善においては重要です。相談をしやすく、退職の際にも素直に離職理由を伝えられるような職場環境が望ましいと言えます。
社員とのコミュニケーション
まずは、常日頃の業務での社員とのコミュニケーション能力を向上させましょう。

些細なことでも話せる関係って大切ですね。それがあれば、辞めたくなる前に相談してもらえそうです。
些細なことでも話せる関係となれば、離職の兆候を早期に察知する可能性も高まります。直属の上司や店長、シフトマネージャーなどの、社員や従業員との接し方を見つめていきましょう。
離職希望者とのコミュニケーション
もし車内で退職希望者が出た場合には、離職希望者との建設的な対話の姿勢が重要となります。

離職を申し出ている社員との対話は特に気を配る必要があります。目的は引き止めることではなく、建設的な話し合いです。
離職を申し出ている社員とのコミュニケーションには、とくに気を配る必要があります。目的は離職を反対することではなく、離職理由を建設的に話し合うことです。
一般的に従業員は、社員や企業には本音を打ち明けにくい傾向にあります。離職理由となれば尚更のことです。そこで日頃の取り組みをもとに、社員に安心して離職理由を伝えてもらうための姿勢を見せることが必須となります。
コミュニケーションやヒアリングが得意な部署を導入するという方法もおすすめです。
低コストで離職改善ができるアプローチ

予算に限りがある企業でも取り組める方法があるなら、ぜひ知りたいです!
中小企業やリソースが限られた企業こそ、離職率の高さはリスクになります。コストに余裕がなくても、すぐに実行できる離職改善策をいくつかご紹介しますので、ぜひ組織力向上のためにご活用ください。
コストをかけずとも、「社員の声を拾う仕組みづくり」から始めるだけで、離職率は改善の兆しが見えます。
PRTimesによると、離職は目に見えないところで原因が発生するケースがほとんどだそうです。よって離職率改善のための事例には、社員や従業員のストレス度合いや不満を見つけるための仕組みが必要であることが多くなります。
【みんなのマネージャ】離職理由を深掘り、離職率改善の事例を持つツール

みんなのマネージャは、まさに現場の声を拾って離職率改善につなげるツールです。私もクライアントに導入をお勧めしています。
社員とのコミュニケーション力向上や、離職理由の活用、離職を防止するための組織づくりには、時間がかかるものです。そんななかで社員に寄り添うことができ、管理職クラスに「従業員のストレス度合いや不満」を届けられるツールがあったら便利だと思いませんか?
みんなのマネージャは、「現場の声が拾えない」「本音がわからない」と悩んでいる企業にコミットする、離職率改善ツールです。

AIによるフィードバック機能とか、現場の心理的安全性向上に役立ちそうですね!
見える化と自動化を掛け合わせて、従業員への簡単で定期的なアンケートとフィードバックを行うため、認識していなかった苦しさや悩みの理由に寄り添うことができます。
店長やシフトマネージャーは、従業員のアンケート結果をもとに適切なコミュニケーションや対策を導入できるため、双方によい働きかけを行い、結果として「離職率の改善」と「企業力の向上」「仕事やプライベートでのコミュニケーションの活性化」などを行えるツールです。

離職率改善は一朝一夕にはいきませんが、適切なツールとアプローチで必ず成果が出ます。まずは現状把握から始めてみてください。
「離職率の改善を行いたいものの、自社に適切な事例がわからない場合」や「離職理由をもとに離職率改善を図りたいものの、取り組みを円滑に進められない」場合には、みんなのマネージャが御社と御社の社員さんをサポートいたします。


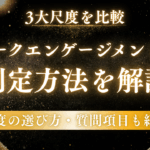
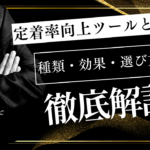
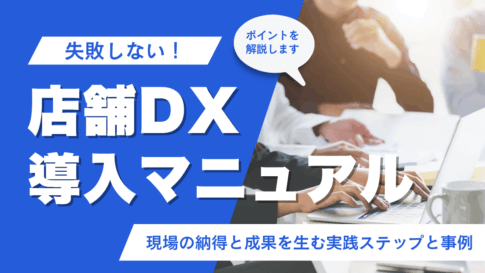


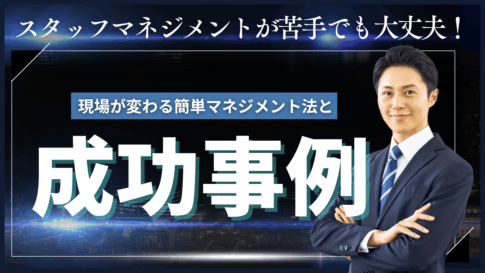

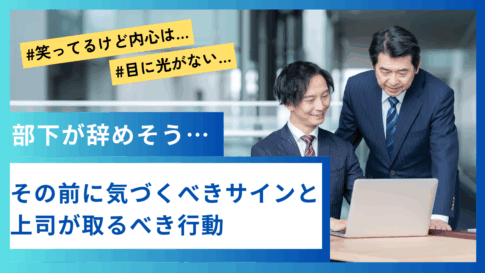
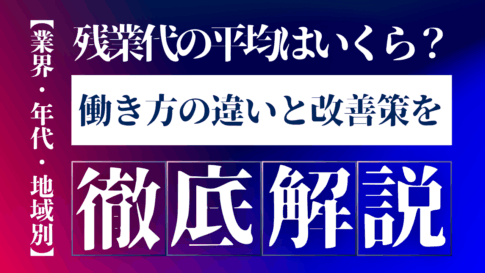




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。