
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。

あれっ、最近なんだが離職希望者が増えているような?

何かのサインの可能性があります。
まずは定着率の正しい計算方法を見直し、データとして分析していきましょう。
従業員の職場定着状況を把握するうえで、定着率の計算は非常に有効です。しかしながら、「誰を対象に計算すればいいのか?」「3ヶ月と1年では何が違うのか?」といった疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、定着率の算出式を基本から丁寧に解説しながら、計算時に見落としがちなポイントや、適切な期間の選び方について詳しくお伝えします。さらに正確な運用に欠かせないデータ管理の考え方や、可視化ツールの活用方法もご紹介。
従業員が安心して働ける職場をつくるための第一歩として、ぜひご活用ください。
- 企業や組織における定着率の計算方法がわかる
- 定着率の計算をするうえでの注意点がわかる
- 定着率向上のための施策を知れる
定着率とは?基本の意味と算出方法
定着率とは、新たに採用された従業員のうち、一定期間後も在籍している割合を示す指標です。企業にとって、従業員がどれほど継続して働いているかは、職場環境の良し悪しやマネジメントの質を測る手がかりになります。
計算は「ある期間終了時点の在籍者数 ÷ その期間の採用人数 × 100」で行います。
| 定着率算出に必要なデータ | 期間設定 | 在籍者数 | 採用人数 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 定着率を算出する期間を定める | その期間の在籍人数 | その期間の採用人数 |
たとえば、10人の新入社員のうち1年後に8人が残っていれば、定着率は80%となります。この数値をただの目安とせず、背景の要因を読み解くことで、離職防止や現場改善の材料として活用できます。
定着率の役割と活用シーン
この指標は、人材の流動性だけでなく、職場がどれだけ働きやすい環境かを知る上でも役立ちます。人事部門はもちろん、現場マネージャーもこの数値をもとに改善の方向性を考えることができます。
特に採用コストや育成の時間がかかる企業にとって、定着率の改善は経営に直結するテーマです。
【定着率】基本式の使い方と注意点
定着率の計算式は
「在籍数 ÷ 採用数 × 100」
が基本です。
「在籍数 ÷ 採用数 × 100」で定着率を求める際、必ず計測日を明確にしましょう。1年後を基準にするのか、年度末かで数値は変わります。また途中退職者の扱いも統一しなければ、他の期間との比較が難しくなります。
定義を曖昧にせず、社内基準を整備してから継続的に計測することが大切です。
定着率を算出する際の見落としがちな注意点
定着率を適切に使うためには、計算の対象者をどう定義するかが非常に重要です。特に、新卒・中途・アルバイトなど、雇用形態によって扱いが異なる場合は注意が必要です。また、在籍人数を「いつの時点」で数えるのかも明確にしておく必要があります。
ここでは
計算ミスを防ぐための具体的な注意点について
- 「入社人数」はどう数える?
- 「在籍人数」はいつの時点の数値化?
- 中途・非正規スタッフの取り扱い
の項目で解説します。
「入社人数」はどう数える?
採用した人数の定義が曖昧だと、定着率の信ぴょう性が低くなります。たとえば、内定辞退や試用期間中の退職者を含めるかどうかで数値は大きく変わります。配属前の段階を除外するなど、会社ごとに明確なカウントルールを持つことが重要です。
「在籍人数」はいつの時点の数値か?
定着率の分母だけでなく、分子にあたる在籍者数も見直す必要があります。例えば、入社からちょうど1年経過したタイミングでの在籍数なのか、年度末時点かによって結果が異なります。

繁忙期と閑散期では社員人数も異なるものです。
繁忙期後など時期によっては離職者が増えることもあるため、計測日を統一することが必要です。
中途・非正規スタッフの取り扱い
契約社員やアルバイトを含めるかどうかも定着率に影響します。業種によっては非正規雇用が大多数を占めるケースもあるため、正社員だけで算出しても実態を反映しないことがあります。
| 中途・非正規スタッフの種類 | 分類方法 | 考慮するべき点 |
|---|---|---|
| 中途 | 新卒ではない採用者 | 定着しやすい可能性がある |
| パート・アルバイト | 非正規雇用フルタイムではない雇用者 | 人員比率が多い企業が多い 定着率が最も低い分類 |
| 新卒 | そのほかの採用者新卒採用の者 | 定着率のコアとなる分類 |
定着率を「何のために使うのか」によって対象範囲を調整しましょう。
定着率の期間設定はどう決めるべきか?
計算期間によって見える課題は異なります。短期では研修制度や受け入れ体制の問題が、長期ではキャリアや昇進制度に関する不満が現れます。
実際には、次の見出しで紹介するポイントに配慮しましょう。
期間設定のポイント
- 期間別でわかることは?
- 業種や職種に合わせた的確な期間設定とは?
- 評価サイクルとの連携の重要性は?
企業によっては3ヶ月・1年・3年のように複数スパンで見ることで、段階的な離職の傾向をつかんでいます。
期間別でわかることの違い
3ヶ月は、初期定着の確認に向いており、研修やOJTの効果が見える指標です。
1年定着率は、日常業務や人間関係への適応を示し、3年定着率になると、キャリアパスの納得度や組織風土の影響が反映されます。
目的に応じて複数のスパンで把握するのがおすすめです。
業種や職種に合わせた期間設定
サービス業や飲食業では、早期離職が多いため3ヶ月での判断が主流ですが、専門性の高い技術職や研究職では、1年あるいは3年以上の視点が必要です。
職種や業界によっては“定着”の意味が変わるため、自社の特性に合わせて期間を設計する必要があります。

弊社の場合はどうしたらよいだろう。

業種や企業カラーに合った設定は、ぜひ我ら管理職チームを頼ってご相談いただければと!
評価サイクルとの連携で効果アップ
定着率を評価制度や1on1のタイミングと合わせると、より有効な活用が可能になります。たとえば、評価面談の前後で離職者が急増するようなら、制度やフィードバックの在り方に問題があるかもしれません。人事データと連動させることで、より本質的な改善につながります。
正確な定着率を把握するために必要な仕組み
属人的な感覚に頼った数値管理では、組織の課題は見えてきません。定着率を継続的に活用するためには、信頼できるデータ管理体制と、現場の状況を補完する仕組みが必要です。
ここでは、実務に役立つ3つの視点として
3つの視点
- データを一元管理する
- 肌感覚での判断を止める
- みんなのマネージャなど、可視化ツールを活用する
について紹介します。
データを一元管理する意義
紙やExcelでの手動管理は、担当者が変わると継続が困難になりがちです。クラウドシステムなどを活用し、入社・退職の履歴を明確に記録しておくことで、期間ごとの推移分析や職種別比較が可能になります。
数値の信頼性は、分析の質にも直結します。的確な管理を試みましょう。
「肌感覚」での判断を排除しよう
「最近辞めた人が多い気がする」といった肌感覚に頼ってしまうと、施策の優先順位を誤る原因となります。データに基づいた可視化ができれば、組織として問題を共有しやすくなり、改善に向けた合意形成も進めやすくなります。感覚ではなく、数字で語る姿勢が求められます。
【推奨】「みんなのマネージャ」のような可視化ツールの活用
感情や人間関係など、定着に影響する“見えにくい要素”を把握するには、エンゲージメントツールが有効です。
「みんなのマネージャ」では、週次アンケートを通じて従業員の状態を可視化し、必要なフィードバックもAIがサポートします。
現場での対話の質が高まり、定着率向上に直結する環境が整います。
定着率の算出方法と注意点を知ろう
定着率の数字は、人材の流出だけでなく、職場の問題を浮き彫りにする重要なヒントを含んでいます。
正しい方法で測定し、その背景にある原因を読み解くことで、職場改善や制度設計につなげることが可能です。そして、可視化やフィードバックの質を高めるツールを導入することで、単なる“管理”から“改善”へと活用の幅を広げることができます。
今こそ、定着率の数字にしっかりと向き合ってみませんか?

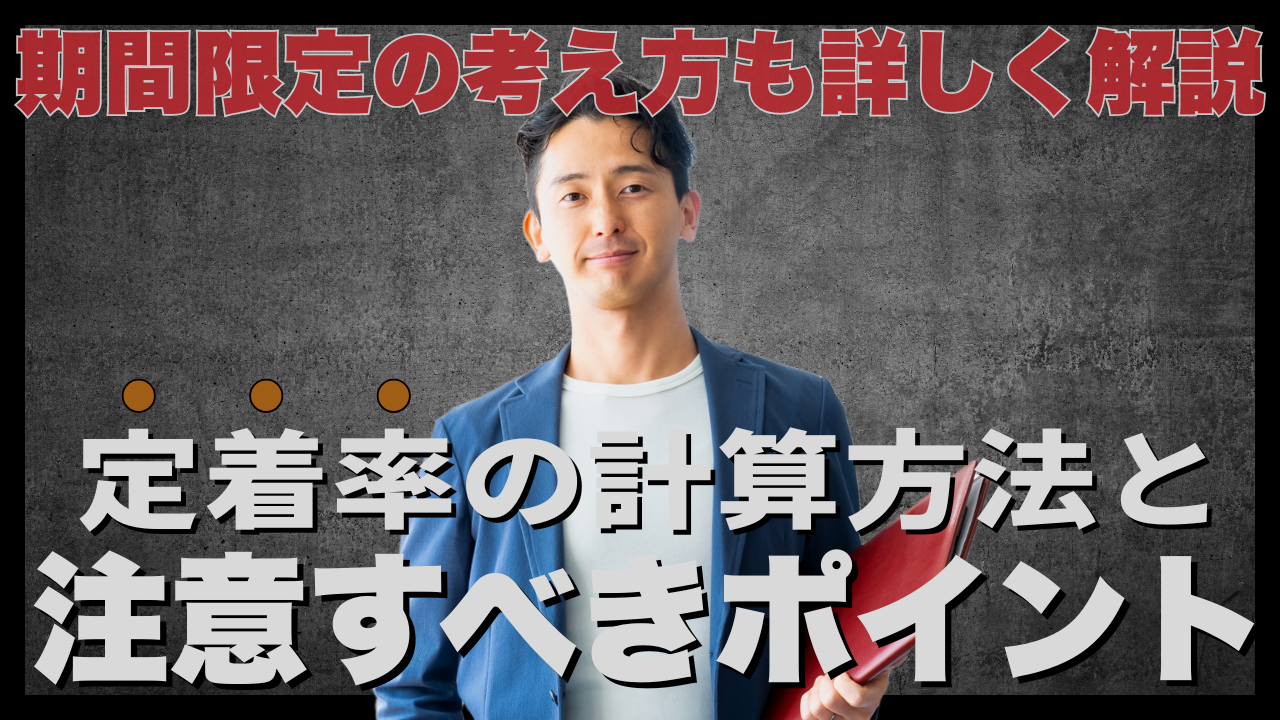


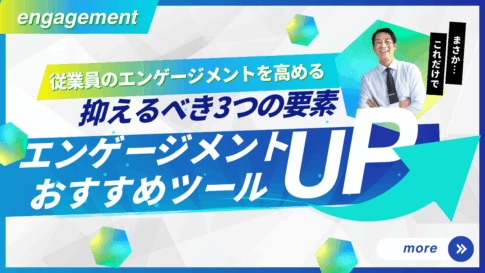
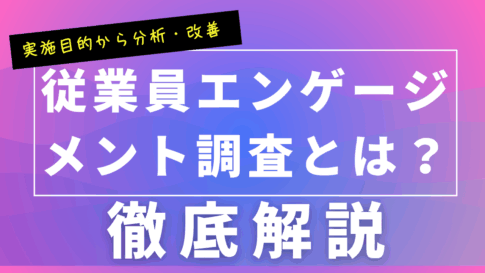
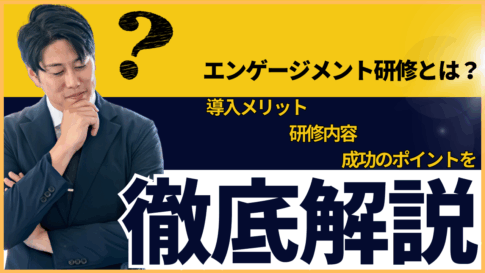
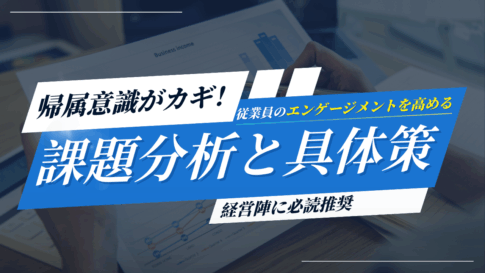

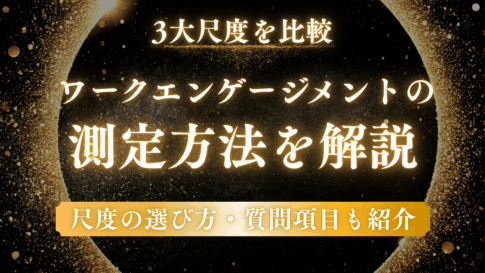





組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。