
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。

社内のマネジメントに「アドラー心理学」を活かしてみたい!

難しそうだけれど社長がおっしゃるのなら……
私も学んでみます!
人間関係に悩んだとき、自分や他人の言動をどう受け止めたらよいのか迷う場面は多いものです。そんなとき、解決の糸口として注目されているのが「アドラー心理学」です。
本記事では、アドラー心理学のエッセンスを平易に解説しながら、日常生活や職場、家庭での実践方法をご紹介します。さらに、チームづくりやエンゲージメント向上に活用されている「みんなのマネージャ」との組み合わせ方にも触れ、より実践的なヒントをお届けします。
- アドラー心理学をわかりやすい内容で解説され、理解できる
- 職場やプライベートでのアドラー心理学の活用法を理解できる
- アドラー心理学と合わせるとよりよい職場での施策を知れる
アドラー心理学の基本と現代社会での価値
アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラーが提唱した「個人心理学」と呼ばれる心理理論です。特徴は「人は過去に縛られず、今と未来に意識を向けることで変化できる」という前向きな思想にあります。
現代社会では、対人ストレスや孤独感が大きな課題となっており、この理論が注目される背景でもあります。自分自身の行動に責任を持ち、他者との対等な関係を築くことを重視するアドラー心理学は、職場や家庭など、あらゆる人間関係に応用可能です。
当記事でははじめに
- フロイトやユングの心理学との違い
- 今の時代にアドラー心理学が必要とされる理由
を解説します。
フロイトやユングとの違い
フロイトは「過去の体験が現在の行動を決める」とする原因論に基づき、ユングは「集合的無意識」に注目しました。一方アドラーは、「人の行動には必ず目的がある」と考える“目的論”を採用しています。
たとえば、ある人が発言を避けるのは「注目を浴びることを避けたい」という目的があるからだという解釈です。
この視点は、他者を責めるのではなく、その背景にある意図に目を向ける柔軟な思考につながります。
今の時代に必要とされる理由
SNSやリモートワークの普及により、物理的な距離だけでなく心理的な距離も感じやすくなっています。そんななか「自分らしくありたい」「相手にどう接すればいいか分からない」と悩む人が増えています。
たとえば、ある人が発言を避けるのは「注目を浴びることを避けたい」という目的があるからだという解釈です。
アドラー心理学は、自分と他者の違いを尊重しながら関係を築くための思考法として、現代の課題にフィットしています。
過去を変えることはできませんが、今の自分の考え方を見直すことで、未来の行動を変えることができるのです。
日常生活に取り入れるアドラー心理学の視点
アドラー心理学の考え方は、日々の人付き合いや自己との向き合い方に活用できます。特に、劣等感にどう対処するか、目的志向の思考で悩みを読み解く方法、そして他者との関係を前向きにする勇気づけの実践は、多くの人にとって取り入れやすいエッセンスです。
続いてはアドラー心理学の視点を
- 劣等感は成長のきっかけ
- 悩みは「目的」で解決できる
- 勇気づけが信頼関係を育てる
の3つの観点で紹介します。
劣等感は成長のきっかけ
「自分には○○が足りない」と感じたとき、多くの人はその劣等感を否定的に受け止めます。しかしアドラー心理学では、それを“成長の種”と捉えます。
| 思考法の違い | 通常 | アドラー心理学 |
|---|---|---|
| 不足するものに出会ったとき | 「自分には○○が足りない」 | 「これは自分の成長の種だ」 |
| エネルギー | マイナスへ働く | プラスへ働く |
| 組織力 | 低下する恐れあり | 向上の可能性大 |
アドラー心理学をわかりやすく噛み砕くと、前向きな成長の種として、自分の現状を認識できるようになります。
大切なのは、他人と比較するのではなく、昨日の自分と比べてどう進んだかに目を向けること。劣等感を自分への否定ではなく、未来への起点と捉え直すことが鍵になります。
悩みは「目的」で理解できる
アドラー心理学では、感情や行動の背景には何らかの目的があると考えます。たとえば「会議で発言できない」のは、「失敗して恥をかくのを避けたい」という目的があるかもしれません。
| 悩みに対するアプローチ | 会議で発言できない | 友達と距離を感じる |
| 行動を選んだ心理 | 恥をかくのを避けたい | 築くつことからにげたい |
なぜそう感じるかではなく「何のためにその行動を選んでいるのか」と捉え直すことで、より冷静な対処にもつながります。
悩みを「行動の目的」で捉えると、変化の可能性が見えてきます。
勇気づけが信頼関係を育てる
「勇気づけ」とは、相手の可能性を信じ、前に進む力を与える関わり方です。これは、ただ褒めることとは異なり、相手の努力や存在そのものに価値を見出す行動です。
たとえば、「最後までやり切ったね」「工夫していたのが伝わったよ」と声をかけることが、相手の内発的なやる気を引き出します。
また、自分自身に対しても「少しずつ前進している」と認める勇気づけは、自己肯定感の土台になります。
仕事に活かすアドラー的マネジメントの視点
アドラー心理学の考え方は、部下育成やチーム運営といったマネジメントにも応用できます。指示や評価で人を動かすのではなく、「信頼」と「主体性」に重きを置くことで、組織全体の関係性と成果を底上げするアプローチです。
続いては、アドラー心理学を取り入れた職場での実践法を
- チームに貢献する意識が生む活気
- 評価よりも共感を優先する姿勢
- 自律を促すフィードバックの工夫
の3ポイントで紹介します。
チームに貢献する意識が生む活気
アドラー心理学では「他者貢献感」が幸福の源とされます。職場でも、メンバーが「自分の仕事が誰かの役に立っている」と実感できれば、やる気と責任感が高まります。
たとえば、「あの資料、すごくわかりやすかったよ」「助かった!」と具体的に伝えるだけでも、貢献したという自己肯定感が育ちます。
こうした関係性は、チーム全体の協力意識や士気の向上にもつながります。
評価よりも共感を優先する姿勢
「よくやった」「すごいね」といった評価は一見ポジティブですが、受け手によっては上下関係を強調されているように感じることもあります。
- アドラー心理学では、上司が部下に対して“共感”の姿勢を持つことが、信頼関係の構築につながるとされています。
- 上下関係の協調を和らげることにもつながります。
「それは大変だったね」「そう感じたのは無理もないよ」と寄り添う一言が、相手に安心感を与えます。評価よりも理解が、信頼される上司になるための鍵なのです。
自律を促すフィードバックの工夫
アドラー心理学の実践では、結果だけでなく過程を認めるフィードバックが推奨されます。たとえば「結果は厳しかったけど、過程で工夫していたことに意味がある」と伝えることで、部下は自分の成長に気づきやすくなります。
このような関わりは、自ら考えて行動する“自律型”のメンバーを育てる土壌となります。一方的に指導するのではなく、「気づき」を引き出す問いかけが、マネジメントの質を変えていきます。
家庭でも活かせるアドラー心理学の関係作り
アドラー心理学は職場や組織のみならず、家庭内の関係改善にも有効です。子育てや夫婦間のコミュニケーションで、感情的にならず信頼をベースに関わる方法として、多くの家庭教育でも注目されています。対等な関係を意識し、お互いの存在価値を認め合うアプローチが、家庭の雰囲気を大きく変えていきます。
当記事では一例として、組織外でのアドラー心理学の活用方法を
- 子どもへの接し方
- 夫婦関係
の2つの観点で紹介します。
職場での人間関係や部下とのやり取りだけではないアドラー心理学の活用方法を知り、より広く実践していきませんか。
子どもへの接し方は「勇気づけ」が基本
子どもを褒めることは大切ですが、過度な承認は“評価されるために頑張る”状態を生む可能性があります。アドラー心理学が提唱する「勇気づけ」は、子ども自身の努力や行動に価値を見出す言葉がけです。
たとえば、「最後まで自分でやったね」「その工夫は君らしいね」といった声かけは、自己信頼を育みます。
親子関係においても、子どもをコントロールするのではなく、一人の人として尊重する姿勢が信頼を深めます。親子関係をうまく気づける上司は、職場でも適切に部下を思いやることができるはずです。
夫婦関係を支える共同体感覚
アドラー心理学では「自分はこの場所に貢献できている」「ここにいていいんだ」と感じられる状態を「共同体感覚」と呼びます。
家庭という小さな社会の中で、お互いの役割や存在に感謝を伝えることで、この感覚は育ちます。
「お疲れさま」「ありがとう」「あなたがいて助かる」といった言葉が自然に交わされる関係は、安心感と信頼を生み出します。感情のぶつけ合いではなく、対等な会話が夫婦の絆を深める鍵となります。
プライベートな場での心の充実は、社会面でもより良い人間関係を築くことにつながるでしょう。
アドラー心理学×みんなのマネージャ活用術
アドラー心理学を日常的に実践し続けるには、理論だけでなく「習慣化できる仕組み」が不可欠です。
そこでおすすめなのが、マネジメント支援ツール「みんなのマネージャ」の活用です。
みんなのマネージャでできること
- アドラー心理学の「勇気づけ」を行う
- アドラー心理学の「共同体意識」を定着
以下では、具体的にどのような形でアドラー心理学の実践を促してくれるのか、そのポイントを紹介します。
勇気づけを日常に取り入れる仕組み
みんなのマネージャは、メンバーの状態を週単位で把握できるパルスサーベイを中心に、個々の心の変化に合わせたアプローチを可能にします。
たとえば最近落ち込み気味の部下に対して、ツール上のヒントをもとに「努力してるの、ちゃんと見てるよ」と伝えるだけでも、その人の自己肯定感は大きく変わります。これはアドラーが説く“存在の価値を認める”勇気づけに他なりません。
ツール「みんなのマネージャ」があることで、勇気づけを「気合や経験」ではなく「仕組み」として実践できるようになり、組織力の向上につながります。
主体性を促すフィードバック設計
アドラー心理学が大切にするのは、相手が“自ら気づき、選んで行動する”ことです。
「みんなのマネージャ」では、1on1の場面で使えるフィードバックテンプレートや行動提案が用意されており、マネージャーや管理職が“答えを与える”のではなく、“問いかけて引き出す”スタイルを自然に実践できるように設計されています。
これにより、部下の内発的な動機を損なわずに成長を促せるマネジメントが実現します。
安心できる職場を支える心理的安全の可視化
アドラー心理学の実践では、「自分はここにいていい」「話しても否定されない」という安心感が重要です。
「みんなのマネージャ」は、エンゲージメントの数値化や課題の可視化を通じて、チーム内の心理的安全性を数値的に把握することができます。このような可視化によって、言葉にならない違和感や孤立感にいち早く気づけるため、適切な対話やフォローがしやすくなります。
職場での人間関係の土壌を整えるという意味でも「みんなのマネージャ」はアドラー心理学と高い親和性があるツールです。
人は変われる!アドラー心理学で組織力を存分に活かそう
アドラー心理学は、「人は変われる」「人はつながって生きている」という前向きな前提に立った思考法です。劣等感や人間関係の悩みを“避けるべきもの”ではなく、“成長へのヒント”として捉える姿勢は、現代においてこそ必要とされています。
特に、家庭や仕事など人と関わるすべての場面で、アドラーの考え方は人間関係をより豊かなものにする力があります。
さらに、その考え方を組織で活かすには「みんなのマネージャ」のようなツールを活用することで、理論と実践をつなぐ仕組みを持つことが大切です。勇気づけやフィードバック、心理的安全性の向上を日常業務の中で実践できる環境が整えば、チームや組織は自然と前向きな方向へ進化していくはずです。



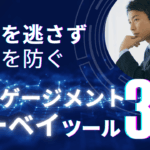
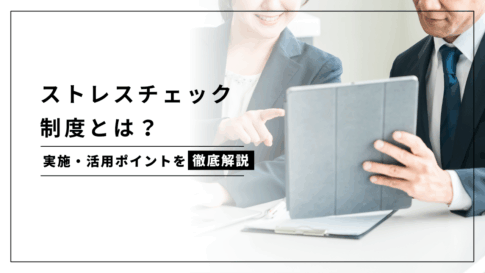
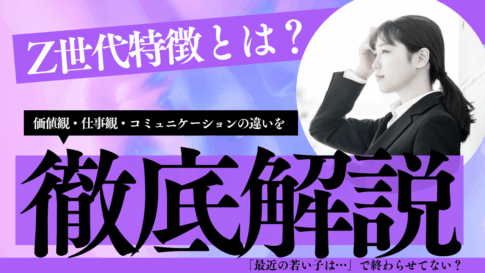

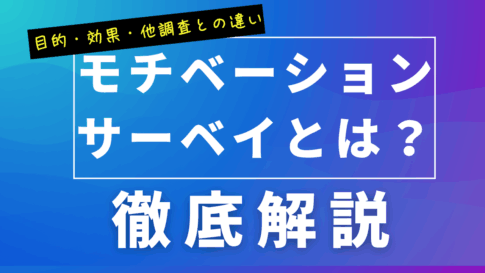

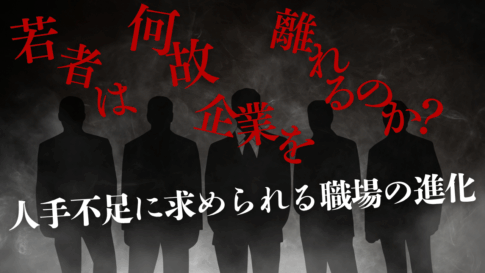
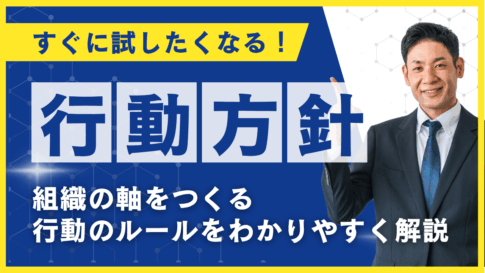
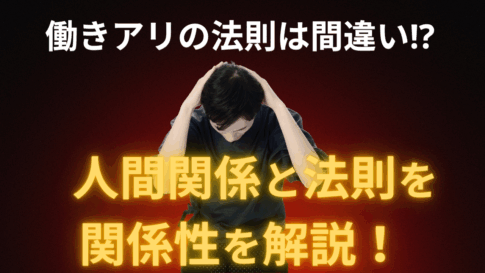



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。