
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
保育士の離職率が高いことは、保育園の経営や園児の安心・安全に直結する大きな問題です。特に私立園では10%を超える離職率が報告されており、人材確保や育成に悩む園長や人事担当者も少なくありません。
本記事では、保育士が離職する主な原因を整理し、離職を防ぐために有効な施策を実例を交えて解説します。あわせて、定着率を67%改善した実績を持つマネジメントツール「みんなのマネージャ」についてもご紹介します。
離職リスクを減らし、安心して働ける職場づくりのヒントを得たい方はぜひご一読ください。
- 保育士の離職率はなぜ高いのか
- 保育士の離職を防ぐ具体的な対策
- 離職率を下げるためのおすすめのツール
保育士の離職率はなぜ高い?現状と背景を知る
保育士の離職率は、他の職種と比べても高い傾向にあります。その背景には、以下のような様々な理由があります。
- 給与水準の低さ
- 過酷な労働環境
- 人間関係のストレス
特に保育園の経営者や採用担当者にとっては、安定的な人材確保が事業継続のカギとなるため、離職率の実態と原因を正しく把握することが重要です。
この章では、最新データや傾向をもとに、保育士の離職問題の全体像を明らかにします。
最新データにみる保育士の離職率
保育士の離職率は、私立か公立かでも異なります。私立と公立の離職率は以下のとおりです。
| 私立 | 10〜12% |
| 公立 | 5〜6% |

私立の保育園のほうが、離職率が高いのですね。待遇改善が、定着率を上げる鍵になるでしょう。
さらに若手層では3年以内の離職率が25%を超えるとのデータもあります。特に初期段階での早期離職が深刻な課題です。
全体として医療・福祉業界の離職率は約14.6%であり、その中でも保育士は高水準を維持しています。離職率の高さは、保育の質や園児の安全にも直結するため、組織として対策が急務です。
私立と公立で異なる離職率の傾向
私立と公立で異なる離職率の傾向があります。
| 公立保育園 | 給料や福利厚生が安定している離職率は低め |
| 私立保育園 | 経営方針が園によって異なる離職率は公立に比べて高め |
公立保育園では自治体の職員として雇用されるため、給与や福利厚生が安定しており、離職率も低めです。
一方、私立保育園では人材確保や待遇改善の取り組みが園ごとに異なり、安定性に差が出やすい傾向があります。また、経営状態や運営方針に左右されやすく、現場の負担が大きくなることが離職につながる要因の一つです。

公立の保育園のほうが公務員のため、待遇が安定しています。
若手保育士の離職が目立つ理由
新卒や入職3年未満の保育士における離職率の高さは「研修体制の未整備」や「期待とのギャップ」が主な原因です。
以下のような理由で、早期に離職を選ぶケースが多く見られます。
- 理想と現実の乖離
- 職場の雰囲気が合わない
- 人間関係の難しさ
適切なフォローやキャリア設計の支援がないままに現場を任されることで、心理的な負担も増加します。
保育士が離職する主な理由とは?
保育士が職場を離れる理由は、一つに絞れないほど多様です。以下のような理由も大きく影響します。
- 給与や労働時間といった待遇面の不満
- 人間関係や精神的なストレスライフステージの変化
これらの要因は単独ではなく、複数が重なって離職という決断につながるケースが多く、職場の管理者はそれぞれの背景を丁寧に理解し、対処する必要があります。
給与や待遇への不満
保育士の平均年収は、他の業種と比較して低い水準にあるとされています。経験年数に応じた昇給が乏しく、責任の重さと報酬のバランスにギャップを感じるケースが多いです。
また、私立園では賞与や福利厚生の差が大きく、待遇面の不公平感がモチベーション低下を引き起こす原因になります。給与水準が保育のやりがいを上回る課題となったとき、転職を選ぶ保育士も少なくありません。

給料や待遇への不満は特に多いようですね。

同じ保育士でも、待遇に差があるのでは考えてしまいますよね。
人間関係・上司との相性
保育士同士、あるいは上司との関係性が原因で離職に至るケースも非常に多いです。職場の人間関係は業務の円滑さに直結し、信頼関係が築けない環境ではストレスが蓄積します。
特に新人保育士が孤立感を抱えたり、相談できる相手がいない場合、職場に安心感を持てずに離職を選ぶ傾向があります。

相談できる相手がいることは、安心感につながります。
長時間労働と心身への負担
保育士は、長時間労働になることもあり、心身への負担がかかることも少なくありません。保育業務は以下のように多岐にわたります。
- 子どもの相手
- 保護者対応
- 書類作成・行事準備など
定時退勤が難しく、長時間労働が常態化している園も少なくありません。心身ともに疲弊し、体調不良や精神的な不調に陥ることで、継続勤務が困難になるケースもあります。
ライフイベントとの両立課題
保育士の多くは女性であり、妊娠・出産・育児といったライフイベントに直面することも多いです。園の制度や理解が十分でない場合、働き続けることが難しくなり、離職につながります。
また、家庭との両立が困難であると感じた際、より柔軟な働き方を求めて転職を考えるケースも増えています。

ライフイベントを機に保育士をやめる人は少なくありません。
保育士の離職を防ぐ具体的な対策
保育士の離職率を下げるためには、現場の課題に寄り添った具体的なアプローチが欠かせません。給与や制度の整備も重要ですが、それ以上に日常的な「対話」や「ケア」がカギになります。
園長や採用担当者は、保育士一人ひとりの状況を正確に把握し、安心して働ける環境を整える役割を担っています。この章では、実践的で現実的な離職防止策について紹介します。

では、実際に離職防止策についてみていきましょう。

園独自の良い部分があると、離職率が下がりそうですね。
面談・アンケートで本音を把握する
職員の不満や悩みを早期に察知するには、定期的な面談やアンケートが有効です。表面的な会話では見えない本音を引き出すために、匿名性のあるサーベイや1on1の導入が推奨されます。

面談やアンケートは、職員の不満や悩みを聞き出すのに効果的です。
保育士が安心して声を届けられる仕組みを整えることで、早期離職のリスクを下げることができます。
業務量と役割の見直しで負担を軽減
日常業務の負担が離職に直結するため、業務の棚卸しと役割分担の見直しが効果的です。以下のようなシステムを活用することにより、保育士が子どもと向き合う時間を確保できます。
- 書類作業のICT化
- 行事準備の簡素化
- 外部委託の活用
職場全体で「無理を前提としない働き方」を目指すことが、長期的な定着につながります。
キャリア支援とスキルアップの機会提供
保育士が成長を実感できる環境づくりも、離職防止において重要です。以下のようなキャリアアップやスキルアップの機会の導入も検討すると良いでしょう。
- 定期研修
- 資格取得支援
- スキル評価制度
「自分は評価されている」「成長できている」と感じることでモチベーションが高まります。中長期的なキャリアビジョンを描けることが、継続意欲の向上に直結します。
メンタルケアと心理的安全性の確保
保育士の仕事は感情労働とも言われ、常に気を張っている状態が続きやすいため、メンタル面での支援が欠かせません。以下のような体制を整え、安心して相談できる風土をつくることが求められます。
- 第三者によるフォロー体制
- カウンセリング
- 定期的なリフレクションの場を設ける
心理的安全性が担保されることで、職員の離職意欲は大きく下がります。

やはり心理的安全性が職場では大切ですよね。

定期的にリフレッシュできる機会があると良いですね。
離職防止に活用できるツール「みんなのマネージャ」とは?
離職を防ぐ取り組みの中でも、マネジメントの質を高め、職員の声を「見える化」する仕組みは大きな効果を発揮します。
「みんなのマネージャ」は、保育現場の人材定着に課題を持つ園に最適なサポートツールです。
以下のような、科学的かつ実践的な機能が多数搭載されています。
- エンゲージメントの数値化
- AIによる行動提案
- 週次サーベイによる状態把握
本章では、園長や人事担当者に向けて「みんなのマネージャ」の特長と導入メリットを紹介します。
保育現場の声を「見える化」する仕組み
「みんなのマネージャ」の最大の特長は、職員のエンゲージメント(組織への関与度や満足度)を定期的に数値化できる点です。
週に1回、3〜7問の簡単なアンケートを実施することで、モチベーションや心理的な状態の変化をリアルタイムで把握できます。AIが状態に応じて質問内容や頻度を調整するため、違和感なく本音を拾い上げることができます。

3~7問の簡単なアンケートなので、答えるハードルが下がりますね。

アンケートとは答えるだけで簡単なので、ぜひ取り入れたいです。
マネージャの育成と行動提案の仕組み
「みんなのマネージャ」は単なる可視化ツールではなく、マネージャ自身の育成支援にも力を発揮します。
回答結果に基づいて、従業員ごとに最適なフィードバック内容や話し方のアドバイスがAIから提案されます。これにより、マネージャごとのスキル差を解消し、園全体で質の高いマネジメントが実現できます。
現場ごとのデータ比較で早期の離職予兆を発見
複数の保育園を運営する法人にとっては、園ごとの課題の見える化も重要です。
「みんなのマネージャ」ではグループ別のエンゲージメントスコアを比較でき、離職予兆の早期発見や他園との改善ポイントの差異分析が可能です。
これにより、問題が深刻化する前に対処でき、組織全体の安定化につながります。

離職予兆を見極めることが大切です。
定着率67%改善の実績とその仕組み
実際に「みんなのマネージャ」を導入した企業では、マネージャ育成と週次チェックの仕組みにより、離職率が67%も改善された事例があります。
離職理由が「なんとなく合わない」から「昇進面談へ変化」したというエピソードもあるほどで、組織としての変化が現場に確実に反映されます。
属人的になりがちなマネジメントをシステム化することで、継続的かつ再現性のある職場改善が実現します。

離職率がかなり改善されていますね。

「みんなのマネージャ」を取り入れるのは有効ですね。

そうですね。ぜひ離職率に悩んでいる採用担当者の人は「みんなのマネージャ」取り入れてみてください。
まとめ
保育士の離職率の高さは、園運営における大きな課題の一つです。給与や労働環境、ライフイベントへの対応といった多面的な要因が重なり、離職という選択を迫られている保育士が数多く存在します。しかし、現場の声を丁寧にすくい上げ、的確なマネジメントを行えば、離職率の改善は十分に可能です。
そのためには、以下のような対策を一過性で終わらせず、継続的に取り組むことが必要です。
- 定期的な面談
- アンケート
- 業務の見直し
- キャリア支援
また、マネジメントの属人化を防ぎ、誰でも質の高い対応ができる体制づくりも重要なポイントです。「みんなのマネージャ」は、保育士の本音を見える化し、マネージャの行動をサポートする仕組みとして、離職防止に非常に有効なツールです。
定着率の改善や組織の一体感向上を実現したい園長・採用担当者の方は、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。


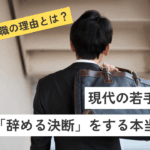
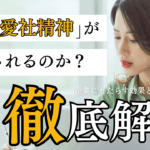
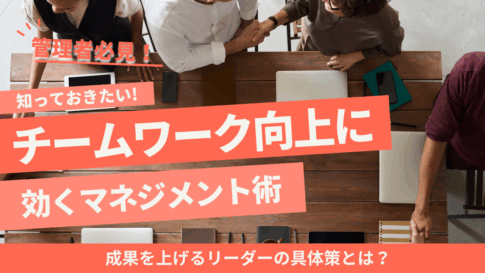

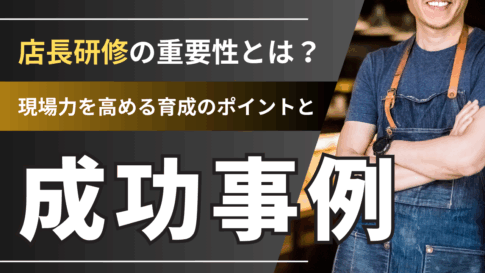
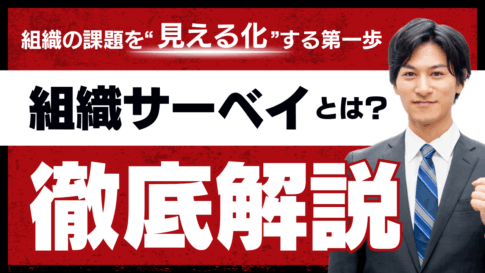
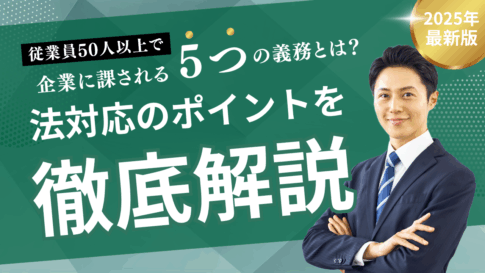
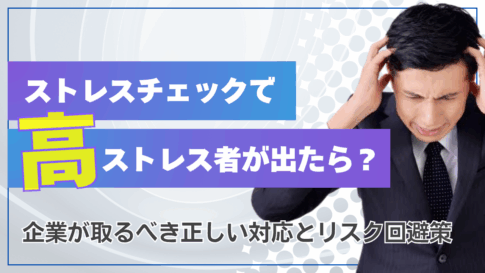
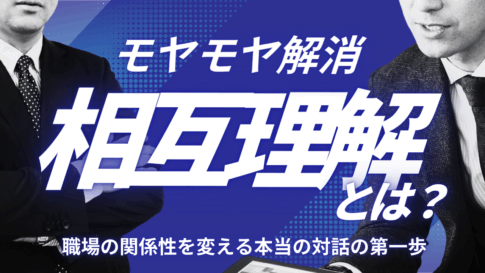
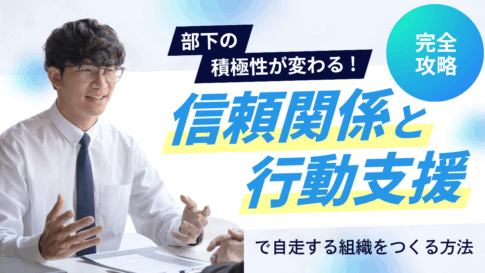



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。