
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「職場に行くのが怖い」と感じる従業員の存在に、企業はどこまで気づけているでしょうか。
人事担当者として、こうした心のサインを見逃さず、適切に対応することは離職リスクを未然に防ぐ鍵となります。
本記事では、従業員が職場に恐怖を感じる主な原因や、その背後に潜むメンタルヘルス上の課題を解説するとともに、企業が取り組むべきセルフケア支援と心理的安全性の構築方法をご紹介します。
特に、エンゲージメント向上を図るツールとして注目される「みんなのマネージャ」の活用法にも触れながら、人材定着と健全な職場づくりに貢献する実践的なヒントをお届けします。
- 「職場に行くのが怖い」と感じる従業員の心理と主な原因
- 人事担当者が気づくべきメンタル不調のサインと対応のポイント
- セルフケア支援・心理的安全性を高める実践的なアプローチ
- 「みんなのマネージャ」を活用した離職防止の方法
従業員が「職場に行くのが怖い」と感じる背景とは?
人事担当者にとって、従業員の離職リスクを事前に察知することは極めて重要です。
その兆候の一つに「職場に行くのが怖い」という心理状態があります。
これは、単なる怠慢や甘えではなく、職場に対する恐怖や不安が積み重なった結果である場合が多いのです。

「頑張れって言葉、悪気なくてもプレッシャーになること、ありますよね…
💡 ポイント
従業員の「怖い」という感情は、表面化しにくい重要なサインです。日頃から従業員の変化に注意を払いましょう。

甘えと誤解せず、背景にあるストレス要因を丁寧に掘り下げましょう。
こうした感情は、本人すらうまく言語化できないまま表出せず、ある日突然の休職・離職という形で表面化します。
本章では、人事が注意すべき職場不安の要因を明らかにし、従業員の心の変化に気づくヒントを提供します。
職場不安を引き起こす主な要因とは?(人間関係・プレッシャー・トラウマ)
「職場が怖い」と感じる背景には、上司との摩擦や孤立感、過去のミスによる自己否定など、複合的な要因が潜んでいます。
特に、評価面談や日常業務の中で、過度なプレッシャーを感じやすい環境がある場合、従業員は徐々に心理的負担を蓄積します。
職場不安を引き起こす主な要因
| 要因カテゴリ | 具体例 | 影響 |
| 人間関係 | 上司との摩擦、同僚からの孤立 | 職場での居場所の喪失感 |
| 業務プレッシャー | 過度な目標設定、評価への不安 | 慢性的なストレス状態 |
| 過去のトラウマ | 失敗への恐怖、叱責の記憶 | 再発への過度な不安 |
また、過去の失敗に対するフォローがなかった場合、それがトラウマとなって残り、再発への恐怖が強まることもあります。
人事はこうした要素を想定し、現場からの小さな兆候にも敏感である必要があります。

トラウマを残さない振り返りと受容の姿勢が、再発防止にもつながります。
適応障害・うつの前兆である可能性も
業務上の不安が継続し、朝になると体調不良や強い不安を訴えるようになった場合、それは心の病の初期症状かもしれません。
特に真面目で責任感が強いタイプの従業員ほど、表面的には普段通りに見えることがあります。
⚠️ 注意すべきサイン
朝の体調不良、遅刻の増加、表情の変化などは、メンタル不調の初期サインの可能性があります。
人事担当者としては、こうした”沈黙のサイン”を見逃さず、適切な面談や産業医への連携を早期に行う体制を整えておくことが重要です。
人事が支援できるセルフケアとメンタル対策の考え方
従業員が安心して働き続けられる環境を整えるには、本人任せにせず、企業側の積極的な支援が必要です。とくにメンタル面での不調を感じ始めた段階で、セルフケアの意識づけや相談体制の整備が求められます。本章では、人事が従業員に対して提供できる具体的な支援方法と、日常的なケアのポイントを解説します。
「否定しない姿勢」の重要性
従業員が抱える不安や恐怖の感情に対し、「まだ働けるはず」「頑張りが足りない」などと否定するのは逆効果です。人事担当者は、まずその気持ちを受け止め、共感を示す姿勢が必要です。

「頑張れ」って言葉、悪気なくてもプレッシャーになること、ありますよね….
💬 適切な対応例
「話してくれてありがとう。まずはあなたの気持ちを大切にしましょう」
このような受容的な姿勢が、従業員との信頼関係を築く第一歩となります。
本人が声に出したこと自体を前向きにとらえ、「話してくれてありがとう」と伝えることが信頼構築につながります。
心理的安全性は、その一言から始まるのです。

「これは心理的安全性の基本姿勢。“否定しない聴き方”が関係性を守ります。
日常でできるストレス軽減のサポート
業務中の緊張や疲労を和らげるには、日常的なリズムのなかでできるケアが有効です。例えば、福利厚生の一環として瞑想アプリやリラクゼーションルームの導入、勤務時間中の休憩の質向上などが挙げられます。
- 瞑想アプリの法人契約による従業員への提供
- 社内リラクゼーションスペースの設置
- 質の高い休憩時間の確保(スマートフォンから離れる時間の推奨)
- 週1回のコンディション日報による自己観察の習慣化
- 適度な運動機会の提供(ウォーキング会、ストレッチ教室など)

スマホを見ないだけで、意外と気持ちが落ち着くって最近気づきました。
また、週1回の状態記録(コンディション日報)などを取り入れることで、従業員自身が自分の状態に気づく機会も提供できます。
人事主導でこうした習慣を文化として根づかせることが望まれます。

書くことで、自分でも気づいてなかった気持ちが見えてくることってありますよね
相談環境の整備が職場定着の鍵に
社内に「安心して相談できる場所」があるかどうかは、離職率に直結します。
人事主導で設置された相談窓口や産業医との定期面談、さらにはメンタルヘルス専門の外部窓口の案内など、選択肢が複数あることで、従業員は「1人ではない」と感じられます。
🤝 相談しやすい環境作り
複数の相談窓口を設けることで、従業員は自分に合った相談先を選択できます。選択肢があることが安心感につながります。
相談のハードルを下げるためには、上司だけでなく第三者のサポート体制が重要です。

直属の上司には言いづらいことも、別の窓口があるだけで安心できます。

選択肢があるだけで“支援されている”という感覚が生まれます。
従業員の不安を放置しないために人事ができること
従業員の「職場に行きたくない」という気持ちは、組織にとって重大なリスクシグナルです。
この感情を見逃したまま放置してしまうと、心身の不調や突然の離職といった深刻な事態につながることがあります。
人事担当者は、従業員の心の状態を可視化し、適切な対話と制度で早期に対応する体制を整えておく必要があります。
本章では、休職支援や職場変更、転職のサポートに関する人事の役割と考え方について解説します。
休職や専門機関受診を促す体制整備
従業員が明らかに不安を抱えているにもかかわらず、無理に出勤させてしまうことは、企業としてのリスク管理の観点からも避けるべきです。
適切な休職制度の整備とともに、「心療内科や産業医への受診をためらわず相談できる」文化づくりが求められます。
- ✅ 休職制度の明文化と従業員への周知
- ✅ 産業医面談の定期実施と緊急時対応体制
- ✅ 心療内科・精神科の紹介先リストの準備
- ✅ 受診時の勤務時間調整や費用補助制度
- ✅ 復職支援プログラムの策定
人事が積極的に情報提供や受診同行を行うことで、従業員の安心感と信頼を高めることができます。
「転職=逃げ」ではないという視点の転換
すべての職場がすべての従業員に適しているとは限りません。特定の環境が本人にとって継続的なストレス源となっている場合、異動や配置転換、あるいは退職という選択肢も時に適切です。
🔄 視点の転換
転職や異動は「逃げ」ではなく、「本人の健康とキャリアを尊重した前向きな選択」として捉えることが重要です。

離職=損失と捉えるのではなく、次の成長ステップと位置づける発想が大切です。
人事としては、離職=失敗ではなく、「本人のキャリアと健康を尊重した選択」として柔軟に捉える視点が求められます。
信頼関係が構築されていれば、従業員自身も前向きな選択ができるはずです。
人事が注目すべき「職場が怖くならない組織作り」とは
従業員が職場に不安を抱かず、安心して働ける環境を整えることは、人事の重要な役割のひとつです。
近年は、エンゲージメント向上を目指した組織改善が注目されており、その実現には「可視化」「フィードバック」「心理的安全性」の3要素が鍵となります。
本章では、それを実現するための具体策として、クラウド型支援ツール「みんなのマネージャ」の導入メリットを交えて解説します。
定期的な状態把握に役立つパルスサーベイ
「従業員の今の気持ちが分からない」という状態を防ぐためには、定期的なアンケートによるコンディション把握が有効です。
「みんなのマネージャ」のようなパルスサーベイは、週1回という高頻度で短問数の質問を実施し、AIが回答に応じて実施頻度を自動調整するため、現場の負担も少なく継続できます。
パルスサーベイの特徴と効果
| 特徴 | 従来の年次調査 | パルスサーベイ |
|---|---|---|
| 実施頻度 | 年1回 | 週1回 |
| 質問数 | 50問以上 | 3-5問 |
| 回答負担 | 大きい | 小さい |
| 変化の把握 | 困難 | リアルタイム |
| 改善アクション | 遅れる | 即座に対応可能 |
これにより、人事やマネージャーが問題のある従業員を早期に察知し、的確にフォローアップすることが可能です。
フィードバックの質を高めるしくみで安心を
従業員が「怖い」と感じる職場の共通点は、否定的で一方的なコミュニケーションが多いことです。
「みんなのマネージャ」では、フィードバック内容だけでなく、伝え方やタイミングまでをAIが提案します。

何を言っても否定されるって感じると、声を上げるのが怖くなりますよね。
📈 フィードバックの質向上
AIによる提案により、マネージャーごとの対応格差が解消され、全従業員が公平で安心感のある対応を受けられるようになります。
これにより、マネージャーごとの差が解消され、どの従業員も公平で安心感のある対応を受けられます。
人事としては、こうした仕組みを活用し、マネージャーの育成支援と現場のフィードバック品質の向上を両立することが期待されます。

伝え方のの個人差を補完するのが、AI活用の本質です。
「みんなのマネージャ」で離職を防ぐ組織改善へ
「みんなのマネージャ」は、従業員のコンディションを数値で可視化し、組織の状態をリアルタイムに把握できるツールです。
タイムライン機能で従業員ごとの変化を追跡できるほか、AIによる優先フォローリストや行動提案により、マネージャーの対応力が大幅に向上します。
- 従業員コンディションの数値化・可視化
- 個人別タイムライン機能による変化の追跡
- AIによる優先フォローリストの自動生成
- マネージャー向け行動提案の自動配信
- 組織全体のメンタルヘルス状況のダッシュボード表示
人事はこの仕組みを活用して、従業員の離職予防、エンゲージメント向上、そして心理的安全性の高い職場文化の実現を推進できます。
まとめ
従業員が「職場に行くのが怖い」と感じる背景には、人間関係や過去の経験、メンタルの不調などさまざまな要因が存在します。人事担当者としては、そのサインを早期に捉え、休職支援・セルフケアの導入・フィードバック体制の強化など、多面的な対応が求められます。
🎯 人事の役割
従業員の心理的安全性を確保し、安心して働ける職場環境を築くことが、現代の人事に求められる最重要課題のひとつです。

ここでなら頑張れるって思える職場があるだけで、救われる人は多いはずです。
とくに「みんなのマネージャ」のようなツールを導入すれば、可視化・対話・改善のサイクルを現場で実行できるようになります。
離職を未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を築くことこそ、現代の人事に求められる最も重要な役割の一つです。

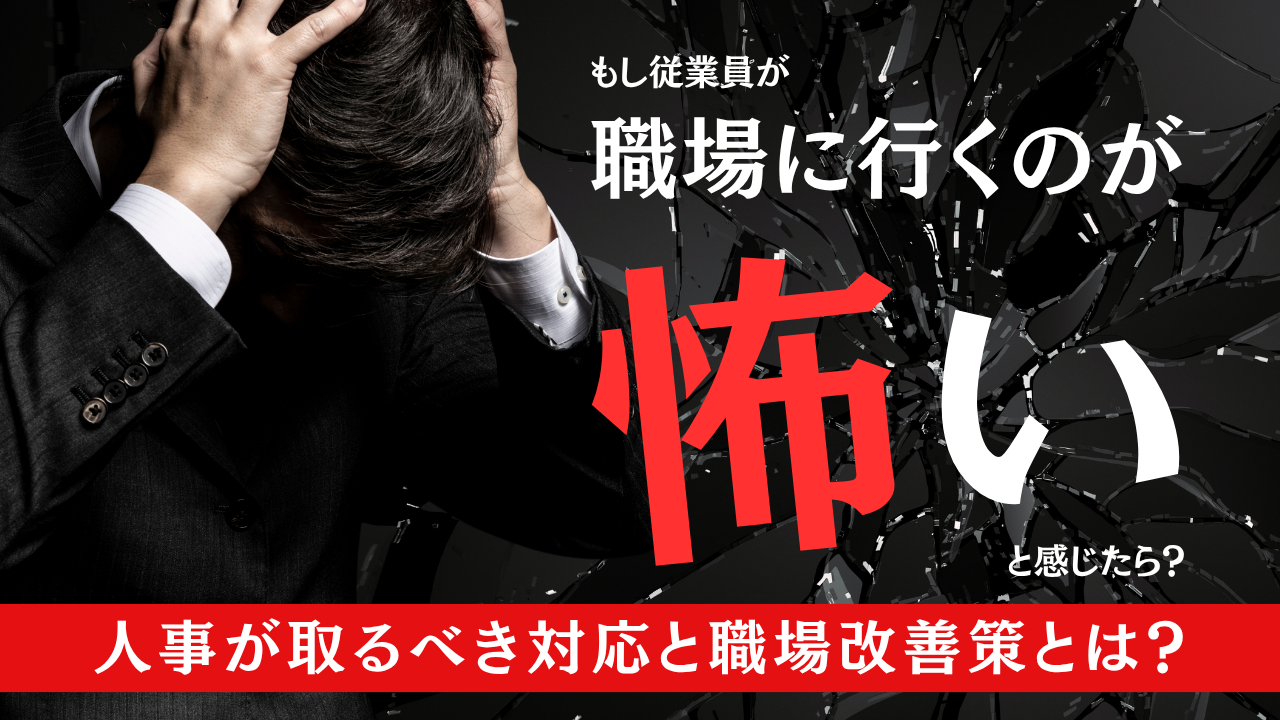

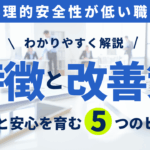
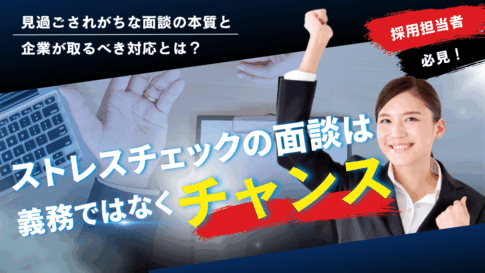

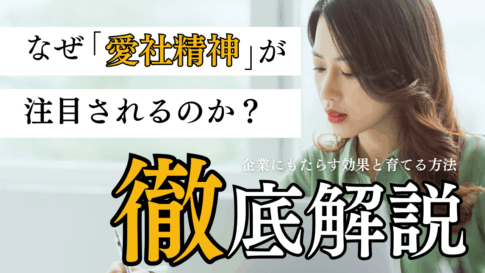
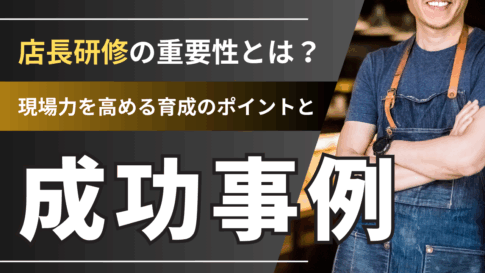
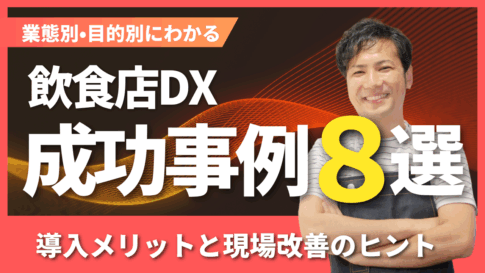
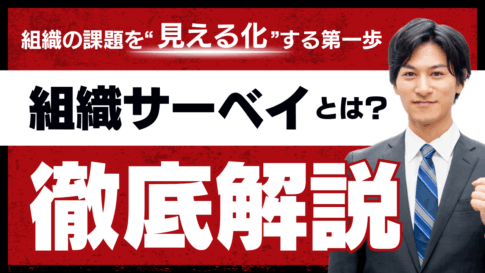
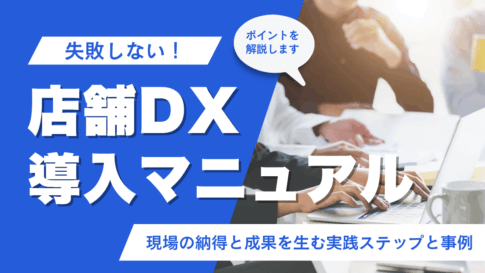




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。