
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
新卒として入社した若手社員が、数ヶ月から1年未満の短期間で会社を辞めてしまう。このような「早期離職」の問題は、今や多くの企業にとって深刻な悩みとなっています。
単なる一過性の現象ではなく、時代の変化に伴う働き手の価値観や環境の変化が背景にあるため、無視できない課題です。
「最近の若者は根気がない」「社会人としての自覚が足りない」などの批判もよく耳にしますが、果たして早期離職の責任は本人にだけあるのでしょうか?実は、採用側や企業の組織文化、育成体制にも大きな問題が潜んでいることが多いのです。
本記事では、早期離職の本質的な理由を探りながら、企業が何をすべきかを見ていきましょう。
- 早期離職の本質的な理由
- 早期離職を止めるための対策
- 早期離職が増えている理由
若手社員の早期離職率が増えている理由

今、若手社員の早期離職率が増えているというのは本当ですか?

はい、残念ながら若者の早期離職は大きな問題となっています。
まずは事実として、近年の早期離職の現状を数字で見てみましょう。
厚生労働省の調査によると、新卒入社者のうち約30〜40%が3年以内に会社を辞めているという驚くべきデータがあります。
さらに、その中でも特に1年以内に離職するケースが目立っており、「早期離職」の問題がクローズアップされています。

こうした高い離職率は決して珍しいことではなく、むしろ多くの企業が経験している「共通の課題」でもあるでしょう。
この背景には、昔ながらの「終身雇用」「年功序列」などの雇用慣行が崩れ、多様な働き方やキャリアの選択肢が広がったことがあります。
転職が以前より一般的になり、若手も「一つの会社にとどまることが必ずしも良いキャリアとは限らない」と考えるようになったのです。また、情報化社会の進展により、SNSや口コミで職場のリアルな様子が共有されやすくなったことも、入社前の期待と実態のギャップを浮き彫りにしています。
つまり、離職のハードルが昔より低くなったことは間違いありません。
「安易に辞めている」わけではなく、働く環境や自分のキャリアに対して真剣に考え、行動している結果でもあるのです。
早期離職が起こる理由

なぜ、早期離職は起きてしまうのでしょうか?

早期離職が起きてしまうのには、理想と現実のギャップが大きな要因となっていることがあります。
ここからは、なぜ早期離職が起きてしまうのか、その理由を見ていきましょう。
1.入社前とのギャップ(リアリティショック)
新卒者が「こんなはずじゃなかった」と感じてしまう大きな理由の一つが、入社前のイメージと実際の仕事内容や職場環境の違いです。採用活動の際、企業は良い部分を強調しがちですが、その結果、期待が過度に膨らみ、入社後の現実と大きな乖離が生じることがあります。
| 理想 | 現実 |
|---|---|
| 宣伝されていた「若手でも意見が言える風通しの良い職場」 | 実際は上司の指示が絶対で自由がない |
| 「裁量権が大きく自己成長できる」と説明された | 実際は単純作業や雑務ばかりで面白みがない |
| 会社の理念やビジョンに共感して入社した | 実際は日々の業務ではその理念がまったく反映されていない |
このような「リアリティショック」は、入社数か月で「この会社は自分に合わない」と感じてしまう原因となり、離職の一番のトリガーとなることが多いです。
2.職場の人間関係に起因するストレス
次に、多くの早期離職者が挙げるのが職場の人間関係の問題です。仕事のやりがいや給与面の不満はもちろんありますが、精神的に大きな負担となるのは、上司や同僚との関係性です。
例えば、以下が挙げられます。
- 指導が厳しいだけでフォローや助言がないため、不安や孤独を感じる
- 職場の雰囲気がピリピリしていて、コミュニケーションが取りにくい
- チームメンバーとの間に壁があり、自分だけ浮いている感覚がある
このような環境は、入社したばかりの若手にとっては特に辛く、精神的な負荷が重なり離職につながりやすいのです。
3. 教育・育成体制の未整備
社員の定着や成長に欠かせないのが、体系的な教育や育成の仕組みです。ところが、入社後の研修やフォローアップが不十分な企業では、新人は自分の役割や成長の方向性が見えづらく、モチベーションを維持できません。
「仕事は見て覚えろ」「教える時間がない」という古い考え方が根強い現場では、若手が試行錯誤するばかりで精神的に疲弊し、やがて離職の道を選んでしまいます。
また、せっかく努力しても評価やフィードバックが曖昧だと、「自分が成長しているのか分からない」という不安が募るため、辞めてしまう原因になります。
4. キャリアビジョンの欠如と評価制度の不透明さ
若手社員は、「この会社でどんなキャリアを描けるのか」「自分はどのように評価されるのか」を常に気にしています。
明確な将来像や公正な評価制度がなければ、努力の意味が見いだせず、やる気を失いがちです。
特に年功序列が強い組織や、評価が人間関係に左右されやすい職場では、「頑張っても報われない」と感じてしまいます。これが長く続けば、早期離職へとつながってしまうのです。
5. 働き方や待遇面の不満
現代の働き手、とくに若手は「ワークライフバランス」を重視する傾向にあります。長時間労働や休日出勤が当たり前の職場、残業代が正当に支払われない環境では、早期離職が増えるのは当然といえるでしょう。

また、育児や介護、自己啓発などのプライベートの事情を尊重してもらえない企業では、若手が「ここで長く働き続けるのは難しい」と判断しやすくなります。
早期離職対策が進まない理由

早期離職が問題となっているのに、対策が進んでいないのはなぜですか?

なぜ自社で早期離職が増えているのか、まずはその原因を探らなければなりません。
対策が進んでいないのには、自社の問題が明らかになっていないことが挙げられます。
「うちの会社を辞めるのは、本人の意識や努力不足が原因」という考えは、企業の根本的な課題解決を遠ざけるだけでなく、若手社員の信頼も失います。
実際には、組織の風土やマネジメントの問題が大きい場合も多くあります。
こうした考え方は、早期離職の連鎖を招き、採用コストや教育コストの無駄遣いを増やすことにもつながります。
若手の本音が組織に届いていない
早期離職の兆候は、本人が明確に言葉にしなくても、態度や行動で見て取れることが多いものです。例えば、以下が挙げられます。
- 会議やミーティングで発言が減る
- 業務への積極性が低下する
- 体調不良を訴えがちになる
- 職場に遅刻や欠勤が増える
こうした変化を上司や管理職が敏感に察知し、早めに対話の機会を持つことが重要です。
しかし、現実には忙しさやコミュニケーション不足、マネジメント層の経験不足などにより、こうしたサインを見逃してしまうケースも少なくありません。
また、若手社員自身も「言っても変わらない」「言いにくい」と感じてしまい、本音を隠す傾向があります。
結果、問題は悪化し、本人が辞める決断をするまで誰も気づかないこともあるのです。
早期離職を防ぐための対策

実際に早期離職の問題を解決するための対策が知りたいです。

ここからは、早期離職を防ぐための対策をご紹介します。
1. 入社前の情報開示を充実させる
採用段階から現実的で具体的な情報を伝えることは、早期離職防止の第一歩です。
- 仕事内容職場の雰囲気
- 求められるスキル
- 勤務時間待遇面
など
可能な限り正確に伝えることで、入社後のギャップを減らせます。
特に、現役社員の声や具体的な1日のスケジュール例を紹介するなど、リアルな情報提供が効果的です。
入社前のインターンシップや職場見学を活用して、体験的に理解してもらう方法もおすすめです。
2.上司や先輩による丁寧なフォローアップ
新入社員にとって、最初の数ヶ月は「職場に馴染めるか」「仕事を覚えられるか」などの不安が大きい時期です。上司や先輩が定期的に面談を行い、困っていることや悩みを聞き出す機会を設けることで、問題が深刻化する前に対応できます。
この際に重要なのは、叱責や批判ではなく、共感やサポートを前提としたコミュニケーションです。
若手が安心して本音を話せる環境をつくることが、離職防止には不可欠です。
3. 教育・育成体制の強化
体系的な研修プログラムやOJT(On-the-Job Training)を整備し、成長過程をしっかり支える仕組みが必要です。
仕事の進め方だけでなく、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルの向上も含め、段階的にステップアップできるカリキュラムを設計しましょう。
評価とフィードバックの体制を明確にし、努力や成果が適切に認められる仕組みも整えることが、モチベーション維持につながります。
4. 働きやすい環境づくり
長時間労働の是正や休暇の取得促進、柔軟な働き方の導入など、若手が安心して働き続けられる職場環境の整備も重要です。
育児や介護と仕事の両立支援をはじめ、多様なライフスタイルに対応できる制度の充実が求められます。
また、メンタルヘルス対策やストレスケアも早期離職防止には欠かせません。

専門機関や社内相談窓口の活用を促し、必要に応じて早期面談やケアが受けられる体制を構築しましょう。
早期離職の背景にある個人の価値観の変化
時代の変化とともに、働く人の価値観も多様化しています。かつては「安定した職に長く勤める」ことが最良のキャリアとされてきましたが、現在では「自分らしい働き方」「やりがい」「成長機会」を重視する傾向が強まっています。
こうした価値観の変化に企業が対応できていない場合、若手は「自分の理想に合わない」と感じて離職を選びやすくなるのです。例えば、以下が挙げられます。
- 仕事の意義や社会的な貢献度を感じたい
- 働く時間や場所の柔軟性を求めたい
- 個々の個性や能力を尊重してほしい
このようなニーズに応えられる組織づくりが、今後ますます重要になるでしょう。
早期離職対策は早めに取り掛かるのが大切
早期離職は単なる「若手の甘え」や「本人の問題」だけでは片付けられない複雑な背景があります。
入社前の期待と現実のギャップ、職場の人間関係、育成体制の未整備、キャリアの見通しのなさ、働き方の問題など、多角的な視点から原因を分析し、企業としての対策を取ることが重要です。
若手社員が安心して働き続けられる環境を整えることは、企業の成長や競争力強化にも直結します。
長期的な視点で人材育成に取り組むことが、早期離職を減らし、優秀な人材の定着を実現する鍵となるでしょう。


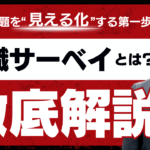

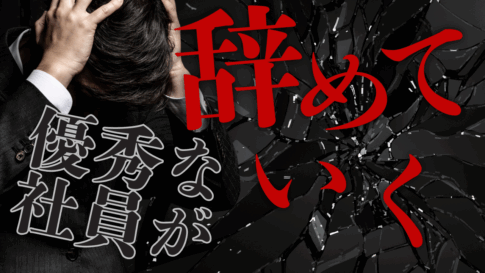
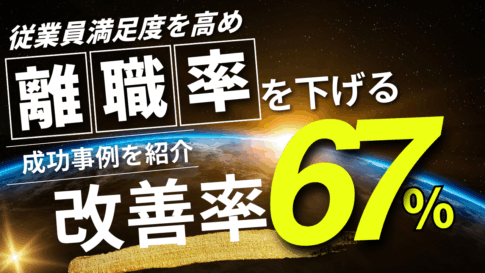
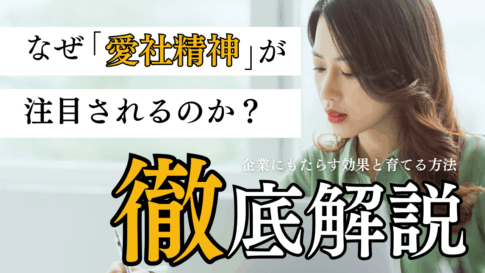
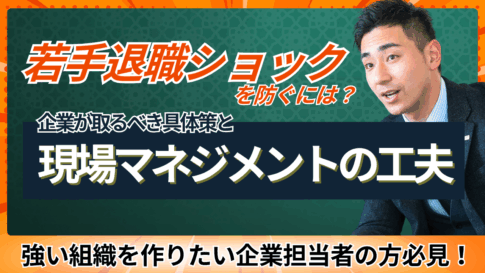
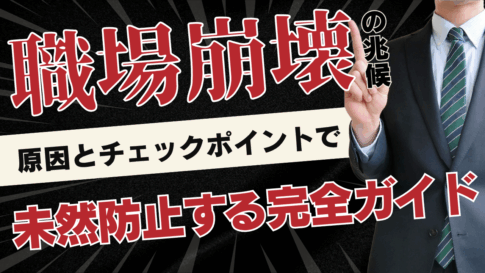
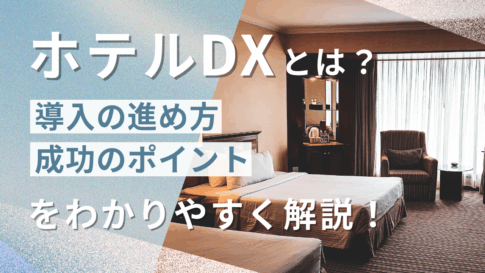
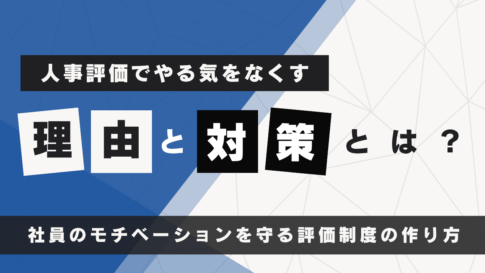




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。