
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。

あの部下、最近元気がないな…
もしかして、やめるつもりなのかも?

そう思ったとき、すでに離職の兆候は始まっているかもしれません。
社員の定着率は、企業の成長に直結する重要な要素です。
とくに今の若手社員は、仕事へのやりがいや上司との関係性に敏感で、ほんの些細な不満が退職につながるケースも増えています。
ですが、早めに気づいて適切に対応すれば、部下の離職を防ぐことは十分可能です。
この記事では、部下がやめそうなサインや、マネージャーが今すぐできる対応策などを実践的な視点でわかりやすく解説します。
「大事な部下を失いたくない」そう思うマネージャーの方に、ぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
- 部下がやめそうなサインとは何か?
- マネージャーが今すぐできる対応策
- 離職リスクを可視化・共有できるツールの活用法
部下がやめそうと感じたときのサインとは

部下がやめそうと感じたときってどのようなサインがあるものなのでしょうか?

モチベーションが低下していたり、仕事に対する意欲が低下していたりなど、さまざまなサインが考えられますよ!
- 突然の態度の変化に要注意
- 日々の業務へのモチベーションが低下している
- 報連相が減ったときは黄色信号
部下がやめそうと感じたときのサインをそれぞれ見ていきましょう。
突然の態度の変化に要注意
部下の退職は、ある日突然伝えられるように思われがちですが、実はその前から「やめそう」というサインを出していることが少なくありません。
例えば、以前は明るく元気だった部下が急に口数が少なくなったり、会話を避けるようになったりした場合、何らかの不満や不安を抱えている可能性があります。
表情の変化、雑談の減少、勤務態度の急変など、ちょっとした違和感が続いたときには注意が必要です。
日々の業務へのモチベーションが低下している
部下のやる気は、言葉よりも行動に表れます。「前は積極的にアイデアを出していたのに、最近は指示待ちになってきた」「ミスが増えている」「納期ギリギリに提出されるようになった」などの変化も、心が職場から離れつつある兆候といえるでしょう。
また、「評価されない」「頑張っても報われない」という思いがあると、部下は次第に会社への関心を失っていきます。そうなると、モチベーションが下がり、業務パフォーマンスにも影響が出てくるのです。
報連相が減ったときは黄色信号
報告・連絡・相談、いわゆる「報連相」が減ってきたときも注意が必要です。部下が積極的に話しかけてこなくなったり、相談事を持ちかけなくなったりするのは、「どうせ聞いてもらえない」「理解してもらえない」と感じている証拠かもしれません。
また、オンラインでのやり取りが中心のチームでは、SlackやChatwork、メールの返信スピードや内容もサインになります。
「いつもよりレスが遅い」「反応がそっけない」と感じたら、心が離れかけているかもしれません。
部下がやめたいと思う理由

どのようなときに部下はやめたいと思ってしまうのでしょうか…?

やめたいと思うきっかけには些細な理由も入ってくることがあります。
- 上司との関係性の悪化評価やフィードバックへの不満
- キャリアパスが見えない不安
- 働きがいの欠如と孤独感
それぞれ詳しく見ていきましょう。
上司との関係性の悪化
職場での人間関係、特に上司との関係は、退職理由の中でも多い項目です。厳しい指摘が続いたり、否定的な言い方ばかりされたりすると、部下は次第に萎縮し、自信を失ってしまいます。
また、信頼関係が築けていないと、部下は「相談しても意味がない」「何を言っても無駄だ」と感じるようになります。そうなると心の距離がどんどん広がり、退職という選択肢が現実味を帯びてくるでしょう。
評価やフィードバックへの不満
「自分の努力が正しく評価されていない」「成果が認められない」などの不満は、働くモチベーションを大きく損ないます。とくに若手社員は、成長意欲が高く、日々の努力に対するフィードバックを求める傾向があります。
定期的な1on1ミーティングやフィードバックの場を設けず、放置してしまうと、「この職場では成長できない」と感じ、転職を考えるようになるのです。
キャリアパスが見えない不安
「この先、自分はどこに向かっていくのか」。キャリアの見通しが立たないことも、退職の大きな要因です。
どれだけ今の仕事にやりがいを感じていたとしても、「このままでいいのだろうか」という漠然とした不安が積もると、転職という選択肢が頭をよぎります。
特に中堅層に差し掛かる30代前後の社員は、将来の役職やスキルアップの道筋を求めています。上司側がそれを提示できなければ、優秀な人材ほど先に見切りをつけてしまうのです。
働きがいの欠如と孤独感
働きがいを感じられなくなったとき、部下は「この職場にいる意味があるのか?」と疑問を持ち始めるケースも少なくありません。また、チームの一員として認められていない、誰にも頼られていないと感じると、孤独感が強まり、職場への愛着は薄れていきます。
在宅勤務やリモートワークが増える中で、孤独感や疎外感が原因で退職を選ぶ人も増えています。
チーム内のつながりを意識的に作ることが、離職防止のカギです。
部下の離職を防ぐための防止策

部下の離職を防ぐために何かできることはあるんでしょうか?

もちろんです!
しっかり対策しておけば、部下の離職をしっかり防げるはずですよ。
- 定期的な1on1で信頼関係を築く
- 目標やキャリアの対話を欠かさない
- 小さな成果も「見える化」して承認する
- チームのつながりを意識して設計する
対策方法を詳しく見ていきましょう。
定期的な1on1で信頼関係を築く
部下がやめそうだと感じたときこそ、1on1ミーティングが有効です。とはいえ、ただの業務確認の場になってしまっては意味がありません。大切なのは、部下の気持ちに耳を傾けること。
「最近どう?」「困っていることはない?」などのフランクな声かけが、安心感につながります。継続的に1on1を行うことで、些細な変化にも気づけるようになります。
目標やキャリアの対話を欠かさない
目の前の仕事だけでなく、3年後、5年後のキャリアについても対話を重ねることが重要です。上司がキャリアに興味を持ってくれているとわかれば、部下の「この職場で成長できる」という実感につながります。
「どのような仕事を任せてみたいか」「どのようなスキルを伸ばしてほしいか」などの具体的な話をしていくことで、部下自身の未来を描きやすくなります。
小さな成果も「見える化」して承認する
部下のやる気を引き出すには、努力や成果をきちんと認めることが欠かせません。口頭での承認はもちろん、ツールなどを使って見える形で称賛するのも効果的です。
以下は、承認の有無によるモチベーションの差を簡単に表にまとめたものです。
| 承認の有無 | 部下の行動傾向 |
|---|---|
| 適切な承認あり | 積極的にアイデア提案、やる気継続 |
| 承認がない | 指示待ち、業務パフォーマンスの低下 |
| 否定が多い | 自信喪失、相談を避ける、退職検討 |
チームのつながりを意識して設計する
リモート環境が増えるなかで、部下が孤立してしまうケースは少なくありません。プロジェクトごとの雑談タイムや、オフラインでの交流イベントなど、つながりを作る場の設計が求められています。
チーム内に信頼関係があれば、ちょっとした不満や不安も共有されやすくなり、問題の早期発見にもつながります。
部下の離職を防ぐにはツールの活用もおすすめ
- 感情の変化を「見える化」する
- 日報やフィードバックの自動化で対話を促進
- 面談記録を蓄積して個別対応の質を上げる
それぞれの活用方法を以下で詳しく見ていきましょう。
感情の変化を「見える化」する
多くの上司が「もっと早く気づけていれば…」と後悔するのが、部下の退職です。忙しい日々のなかで、部下の些細な変化を見逃してしまうのはよくあることです。そこで役立つのが、「部下の状態を可視化できる」ツールの活用。
例えば、「最近仕事が楽しい」「不安を感じている」などの気持ちを簡単に記録できる機能があると、言葉にならない感情の変化にも気づきやすくなります。
上司自身の「気づく力」を補完してくれる存在とも言えます。
日報やフィードバックの自動化で対話を促進
「1on1をやろうとしても、何を話していいかわからない」「フィードバックの時間が取れない」という悩みも多く聞かれます。こうした場面でも、コミュニケーションを仕組み化するツールが有効です。
日報機能やミーティングのサポート機能を活用すれば、部下の悩みや達成感を日々把握できるようになり、会話のきっかけが生まれます。
また、承認や称賛のリアクションが簡単に送れると、忙しい中でもタイムリーに部下を認められます。
面談記録を蓄積して個別対応の質を上げる
部下ごとに性格も課題も異なる中、対応の一貫性を保つのは簡単ではありません。そこで役立つのが、過去の1on1内容やフィードバックを記録・共有できるツールです。
記録を振り返ることで、前回の話の続きからスムーズに話せたり、同じ失敗を繰り返さずに済んだりします。
「ちゃんと自分を見てくれている」と部下が感じることで、関係性も深まるでしょう。
企業が離職率を下げるために実践している仕組み

企業では実際にどのようなことに取り組んでいるのか知りたいです。

企業によって離職防止の取り組みは異なるのですが、その中でも効果的な方法を以下で見ていきましょう。
感謝と称賛の文化を育てる
企業の離職率を下げるカギは、実はとてもシンプルな「ありがとう」にあります。自分の行動が誰かの役に立っている、認められているという実感が、働く意欲につながるのです。
感謝を伝える文化を根付かせるには、経営層やマネージャーが率先して実践することが大切です。
また、社内SNSやフィードバックツールを活用して、称賛を「見える形」にすることで、感謝の連鎖が生まれやすくなります。
評価制度とキャリア支援の整備
社員が安心して働き続けるためには、フェアな評価制度と、将来像を描けるキャリア支援が欠かせません。評価の基準が曖昧だったり、昇進のルールが不透明だったりすると、社員は不安を抱えてしまいます。
スキルアップ支援やキャリア面談、社内での挑戦機会を設けることで、「この会社で成長できる」と感じられる環境を整えられます。
「属人管理」から「チームで支える」体制へ
「部下の管理はマネージャー個人に任せる」という属人的なスタイルでは、限界があります。むしろ、チーム全体で部下を支える体制が重要です。
人事部や上層部、別部署のマネージャーなどが協力し、情報共有とサポート体制を築くことで、部下の離職リスクを組織全体で防ぐことが可能になります。
そのためにも、共通のツールや仕組みを取り入れることが有効です。
「みんなのマネージャ」で部下の離職を防ぐ
最後に、部下のマネジメントをより良くするために、多くの企業で導入が進んでいるおすすめのツールをご紹介します。それが、スカイストーン株式会社が開発・販売している「みんなのマネージャ」です。
「みんなのマネージャ」でできること
| 機能 | 内容 |
|---|---|
| 感情の記録 | 部下の毎日の感情を簡単に入力。やる気や不安の変化を把握可能。 |
| 1on1支援 | 面談の記録やテンプレートを活用し、効果的な1on1をサポート。 |
| 日報・フィードバック機能 | 自動で情報を蓄積。称賛のリアクションも簡単にできる。 |
| 組織分析 | チーム全体の状態を可視化し、マネジメントの質を向上。 |
「みんなのマネージャ」を活用することで、なんとなくの不安を確かなデータに変換し、部下一人ひとりの離職リスクに早めに対処できるようになります。
今こそ、マネジメントを変える時
優秀な部下がやめてしまうのは、企業にとって大きな損失です。しかしその芽は、日常のなかに必ず現れています。
「みんなのマネージャ」のようなツールを活用し、可視化・対話・称賛を仕組みとして実現できれば、部下の離職リスクは大きく減らせます。
これを機に、属人的なマネジメントから脱却し、チームで部下を支える時代へと一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
部下の離職リスクを可視化や対話で防ぐ
「なんとなく部下がやめそうだ」と感じたとき、それは既に黄色信号が点滅している証拠です。しかし、きちんと向き合い、対話を重ねれば、退職という結果を避けることもできます。
部下の変化に早く気づくためには、日頃からの1on1や雑談の機会が欠かせません。

また、努力を認める称賛の文化、キャリアの対話、感情の変化を拾うツールの導入など、仕組みとして支える環境づくりも重要です。

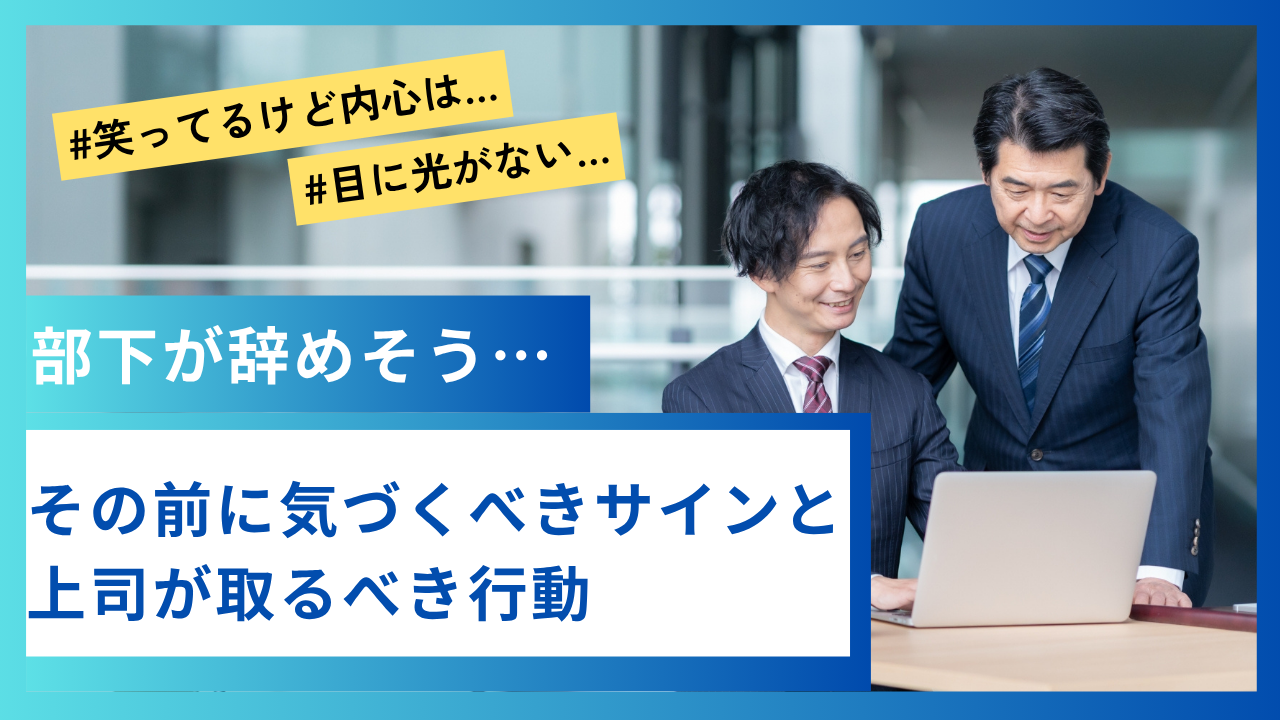
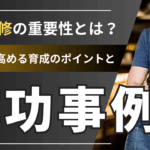
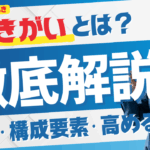
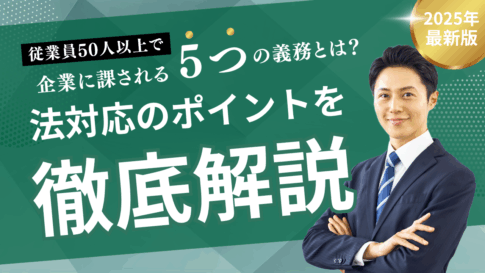
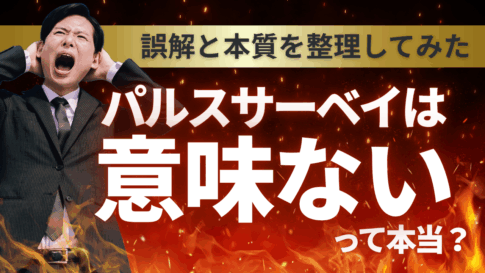
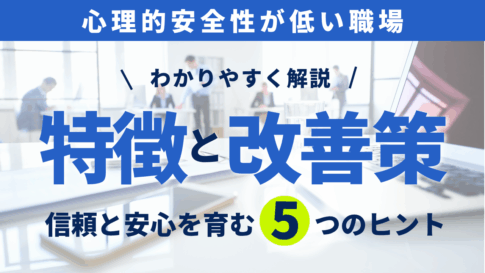


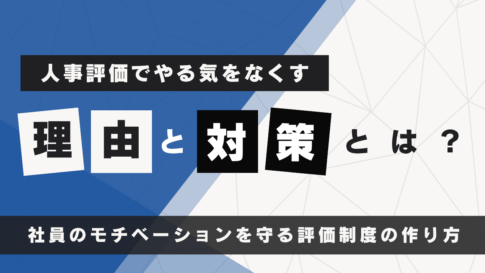
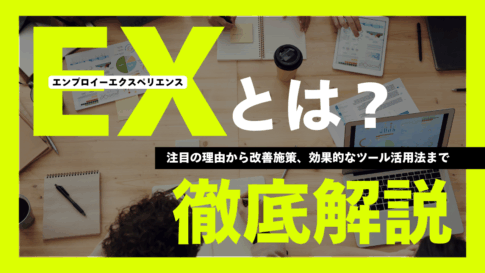
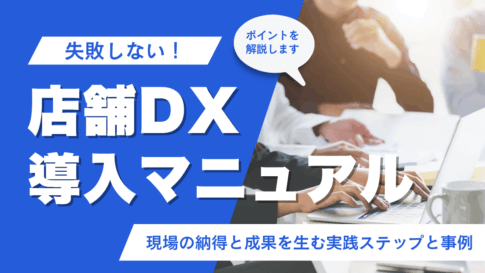



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。