
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
あなたは最近、こんなモヤモヤを感じたことはありませんか?「なんとなくチームに温度差がある気がする。」「部下の気持ちが読めない。」「上司とどうも話がかみ合わない。」

一緒に働いている人たちとの関係性は難しいものですよね…。
こうした職場での違和感の多くは、突き詰めると相互理解の欠如にたどり着きます。
「相互理解」とは単なる情報共有ではありません。お互いの価値観、背景、気持ちを知ろうとする姿勢が根底にあります。
そして、それはチームの信頼関係や心理的安全性を生み、最終的には組織全体の生産性や定着率にも影響を与える重要な土台となるでしょう。
本記事では、ビジネスでの「相互理解」の本質とその必要性、職場で実践するためのステップなどを解説していきます。
- 相互理解の重要性
- 理解と相互理解の違い
- 職場で実践するためのステップやポイント
相互理解とは

相互理解とはどのようなものですか?

まずは、相互理解とは具体的にどのようなものなのかを見ていきましょう。
- 単なる「理解」と「相互理解」の違い
- ビジネスシーンでなぜ相互理解が重要か
単なる「理解」と「相互理解」の違い
「相手の言いたいことは理解したよ」という場面、よくあるでしょう。
しかし、それが本当に「相互理解」だったかを振り返ると、案外片側だけの理解に過ぎなかったりします。
| 概念 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 理解 | 相手の言っていることを受け取ること | Aさんが「納期が厳しい」と言っているのを理解する |
| 相互理解 | 双方が相手の考えや背景を深く理解し合う | Aさんが「納期が厳しい」という理由(体調や家庭事情)をBさんも理解し、Bさんの立場(会社のプレッシャー)もAさんが理解する |
相互理解とは、「あなたはそう思っているんだね、私はこう感じている」と双方の意見や立場を尊重し合い、歩み寄ろうとする対話のことです。
ビジネスシーンでなぜ相互理解が重要か
相互理解の欠如が原因で、こんな問題が起きていませんか?
- 指示した内容がうまく伝わらない
- 会議で発言が出ない
- 若手社員がすぐに辞めてしまう
- チームに一体感がない
こうした課題の根本には「話し合っているのに、お互いのことが見えていない」というギャップが横たわっていることが多いのです。
特に昨今の職場は、多様な価値観・ライフスタイルが混在する場になっています。だからこそ、「わかっているつもり」が一番危険です。
相互理解は、働きやすさと成果の両立を支える基盤なのです。
相互理解がある組織とない組織の違い
相互理解がある組織とない組織では明確な違いが生まれます。具体的にどのような違いが生まれるのかを見ていきましょう。
相互理解がある組織の特徴
相互理解がある組織では、以下のような特徴が見られます。
| 観点 | 相互理解がある組織 |
|---|---|
| コミュニケーション | 上司・部下問わず率直に意見が言える |
| 信頼関係 | 背景や意図を汲んだ行動が多く、トラブルが少ない |
| 離職率 | 感情面でのケアができるため、定着率が高い |
| チームワーク | 目標や価値観が共有されていて、一体感がある |
相互理解がない組織の課題
逆に、相互理解が不足している組織では以下のような問題が起きがちです。
| 問題点 | 内容 |
|---|---|
| コミュニケーション不足 | 上司の意図が伝わらない、部下が本音を言えない |
| モチベーションの低下 | 「わかってもらえない」と感じると意欲が下がる |
| 離職のリスク | 感情面のフォローがなく、孤立感から退職に至ることも |
| 無駄な衝突 | 背景が共有されていないため、誤解や衝突が頻発する |
相互理解を高める方法

相互理解はどうしたら高められるのでしょうか?

相互理解を高めることで、従業員のモチベーションがアップしたり、より良い会社づくりができたりなど多くのメリットがあります。
ここからは、相互理解を高める方法を詳しくご紹介します。
- 1on1ミーティングの活用
- 傾聴の姿勢を育てる
- 価値観の違いを前提とした関わり方
1on1ミーティングの活用
近年、多くの企業で取り入れられているのが「1on1ミーティング」です。これは、上司と部下が定期的に1対1で話し合う時間を持つことで、関係構築と情報共有を目的とした取り組みです。
ポイントは指導ではなく対話を意識すること。
- 相手の話を否定せずに聞く
- 価値観や背景に耳を傾ける
- 問題解決ではなく、気持ちの共有から始める
このような姿勢を持つことで、従業員からの信頼の芽を育てられるでしょう。
傾聴の姿勢を育てる
相互理解の基本は「傾聴」です。ただ黙って聞くのではなく、相手の立場になって感じる、考えるという積極的な受け止めが必要です。
普段から相手の話を「遮らず、否定せず、最後まで聞く」習慣をつけましょう。
価値観の違いを前提とした関わり方
全員が同じ考えや働き方をしているわけではありません。年代、性別、働く目的などそれぞれが異なるからこそ、違いを前提とした対話が必要です。
「それは違う」と決めつけず、「そう考える背景には何があるんだろう?」と一歩引いた視点を持つことで、自然と相互理解に近づいていきます。
相互理解を阻む要因

なかなか相互理解がうまくできません…

相互理解を高めようと思ってもうまくいかないのには、以下のような理由が考えられます。
なぜ相互理解がうまくできないのか、原因を把握したうえで取り組みましょう。
- 心理的安全性の欠如
- 情報の非対称性
- 「忙しさ」によるコミュニケーション不足
それぞれの要因を詳しく見ていきましょう。
心理的安全性の欠如
「こんなこと言ったら嫌われるかな」「評価が下がったら困る」。
このような不安が職場にあると、そもそも本音で話すことができません。
これは「心理的安全性」が確保されていない状態といえます。心理的安全性とは、「自分の意見を言っても否定されない」「間違っても責められない」などの安心感のことです。
相互理解は、信頼と安心の上でしか成り立ちません。まずは、信頼関係を築いていくことを意識しましょう。
情報の非対称性
「マネージャーが「現場の状況」を知らない」
「部下が「経営の意図」を理解していない」
上記のように、持っている情報が違うことで、判断や行動にズレが生じます。
情報の偏りや壁が相互理解の妨げになります。特に、階層がある組織では「伝えているつもり」がとても危険です。
「つもり」ではなく、「確信を持って伝えた」状態を作るのが重要です。
「忙しさ」によるコミュニケーション不足

どうしても業務に追われて時間が取れないから、対話の優先度が下がってしまう…

現代のビジネス環境では、多くの職場でこの慢性的な忙しさが相互理解の障害になっています。
しかし、5分でも話す時間を取るだけでも、意外なほど関係性を変えることもあります。短くても質の高い対話を重ねられるように意識しましょう。
「忙しいから時間がない」ではなく、短時間でも時間を作ることで、従業員が相談しやすい環境を整えられます。
相互理解を実践している企業の事例
ここからは、実際に相互理解を実践している企業の事例を見ていきましょう。
日常会話を重視する企業
あるベンチャー企業では、「業務とは関係のない雑談」を奨励しています。
Slackなどで週に1回「週末何してた?」などのテーマを投稿し、誰もが気軽にコメントできる環境を整えているのです。
一見無駄に見えるこうしたコミュニケーションが、実は相互理解の土台を作り、いざという時の協力体制に大きな違いを生んでいます。
人事評価に「共感力」を盛り込む企業
あるIT企業では、マネージャー評価の項目に「傾聴力」「共感的対応」を含めています。
成果主義だけでなく、人との関わり方を定量的に評価することで、相互理解の姿勢を組織全体に浸透させています。
これは、マネージャーに「聞くこと」の価値を再認識させる仕組みでもあるでしょう。
デジタルツールを活用して“見える化”する企業
リモートワークが進む中、社員の状態を「顔を見て把握する」ことが難しくなりました。
ある企業では、組織サーベイや1on1の記録ツールを活用して、社員の気持ちや関係性を“見える化”する仕組みを導入しました。
関係性に潜むリスクの早期発見や、ピンポイントな声かけが可能になり、従業員の満足度の向上につながったようです。
相互理解を実践したいなら「みんなのマネージャ」
「みんなのマネージャ」は、スカイストーン株式会社が開発した、1on1を軸としたマネジメント支援ツールです。
単なるスケジューラーではなく、「相互理解」を促進するための仕組みが多数組み込まれています。
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 定期的な1on1のサポート | 上司・部下が対話する機会を自動で設定、記録、振り返りできる機能 |
| 感情・モチベーションの把握 | 社員の心理状態をグラフなどで“見える化”し、ギャップや変化を早期に察知 |
| 育成観点のテンプレート支援 | 傾聴・承認・フィードバックなど、育成スキルを支えるテンプレートも豊富 |
相互理解は感覚的なスキルと思われがちですが、ツールを使えば仕組みとして再現可能です。
「対話」と「記録」の仕組みを提供
相互理解で重要なのが、継続的な対話と、それを振り返る仕組みです。しかし、忙しい現場では1on1の実施自体が後回しにされがちですし、記録も「その場限り」で終わってしまうことが少なくありません。
「みんなのマネージャ」は、1on1の予定を自動でリマインドしてくれるだけでなく、話した内容をその場で記録し、後日振り返れる機能を備えています。
過去の対話履歴を元に、「どこで認識のズレが生じたのか」「前回と比べてモチベーションがどう変わったか」などを可視化することで、単なる雑談を戦略的な対話へと変えてくれるのです。
こうした習慣化と可視化の仕組みが、相互理解の土台を安定させてくれます。
上司と部下のギャップを可視化
マネージャーと部下の間には、意識のズレや見えない温度差が存在していることが少なくありません。「うまくやれていると思っていた」「悩んでいるとは思わなかった」などの認識違いは、深刻なミスコミュニケーションの原因になります。
「みんなのマネージャ」は、感情の変化やモチベーション、職場環境に関する意識を定期的に可視化し、双方のギャップを数値やグラフで確認できる機能を搭載しています。
例えば、マネージャーが順調と捉えていても、部下はストレスを感じているなどのズレが見つかることも。
そのギャップを認識することで、タイミングの良いフォローや、適切なフィードバックが可能になります。

見えない溝を見える化することが、信頼関係を築く第一歩になるでしょう。
マネージャーの負担を軽減しつつ育成

マネジメント職についたけど、部下と向き合う時間が足りないし、そもそも1on1で何を話したらいいかわからない…。

このようなマネージャー側の悩みも、相互理解が進まない要因のひとつです。
「みんなのマネージャ」は、対話をリードするためのテンプレートや質問例を豊富に用意しています。そのため、経験の浅いマネージャーでも自然と育成的な会話を進められるようになります。
また、蓄積されたデータを基に、部下ごとの状態や育成進捗も一覧で把握できるため、「なんとなくの感覚」ではなく、根拠あるマネジメントが可能です。
相互理解を高めることで組織の未来が変わる
「人が人と働く以上、最終的にすべての成果は関係性によって決まる」
これは、マネジメントの本質を突いた言葉です。
その関係性を育てる鍵が「相互理解」であり、それは日々の対話、聴く姿勢、違いを受け入れる心から始まります。
とはいえ、すべてのマネージャーが自然にそれをできるとは限りません。だからこそ、「みんなのマネージャ」のような仕組みによるサポートが今、求められているのです。
- まずは1on1で話してみること
- 相手の言葉の裏にある背景に目を向けてみること
- 違いを否定せず、「なるほど」と受け止めてみること

この小さな積み重ねが、信頼ある組織を育てていくのです。


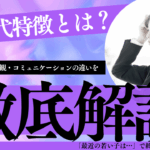
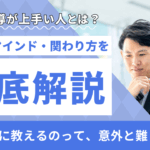
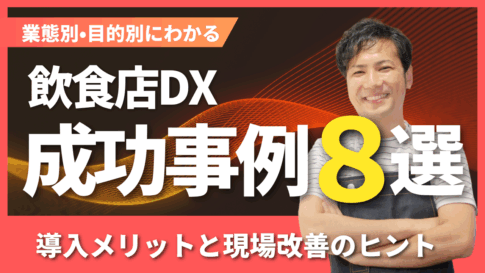
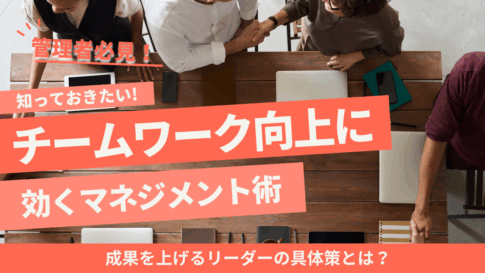
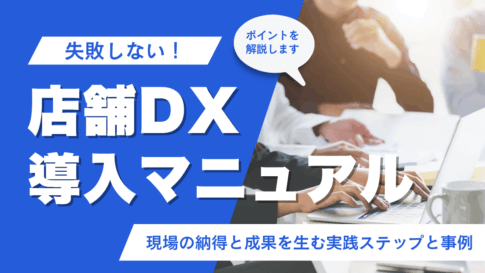
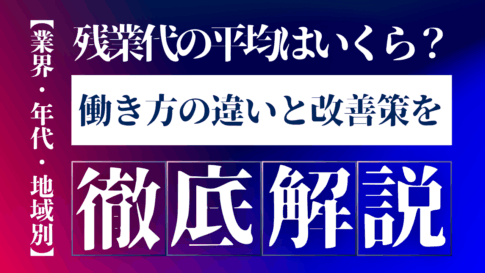
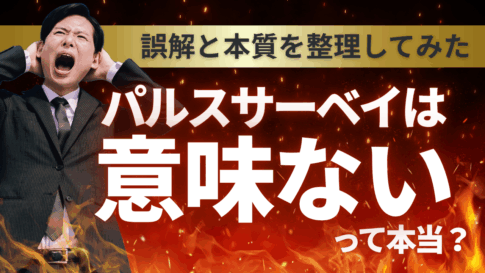
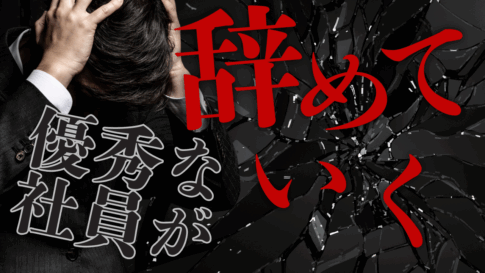

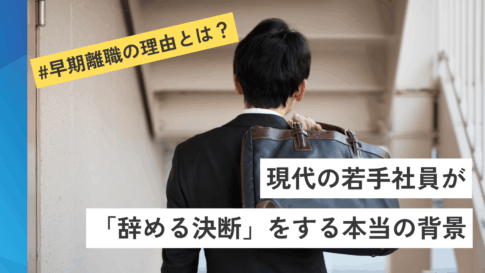



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。