
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「最近よく聞くようになったエンプロイーエクスペリエンス(EX)って、具体的に何のこと?」
と感じている方も多いのではないでしょうか。
EXとは、従業員が企業で働く中で体験するすべての出来事を指し、今や従業員満足やエンゲージメントを超えて、企業の業績やブランドにも影響を与える重要な概念となっています。

EXは単なる福利厚生ではなく、組織文化やマネジメントの質まで含む“戦略資産”といえます。
本記事では、EXの定義や背景から、具体的な改善施策、導入企業の取り組み、そして「みんなのマネージャ」を活用した実践方法までを、分かりやすく解説します。
これからの人材戦略においてEXは避けて通れないテーマです。ぜひ参考にしてください。
- エンプロイーエクスペリエンス(EX)の基本的な定義と、ES(従業員満足度)・エンゲージメント・CX(顧客体験)との違い
- EXが企業にもたらす具体的なメリット
- EXを構成する3つの要素と改善のポイント
- EX向上に有効な施策と支援ツール「みんなのマネージャ」の活用法
エンプロイーエクスペリエンス(EX)とは
エンプロイーエクスペリエンス(EX)は、従業員が企業で体験するすべての出来事のことです。
採用から退職までの各フェーズで、従業員がどのような印象を抱くかが、定着率や生産性に直結します。ここでは、EXの定義や注目される背景、他指標との違いを通じて、基礎を押さえていきます。

異動や評価のタイミングって、たしかに印象に残りやすいですよね。
EXの定義と注目される背景
EX(Employee Experience)とは「従業員の体験」を意味し、満足度や業績への影響を含めて幅広く捉えられています。
働き方改革やコロナ禍を契機に、職場の快適さだけでなく、心理的安全性やキャリア支援といった観点も重要視されるようになりました。

心理的安全性の確保は、イノベーションや主体性の発揮にも直結します。
従業員の感情や印象を含めた全体設計が、企業成長のカギとなっています。
| 指標名 | 対象範囲 | 主な目的 | 評価軸 |
|---|---|---|---|
| エンプロイーエクスペリエンス(EX) | 従業員の体験全般 | 組織力・定着力の向上 | 体験の質・満足感 |
| 従業員満足度(ES) | 従業員の満足度 | 環境や待遇の改善 | 環境・待遇 |
| エンゲージメント | 組織・仕事への愛着と熱意 | 生産性・貢献意欲の最大化 | 熱意・自発性 |
カスタマーエクスペリエンス(CX)との違い
EXと混同されやすいのがCX(顧客体験)です。

従業員が満足していない組織では、顧客満足の継続も難しいのが現実です。
カスタマーエクスペリエンス(CX)は、顧客が商品やサービスを利用する過程で得る体験全般を指します。一方で、エンプロイーエクスペリエンス(EX)は、従業員が職場で日々接するすべての事象が対象です。
良好なEXが質の高いCXを生み出すという視点から、企業にとって両者は連動して取り組むべき課題となっています。
従業員満足度(ES)やエンゲージメントとの違い
従業員満足度(ES)は、職場環境や待遇への満足度を測る指標です。
エンゲージメントは、組織への愛着や貢献意欲を表します。対してEXは、それら感情が生まれる前提となる「体験の質」全体を扱います。
EXを高めることで、ESやエンゲージメントの向上が自然に促進される構造にあります。
EXが注目される理由と企業へのメリット
企業の持続的成長には、従業員の体験価値を高めることが不可欠です。ここでは、EXが企業業績や採用力、ブランド形成にどう貢献するかを具体的に解説します。

この構造を理解して施策を設計することが、持続可能な改善の鍵です。
EXが業績や人材定着率に与える影響
業績とEXの関係は、数値で表すことにより影響を明確にできます。EXの数値が高いということは、従業員が前向きに働ける環境づくりができているということです。
その結果、業務効率や顧客対応の質が向上します。さらに離職率も低下するため、採用や育成のコスト削減と組織の安定化に大きく寄与します。
| 指標項目 | 高EX企業 | 低EX企業 |
|---|---|---|
| 離職率 | 10%以下 | 30%以上 |
| 売上成長率 | +15% | +2% |
| 顧客満足度 | 4.5/5 | 3.2/5 |
| 社員満足度 | 85%以上 | 60%未満 |
社員の体験が企業ブランディングに与える効果
従業員の声は、企業イメージに直結する時代です。
SNSや口コミを通じて、企業文化や働きやすさが公開される昨今、EXの良し悪しは企業ブランドの形成に大きな影響を与えます。
よい体験は魅力的な職場として認知され、優秀な人材の採用にもつながります。

人事施策は広報・ブランディングと密接に連動している時代です。
エンプロイーエクスペリエンスの構成要素とは
EXは職場の雰囲気や人間関係だけでなく、働く空間や業務ツールまでを含めた多面的な概念です。
ここでは、EXを構成する3つの要素に分けて、その具体的な内容を整理します。
物理的環境(オフィス・設備など)
従業員の集中力やストレスに直接影響を与えるのが、働く場所の環境です。
自然光のある明るいオフィス、集中とリラックスが両立できる空間設計、使いやすい設備などが快適な物理環境を形成します。
レイアウトの自由度やリモートワークへの対応も、柔軟な働き方を支える重要な要素です。
こうした環境が、従業員の健康や業務効率を支えます。
デジタル環境(社内システム・ツール)
業務のストレスはツールの使い勝手で大きく変わります。効率的な仕組みはEXの土台です。
勤怠管理、チャット、情報共有などのシステムが、使いやすく整備されているかどうかは、生産性とストレスの大きな分かれ目になります。
煩雑なシステムは従業員の不満の温床となるため、直感的に使えるツールの導入や継続的な改善が求められます。

ツールの導入では現場の声を反映するプロセスが欠かせません。

操作が難しいと、最初から「やる気」が削がれちゃうんですよね…。
文化・コミュニケーション・人間関係
安心して働ける職場には、信頼関係と対話の文化が根付いています。
意見が言いやすく、挑戦が歓迎される心理的安全性のある環境は、従業員のモチベーションと定着に大きく寄与します。
マネージャーのフィードバック力や、部署間の協力体制も、働きやすさを左右する重要なポイントです。
- 意見を否定せずに傾聴する文化
- ミスを責めず、改善に導く姿勢
- 成果だけでなく努力も賞賛する仕組み
- 縦と横の連携がスムーズな関係性
EXを改善するための具体施策
EX向上は一時的な取り組みではなく、組織全体で継続的に取り組むべきテーマです。ここでは、よく導入されている具体的な施策を5つに分けて紹介します。

単発施策で終わらせず、PDCAを回せる運用体制が重要です。

「やりっぱなしじゃなくて、ちゃんと振り返って改善してくれる」』って感じられると、信頼も増します
- ジャーニーマップの作成
- オンボーディングと定着支援
- サーベイとフィードバック制度の整備
- 評価制度と報酬の見通し
- デジタルツールの活用
従業員ジャーニーマップの作成
EX向上の第一歩は、従業員の体験を可視化することから始まります。
ジャーニーマップとは、採用から退職までの一連の従業員体験を時系列で整理した図です。

入社直後のバタバタ、思い出すと「もう少し丁寧にサポートしてほしかった…」って感じました。
どのタイミングで不安やストレスが生じやすいか、満足感が高まる場面はどこかを明確にし、具体的な施策の設計につなげることができます。
| フェーズ | 主な接点 | 推奨施策例 |
|---|---|---|
| 採用 | 面接、会社説明会 | 選考中のフィードバックの充実、入社前の情報提供 |
| 入社~3か月 | オンボーディング、OJT | メンター制度、1on1面談の実施 |
| 配属後~評価期間 | 定期業務、評価面談 | パルスサーベイ、成長面談の定期実施 |
| キャリア後期・退職時 | キャリア面談、退職面談 | キャリア支援、退職後のアフターフォロー体制 |
オンボーディングと定着支援
新入社員が早期に馴染むための施策は、離職防止と長期的活躍に直結します。入社直後の不安や孤独感を解消するには、1on1やメンター制度の導入が有効です。

先輩とざっくばらんに話せたのが、一番安心できました。
特に最初の3か月間は定着のカギとなるため、業務マニュアルの整備や社内交流機会の提供など、丁寧なフォローが必要です。
サーベイやフィードバック制度の整備
従業員の声をすくい上げ、組織全体に反映させるためには、データに基づく対話体制が欠かせません。
パルスサーベイを活用すれば、短期的な感情変化や不満をリアルタイムで把握できます。また、フィードバックは制度化しないと属人化しやすいため、マネージャー向けの研修やテンプレート化も有効です。

なんか最近しんどいなぁ」ってときに拾ってもらえると、救われます…
- 回数ではなく質を意識する
- 評価と育成を分けて設計する
- マネージャー研修で伝え方を学ばせる
- フィードバック内容を記録・共有する体制を整える
評価制度と報酬の見直し
評価と報酬の納得感は、EX向上の原動力になります。
評価制度を設ける際に重要なのは透明性です。
不透明な評価基準や報酬体系は、従業員のモチベーションを下げる要因となります。

評価者のバイアスを減らす仕組みづくりもEXに直結します。
360度評価やスキル評価の導入、成果に応じた手当制度など、納得感を高める仕組みを整えることが重要です。
- 成果と報酬が明確に連動しているか
- 成果以外の行動や価値観も評価しているか
- 納得感のある評価基準が周知されているか
- 評価者の訓練が行われているか
デジタルツールの導入と活用
従業員の業務負担を軽減し、効率的な働き方を実現するには、デジタルツールの導入が効果的です。
勤怠管理やフィードバックツール、AIによる行動提案など、便利な仕組みを取り入れることで、日常業務のストレスを軽減できます。現場の声を取り入れながら、継続的な見直しを行うことが重要です。

「やって終わり」じゃなくて、現場の反応を見ながら調整してくれると嬉しいです。
EX向上に役立つ「みんなのマネージャ」活用法
施策を実施しても、現場での運用が伴わなければEXは定着しません。ここでは、現場マネージャーの実行力を支援する「みんなのマネージャ」の活用法を紹介します。
このツールは、週次サーベイで従業員の状態を把握し、AIが最適な対話や対応を提案。フィードバックの質やマネジメントの均質化をサポートし、属人性を排除したEXの実践を可能にします。
- 従業員の状態を可視化する週次サーベイ
- AIによる行動提案とフィードバック支援
- スキル評価とインセンティブ連動機能
EX可視化とAIによる行動提案
「みんなのマネージャ」には、従業員の状態を「見える化」し、マネージャーが即時に対応できる仕組みが整っています。
週1回のパルスサーベイで、モチベーションや貢献意欲などを定量的な把握が可能です。AIが従業員の状況に応じてサーベイ頻度を調整し、離職や不調の兆候を早期に検知します。
さらに、マネージャーに対して「どのように声をかけるか」といった具体的な行動提案が行われ、迷わずアクションを起こせるようになります。
- パルスサーベイ(週次アンケート)による状態把握
- AIによる個別最適化されたサーベイ頻度調整
- マネージャーへのフィードバック提案
- スキル評価とインセンティブ管理機能
心理的安全性を高めるフィードバック支援
質の高いフィードバックは、心理的安全性のある職場づくりに直結します。
「みんなのマネージャ」は、1人1アカウント制の実名で透明性を担保しつつ、本音を引き出せる設計になっています。
また、マネージャー向けに話し方や伝え方のサポートも行い、経験に左右されずに効果的な対応が可能です。これにより、従業員は自分の考えや気持ちを安心して表現できるようになります。
スキル管理やモチベーション向上施策
成長実感を得られる職場環境づくりには、スキルの「見える化」と評価が不可欠です。
「みんなのマネージャ」では、業務ごとに必要なスキルの習熟度を自己評価と他者評価の平均点で数値化する機能を搭載しています。スキル管理やモチベーション向上施策は、インセンティブや時給への反映に活用できます。
| 業務カテゴリ | スキル評価(5段階) | インセンティブ例 |
| 接客対応 | 4.5 | 時給50円アップ |
| キッチン業務 | 3 | スキルアップ研修受講可能 |
| 店舗管理 | 5 | 月間MVP・特別手当支給 |
まとめ
エンプロイーエクスペリエンス(EX)は、従業員が職場で感じるすべての体験を設計し、改善するための重要な視点です。
従業員が安心して成長できる環境を整えることで、離職率の低下や業績の向上、採用力の強化など、多くの企業メリットが得られます。
特に、物理環境やデジタルツールだけでなく、フィードバックや評価制度、職場文化まで含めたトータルな設計が求められます。
こうした取り組みを支えるためには、現場で活用できる支援ツールの存在も重要です。「みんなのマネージャ」のように、従業員の状態をリアルタイムで把握し、マネジメント行動を標準化する仕組みを活用すれば、持続的なEX改善が可能となります。
従業員一人ひとりが「この会社で働いてよかった」と思える体験を積み重ねることで、企業全体の魅力と競争力を高めていきましょう。

個人に依存しないマネジメントが、EXの再現性と公平性を支えます。

そんな職場、理想だけど…ちゃんと向き合ってくれる会社なら信じたくなります。

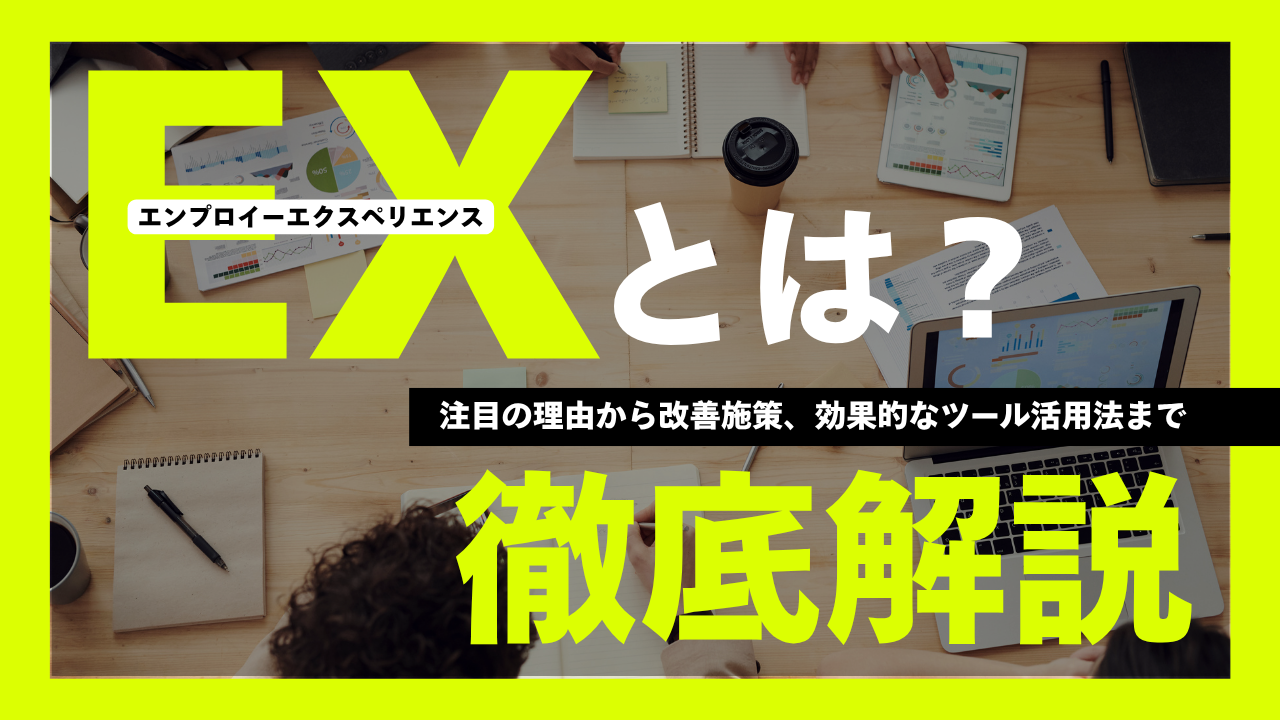
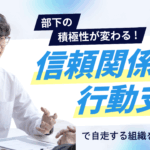
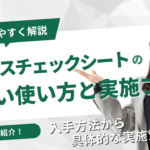

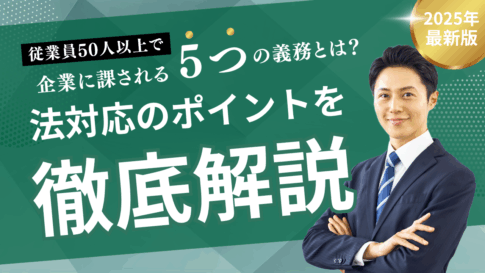
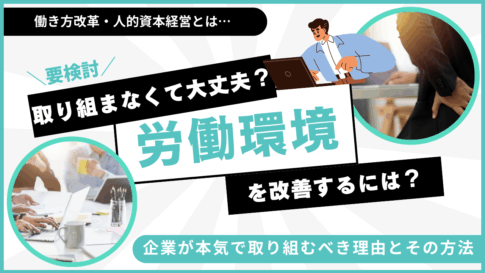


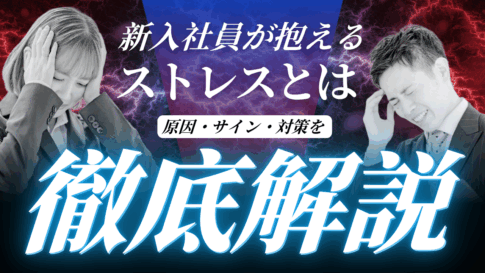

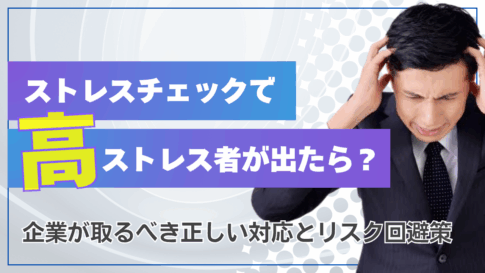



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。