
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された場合、企業はどのように対応すべきでしょうか?単に産業医との面談を手配するだけでは、従業員のメンタル不調や離職を防ぐには不十分です。
適切な対応を怠れば、訴訟リスクや職場環境の悪化にもつながりかねません。本記事では、以下のようなことをわかりやすく解説します。
- 高ストレス者への実践的な対応策
- 継続的なサポート体制の整備
- 最新の支援ツール「みんなのマネージャ」の活用
ストレスチェックを“やるだけ”で終わらせない、実効性のある活用方法を知りたい方はぜひご覧ください。
- ストレスチェックで従業員に高ストレスが出た場合の対処法
- 再発防止のための定期的な対策
ストレスチェックで「高ストレス者」と判定されたらどうすべきか?
ストレスチェックで「高ストレス者」と判定された場合、企業は迅速かつ適切な対応を取ることが求められます。
まず重要なのは、従業員が申し出た場合に確実に面接指導を実施する体制を整えておくことです。さらに、面談結果に基づいた業務環境の見直しや、職場での人間関係への配慮も不可欠です。
高ストレス状態が放置されると、以下のようなことにつながる恐れがあります。
- メンタル不調
- 休職
- 退職
また、企業側が対応を怠った場合には、労働問題や訴訟リスクにも発展しかねません。この記事では、ストレスチェック後に企業が取るべき対応の具体的な流れとポイントをわかりやすく解説していきます。
まず企業が確認すべき「本人の申し出」とそのフロー
ストレスチェック後に「高ストレス」と判定された従業員には、まず面接指導の申し出ができることを確実に周知する必要があります。申し出があった場合は、遅滞なく産業医との面談を手配しなければなりません。

申し出があった場合は、すぐに対応を行いましょう!
重要なのは、この申し出制度が本人の自由意思に基づくものであり、企業側が誘導や圧力をかけてはいけないという点です。申し出から面談実施までの手順を明文化し、担当部署や責任者を明確にしておくことで、トラブルや対応漏れを防ぐことができます。
また、申し出がなかった場合でも、上司や人事が従業員の変化に気づきやすい体制づくりが必要です。
面接指導の手配と実施ポイント
面接指導を実施する際には、従業員のプライバシーを尊重しつつ、メンタルヘルスの専門知識を持つ産業医と連携することが重要です。

プライバシーを守ることが重要ですね!
面談の目的は、「高ストレスの原因を把握し、改善に向けた支援策を検討すること」にあります。面談結果に応じて、勤務時間の調整や業務内容の見直しなど、職場環境の改善に結びつける対応が求められます。
また、面談記録の適切な保管や、本人へのフォローアップの有無も確認すべきポイントです。形だけの面談で終わらせず、実効性のある対策に落とし込む姿勢が企業には求められています。

これからの対策も大切です。
高ストレス者への対応が不十分だと起こるリスクとは
高ストレスと判定された従業員に対する対応が不十分な場合、企業にはさまざまなリスクが発生します。
最も深刻なのは、従業員がメンタル不調に陥り、休職や離職、最悪の場合は労災認定に至るケースです。また、企業の対応が不適切であった場合には、安全配慮義務違反として訴訟に発展する恐れもあります。
これらの事態は、経営面にも大きな損失をもたらすことになります。未然に防ぐためには、制度に従うだけでなく、従業員の声をすくい上げる仕組みや信頼できる相談体制の整備が欠かせません。対応の質が企業の信頼に直結する時代です。
高ストレス者に対する社内対応の具体策
高ストレスと判定された従業員に対しては、面接指導だけでなく、社内での実務的な支援体制が不可欠です。職場環境の改善や業務負荷の見直し、さらには人間関係のトラブルへの対応など、多角的なアプローチが求められます。
人事部門だけで対応を完結させようとせず、現場の管理職と連携しながら、継続的なフォロー体制を築くことが大切です。従業員が安心して働ける職場を実現するためには、一時的な対応にとどまらず、日々の観察と対話の積み重ねが必要になります。
ここでは、高ストレス者への対応として実際に機能する3つの具体策を紹介します。
勤務時間や業務内容の調整による負荷軽減
ストレスの大きな要因となりやすいのが、過重労働や業務内容の過多です。高ストレス者が業務を継続する中で無理を重ねると、やがて体調不良や休職リスクが高まります。
そのため、産業医の助言や本人の状況を踏まえて、以下のような業務負荷の調整が必要です。
- 勤務時間の短縮
- 残業の制限
- 一部業務の再配分
単なる“優遇措置”ではなく、長期的な戦力維持のための戦略的な判断と捉えるべきです。また、調整内容を周囲にも適切に説明し、職場全体の理解を得ることも重要なポイントです。

職場全体の理解を得られるかがカギです。
職場の人間関係トラブルへの対応
高ストレスの背景には、職場の人間関係に起因する問題が潜んでいることが少なくありません。上司とのコミュニケーション不全や同僚との摩擦、孤立感などが積み重なると、ストレスが慢性化する可能性があります。
こうした課題に対しては、ヒアリングや第三者の仲介を通じて状況を可視化し、誤解や不満を丁寧に解消することが求められます。

信頼のおける第三者に依頼すると良いでしょう。内部者ですと、感情が入ってしまいますので、第三者に頼むことをおすすめします。
必要に応じて部署異動や配置転換を検討する柔軟な対応も視野に入れるべきです。人間関係の修復には時間がかかるため、粘り強い支援が不可欠です。
継続的なサポート体制の整備(1on1、相談窓口など)
高ストレス者への対応は、一度限りの面談では不十分です。継続的なフォローアップ体制を整えることで、従業員の状態を中長期的に見守ることができます。たとえば、以下のような制度の導入などが効果的です。
| サポート体制 | 詳細 |
|---|---|
| 定期的な1on1面談 | 上司や産業医との定期的な面談 |
| 社内に設置された相談窓口 | 対面・電話・メール・チャット |
| EAP(従業員支援プログラム) | カウンセリング・研修・コンサルテーション・様々なサービスの提供 |
重要なのは、従業員が「困ったときにすぐ相談できる」と感じられる環境を整えることです。心理的安全性のある職場を築くことで、従業員の早期復調や離職防止にもつながります。

様々な相談方法を置いておくと、従業員が相談しやすい場合があります。

対面の窓口のほか、メールや電話での相談も受け付けると良いですね!
ストレスチェックを「対策型」に進化させるポイント
多くの企業では、ストレスチェックを「実施すること」自体が目的になりがちです。しかし、本来の目的は従業員のメンタル不調を未然に防ぎ、健全な職場づくりを支援することにあります。つまり、チェック結果をいかに「活用するか」が最も重要です。
単に数値を確認するだけでなく、職場全体の傾向を把握し、具体的な改善策へとつなげる視点が求められます。この章では、ストレスチェックを“形骸化”させず、真に役立つ「対策型ツール」として活用するための重要なポイントを解説します。
集団分析の活用で組織課題を可視化
ストレスチェックの結果は、個人だけでなく職場全体の傾向を把握するための「集団分析」にも活用できます。
たとえば、特定部署だけでストレス反応が高い傾向が見られる場合、業務量の偏りやマネジメント課題が存在する可能性があります。
こうした課題を可視化し、部署単位で対策を講じることで、組織全体のストレス要因を根本から見直すことができます。個別対応と並行して、集団レベルでの改善を図ることが、働きやすい環境づくりには欠かせません。

特定部署だけストレス反応が高い場合、業務量の方偏りを確認しましょう。
高ストレス者の再発を防ぐサポート体制の整え方
ストレスチェックで「高ストレス」と判定された従業員が一時的に改善しても、同じ環境や習慣が続けば再発のリスクは避けられません。再発防止には、継続的なストレス管理が可能な仕組みが必要です。
たとえば、以下のようなものを組み合わせると、早期の変化検知が可能になります。
- 定期的な簡易アンケートの実施
- 従業員の状態を可視化するダッシュボード
- AIによる注意喚起機能
再発を未然に防ぐ取り組みは、従業員の安心感を高め、企業への信頼にもつながります。
みんなのマネージャなら、高ストレス者の「見逃し」を防げる
「ストレスチェックの結果を活用したいが、具体的な対応が難しい」「人事や上司が従業員の変化に気づけない」といった悩みを抱える企業は少なくありません。そんな課題を解決するのが、マネジメント支援ツール「みんなのマネージャ」です。
本ツールは、以下のような機能を備えています。
- AIによるパルスサーベイ
- 専門家監修の行動提案機能
従業員のストレス状態をリアルタイムで把握し、管理者が迅速かつ的確に対応できる環境を整えます。
心理的安全性を高める設計により、従業員が本音を話しやすくなり、早期の変化検知と対話を促進。高ストレス者を「見逃さない」マネジメントを実現します。

ぜひみんなのマネージャを使ってみてください!

適切なツールを取り入れることで、業務効率が図れます。
まとめ
ストレスチェック制度は、従業員の心身の健康を守るための大切な仕組みです。しかし、「チェックをしただけ」で終わらせてしまっては、その本来の効果は発揮されません。
高ストレスと判定された従業員への適切な対応は、メンタル不調や離職を未然に防ぐだけでなく、組織全体の生産性と信頼性を高める重要なステップです。また、再発防止のためには欠かせません。
- 継続的なサポート体制
- 職場環境の改善
「みんなのマネージャ」のような支援ツールを導入することで、現場のマネジメント負担を軽減しながら、個人と組織の両面で健康経営を推進することができます。今こそ、ストレスチェックの“その後”を見直す時です。

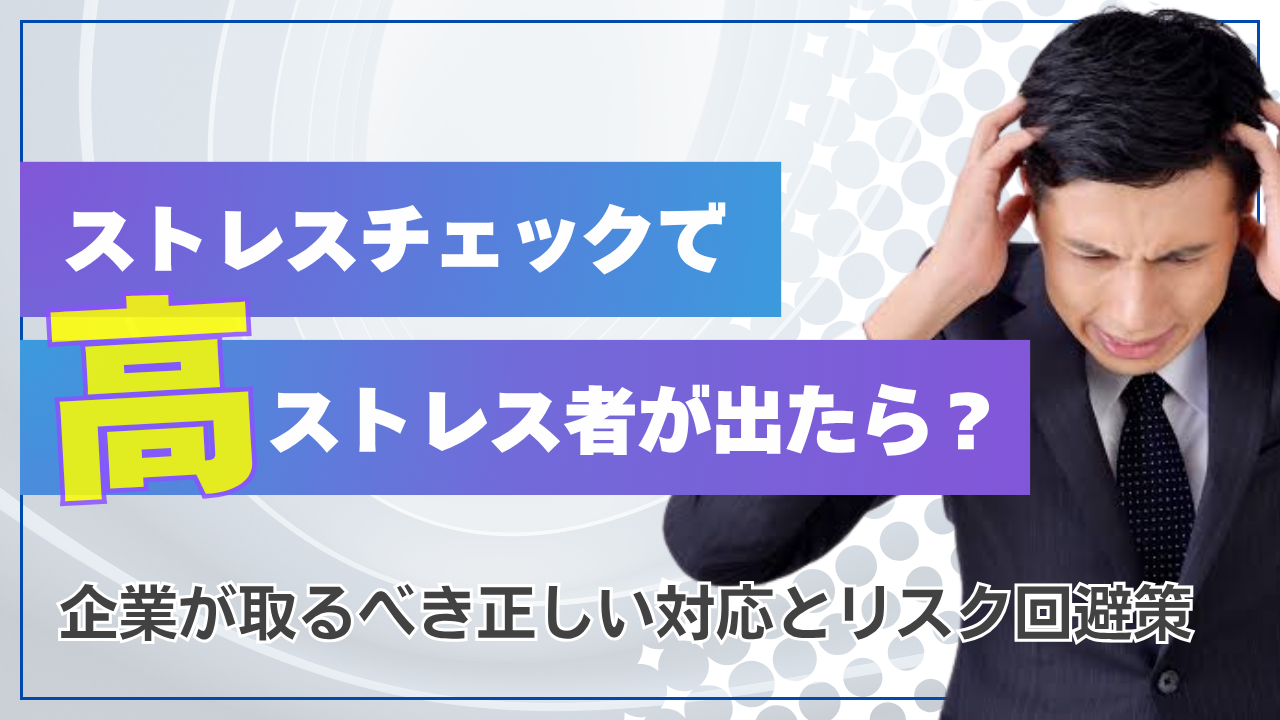

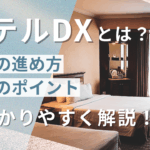
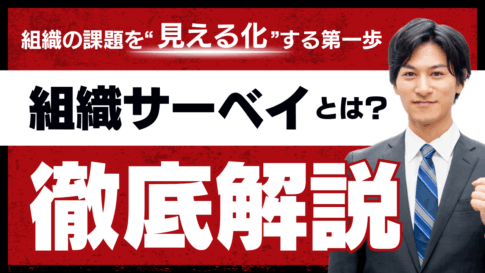


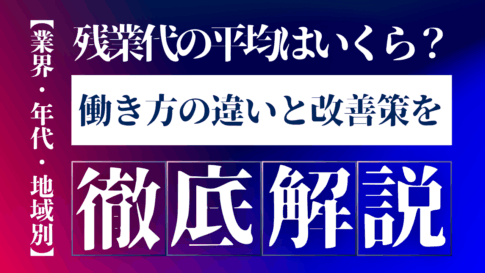
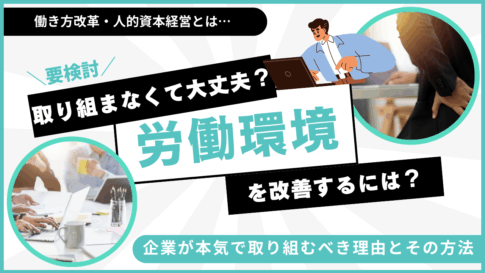

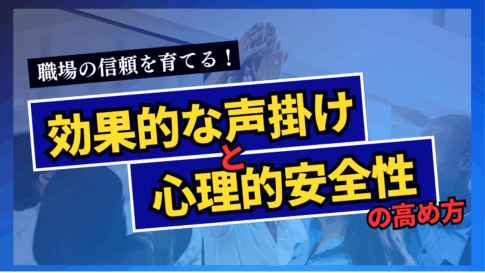
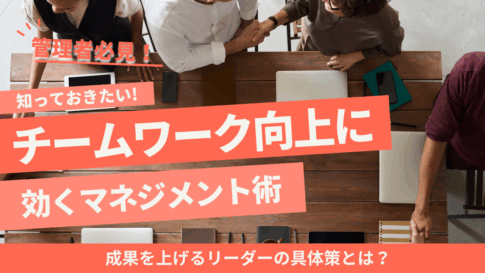



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。