
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。

また、ストレスチェックの時期か…

働く人の心のSOS、見逃していませんか?
年に一度のこの取り組みに対し、多くの企業や従業員が義務的な雰囲気で受け止めているのが実情です。特に高ストレス者に対する面談については、企業側も形式的に済ませてしまったり、従業員側も「どうせ何も変わらない」と消極的な姿勢になっていたりすることも。
しかし実際には、このストレスチェック後の面談こそが、職場改善や人材定着の鍵となる重要なプロセスです。うまく機能させれば、単なる健康管理の枠を超え、組織のパフォーマンス向上やエンゲージメント強化にもつながります。
この記事では、ストレスチェックでの「面談」の意義や実施方法、企業がとるべき適切な対応をわかりやすく解説していきます。
- ストレスチェック制度の基本
- ストレスチェックの面談を行う目的
- ストレスチェックの面談を行った後の行動が大切
ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度ってなんですか?

まずは制度の全体像をおさらいしましょう。
ストレスチェック制度は、2015年12月に労働安全衛生法の改正によって義務化されたものです。常時50人以上の労働者を雇用する事業場で、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられています。
ストレスチェックの主な目的は以下の通りです。
- 従業員が自らのストレス状態に気づくこと
- 高ストレス者を早期に把握し、必要に応じて面談などを行うこと
- 職場環境の改善を図ること
面談は「高ストレス者が希望した場合」に実施されるもので、あくまで本人の申出に基づくという点がポイントです。つまり、企業は本人が申し出ることを前提に準備を整える必要があるわけです。
面談を希望する従業員がいれば助けてほしいサインかもしれない
ストレスチェックの結果、高ストレスと判定されたとしても、面談を希望する人は必ずしも多くありません。中には「面談を希望すると評価に影響するのでは」「上司に知られたくない」などの不安から、申し出をためらう従業員も少なくないでしょう。
しかし、そうした中でも「面談を希望する」行動をとる従業員は、ある意味で最後のSOSを出している可能性があります。
- すでに体調に影響が出ている
- 職場での人間関係や業務量に限界を感じている
- 仕事への意欲が著しく低下している
上記のような背景がある場合、早期対応ができればメンタル不調の重症化や長期休職を未然に防げる可能性があります。
つまり、面談は「リスク回避」の機会であると同時に、「組織改善」の出発点でもあるのです。
面談を成功させるためのポイント

ストレスチェックの面談を成功させるにはどうすればよいのでしょうか?

難しい問題ですよね…。
労働安全衛生法上、面談は原則として産業医などの医師が行うことになっています。しかし、単に面談を設定するだけではなく、「どう受け止め、どう活かすか」が重要です。
以下の3つの視点で面談を組み立てていくことが求められます。
1. 傾聴と信頼形成
面談では、まず何よりも「安心して話せる空間」をつくることが第一です。話す側が「否定されない」「評価されない」と感じることで、ようやく本音が出てきます。
産業医だけでなく、同席する場合の人事担当や上司も、決して先入観や評価の目で話を聞かないことが大切です。
2. 問題の可視化と背景の把握
従業員の話からは、単なるストレスの有無だけでなく、その原因が業務負荷なのか、職場環境なのか、個人的な問題なのか、などの背景が浮かび上がってきます。
特に業務上の構造的な課題が見えてくることも多いため、記録をとり、組織全体へのフィードバックにつなげることが望まれます。
3. 対応策の共有と実行計画
面談で明らかになった課題は、組織としてどう対応するかを明確にしなければ、従業員の信頼は得られません。
休職や配置転換だけでなく、業務量の調整、勤務時間の見直し、定期的なフォローアップなど、具体的なアクションが必要です。
「面談の後」が重要だと言われる理由

面談の後もフォローが必要なのですか?

実は、ストレスチェック制度が形骸化してしまう最大の原因は、面談のあとに何もしないことにあります。
せっかく面談を行っても、
- 口頭だけで終わってしまう
- 職場に何の変化もない
- 面談内容がうやむやになる
などの状態では、従業員側からすれば「言っても無駄だった」と感じてしまいます。
そうなると、次回以降のチェックや面談にも消極的になり、組織としての学びや改善機会を失ってしまうのです。
逆に言えば、面談後の対応こそが信頼関係を築き、組織文化を変えるチャンスです。そのためには、記録の残し方、フィードバックの仕組み、上司との連携体制など、「面談後の流れ」を設計しておくことが欠かせません。
面談結果を職場の改善につなげるためのステップ
ストレスチェック後の面談は、単なる一時的なヒアリングでは意味がありません。本当に大切なのは、面談で得た気づきをどう活かすかです。
ここでは、面談の結果を職場全体の改善へと結びつけるための基本ステップを整理しておきましょう。
ステップ①:面談記録の整理と共有
産業医との面談内容は、本人の同意がある範囲で人事や上司と共有されます。このとき、ただ内容を伝えるだけでなく、具体的な問題や改善要望を整理することが重要です。
「今後も働きたいが業務量に限界を感じている」「直属の上司とのコミュニケーションにストレスがある」など、改善可能なポイントを抽出しておくことで、次の行動に移しやすくなります。
ステップ②:職場の現状把握と課題の特定
面談結果が個人レベルの話に留まらない場合、同様のストレス要因が他のメンバーにも影響している可能性があります。
例えば、特定の部署で高ストレス者が集中しているとしたら、上司のマネジメントやチーム体制に問題があるかもしれません。
全体傾向を把握するには、ストレスチェックの集団分析や面談履歴を見える化する仕組みが役立ちます。
ステップ③:改善策の立案と実行
課題が特定できたら、それに対して現実的かつ具体的な改善策を立案・実行する段階へと進みます。対応が個人単位であっても、チーム単位であっても、「いつ、誰が、どのように」行動するかを明文化しておくことがポイントです。
可能であれば、従業員本人にも合意を取りつけておくと、安心感と信頼につながります。
マネージャーや上司が取るべき具体的な行動

マネージャーや上司が取るべき行動はありますか?

ストレスチェック制度は制度上「産業医面談」とされていますが、実際の職場改善は日々のマネジメントにかかっています。つまり、現場の店長やリーダー、マネージャーの行動がすべての鍵を握っていると言っても過言ではありません。
では、マネージャーがとるべき行動とはどのようなものでしょうか?
| 具体例 | 内容 |
|---|---|
| こまめな声かけと観察 | ストレスは見えにくいため、「なんとなく元気がない」「最近表情が暗い」など、小さな変化に敏感であることが大切 |
| 心理的安全性の確保 | 部下が安心して悩みや違和感を伝えられる雰囲気づくりは、上司の振る舞いに大きく左右される |
| 柔軟な働き方の検討 | 業務量の調整、休暇取得の奨励、リモートワークの導入など、ストレス軽減のための選択肢を提示できるかが問われる |
| ストレス要因の棚卸し | チームとして抱えている課題(人手不足、業務過多、評価の不透明感など)を構造的に分析し、上層部と共有していく努力も必要 |
「みんなのマネージャ」で実現できる行動の可視化と早期対応
ここでご紹介したいのが、スカイストーン株式会社が提供する「みんなのマネージャ」というマネジメント支援ツールです。
このツールは、現場のマネージャーが従業員との関わりを記録し、「行動ログ」として残すことができるものです。特にストレスチェック後の面談やその後のフォローアップで、以下のような効果を発揮します。
面談内容と対応履歴の記録・共有がスムーズになる
面談で話した内容、合意した対応策、進捗などをクラウド上で記録・管理できます。産業医、人事、マネージャー間の情報連携もスムーズに行えるため、「聞いたはずの話が伝わっていなかった」「対応が抜けていた」などのトラブルも回避可能です。
部下のストレスサインを気づきやすくなる
みんなのマネージャには、日々の関わりを定期的に振り返る機能や、行動傾向の変化に気づけるダッシュボードなどが搭載しています。そのため、マネージャーが異変の兆しを察知しやすくなります。
フィードバック文化を自然に根付かせる
「みんなのマネージャ」では、日常的に部下の良い行動を承認・記録する機能も備えているため、評価と対話の文化が自然と定着しやすくなります。
結果的に、従業員の心理的安全性の向上、離職防止、モチベーションアップにもつながっていくでしょう。
ストレスチェックを企業の文化にするためにできること
制度としてのストレスチェック面談を、企業の「文化」に昇華させるには、トップから現場まで一貫した意識改革が必要です。
- 面談はやらされるものではなく、信頼を築く機会と捉える
- 面談は産業医だけでなく、マネージャーや人事も巻き込む
- 面談後のアクションを可視化・実行し、改善につなげる面談の積み重ねを「組織の成長記録」として価値づける
上記のようや姿勢があれば、従業員は「話してもムダ」ではなく「ここでなら話していい」と感じるようになり、ストレスチェックが生きた仕組みとして機能しはじめます。
面談で終わらせないことで職場が変わる
ストレスチェック後の面談は、形式的に済ませてしまえばただの義務です。しかし、そこで交わされた会話に耳を傾け、改善行動へとつなげていけば、それは組織にとっての大きな成長のチャンスとなります。
現場のマネージャーが適切に関与し、日々の対話や行動を記録・可視化する体制を整えれば、ストレスチェックは単なる健康診断ではなく、職場改善の起点になります。

単に面談の有無を確認するだけでなく、その先の対話と改善を支援する仕組みが、今まさに求められているのです。

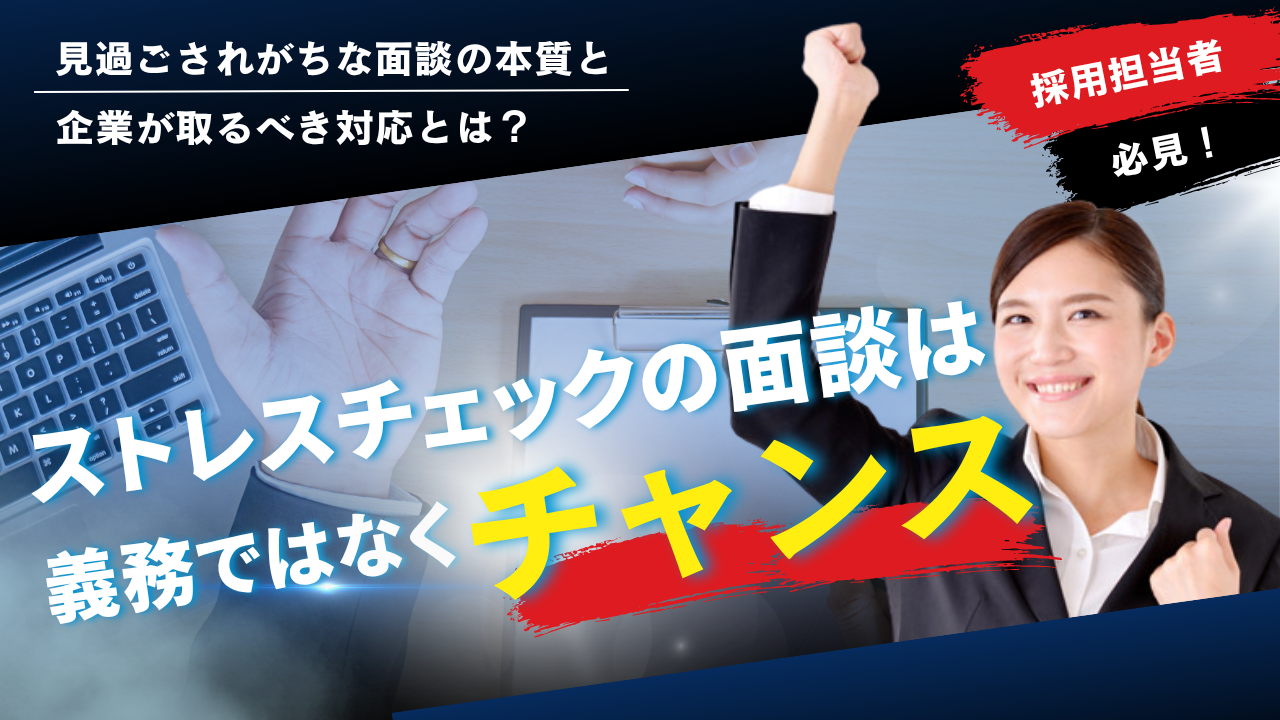

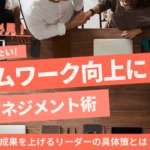
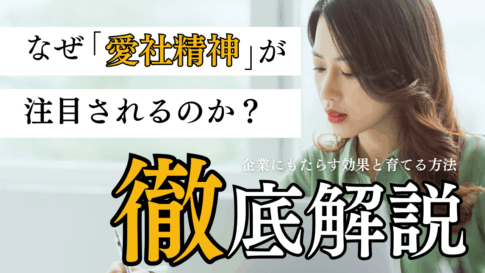
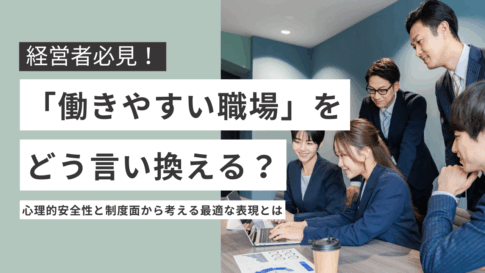
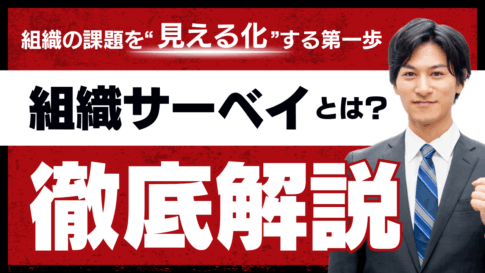


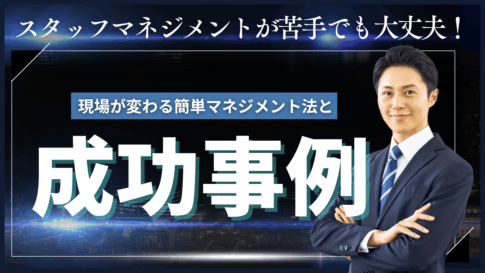
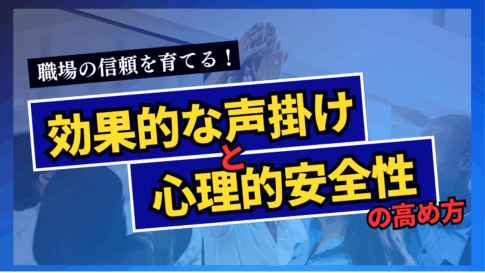
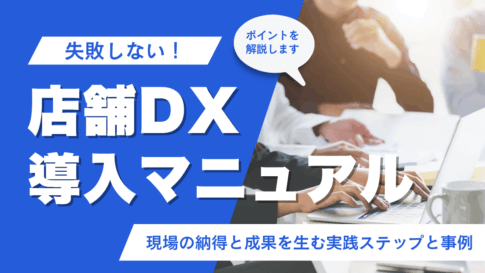



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。