
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「チームの雰囲気が悪い」「メンバーが指示待ちで動かない」「成果が出ない」——。そんな悩みを抱えるマネージャーは少なくありません。チームワークの向上は、個人任せにせず、リーダーが意識して関わることで確実に変えていける領域です。
本記事では、明日から実践できる具体的なマネジメントの手法を紹介します。1on1の活用法から効果的なフィードバックのポイント、さらには属人化を防ぐ仕組みまで、再現性あるチームビルディングの秘訣を解説します。
- チームワークの向上に効くマネジメント術
- 1on1の活用法から効果的なフィードバックのポイント
- 属人化を防ぐ仕組み
なぜチームワークの向上が必要なのか?

なぜ働くうえでチームワークが必要なのですか?

チームワークの向上は、単なる「仲の良さ」を意味するものではありません。組織として成果を出すために、メンバーが互いの役割や目的を理解し、補完し合いながら動ける状態を作ることが本質です。
とりわけ、マネージャーやリーダーはチームの方針や文化を作る立場にあります。日々の関わり方一つで、職場の空気が大きく変わるのです。
近年はリモートワークや非対面の働き方が増えたことで、従来以上に「見えない関係性」のマネジメントが重要視されています。
マネージャーの影響力とチームの成果の関係
成果を上げるチームの多くは、メンバーの自律性が高く、主体的に行動しています。しかしこの状態を作るには、リーダーのサポートが不可欠です。具体的には、方向性の提示、目標の共有、個々の強みに合ったタスクの割り当てなどを通じて、メンバーが安心して行動できる環境を整える必要があります。
| マネージャーの行動 | チームへの影響 | 期待される成果 |
|---|---|---|
| 明確な方向性の提示 | 迷いの軽減 | 効率的な業務遂行 |
| 目標の共有 | 一体感の醸成 | モチベーション向上 |
| 個別の強みを活かした役割分担 | 能力発揮の促進 | 生産性向上 |
こうした働きかけが、最終的には成果に直結します。
放置されがちな「現場任せ」のリスクとは
「現場でなんとかしてくれるだろう」とマネージャーが関与を控えていると、チーム内に不満やすれ違いが生まれがちです。特に、新しく配属されたメンバーや経験の浅い部下にとっては、サポート不足が成長停滞や早期離職に繋がるリスクがあります。
現場任せは短期的には楽に見えても、長期的にはチームの安定性や信頼関係を崩す要因になります。
チームワーク向上のためにマネージャーがまずやるべき3つのこと

チームワークを向上するにはどうすればいいのでしょうか?

チームワークを高めたいと考えるなら、マネージャー自身が「空気づくり」の起点にならなければなりません。特別な制度やコストのかかる施策よりも、日々の行動とコミュニケーションこそが最も効果的です。
ここでは、今日から取り組める3つの具体的な行動を紹介します。どれもシンプルでありながら、メンバーの心理的安全性とエンゲージメントを高める基盤となるものです。
ビジョンと目標の共有で方向性を揃える
チームがばらばらに動いてしまう大きな原因は、「どこに向かっているのか」が共有されていないことです。マネージャーは、組織や部署のビジョン、今期の重点目標などを定期的に言葉にして伝えましょう。
- 長期的なビジョン: 組織が目指す理想の姿を具体的に描く
- 中期的な戦略: 3〜6ヶ月スパンでの重点課題を明確化
- 短期的な目標: 月次・週次での達成すべき具体的な成果
短期的なタスクの指示にとどまらず、「なぜ今これをやるのか」という背景まで共有することが、メンバーの納得感と動機づけにつながります。
信頼関係を築く1on1の習慣化
メンバー一人ひとりの気持ちや悩みを理解するには、1on1ミーティングが欠かせません。1回10〜15分程度でも構いません。大切なのは、定期的かつ継続的に行うことです。
業務の確認だけでなく、最近の体調、モチベーション、キャリアへの希望なども話題にしていくと、信頼関係が自然に築かれます。特に「話を聴く姿勢」が信頼の土台になります。
「称賛文化」を取り入れて心理的安全性を高める
努力や成果に対してポジティブなフィードバックを贈る文化が根づいたチームは、雰囲気が明るく、挑戦も生まれやすくなります。マネージャーは率先して、「気づき」「認める」「言葉にする」を意識しましょう。
- 小さな改善の認知: 些細な工夫でも積極的に声をかける
- プロセスの評価: 結果だけでなく取り組み姿勢を評価
- チーム内での共有: 他メンバーの前で成果を称賛
ちょっとした改善でも「〇〇さんの工夫が助かりました」と伝えるだけで、本人のモチベーションが大きく向上します。チームメンバー間での称賛も促すと、さらに効果的です。
効果的なフィードバックのやり方とは?
フィードバックは、チームワークを育てるうえで最も重要なコミュニケーションの一つです。しかし「どのように伝えるべきか分からない」「ついネガティブに聞こえてしまう」と悩むマネージャーは少なくありません。
ここでは、フィードバックを前向きな行動につなげるための基本的な考え方と実践のポイントを解説します。
伝え方次第でやる気が変わる:言葉の選び方
フィードバックは、同じ内容でも伝え方によって受け取り方が大きく変わります。たとえば「ここを直してほしい」という指摘も、「これを意識するとさらに良くなる」といった言い回しに変えるだけで、受け取る側のモチベーションが向上します。
| 避けるべき表現 | 推奨される表現 | 効果 |
|---|---|---|
| 「ここを直してほしい」 | 「これを意識するとさらに良くなる」 | 建設的な改善意識 |
| 「あなたが悪い」 | 「私はこう感じた」 | 責任追及から意見共有へ |
| 「いつもダメ」 | 「今回の件について」 | 具体的で改善可能な指摘 |
主語を「私」にして「私はこう感じた」と伝えることで、相手を責めずに意見を述べることもできます。
「結果」ではなく「行動」に注目する重要性
結果ばかりに焦点を当てると、評価される側はプレッシャーを感じたり、誤解を生んだりしがちです。大切なのは「どんな行動をとったか」「どのように工夫したか」というプロセスに目を向けることです。
行動を具体的に評価することで、次の改善につながりやすくなり、本人も努力の方向性を理解しやすくなります。
「みんなのマネージャ」が提案するフィードバック支援機能とは
フィードバックを日常化するには、属人的なやり方では限界があります。そこで注目したいのが「みんなのマネージャ」のフィードバック支援機能です。
従業員の状態に応じてAIが最適なフィードバック方法を提案してくれるため、迷わず伝えるべきポイントが分かります。伝え方のトーンや構成、注意点まで提案されるため、経験に依存せず高品質なフィードバックが可能になります。
チームワーク向上を仕組み化するには?

チームワーク向上を仕組み化したいのですが…

チームワークを一時的な雰囲気づくりではなく、継続的に保ち、育てていくには「仕組み化」が必要です。
マネージャーの熱意や努力だけに依存していると、忙しさや人員の変動に影響され、取り組みが途切れてしまいがちです。
属人化を防ぎ、誰がマネージャーであっても安定的に機能する仕組みを整えることで、組織は自律的に成長できるようになります。
継続的な状態把握と対話の仕組みがカギ
チームの状態を正確に把握し続けるには、勘や主観では限界があります。アンケートやサーベイを活用し、モチベーションや信頼度、チームへの貢献度などを定期的に「見える化」する仕組みが有効です。
- 週次チェック: 簡易なパルスサーベイで状態変化を捉える
- 月次サーベイ: より詳細な満足度や課題を把握
- 四半期評価: 中長期的な成長と課題の振り返り
特に、週次や月次での簡易なチェックを繰り返すことで、チームの変化に早く気づき、対処が可能になります。また、これをもとにした1on1やチームミーティングの質も向上します。
「みんなのマネージャ」で可能になる、AIによる行動提案と1on1支援
「みんなのマネージャ」は、メンタルヘルスとマネジメントの専門家が監修したエンゲージメントサーベイシステムです。AIが従業員の状態に応じて1on1の優先度やフィードバック内容、声かけのタイミングまで提案してくれるため、マネージャーの行動が標準化され、チームマネジメントの属人化を防ぐことができます。
LINE連携やタイムライン表示など、現場にとって使いやすいUIも特徴です。
導入企業での成果例(離職率67%改善、現場の定着強化)
実際に「みんなのマネージャ」を導入した企業では、離職率が67%改善した例も報告されています。また、昇格者の現場適応率も高まり、マネージャーの成長とともにチーム全体の定着率が向上しました。
「なんとなく辞める」といった曖昧な離職理由が減り、具体的な育成や改善につながるフィードバック文化が根づいたことが成功の要因です。
まとめ
チームワークの向上は、組織にとって一過性のイベントではなく、日々の積み重ねによって築かれる文化です。その鍵を握るのが、マネージャーの関わり方です。

ビジョンの共有、信頼を育む1on1、心理的安全性を高める称賛文化、そして適切なフィードバックなど、どれも特別なスキルを必要とするものではありません。意識と仕組みさえ整えば、誰でも取り組むことが可能です。
マネージャーの関わり方がチームを変える
マネージャーは「成果を出す責任者」であると同時に、「環境を整える支援者」でもあります。個々の行動や感情に目を向け、適切なサポートを行うことで、チーム全体の雰囲気や生産性が大きく変化します。放っておくのではなく、寄り添いながら導く姿勢が、チームワークの土台を作ります。
再現性あるマネジメントの仕組みで「属人化」を打破しよう
属人化されたマネジメントは、組織全体の成長を妨げるリスクがあります。その対策として、「みんなのマネージャ」のような仕組みを活用することで、誰がマネージャーになっても一定の質を保てる体制が整います。
感覚や経験に頼るのではなく、データと仕組みをもとにしたマネジメントへ移行することが、これからのチームワーク向上に必要不可欠です。

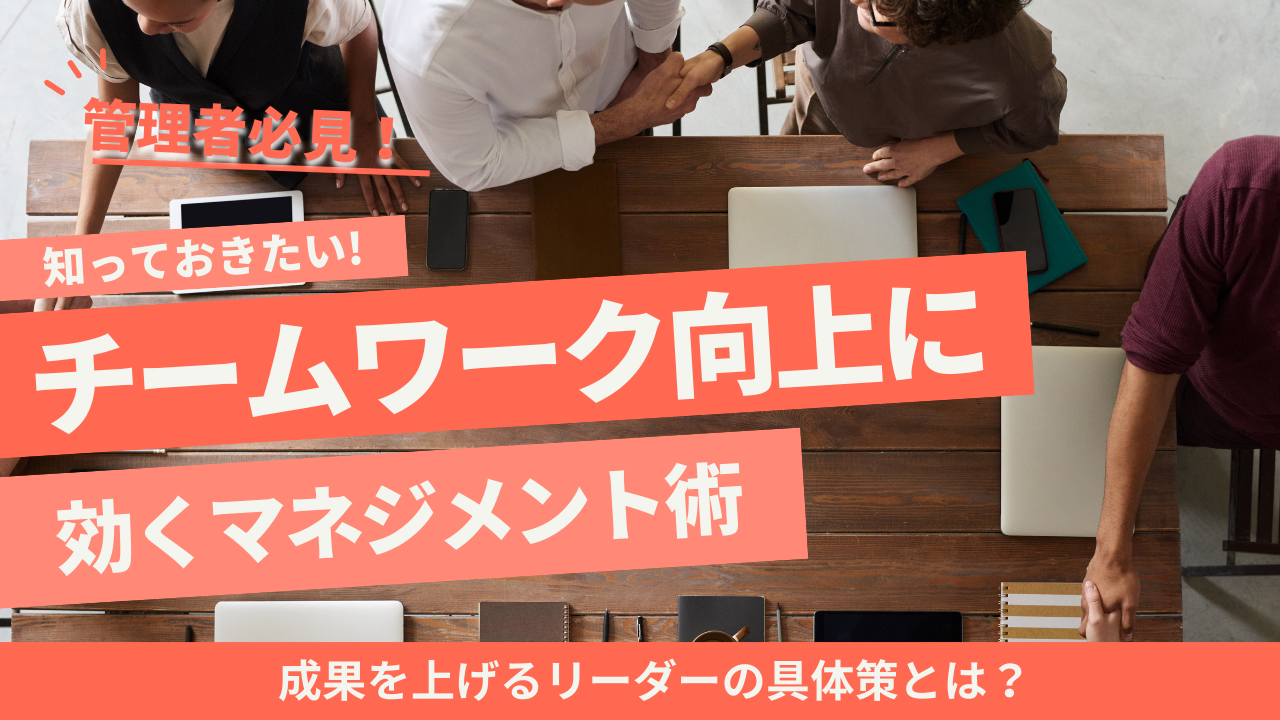
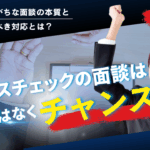

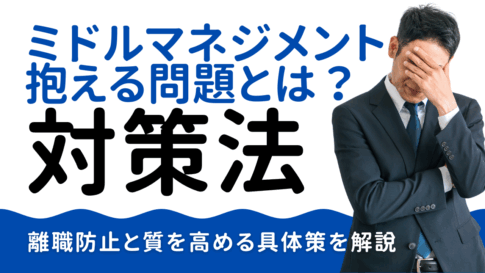
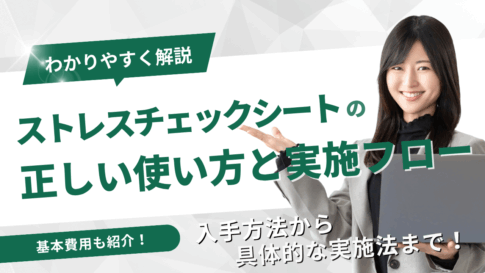
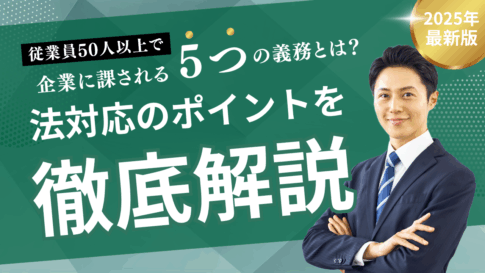
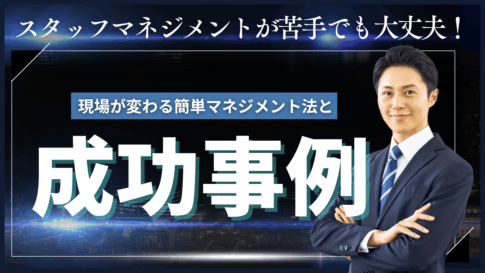
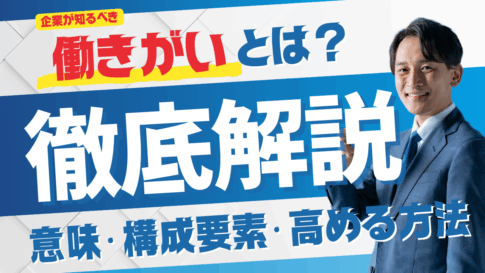
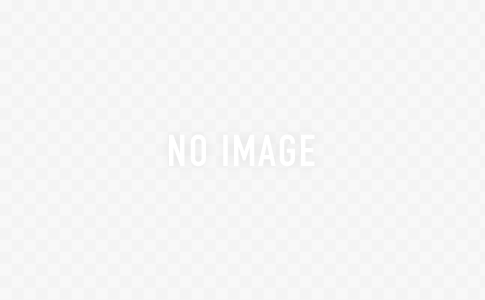
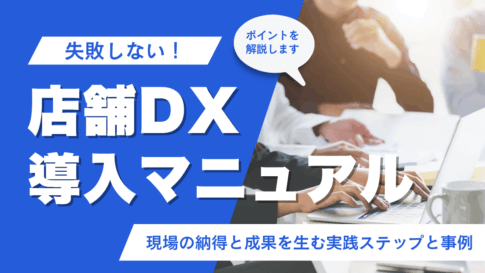
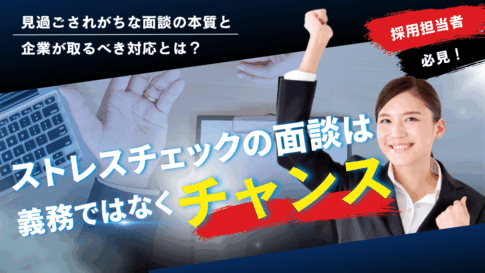



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。