
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「ストレスチェックって、実際に何をすればいいの?」そんな疑問を抱える企業担当者の方も多いのではないでしょうか。ストレスチェック制度は、従業員50人以上の事業所で年1回の実施が義務付けられている重要な取り組みです。
本記事では以下のようなことを、わかりやすく解説します。
- 厚生労働省が推奨するチェックシートの様式
- 具体的な入手方法
- 実施までの流れ
- 結果を活かした職場改善の方法
さらに、制度を効果的に活用するための支援ツール「みんなのマネージャ」の活用法もご紹介。ストレスチェックを“実施するだけ”で終わらせないためのポイントを押さえましょう。尚、「みんなのマネージャ」でも現在ストレスチェック機能を開発中で、近日中に実装する予定です。
- ストレスチェックシートとはなにか
- ストレスチェックシートの様式や入手方法
- 従業員のストレスの可視化におすすめのツール
ストレスチェックシートとは?まずは制度の基本を理解しよう
ストレスチェックシートは、職場におけるメンタルヘルス対策として2015年に義務化された制度に基づくものです。従業員のストレス状況を把握し、早期対応を図る目的で導入されています。
50人以上の従業員がいる事業所では、年1回以上のストレスチェックが法的に求められており、従業員の心身の健康維持だけでなく、組織の離職率低下や生産性向上にもつながる取り組みといえるでしょう。
まずは制度の概要を理解することが、スムーズな実施の第一歩です。
ストレスチェック制度とは何か?背景と法的根拠を解説
ストレスチェック制度は、「労働安全衛生法」の改正によって2015年12月より施行されました。この制度の背景には、職場のメンタルヘルス不調や自殺、過労による問題が社会的に深刻化したことが挙げられます。
ストレスチェックは、従業員本人が自己のストレス状態に気づくことを促し、企業側が職場環境の改善を行うためのきっかけとなる仕組みです。実施には医師や保健師などの産業医が関与し、プライバシー保護も義務付けられています。
誰が対象?企業の義務と実施のタイミング
ストレスチェックの対象者は、原則として常時使用する労働者であり、雇用形態にかかわらずおこなわれます。
- 正社員
- パート
- 契約社員
ただし、短期雇用など一部除外条件もあります。実施義務があるのは、従業員が50人以上いる事業所で、年1回以上の頻度で行う必要があります。

従業員が50人いる会社では必須です。
チェックの結果は本人に通知され、希望すれば医師の面談指導を受けることができます。企業側はその対応履歴を記録し、再発防止や職場環境改善につなげる責任があります。
ストレスチェックシートの様式と入手方法
ストレスチェックシートは、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」が一般的に用いられています。この様式は、以下のようなことを包括的に評価できるよう設計されています。
- 職場のストレス要因
- 心身の反応
- 周囲の支援環境
企業はこの標準シートをそのまま使用することが推奨されており、厚労省の公式サイトからPDFやExcel形式で無料ダウンロードが可能です。実施の正確性を担保するためにも、まずは公的な様式の活用が基本です。
厚生労働省が提供する標準シート(57項目)
「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」は、職場のストレスチェックにおける基本的な調査票です。このシートは、以下のような項目に分類され、従業員のストレス状況を多面的に可視化できます
- 仕事の量や質
- 職場の人間関係
- 身体的・精神的反応
- 上司や同僚からの支援
質問はすべて選択式で、集計しやすく、専門家による高ストレス者の判定にも対応しています。信頼性が高く、多くの企業がこの形式をそのまま使用しています。

質問は選択式なのですね!
Excel版・PDF版のダウンロードリンクと使い方
厚生労働省の公式サイトでは、ストレスチェックシートをExcel形式またはPDF形式で配布しています。Excel版は回答の自動集計ができるため、実施負担が軽減されます。PDF版は紙面での配布や手書き回答に適しています。
導入にあたっては、以下のような方法で対応が可能です。
- シートを印刷して配布する方法
- オンライン上での回答受付
ただし、結果管理や個人情報の保護には十分な配慮が必要です。実施後は医師の面談勧奨や環境改善につなげましょう。
独自テンプレートは使える?カスタマイズ時の注意点
独自にカスタマイズしたテンプレートを使用することも可能ですが、制度上の要件を満たす必要があります。とくに、厚労省が定めた「3領域」を含まない構成では、法的義務を果たしたことにはなりません。
- 職場のストレス要因
- 心身の反応
- 周囲のサポート
また、高ストレス者の判定基準も曖昧になりがちです。制度に準拠した信頼性あるチェックを行うためには、公式フォーマットの活用が安全で確実といえるでしょう。

厚生労働省には公式のフォーマットがあります。
ストレスチェックの流れと実施方法
ストレスチェックは単にシートを配布して終わるものではなく、事前準備から実施、フォローアップまで一連の流れが重要です。
- チェック項目や担当者の選定、個人情報の取り扱いルールなどを明確にしたうえで、実施体制を整える
- 従業員へ調査票を配布し、回答を回収・集計する
- 結果通知と高ストレス者への対応を行い、必要に応じて職場環境の改善策を実施
この一連の流れが、制度の信頼性と効果を高めるカギとなります。
準備段階で押さえるべき3つのポイント
ストレスチェックの実施にあたり、事前の準備は非常に重要です。
- 「実施者の決定」をし、医師や保健師など専門資格を持つ者に依頼する
- 「実施計画の策定」をし、対象者の範囲や実施時期、運用ルールを明文化する
- 「情報管理体制の整備」をし、結果の取扱いやプライバシー保護に関する社内の取り決めを設け、従業員に安心して回答してもらえる環境を整える
これらの準備が、制度の成功を左右します。
実施から集計・結果通知までのフロー
ストレスチェックの実施は、原則として年1回以上、従業員の勤務時間内に行われます。チェックシートは紙またはオンラインで配布され、集計は実施者または代行機関が行います。その後、個人結果は本人に通知され、プライバシーを厳守した形で管理されます。

プライバシーは守られるため、受ける人は安心です。
本人が希望する場合、医師による面談指導の機会が提供され、事業者はその申し出を拒むことはできません。これらの手順は法令で定められており、計画的な運用が求められます。
高ストレス者の基準と対応方法
高ストレス者とは、ストレスチェック結果が一定の基準を超えた従業員を指します。判定には厚生労働省の「評価基準表」を使用し、点数が高い者に医師面談の機会を提供する必要があります。
企業は本人の申し出に基づいて、以下のような必要な措置を講じます。
- 産業医との面談
- 業務改善
- 配置転換
この対応は「形だけ」のものにせず、実質的な改善に結びつけることが重要です。適切な対応が、企業の信頼と従業員の安心につながります。
ストレスチェックをより効果的にする方法
ストレスチェック制度は、形式的に実施するだけでは十分な効果は得られません。チェック後の結果をいかに活用し、従業員との対話や職場改善に結びつけるかが重要なポイントです。
また、定期的に継続実施しながら傾向を分析することで、離職リスクの早期発見やマネジメントの質向上にも役立ちます。
従業員の心身の状態を見える化し、信頼関係のあるフィードバックを重ねていく仕組みづくりが、企業全体の健全な成長を後押しします。
実施だけで終わらせない「対話」と「改善」
ストレスチェックの真価は、結果を活かして職場環境を改善することにあります。高ストレス者への面談対応だけでなく、チェック結果をもとにチーム単位の課題を共有し、対話の機会をつくることが重要です。
たとえば、「上司との関係性が弱い」「業務負荷が偏っている」など、集団分析によって見える課題に対し、以下のような対策をおこなうといった具体策を講じます。
- 定期的な1on1ミーティング
- 業務フローの見直し
そうすることで、従業員のエンゲージメント向上にもつながります。
「みんなのマネージャ」で可視化と継続支援を実現
ストレスチェックを「効果的に活用したい」「結果を継続的にフォローしたい」と考える企業にとって、「みんなのマネージャ」は非常に有効なツールです。
「みんなのマネージャ」には以下のような機能があります。
| 従業員の状態を見える化 | メンバーごとの回答状況やコンディションをダッシュボードで一目で確認 |
| AIによる行動提案 | 日々の対話や声がけの内容をAIが自動で提案 |
| スキル・評価の自動採点 | 自己評価上司からの評価360°評価の結果 |
このサービスは、週1回の高頻度なパルスサーベイで従業員のモチベーションやストレス傾向を可視化し、AIが状況に応じたフィードバック内容まで提案します。
また、店長やマネージャが適切なコミュニケーションを行うための支援機能が整っており、ストレスチェックの“その後”をしっかりとフォローする体制が構築できます。

ストレスチェックのそのあとが大切ですね。

はい!従業員の人をしっかりをとフォローしてあげましょう。
まとめ
ストレスチェックシートの活用は、従業員のメンタルヘルスを守るだけでなく、職場全体のパフォーマンス向上にも直結する重要な施策です。ただ単に実施するだけでは意味がなく、チェック結果をもとに以下のように考えることが、制度の本質です。
- 何を改善するか
- どのように支援するか
厚労省の標準様式を活用しながら、継続的に振り返りと対話を行う仕組みを構築することが求められます。その点で、「みんなのマネージャ」のように、日常的に従業員の状態を可視化し、個別に寄り添えるツールは、ストレスチェックの効果を最大化する強力なパートナーとなるでしょう。
制度を「定着」させる一歩として、導入を検討してみてはいかがでしょうか。


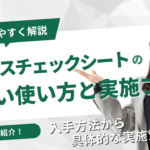
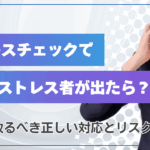
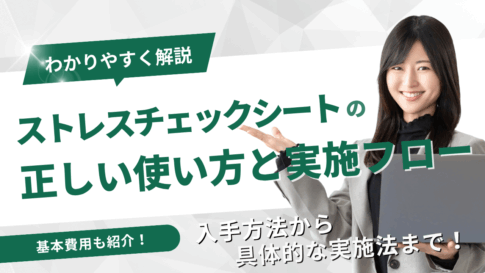
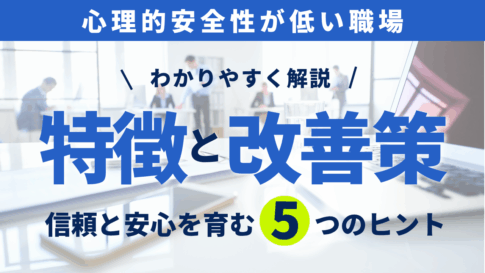
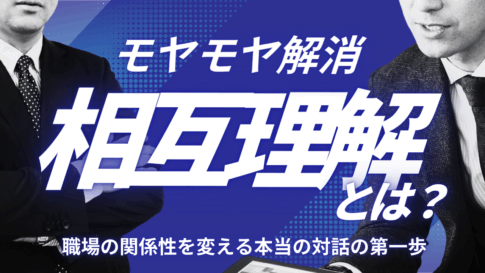
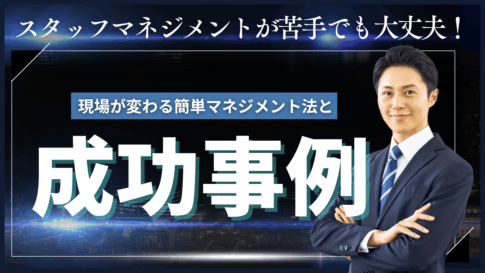
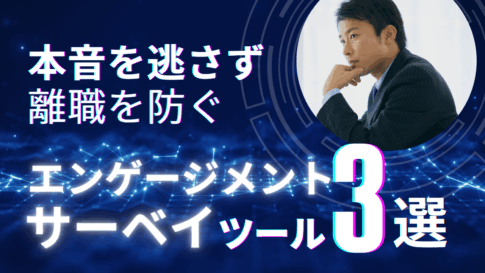
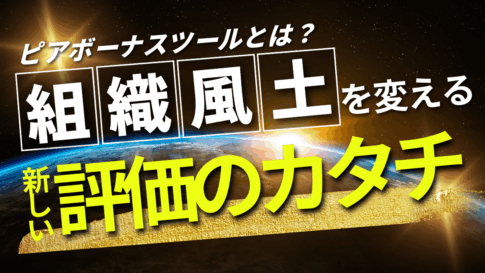
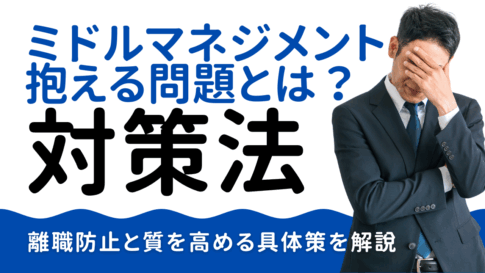
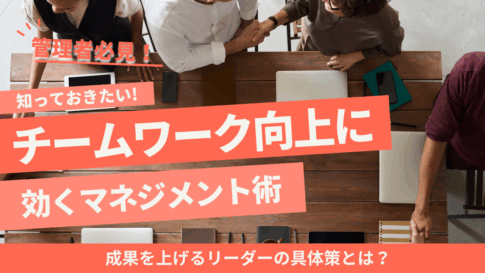



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。