
飲食店向け経営・DXコンサルタント(ジュニアアソシエイト)
新卒で大手IT企業に入社し、飲食店の業務システム開発に携わる。当時から佐藤をメンターとして仰ぎ、その「現場ファースト」の姿勢に強く感銘を受ける。その後、佐藤のコンサルティング会社設立に際し、自身のデジタルスキルと現場への情熱を活かしたいと志願し、創業メンバーとして参画。
「スタッフがすぐ辞めてしまう」「業務が非効率なのに改善できない」そんな悩みを抱える店舗運営者にとって、DX(デジタルトランスフォーメーション)は単なるIT導入ではなく、組織を進化させる鍵です。
本記事では、現場に混乱を起こさずにDXを導入し、成果につなげる具体的なプロセスとポイントを解説します。成功事例を交えながら、「使いこなされるDX」の条件を一緒に考えていきましょう。

DXとは、デジタルのデータ管理やシステムに移行することを指します。

私世代は問題なくても、一回り上の世代の方には馴染みにくいこともありそうですね……。
店舗DXとは何か?求められる背景を読み解く
店舗業界では近年、「DX」という言葉が不可欠なワードとなっています。
DXとは単なるシステム化ではなく、働き方や意思決定の仕組みをテクノロジーの力で根本から変えていく取り組みです。
店舗DXが求められる背景にあるもの
- スタッフの定着率が悪い
- 意思決定の取り組みや教育が定着しにくい
- 企業のリソース不足
多くの店舗では、人手不足や定着率の低さ、マネジメントの属人化といった問題に直面しています。こうした状況において、DXは業務の効率化だけでなく、現場の心理的負担を減らし、スタッフと店舗の成長を同時に支える手段として注目されています。
店舗DXを成功に導く5つのステップ
現場で本当に使われ、成果が出る店舗DXを実現するには、計画的な導入ステップが欠かせません。
以下では、現場が納得し、定着するまでの基本的な5ステップをご紹介します。
店舗DXのためのステップ
- 店舗の現状把握と課題の可視化
- 導入目的と成果指標の設定
- 現場に馴染むツールの選択
- 限定エリアでの試験導入
- 効果検証と改善ループの構築
それぞれのステップを噛み砕いてご紹介しますので、ぜひ自社に取り入れてみませんか。
ステップ1|店舗の現状把握と課題の可視化
最初に行うべきは、日々の業務のどこに無駄があるのか整理することです。あわせてデジタルに促すべき部分と人の手で行うべき部分を明確にします。
従業員の離職率やスタッフの不満点、マネジメント体制のばらつきなど、現場の実情を多角的に分析しましょう。現場の声をもとに課題を明確化することで、DX導入の目的と着地点がぶれなくなります。
ステップ2|導入目的と成果指標(KPI)の設定
導入目的が曖昧なままでは、DXは形骸化します。
「人材の定着率を改善したい」「スタッフ育成の進捗を可視化したい」といったように、具体的なKPIを設定することがポイントです。
数字として追える目標を明示することで、現場も納得して行動に移しやすくなります。
ステップ3|現場に馴染むツールの選択
システム導入は「何を入れるか」ではなく「誰がどのように使うか」が成功の分かれ目といえます。
| ツールに依頼 | 人による実施 | |
|---|---|---|
| 店舗売上 | 管理、グラフ化 | データをもとに改善策を分析 |
| 採用 | 面接の日取り設定 | 面接の実施 |
| 教育 | 動画視聴教材などの設定 | 細やかなフィードバック |
使い勝手が悪いツールでは社内に定着しません。店舗の実情に合った設計のツールのほか、マネジメント初心者でも使いこなせる機能が搭載されているツールなどが求められます。

店舗内を何でもかんでもDXすれば良いわけではないのだから難しい。
ステップ4|限定エリアでの試験導入
一部の店舗や時間帯から試験的に導入していきます。一斉導入を避けることで、リスクを抑えつつ、現場の反応も確認できるというメリットがあります。
| 限定導入の例 | 試験的DX導入方法 |
|---|---|
| チェーン展開店舗 | 店舗別に導入 |
| 飲食店 | アイドル時間帯などから導入 |
| 独立系経営 | 場所別に導入 |
スモールスタートで得たフィードバックは、運用改善の貴重な材料となります。
ステップ5|効果検証と改善ループの構築
最後には試験運用の結果を数値と現場の意見から評価し、改善を加えながら本格展開へ進めましょう。定着させるためには、現場スタッフの声に耳を傾け、改善を重ねていく柔軟性が不可欠です。
店舗DXを軌道に乗せるコツとは?
DXの成功は、ツールだけでなく「人」の動きによって決まります。
社員が動いてくれるDX導入のために
- 方向性の明確化を行う
- 管理職や経営部から浸透させていく
- 現場に不安を与えない信頼性を求める
続いては、現場に協力的に動いてもらうための「管理職・経営者の心得」を紹介します。
トップの旗振りと現場の共感が不可欠
経営層の明確な方向性と、現場の納得感が揃って、初めてDXは機能します。一方通行の指示ではなく、現場の課題や不安に耳を傾けながら、現実的な着地点を設計していくよう心がけましょう。
数値をもとに対話する文化を醸成する
スタッフの体調やモチベーション、スキル成長などをスコアで把握することで、感覚ではなくデータに基づいたマネジメントが可能になります。
これにより、1on1などの対話の質も格段に上がります。
現場の安心感を高める支援・教育体制
特に初めてDXに触れる現場では、「どう使えばいいか」が明確でなければ導入効果は薄れます。操作説明に加えて、活用目的や行動指針まで伝えるサポート体制が必要です。

社員は我が社の宝ですので、何よりも寄り添って、大切にしていきたいと考えています。

社長がそう言ってくださる会社で、とても助かっています!
実際の成功事例から学ぶ現場主導の変化
例えば、関東圏で20店舗以上を展開するカジュアルレストランチェーンでは、従業員の状態をリアルタイムで把握できるパルスサーベイを導入した結果、従来30%を超えていた離職率を、2年で15%以下に半減させることに成功しました。
また、スキルの自己評価と他者評価を取り入れた評価制度の導入で、スタッフのやる気と成長実感も向上しました。
「辞めたい」ではなく「昇進したい」と話すスタッフが増えたという声もあり、現場の空気が変わったことがうかがえます。
「みんなのマネージャ」が選ばれる理由とは?
「みんなのマネージャ」は単なるサーベイツールではありません。スタッフの感情・行動の傾向をリアルタイムで捉え、フォローが必要なメンバーをフラグ立て。また、AIがデータに基づいたマネジメント行動提案を行います。
さらに、実名制を採用することで心理的安全性と透明性を両立。属人化しがちなマネジメントを数値化し、標準化することが可能です。
導入から定着まで専門家が伴走する体制もあり、「現場で使いこなされるDX」を実現するための強力なパートナーになります。
店舗DXのカギは協力にあり!
店舗DXの鍵は、テクノロジーだけでなく、人の理解と協力を得ながら進めていくプロセスにあります。計画的に導入し、現場の声に基づいて調整を重ねることで、形だけで終わらないDXが実現します。
「みんなのマネージャ」が組織内協力に貢献します
「みんなのマネージャ」は、現場の声に寄り添いながらマネジメントの質を高め、離職率の低下や育成の標準化を後押ししてくれるツールです。人が辞めずに成長し続ける店舗を目指すなら、今こそその一歩を「みんなのマネージャ」と踏み出してみませんか。


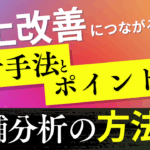
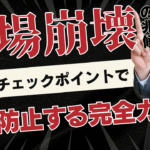
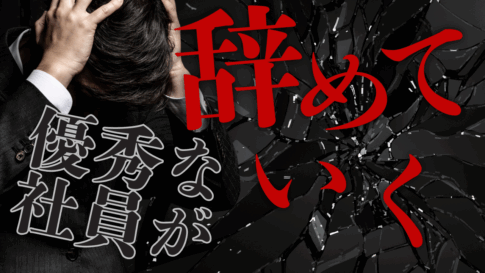
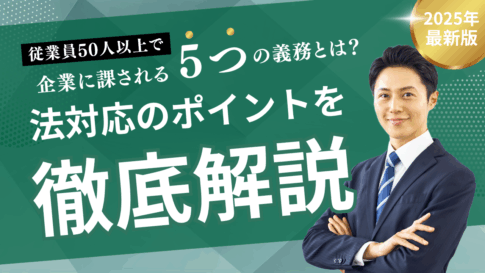
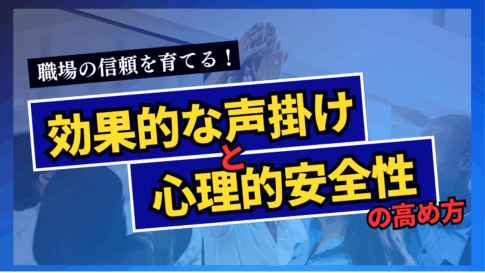
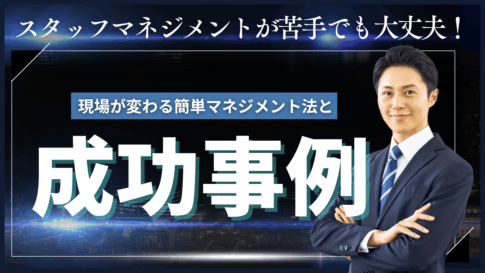
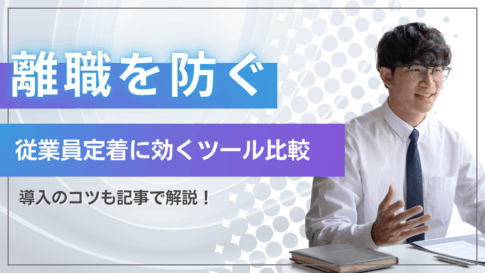


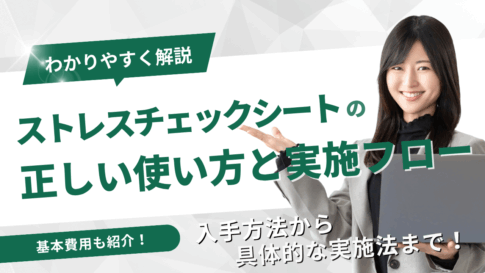



飲食店向け経営・DXコンサルタント
大手IT企業で飲食業界向けシステムの開発に携わった後、ITと現場のギャップを埋めるべく独立。現在は、個人店から多店舗展
開の企業まで、幅広い飲食店のDX推進をサポート。デジタル技術を駆使して、バックヤードの非効率な業務をなくし、従業員がより楽しく働ける環境を創り出すこと。そして、その結果として、お客様に最高の体験を提供できる店が増えることをミッションに活動中。