
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「なんとなく職場がぎくしゃくしている」「会話すら減ってきた気がする」その違和感、放置していませんか?
職場崩壊は、ある日突然起こるのではなく、段階を踏んで進行します。

社長が気がつくのは一番最後、かも。

そうならないようしていただけると、社員も働きやすいです。
本記事では、見逃しがちな兆候とその背景にある原因を掘り下げ、すぐ取り入れられる対策までを一貫してご紹介します。心理面のケアやマネジメント強化を図りたい方にとって、役立つ情報を詰め込みました。
- 職場崩壊のサインがわかる
- 職場崩壊を未然に防ぐ方法を知れる
- 職場崩壊を防ぐツール「みんなのマネージャ」を知れる
職場崩壊の本質:実態とその特徴
職場崩壊とは、組織内の機能が失われ、業務効率や信頼関係が著しく損なわれた状態を指します。
たとえば、指揮命令系統があいまいで誰が責任を持つのか不明になり、まともな報連相すら成立しない状態です。

組織を形作りには、まずは私の立ち位置からですな。
現代ではテレワークや多様な働き方の導入により、目に見えにくい形で人間関係にヒビが入りやすくなっています。
そういった環境変化が、職場崩壊の入り口となるケースが増えているのです。
なぜ今、職場崩壊がじわじわ増えているのか
コロナ以降、多くの企業がリモートや時差出勤を取り入れましたが、その結果「会わないけど仕事はする」状態が常態化し、職場の温度感や雰囲気が見えにくくなりました。
さらに物価や社会情勢の不安が心理的プレッシャーを高め、ちょっとした衝突でも組織に大きな影響を与えかねない環境となっています。
職場崩壊につながる主要原因
崩壊は一度では起こらず、複数の要因が重なることで進行していきます。中でもマネジメントの弱体化、評価制度の不透明さ、心理的安心感の欠如、業務負担の不均衡が主要因です。これらが少しずつ作用し合い、気づかないうちに組織が崩れ始めます。
職場崩壊につながる主要原因
- 責任の所在があいまいなマネジメント
- 心理的安全の低下
- 会話の現象
- 昇進や評価制度に対する不信感
- 業務負担の偏り
続いての見出しでは、職場崩壊の主要な原因について触れていきます。
責任の所在があいまいなマネジメント
マネージャが「誰に何を任せるか」をあいまいにしている場合、チームメンバーは自分の役割に自信が持てず、不安を抱えることになります。
誰が決定を下すのかが不明瞭だと、トラブル時に対応が後手に回り、信頼性が失われる構図が生まれます。
立場や序列、管理者などが不透明な場合、スタッフが働きにくさを感じてしまうことがあるため注意しましょう。
心理的安全の低下が会話を閉ざす
「言いたいことが言えない」「相談すると怒られるのではと怖い」といった感情が広がると、建設的な意見交換が止まり、組織は硬直化します。
本音が出なければ問題は内に閉じ込められ、改善の芽は育ちません。社内の会話の現象は、職場崩壊の芽となります。
昇進や評価制度の不透明さ
評価軸が不明瞭だったり、言動に基づく評価ではなく“気に入られる人”が評価されると感じられる場合、不公平感が蓄積されます。これは職場全体のモチベーションを大きく削ぐ要因となります。
信頼性のある評価制度
- 数値や指標ができている
- 「次の昇進までのステップ」が伝えられている
- 上司の主観ではないと、スタッフ全員がわかる
社員にとって不満になりにくい、的確に目の行き届いた評価制度を導入しましょう。

基本わかりやすいのですが、「次のステップに上がるための指標」が見えると嬉しいかなと感じています。

よし、来月は評価制度を改めてみようと思います。
負担の偏りによる疲弊
業務を特定のメンバーに集中しすぎる職場では、疲労が蓄積しやすく、それに見合う支援やフォローがなければ、組織は疲弊していくばかりです。
負のサイクルは、士気の低下を加速させます。
業務は等しく分配するほか、部署やチームごとの偏りがあるのであれば適切な人事異動も検討しなければなりません。
職場崩壊の兆候チェックリスト
崩壊が進む前には、必ず何らかのサインが出ています。ここでは取り組むべきポイントを明確にしましょう。
| 職場崩壊チェックリスト | 表面化している現象 | 背景 |
|---|---|---|
| 職場内 | 会話が急減していないか | 職場への不信感が増している |
| スタッフ個人 | 体調不良者が増えていないか 連日顔色のすぐれないスタッフがいないか | 本人が気かついていないうちに心身がサインを発しているケースも |
| チーム内 | 退職や異動希望が極端に増えていないか | 職場崩壊がかなり進んでいる |
もし複数当てはまるようであれば、早急な対策が望まれます。
会話量の急減
雑談や業務連絡の減少は、人間関係の希薄化を意味します。コミュニケーションが減るほど、誤解や軋轢が累積しやすくなります。
同時に職場内の空気も悪くなっていくでしょう。
体調不良やメンタル安定の乱れ
急に欠勤や遅刻が増えたり、普段明るい人が不機嫌に見えたりする場合、職場環境の変化が影響している可能性があります。
体調不良やメンタル不調は、スタッフ本人も気がついていないケースがあります。
会社のためだけではなく、スタッフの今後のライフスタイルのためにも、負担をかけないことと、不調にいち早く気がつくことが必要です。
離職や部署異動希望の広がり
ひとりが辞めると、それを見た他のメンバーも「このままでは……」と不安になり離職・異動希望が増えるケースが目立ちます。
退職や離職希望者、異動希望者などが極単に増えているのであれば、その時期の職場環境やチーム内の環境を見直してみましょう。
無関心層の増加と自主性の喪失
「どうせ変わらない」といった諦めムードが広がると、報告・連絡・相談(報連相)すら形骸化し、職場の能動的な雰囲気が消えていきます。
周辺に退職や異動の希望者が増えることで、無関心層が増加する可能性もあります。取り返しのつかない職場崩壊を起こしてしまう前に、スタッフの無関心に気がつき、何らかの策を練る必要があるでしょう。
今すぐできる崩壊防止策
兆しを察知したら、すぐに行動を起こすことが肝心です。当記事では、次のような方法を例として取り上げ、職場崩壊の防止方法をご紹介します。
職場崩壊の防止策
- 定期的なアンケートの実施
- 双方向コミュニケーションの推奨
- 「みんなのマネージャ」のようなマネジメント支援ツールの活用
以下の方法は早期段階でも実施しやすく、組織風土や対話文化の再構築に有効です。ぜひ現場に取り入れてみてください。
定期的な状況把握アンケートの実施
スタッフが抱えている不満や疑問のほか、業務に関する意欲を見える化するものです。
感情や状態を「なんとなく」ではなく、週単位・月単位でデータとして収集することで、変化を早めに察知できます。パルスサーベイのような、高頻度の調査も有効です。
双方向コミュニケーションの推奨
指示命令型ではなく、1on1ミーティングや部下の声に耳を傾ける姿勢を重視しましょう。
フィードバックを「叱責」ではなく「育成目的」と位置づけることがポイントです。
1on1ではスタッフに寄り添う姿勢を見せることが重要ですので、もしモチベーションの低さを察知しても、叱責してはいけません。
双方向でコミュニケーションが取りやすい職場づくりのための時間として、活用しましょう。
「みんなのマネージャ」を活用した予兆検知と支援
エンゲージメントやストレス状態を可視化する「みんなのマネージャ」は、従業員サーベイの自動化とAIによる解析結果から具体的な行動アドバイスまで提供します。これにより属人的な判断に頼らず、組織的にケアを進めることが可能。
まさに職場崩壊を未然に防ぐための最適なツールです。
みんなのマネージャで職場の異変をいち早く察知!
職場崩壊は、ゆるやかではあるが確実に進行するプロセスです。モヤモヤや違和感を放置せず、早めに兆候をキャッチできる組織体制が重要です。
日常的なアンケート、対話文化の醸成、そして「みんなのマネージャ」のような支援ツール導入を備えることで、安心できる労働環境を維持し、組織の健全な成長につなげることができます。
職場とスタッフを守るために、自社に職場崩壊を防ぐための仕組みやツールを取り入れていきませんか。

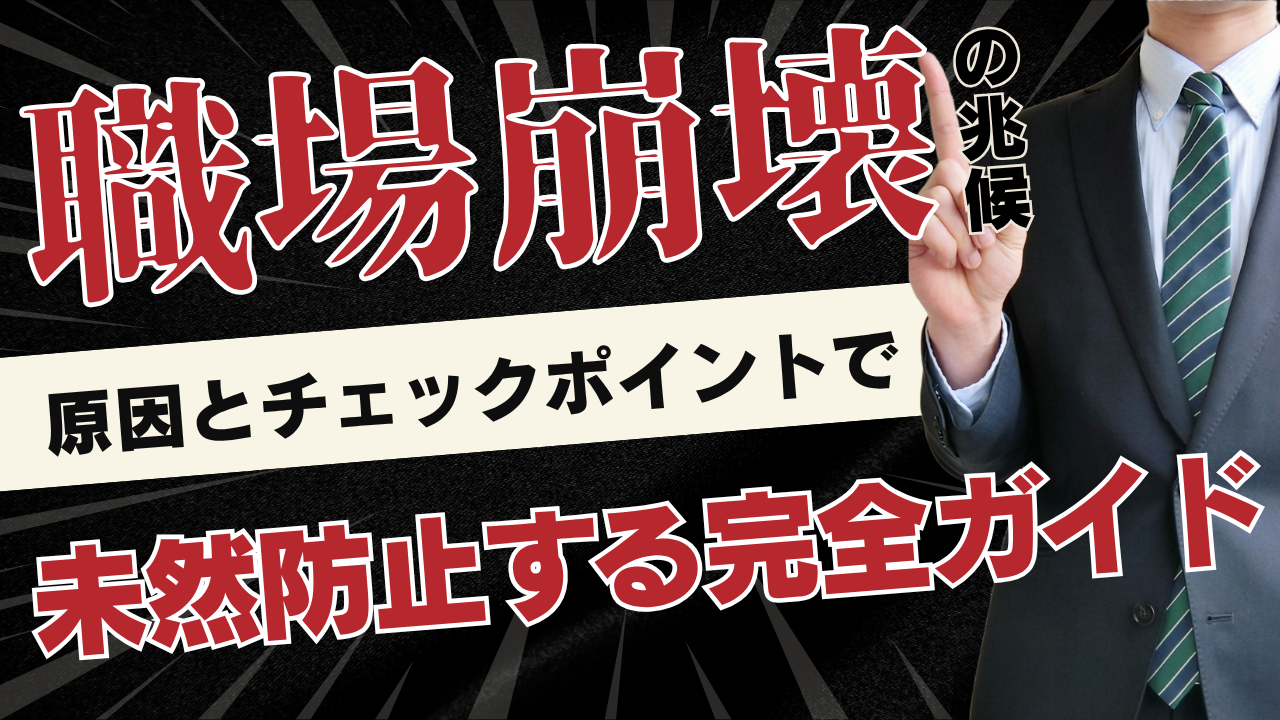
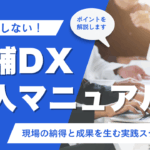
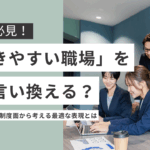
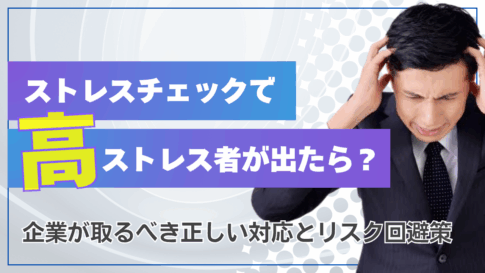
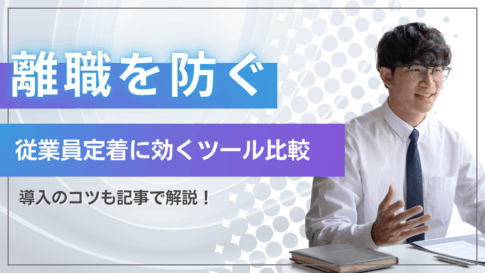
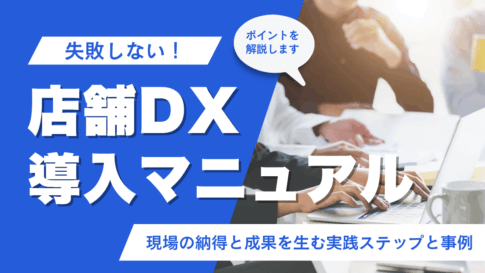
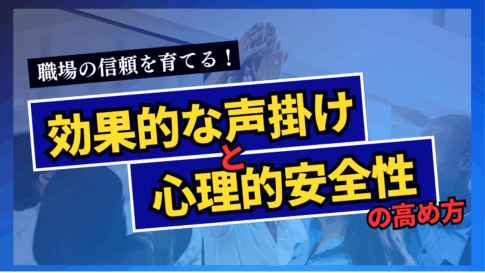


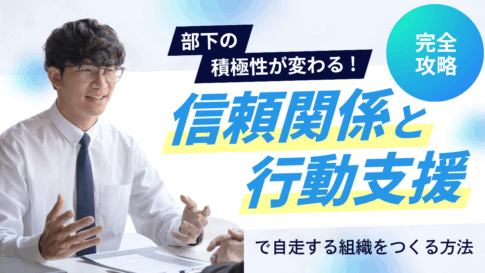




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。