
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。

最近、自分の残業代が妥当なのか、他の業界や地域がどのくらい残業してるのか気になります!

働く上で残業代の仕組みがどうなっているか気になりますよね!業界別・年代別・地域別に残業代と残業時間の実態を徹底比較し、どの職場が残業代をしっかり支払っているのか、どんな働き方が主流なのか見ていきましょう!
働き方の課題を改善するヒントとして、「みんなのマネージャ」の活用方法もご紹介します。自分に合った無理のない働き方を見つけるための参考に、ぜひ最後までご覧ください。
- 業界・年代・地域ごとの残業代や残業時間の”リアルな実態”がわかる
- 自分の残業代が”適正かどうか”を判断する視点が身につく
- 「みんなのマネージャ」を使って働き方を”見える化”するメリットがわかる
業界別の残業代平均と残業時間の傾向とは?

残業代ってどの業界でも一緒なのでしょうか?

残業代は業界によって支給額や残業時間に大きく異なります!業界別に平均残業代や残業時間のデータを紹介し、それぞれの特徴や働き方の違いを分析しましょう!
例えば、製造業や建設業のように現場での作業時間が固定されやすい業種では、比較的残業が発生しやすく、残業代も高くなる傾向があります。
一方、教育業界や福祉業界では、残業が慢性的であってもサービス残業となるケースが多く、実際に支払われる残業代は少ないという現実もあります。
自分の所属する業界がどの位置にあるのかを知ることで、今後のキャリア設計にも役立てることができます。
残業代が高い業界・低い業界ランキング
残業代の金額は単なる「時間の長さ」だけで決まるわけではありません。実は、どの業界に所属しているかによって、残業代の支給額には大きな差が生まれます。ここでは、残業代が高い業界・低い業界それぞれの背景にある「理由」に注目し、業界別にその違いを整理した表を紹介します。
【残業代が高い業界】
| 順位 | 高い業界 | 平均残業代(月額) | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電気・ガス業 | 約51,601円 | 賃金水準が全体的に高く、技術職やインフラ業務の特殊性から単価も高い |
| 2 | 情報通信業 | 約33,423円 | 専門職が多く、時間外労働が多い一方で、給与体系が成果報酬型で高い |
| 3 | 金融・保険業 | 約25,816円 | 資本力があり、基本給が高めな上、残業が多く割増賃金も支払われる |
参考:残業代はいくら?業界や年代、都道府県別の平均を弁護士が解説!
参考:残業代の平均はいくら?時間単価などを年代・業界別に詳しく比較
【残業代が低い業界】
| 順位 | 低い業界 | 平均残業代(月額) | 理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育 | 約6,721円 | サービス残業が多く、長時間労働でも適切に支払われない傾向がある |
| 2 | 介護・福祉業 | 約7,170円 | 賃金水準が業界全体で低く、残業代もみなし残業で抑えられるケースが多い |
| 3 | 小売・飲食業 | 約8,689円 | シフト制が多く、労働時間が曖昧になりやすく、正確に支払われにくい傾向 |
参考:業界・年代別の平均残業代はいくら?計算方法を弁護士が解説!
このように、業界ごとに残業代の金額に差が出る背景には、給与水準だけでなく、職場文化や制度設計、業務の性質といった複数の要素が関係しています。自分が今いる環境がどのような前提で成り立っているのかを知ることが重要です。
業界別の傾向から読み解く働き方の違い
残業時間や残業代のデータから見えてくるのは、業界ごとの働き方の文化です。たとえば、専門職が多く自己裁量で仕事を進めるIT業界では、成果重視の風土が強く、残業も自発的であるケースが目立ちます。
逆に、現場主導型の製造業や小売業では、シフトに合わせた業務遂行が求められ、労働時間の柔軟性が低い傾向があります。こうした文化や慣習の違いは、職場選びにも大きな影響を与える要素となります。
年代別で見る残業代と残業時間の特徴
働く年代によって、残業の内容や支給される残業代には大きな違いがあります。若手社員は経験やスキルを積む過程で残業が多くなりがちですが、30代以降は管理職になることで残業代が支払われなくなるケースも増えます。
この章では、20代から50代までの年代別に残業時間と残業代の実態を紹介し、年齢ごとの働き方の違いや課題に迫ります。
ライフステージの変化によって働き方の優先順位が変わり、残業の受け入れ度合いにも差が生まれます。
20代・30代・40代・50代、それぞれの残業実態
残業の状況は年齢やキャリアステージによって大きく変化します。スキルの習得期とされる20代から、管理職や家庭の責任が重なる40代・50代まで、それぞれの年代ごとに残業の背景や影響は異なります。
以下の表では、20代・30代・40代・50代の年代別に、残業実態の特徴を簡潔にまとめました。
| 年代 | 残業実態の特徴 |
|---|---|
| 20代 | 中堅社員への移行期。業務量が増える一方でスキルは未熟なため、残業が発生しやすい傾向 |
| 30代 | 責任ある立場になり、部下の指導など業務の幅が広がる。残業時間が長時間化しやすい。 |
| 40代 | プレイングマネージャーとして役割が増え、社内外の調整業務が多くなる。 |
| 50代 | 健康面や家庭の事情を重視する傾向が強まり、残業時間減少するケースが見られる |
このように組織としても各年代に応じた、柔軟なマネジメントが求められる時代になってきています。
年齢とともに働き方の優先順位や残業に対する考え方も変化していきます。自分の年代の傾向を知ることで、今後の働き方を見直すヒントが得られるかもしれません。
年代による働き方・収入差の背景とは
年代による残業代の差は、単純に時間の長さだけでなく、役職や賃金体系、ライフスタイルの変化が影響しています。
例えば、20代は月給が低く残業代が収入の大部分を占めることもありますが、30代以降は昇進により基本給が上がる一方、残業代は固定残業や管理職によってカットされる場合もあります。
このように、年代による収入構造の変化は、長期的なキャリアプランの構築に重要な要素となります。
ライフステージ別に見る残業のリアル
結婚や出産、介護などライフステージの節目で働き方に対する価値観が変わることがあります。20代はキャリア形成期として積極的に働く傾向がありますが、30代以降は家庭との両立が重要となり、残業を避ける意識が強まります。
また、働き方の多様性が広がる中、自分にとって無理のない働き方を見直すきっかけにもなります。
企業側もワークライフバランスに配慮した制度設計が求められるようになってきています。
都道府県別・地域別の残業代の平均と地域差

住んでいる都道府県や地域によっても残業代は変わってくるのでしょうか?

地域によって残業代や残業時間には顕著な差が存在します。都市部と地方では、業種の分布や企業規模の違いによって、働き方や給与体系が大きく異なります。
この記事では、東京・大阪などの大都市圏と地方都市の平均残業代や残業時間を比較しながら、地域による働き方の違いを可視化していきます。
UターンやIターンを検討している人にとって、地域別の残業実態を把握することは非常に重要です。
東京・大阪・地方都市の残業代比較
東京は大手企業の本社が集中しており、比較的高水準な残業代が支払われている傾向があります。一方、大阪も商業都市として活発な経済活動があり、東京に次ぐ水準となっています。
これに対して地方都市では、企業規模や業種が限られるため、残業代は平均して低めに設定されているケースが多いです。総務省や厚労省の統計からも、都市部と地方の残業代には月1万円以上の差があるというデータもあります。
地域差が生まれる理由とは?
残業代の地域差は、賃金水準の違い、生活コスト、業種構成など複数の要因が絡み合っています。例えば、東京では家賃や生活費が高いため、企業はそれを見越して給与全体を高めに設定する傾向があります。
また、都市部ではITや金融など高付加価値な業種が集中しており、結果として残業代も高くなります。一方で地方では製造業や流通業が中心で、時間給が低く抑えられる傾向があるのです。
残業代の比較から見えてくる課題と対策

なぜ残業代にこのような差があるのでしょうか?

その原因ですが、実は多くの企業が見落としがちな構造的な問題が、働く人の不満や離職リスクを引き起こしています。
ここでは、残業代に関する現場の実情から見えてくる代表的な課題を3つに整理してご紹介します。
- 残業代が適切に支払われていないケースが多い
- 役職によって残業代の扱いに格差がある
- 働き方の実態が”見えない”ことによる早期退職の増加
こうした課題を放置すると、従業員のモチベーション低下や人材流出につながる恐れがあります。だからこそ、企業も個人も残業の実態を正しく把握し、改善のためのアクションを取ることが求められます。
この章では、そうした働き方のギャップをどう是正し、より健全な労働環境を実現するかについて考察します。加えて、職場の現状を「見える化」する手段として「みんなのマネージャ」の活用も紹介します。
業界・年代・地域で変わる働き方への向き合い方
働き方は一律ではなく、個人の環境や職場文化によってさまざまです。しかし、どんな環境であっても重要なのは「自分に合った働き方を選ぶ」視点を持つことです。
特定の業界に所属しているからといって残業が当たり前である必要はなく、会社選びや部署移動、ライフプランの見直しによって改善する余地はあります。現状に不満がある場合は、まずその要因を把握し、環境を変える勇気を持つことが働き方改善への第一歩となります。
自分の残業代は適正?見直すポイント
毎月の残業時間に対して、どれだけの残業代が支払われているのかを定期的に見直すことが大切です。基本給や割増率、残業時間をもとにした計算式に照らし合わせることで、不払いの有無を確認できます。
また、固定残業代制度の場合には「何時間分の残業代が含まれているのか」を明確に把握することが重要です。少しでも不透明な点があれば、労基署や社内の相談窓口に問い合わせるなど、早めの行動がトラブルを防ぎます。
「みんなのマネージャ」で残業・働き方を可視化するメリット
働き方の可視化を支援するツールとして注目されているのが「みんなのマネージャ」です。このシステムは、従業員のエンゲージメントやストレス状態を定期的なアンケートで可視化し、マネージャーや経営層が問題を早期に把握することができます。
残業が多すぎる従業員や、モチベーションが下がっているスタッフをAIが自動で検出し、適切なフィードバックや支援を促す仕組みが整っています。
属人的なマネジメントを脱却し、組織全体で「無理のない働き方」を育む環境を構築することができます。
まとめ
この記事では、「残業代 平均」というキーワードを軸に、業界・年代・地域別の残業代や残業時間の実態を比較しながら、働き方の現状と課題について解説してきました。業界ごとの文化や給与体系、年齢によるライフステージの違い、地域による経済環境の差など、残業にまつわる事情は多岐にわたります。
また、自身の残業代が適正かを把握することも、キャリア設計や生活設計において重要な視点です。制度の理解不足や職場の慣習によって、知らず知らずのうちに不利益を被っている可能性もあります。
残業を“当たり前”とせず、より良い働き方を目指す第一歩として、本記事の情報を活用いただければ幸いです。

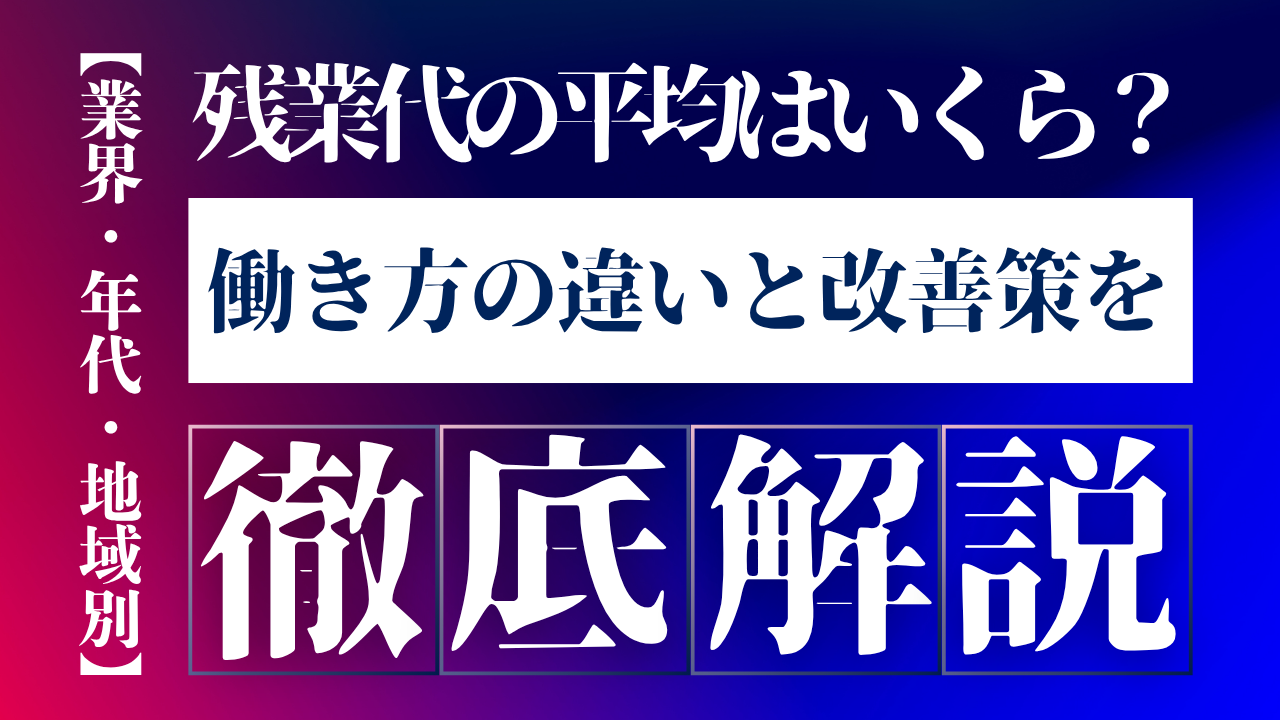
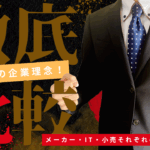
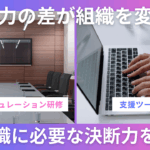
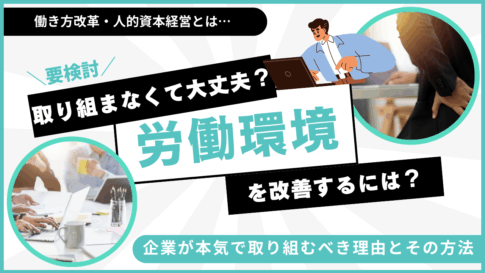
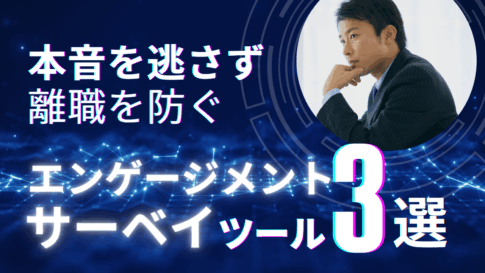
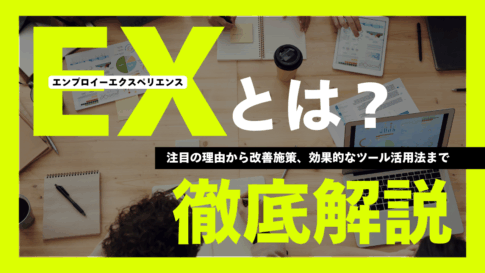
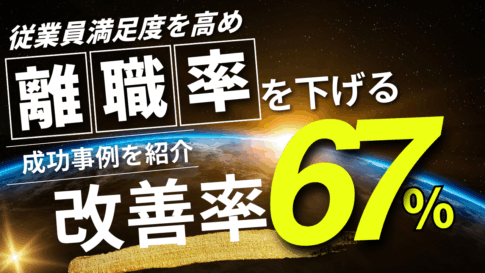
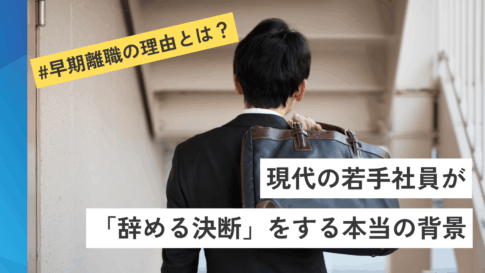
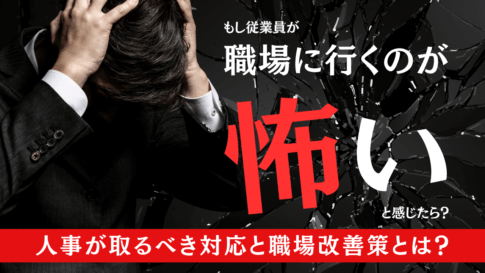
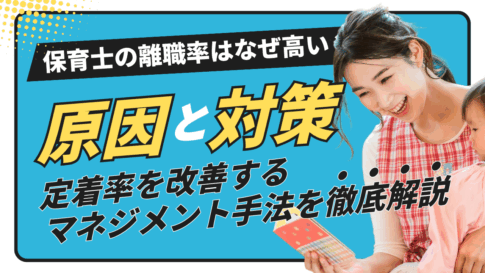
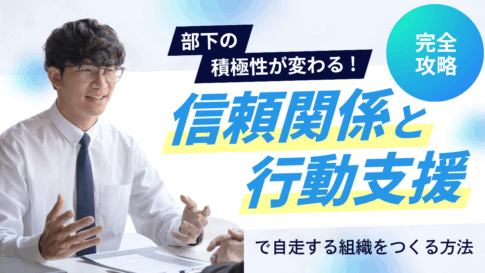



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。