
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
近年、「働き方改革」や「人的資本経営」という言葉が注目を集めています。その背景には、単に給料を上げる・福利厚生を整えるだけではなく、従業員が安心して能力を発揮できる労働環境の整備が強く求められるようになったことがあります。
では、そもそも「労働環境の改善」とは何を指すのでしょうか?そして、企業はどのようにして具体的な施策を進めていくべきなのでしょうか?
本記事では、労働環境を改善するための基礎知識から、実際に企業が取り組める方法までを徹底解説します。
- 労働環境の改善とは
- 労働環境を改善するためのポイント
- 実際に企業が取り組める方法
労働環境の改善とは

労働環境の改善とは具体的にどのようなことを指すのですか?

職場環境をよくする、とは漠然としたテーマに聞こえますが、実際には多くの具体的な要素が含まれています。
まずは「労働環境」という言葉が指す範囲と、改善が急務とされる社会背景を整理してみましょう。
労働環境の定義とは?
労働環境とは、従業員が日々働く場に関する物理的・制度的・人間関係的なあらゆる要素を指します。たとえば以下のような領域が該当します。
| 要素 | 内容の例 |
|---|---|
| 物理的環境 | オフィスの設備、空調、照明、清掃状況など |
| 就業制度・ルール | 勤務時間、休暇制度、リモートワーク可否など |
| コミュニケーション | 上司との関係、チーム内の連携、フィードバックのしやすさなど |
| メンタル・健康管理 | メンタルヘルス支援、産業医体制、長時間労働の防止 |
企業によって、どの部分が「改善すべき課題」になるかは異なりますが、いずれにせよ従業員がストレスなく能力を発揮できる環境づくりが共通の目的となります。
なぜ今、労働環境の改善が求められているのか
コロナ禍以降、テレワークやハイブリッド勤務が一気に浸透したことで、企業は「オフィスに来て働くことが当たり前」という価値観を見直す必要に迫られました。さらに、Z世代・ミレニアル世代などの若年層は、「報酬」だけでなく「働きがい」「人間関係の快適さ」「心理的安全性」を重視します。
また、厚生労働省の調査によれば、労働環境が原因でメンタル不調を訴える労働者の割合は年々増加傾向にあります。上記の背景から、労働環境の改善は今や「人材確保」や「離職率対策」に直結する重要課題となっているのです。
労働環境が悪いと起こる企業リスクとは
労働環境の悪化は、単なる「社員の不満」にとどまりません。企業にとって大きなコストとなる具体的なリスクも存在します。
| リスクの種類 | 内容 |
|---|---|
| 離職率の上昇 | 劣悪な環境は社員の早期離職・流出を招く |
| 生産性の低下 | 不安や不満が集中力を奪い、業務効率が下がる |
| 採用コストの増加 | 求職者が企業の労働環境を調査する時代。悪評は致命的 |
| 法的リスク | 長時間労働やハラスメント放置による訴訟・是正勧告等 |
特にSNSなどの情報発信ツールが発達した現在では、社内の声が外部へ伝わるスピードも速くなっています。企業としてのブランド価値を守るためにも、働く人にとっての「安心できる場づくり」は無視できないテーマです。
労働環境を改善するためのポイント

労働環境を改善するためのポイントが知りたいです。

労働環境を改善するには、単に「オフィスを快適にする」などのハード面だけでなく、制度や人間関係のソフト面まで含めた総合的なアプローチが求められます。
ここでは、労働環境を改善するためのポイントを解説します。
- 物理的な作業環境の改善
- 労働時間と制度設計の見直し
- コミュニケーション環境の整備
- 評価制度・人材育成の最適化
- メンタル・健康支援体制の構築
物理的な作業環境の改善
働く場所が快適でないと、どれだけ制度が整っていても生産性は上がりません。空調・照明・椅子や机の ergonomics(人間工学)設計など、長時間座っていても疲れにくい環境を意識することが基本です。
また、近年は「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」と呼ばれる、業務に応じた座席選択型のオフィス設計も注目されています。
労働時間と制度設計の見直し
長時間労働の常態化や、有休の取りにくさは、従業員の不満の大きな要因です。フレックス制度やリモートワークの導入、時間単位有休の導入など、柔軟な勤務体系を整備することが重要です。
単に制度を作るだけでなく、「取りやすい空気感」「上司の理解」などの文化醸成が伴ってこそ、制度が実効力を持ちます。
コミュニケーション環境の整備
オンライン会議やチャットツールが普及したことで、業務連絡は円滑になった一方、「雑談」や「フィードバック」の機会が減っていると感じる人も少なくありません。特にリモートワーク主体の企業では、社員間の信頼関係や心理的安全性の低下が問題となっています。
コミュニケーション環境の改善には、以下のような施策が有効です。
| 施策内容 | 目的・効果 |
|---|---|
| 1on1ミーティングの定期実施 | 上司と部下が定期的に対話し、信頼関係を築く |
| ピアボーナス制度の導入 | 社員同士が感謝や称賛を送り合い、ポジティブな関係を促進 |
| オンライン雑談タイムの設置 | 雑談を通じて部署を超えた関係性をつくる |
「ピアボーナス」については、具体的なツール導入によって形にすることもできるため、後ほどご紹介します。
評価制度・人材育成の最適化
「何をどう頑張っても評価されない」「上司の主観だけで査定される」——このような不満があると、社員のモチベーションは簡単に下がってしまいます。透明性があり、納得感のある評価制度こそ、組織の信頼を育む土台です。
そのためには、以下の要素を評価制度に取り入れることが効果的です。
| 評価の要素 | 内容例 |
|---|---|
| 成果評価 | 数値目標の達成度やプロジェクト貢献度など |
| 行動評価 | 協調性やリーダーシップ、問題解決力などの非数値的行動 |
| フィードバック制度 | 上司だけでなく同僚や他部署からの360度評価を取り入れる |
このように多面的な評価ができると、評価への不信感を減らし、成長の方向性も明確化されます。
メンタル・健康支援体制の構築
ストレスや不安を抱えながら仕事をしていると、集中力や創造性が著しく低下します。特に、メンタル不調は早期に気づかないと、長期的な離脱や離職にもつながります。
企業としては、以下のようなケア体制を整えることが大切です。
| 項目 | 実施例 |
|---|---|
| ストレスチェック制度 | 年1回以上の全社的なストレスチェックと結果分析の共有 |
| 相談窓口の設置 | 社外カウンセラーや産業医との面談制度を設ける |
| 福利厚生による支援制度 | リフレッシュ休暇、ウェルネス支援費、メンタルケア研修など |
健康経営という考え方が広まる中、単なる義務的対応ではなく、「従業員が本当に必要としている支援」への投資が今後ますます重視されるでしょう。
企業の労働環境の改善を後押しするツール
ここまで述べたように、労働環境の改善はあらゆる側面からのアプローチが求められます。とはいえ、忙しいマネージャーが制度運用や関係構築を感覚や経験だけに頼っている状態では、限界があります。
そこで、注目されているのが「支援型マネジメントツール」の導入です。
マネジメントの属人化を防ぐ「支援型ツール」の必要性
多くの企業で見られる課題の一つが、「マネージャーの力量に頼った属人的マネジメント」です。部下との関係構築や1on1の質、評価の公平性などが個人の能力や経験に依存している状態では、労働環境の質も安定しません。
その課題を補完するのが、「みんなのマネージャ」のような、管理職支援に特化したツールです。
「みんなのマネージャ」で変わる現場マネジメント
スカイストーン株式会社が提供する「みんなのマネージャ」は、日々のマネジメントを可視化・サポートし、現場の指導・支援の質を底上げするためのツールです。具体的には以下のような機能があります。
| 機能 | 効果 |
|---|---|
| 1on1面談の記録と振り返り | 継続的な対話と信頼関係構築をサポート |
| チームメンバーのコンディション把握 | 従業員の状態を見える化し、早期フォローが可能に |
| 行動ログやフィードバック機能 | 公平な評価や育成に役立つ、行動実績の蓄積と振り返りが可能 |
ツールによってマネジメントの質が平準化されれば、組織全体としての労働環境も安定します。
導入企業での改善事例
実際に「みんなのマネージャ」を導入した企業では、以下のような効果が報告されています。
- 部下からの「上司との関係に安心感がある」との回答が7割以上に
- 離職率が導入前に比べて約15%減少1on1の実施率が2倍以上に増加
管理職の属人化したマネジメントから仕組みに基づく支援型マネジメントへとシフトできたことが成功のカギとなっています。
労働環境の改善は管理職支援から始まる
労働環境の改善は、ただの福利厚生の強化や働き方改革の一環ではありません。それは、「人が安心して働ける土壌を企業が責任を持って整えること」に他なりません。
とくに、現場の空気感や評価制度、マネジメントの質は、従業員の離職や生産性に直結する要素です。だからこそ、マネージャーが適切に支援される環境整備が急務なのです。

スカイストーン株式会社が開発した「みんなのマネージャ」は、マネジメントの属人化を防ぎ、誰でも育てられる組織づくりを支援するツールです。人が辞めない組織、成長し続けるチームを目指すなら、まずはマネージャーの働き方から見直してみましょう。

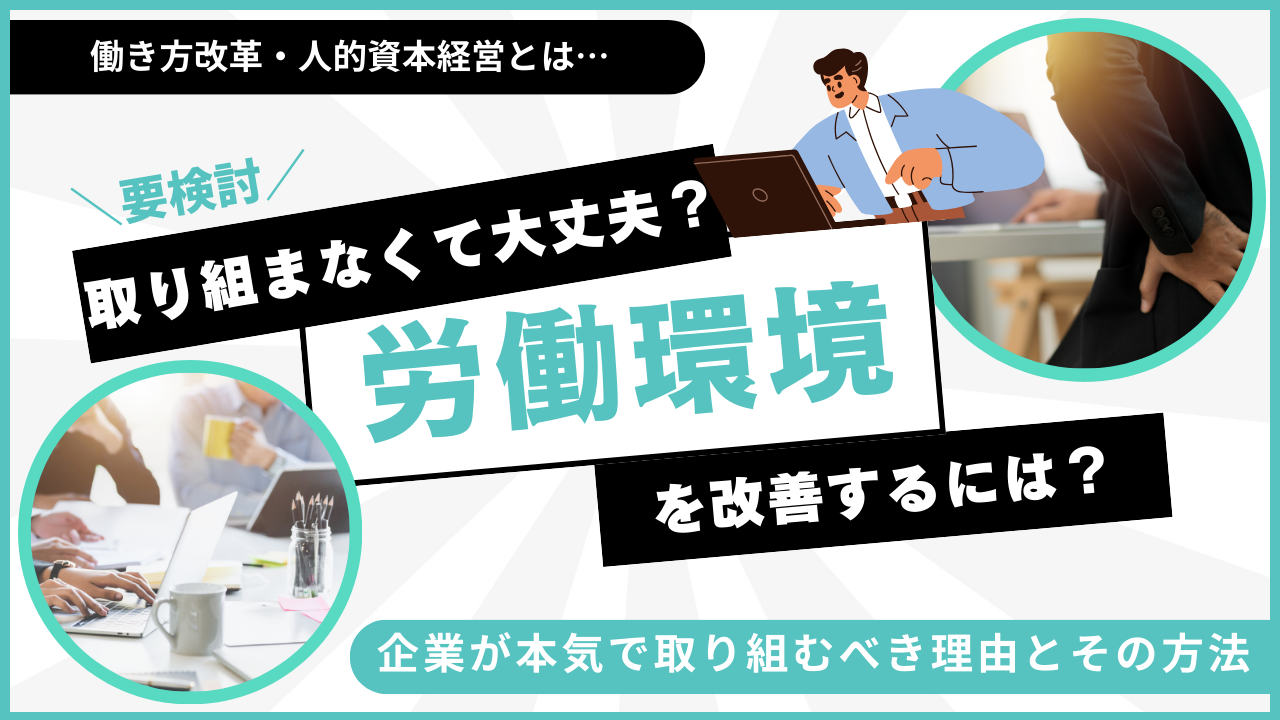

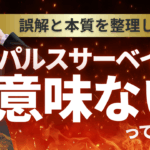
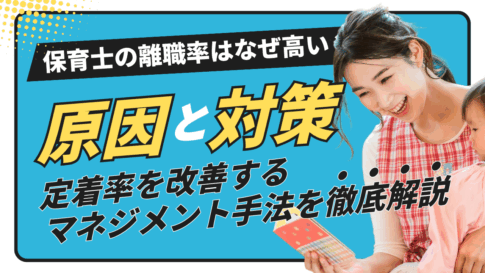
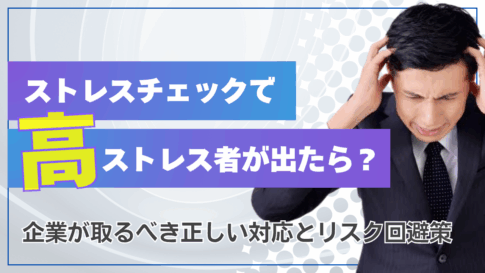
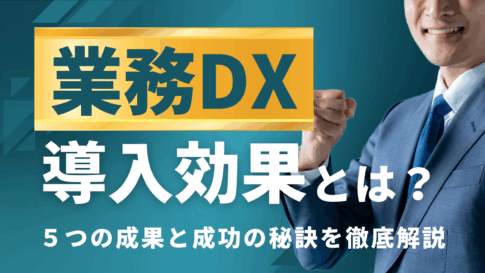
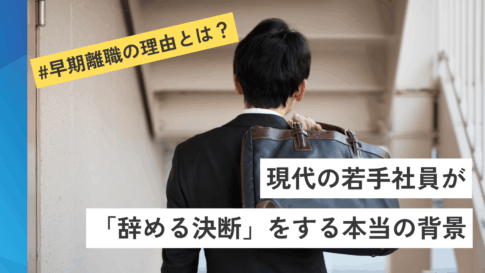
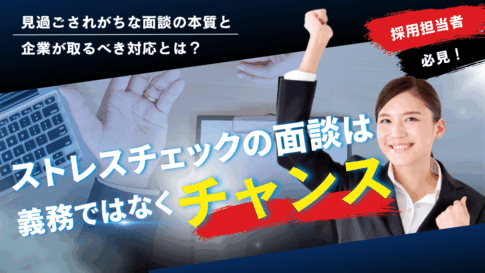
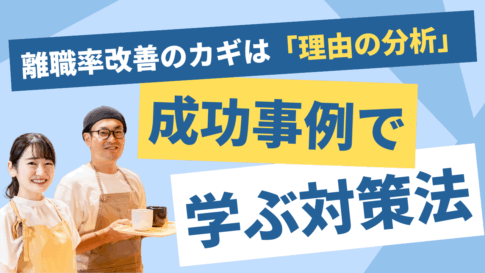
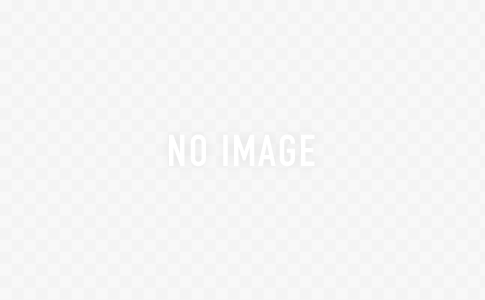




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。