
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「職場でのストレスが気になるけれど、具体的に何をすればいいかわからない」
そんな悩みを抱える企業や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
近年、メンタルヘルス不調による休職や離職が社会問題となる中、従業員のストレス状況を把握し、適切な対策を講じることは企業の重要な責任の一つです。
そこで注目されているのが、職業性ストレス簡易調査票(ストレスチェック制度)です。
法律で義務化された背景や、簡単に取り組める仕組みが整っていることから、従業員のメンタルヘルスケアの第一歩として多くの現場で導入されています。
本記事では、職業性ストレス簡易調査票の概要やメリット、実施の流れ、結果の活用方法まで、専門的な視点でわかりやすく解説します。
- 労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度の概要や目的
- 職業性ストレス簡易調査票のメリットや注意点について
- 職業性ストレス簡易調査票を実施する重要性について
職業性ストレス簡易調査票とは

職業性ストレス簡易調査票とは何ですか?初めて聞きました。

働く人のメンタルヘルス不調を未然に防ぐため、企業に導入が義務付けられているのが「ストレスチェック制度」です。
その中で広く使われているのが、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票」です。
ここでは、職業性ストレス簡易調査票の基本的な定義や目的について詳しく解説していきます。
労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」
職業性ストレス簡易調査票は、労働安全衛生法に基づいて2015年12月から義務化された「ストレスチェック制度」で用いられる調査票です。

ストレスチェック制度は、従業員が50人以上いる事業所に対して、年に1回以上、全従業員のストレス状況を確認することを義務付ける制度です。
目的は、従業員の心理的負担の程度を把握し、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境の改善につなげることにあります。
ストレスが高い従業員に対しては、医師の面接指導を実施するなど、早期の対応が推奨されています。
制度上、この簡易調査票の活用により、従業員が自身のストレス状態を客観的に知る機会を得られる点が重要です。
- 労働安全衛生法に基づいて2015年12月から義務化された
- 従業員50名以上の事務所は義務付けられている
- 従業員のメンタルヘルス不調の改善・未然防止・が目的
- ストレスが高い従業員へは、医師の面談指導を実施すること
職業性ストレス簡易調査票の定義と目的
職業性ストレス簡易調査票は、国が推奨する57項目の標準質問票です。
厚生労働省が監修し、心理学的に信頼性・妥当性のある設計となっています。
- 仕事の量や質
- 対人関係
- 身体的症状
- 心理的症状
この調査票の目的は単に数値化するだけでなく、結果を元に職場全体の課題を把握し、環境改善や個別対応のきっかけにすることです。

個人のメンタルヘルスの維持と、組織全体の健康経営を両立させるための重要なツールといえるでしょう。
職業性ストレス簡易調査票の構成と特徴
職業性ストレス簡易調査票は、従業員のストレス状態を正しく把握するために設計された質問票です。

大きな特徴は、「誰でも短時間で回答しやすく、かつ科学的に信頼性が高い」という点にあります。
ここでは、ストレスチェック制度で広く採用されているこの調査票が、どのような構成になっていて、どのような工夫がされているのかを見ていきましょう。
全57問の質問項目
職業性ストレス簡易調査票は、全部で57問の質問から構成されています。

質問は「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」という3つのカテゴリーに分かれており、従業員が感じるストレスの全体像を網羅的に把握できるよう設計されています。
- 業務量の多さに関する質問
- 仕事の裁量権に関する質問
- 職場の人間関係に関する質問
- 身体的な不調や気分の落ち込みに関する質問
- 上司や同僚、家族からのサポートの有無に関する質問
これにより、単に「ストレスがあるかどうか」だけでなく、その背景にある原因や周囲の環境まで把握できるのが特徴です。
回答のしやすさと匿名性
職業性ストレス簡易調査票は、誰でも短時間で回答できる設問形式になっています。

すべての質問は5段階程度の選択式で、専門知識がなくてもスムーズに答えられるよう配慮されています。回答時間はおおむね10分程度です。
さらに、ストレスチェック制度の目的は従業員のメンタルヘルスを守ることにあり、回答は匿名性やプライバシーが守られるよう取り扱われます。
回答内容が人事評価などに不利益に利用されることは法律で禁止されているため、安心して本音を答えられる仕組みが整っています。
こうした「負担の少なさ」と「安心感」が、継続的な実施において重要なポイントです。
職業性ストレス簡易調査票を活用するメリット
職業性ストレス簡易調査票は、単に法律で義務付けられたから実施するだけのものではありません。
企業にとっても従業員にとっても、多くのメリットがあります。
ここでは主な3つのメリットについて解説します。
- 従業員のメンタルヘルスの維持・向上
- 職場環境の改善につながる
- 法律遵守と企業価値の向上
従業員のメンタルヘルスの維持・向上

職業性ストレス簡易調査票を活用することで、従業員一人ひとりのストレス状態やメンタルヘルスの傾向を早期に把握できます。

どうしてそんな早期にメンタルヘルスの傾向を把握できるんですか?

メンタルヘルス不調は、初期の段階では本人が自覚していなかったり、声に出しにくかったりするものだからです。
しかし、調査票の結果からストレスが高い状態や危険信号が見えることで、企業側が早めにケアのアクションを取れるのが大きなメリットです。
実際、定期的にストレスチェックを実施しフォロー体制を整えることで、休職や離職を未然に防ぎ、従業員が安心して働き続けられる環境が整います。
メンタルヘルスの維持・向上は、長期的に企業の生産性向上にも寄与します。
職場環境の改善につながる
職業性ストレス簡易調査票は、従業員個人の状態を見るだけでなく、職場全体の課題や傾向を把握するためのツールとしても有効です。
- 上司のサポートが不足していること
- 業務量が過剰になっていること
- 職場の人間関係に問題があること など
その結果をもとに改善計画を立て、職場環境の見直しや制度改革につなげることで、従業員満足度の向上、エンゲージメント強化が期待できます。
働きやすい環境をつくることで、採用力や定着率の向上にも好影響があります。
法律遵守と企業価値の向上
職業性ストレス簡易調査票は、労働安全衛生法で義務付けられたストレスチェック制度の標準的な調査票です。

従業員数が50人以上の事業場では、年1回の実施が義務となっているので、法律を遵守するためにも欠かせませんね。
この義務を適切に履行している企業は、労務管理がしっかりしているという社会的な評価を得ることができます。
さらに、メンタルヘルス対策に積極的な企業は、健康経営やホワイト企業認定などの評価基準にも合致し、企業価値やブランドイメージの向上にもつながります。
法律を守りながら従業員の健康と働きやすさを支えることが、結果的に企業の持続的な成長につながるのです。
職業性ストレス簡易調査票の実施の流れ
職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスチェックは、単に「調査票を配って回収するだけ」ではなく、法律に沿った手順で適切に実施する必要があります。
職業性ストレス簡易調査票の実施の流れは、主に以下4つのステップです。
- 実施計画の策定
- 調査票の配布と回答の回収
- 集計・分析と結果の通知
- 職場環境改善とフォローアップ
これから職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスチェックを実施する企業は、参考にしてみてください。
職業性ストレス簡易調査票の疑問と注意点
職業性ストレス簡易調査票を実施するにあたり、従業員からよく寄せられる疑問や注意すべきポイントがあります。
不安や誤解を解消するために、よくある質問に沿って解説します。
- 回答しなかった場合のペナルティはあるのか
- 結果を人事評価に利用されないのか
- 小規模事業所でもやるべきなのか
- 集団分析の際のプライバシーは守られるのか
回答しなかった場合のペナルティはあるのか

ストレスチェックは法律で「実施」が義務付けられていますが、「受検」はあくまで従業員の任意です。
そのため、回答しなかったからといって法的なペナルティや処分を受けることはありません。
ただ、従業員自身の健康状態を知る大切な機会なので、積極的な受検が推奨されます。
結果を人事評価に利用されないのか
調査票の結果は、本人の同意がない限り事業者や上司に開示されることはありません。

結果は医療職や産業保健スタッフのみに知らされ、法律で「人事評価等に利用してはならない」とされています。
安心して本音で回答し、自身の健康管理や職場改善に役立てましょう。
小規模事業所でもやるべきなのか

ストレスチェック制度は常時50人以上の労働者がいる事業所に義務付けられていますが、50人未満の事業所でも実施は可能です。
義務ではないものの、メンタルヘルス不調の予防や離職防止の観点から、小規模事業所でも導入するメリットは大きいです。
コストや実施方法も簡略化できるため、検討してみると良いでしょう。
集団分析の際のプライバシーは守られるのか
ストレスチェックでは、個人結果とは別に部署単位などで集団分析が行われることがあります。
この際も、匿名化された集計データのみが使用され、個人が特定される形では共有されません。
分析結果は職場環境改善に活用されるものであり、従業員のプライバシーは法律でしっかり守られていますので安心です。
職場のストレス対策の重要性

現代の職場環境において、メンタルヘルスの問題は企業の業績や従業員の生産性に大きな影響を与える重要な課題です。

そんなに大きな問題があるんですね。

その通りです!ストレスを放置すると、社員のモチベーション低下や離職率の増加、さらには業務ミスや休職者の増加といった問題を引き起こします。
だからこそ、企業は積極的にストレス対策を講じ、健康的で働きやすい職場環境を整備することが求められています。
ここでは、職場のストレス対策の重要性を解説します。
心の健康が業績や生産性に与える影響
従業員の心の健康状態は、仕事の質や効率に直結します。
心の健康と心のストレスで、それぞれ職場と従業員に与える影響は以下の通りです。
| 職場・従業員の状態 | 起きること |
|---|---|
| メンタルヘルスが良好 | 集中力の低下判断力の鈍化業務ミスの増加仕事への意欲が減退 など |
| 高ストレスが継続 | コミュニケーションの活発化チームワークの向上業績アップや売上アップ情報共有の円滑化 など |
こうした点から、心の健康は企業の成長を支える重要な要素と言えます。
企業文化としてのメンタルヘルスケア
持続可能な組織運営のためには、メンタルヘルスケアを企業文化として根付かせることが必要です。
経営層の理解とリーダーシップが重要であり、職場のストレスを早期に察知して対応できる体制づくりや、従業員が相談しやすい環境づくりが求められます。

また、ストレスチェック制度の導入や定期的な研修を通じて、メンタルヘルスの重要性を全社員が共有することも大切です。
こうした文化が浸透することで、従業員の健康維持だけでなく、企業の信頼性向上にもつながります。
まとめ
職場のストレス対策は、従業員の健康維持だけでなく、企業の生産性や業績向上にも大きく影響します。

効果的なメンタルヘルスケアを実現するには、ストレスチェックの実施だけでなく、結果を活かした職場環境の改善やフォロー体制の整備が欠かせません。
そこで、「みんなのマネージャ」のようなサーベイツールを活用すると、従業員のストレス状況をリアルタイムで把握しやすくなり、早期対応が可能になります。
スタッフの声を見える化し、管理者とチームのコミュニケーションを促進することで、より良い職場環境づくりに役立ちます。
ストレス対策を強化し、健康で働きやすい職場を目指す企業は、ぜひ「みんなのマネージャ」の導入を検討してみてください。


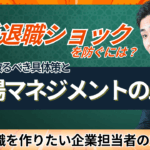
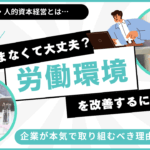


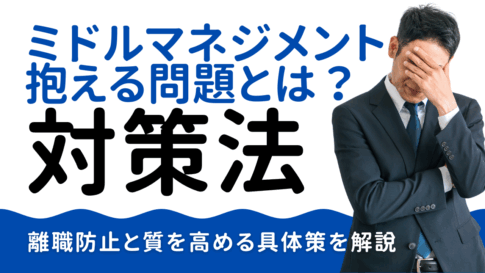
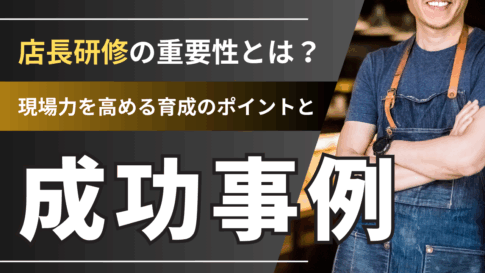

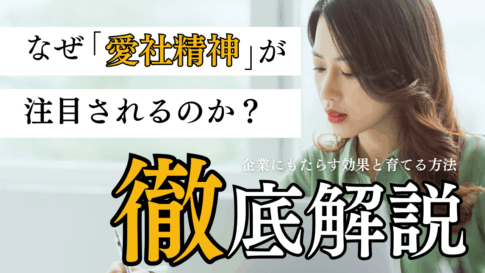
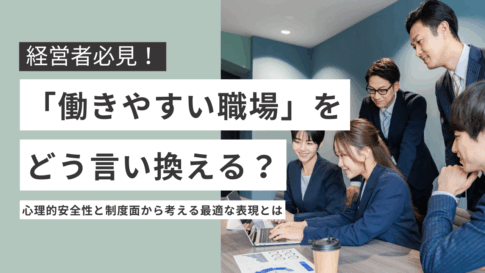
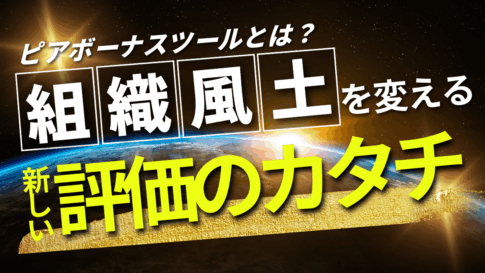



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。