
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
若手社員の突然の退職は、企業にとって大きな損失です。育成にかけたコストが無駄になるだけでなく、現場の混乱や士気の低下にもつながります。
特に近年は、入社後のリアリティショックや人間関係の悩みから、入社1年以内で離職する若手が増えています。
本記事では、若手が辞めてしまう背景を深掘りし、企業が実践できる具体的な離職防止策をご紹介します。さらに、現場の負担を軽減しつつ定着率を向上できる最新のマネジメントツール「みんなのマネージャ」についても詳しく解説します。
若手の離職を防ぎ、強い組織を作りたい企業担当者の方はぜひ参考にしてください。
- 若手が早期退職する
- 背景若手の退職を防ぐ企業の対策
- 若手の退職を減らすためのおすすめのツール
若手社員の退職が企業にもたらす深刻なショックとは
若手社員の退職は、企業にとって大きなダメージをもたらします。特に育成に力を入れていた人材が突然辞めてしまうと、残ったメンバーの士気が低下し、業務のパフォーマンスにも悪影響が出ます。
さらに、企業が投資した採用・教育コストが無駄になるだけでなく、採用活動のやり直しによって追加コストが発生します。若手の退職が頻発すると「離職率の高い会社」というネガティブなレッテルが市場で付いてしまい、次の採用にも悪影響を与えます。
若手の離職は単なる人数減ではなく、企業全体の成長停滞やイメージダウンにも直結します。特に日本では少子化が進む中、若手の確保と定着は企業経営の最重要課題です。この問題を放置すると、長期的な競争力低下も避けられません。
予期しない若手の退職が引き起こす組織リスク
若手社員の突然の退職は、現場に深刻な混乱をもたらします。急な欠員補充のため、周囲のメンバーは急ピッチで業務の引き継ぎを行う必要があり、結果としてチーム全体のパフォーマンスが落ちます。
また、予定していたプロジェクトが頓挫したり、顧客対応に支障が出るなど、ビジネス上のリスクも顕在化します。特に小規模組織や現場型の職場では、一人の退職でも業務が立ち行かなくなることもあります。
退職者の後任が決まるまでの間、既存メンバーの負担が増え、残された人も疲弊し、連鎖的な離職を引き起こすリスクが高まります。このような悪循環を避けるためには、若手の早期離職の兆候を察知し、事前に手を打つことが重要です。

早期退職に先手を打つことも大切です。
採用・育成コストが水の泡になる理由
企業は若手社員の採用と育成に多くのコストと時間を投資しています。新卒採用であれば、以下のような様々なステップでコストが発生します。
- 求人広告
- 説明会
- 人事面接
- 内定フォロー
- 入社研修
さまざまなステップでコストが発生し、中途採用でも採用費用は決して安くありません。しかし、せっかく採用した若手が早期退職すると、これらの投資はすべて無駄になってしまいます。
加えて、現場でのOJTやスキル育成の時間も失われ、生産性の向上という本来の目的が達成できません。採用費や教育費だけでなく、人事や現場のリソースまで浪費されるため、組織全体の非効率を生み出します。

求人には以外にもコストがかかるものです。
若手が定着せず辞めることは、単なる一人分の損失ではなく、企業経営にとって深刻な資源の損失です。
若手社員が早期退職する背景とリアリティショックとは
若手社員が短期間で退職してしまう背景には、「リアリティショック」と呼ばれるギャップがあります。入社前には希望と期待を抱いて入ってきた若手が、現場の現実を知ったとたんに大きな落胆を感じ、早期離職してしまうのです。
このショックは、以下のように多岐にわたります。
- 仕事内容のミスマッチ
- 上司や同僚との人間関係
- 労働時間
など多岐にわたります。特に成長意欲の高い若手ほど、「このままで良いのだろうか」と不安を抱えやすく、すぐに次のキャリアを考え始めます。

若手は次に行くところも多いですので、退職のリスクが高まります。
この現象は特に入社1年以内に多く見られ、企業側の早期フォローが不可欠です。若手退職を防ぐには、まずこのリアリティショックがどこで起きるのかを理解し、環境改善を行うことが重要です。
入社後ギャップ:思い描いていた業務と現実のズレ
入社前の説明と実際の仕事内容が異なると、若手社員は強い違和感を覚えます。
- 希望部署に配属されなかった
- やりたかった業務ができない
- 単純作業ばかり
という不満が蓄積され、離職の引き金になります。また、「成長できる職場」と期待していたのに、日々の業務が単調で成長実感が得られない場合も、早期離職の原因となります。
この入社後ギャップは、企業側の採用時説明不足や、配属ミスマッチが主な要因です。

入社後のギャップをいかに減らせるかが大切ですね!
早期のフォローアップ面談や、業務内容の可視化、キャリア形成の相談機会を設けることが、ギャップ解消につながります。
成長実感が得られず「やりがい」を失う若手の心理
現代の若手社員は、「やりがい」や「成長実感」を重視する傾向が強くなっています。しかし、入社後に仕事の成果が見えづらかったり、評価が曖昧であったりすると、「自分は成長しているのだろうか?」という不安が募ります。
この不安は、日々の業務がルーティン化している職場や、フィードバック文化が不足している環境で特に顕著です。特に若手はキャリアの初期段階であるため、成長できていないと感じると、すぐに次の成長機会を求めて転職を検討します。
この心理を軽視すると、優秀な若手が早期に流出するリスクが高まります。以下のような機会を提供することで、若手の成長実感とエンゲージメントを高めることが可能です。
- 定期的な目標設定
- フィードバック
- スキルアップの機会
周囲との人間関係・孤独感も大きな退職要因に
若手社員の離職理由として意外と多いのが、周囲との人間関係です。特に以下のようなことは、特に入社間もない若手にとって大きなストレスになります。
- 上司や同僚とのコミュニケーション不足
- 相談しづらい雰囲気
- 孤立感
リモートワークの普及も相まって、以前よりも孤独感を感じやすい職場環境が増えています。
また、現場によっては年齢層が高く、若手が少数派になってしまい、気軽に話せる相手がいないというケースもあります。このような環境では些細な悩みも抱え込みやすくなり、離職につながります。人間関係の悩みは、業務改善だけでは解決しません。

孤独感は早期退職につながりやすいです。

若手は入社したばかりということもあり、余計に孤独感があるのはつらいです。
定期的な1on1面談や職場内のコミュニケーション施策を通じて、心理的安全性を確保することが若手定着のカギとなります。
若手の退職を防ぐ効果的な企業施策とは
若手社員の退職を防ぐためには、組織としての積極的な施策が欠かせません。特に重要なのは、日々のコミュニケーションとリアルタイムな心理状態の把握です。
若手は悩みや不安を口に出すことが少なく、我慢の限界を迎えてから突然退職を切り出すケースが少なくありません。そのため、定期的な1on1面談や簡単なパルスサーベイを活用し、日々の小さな変化を拾い上げる仕組みが必要です。
また、配属段階でのミスマッチを防ぐ配慮や、キャリアパスの提示による成長支援も重要です。組織として「あなたの成長をサポートしている」というメッセージを伝え続けることで、若手のエンゲージメントは飛躍的に向上します。離職リスクは事後対応ではなく、事前対応で最小化することが効果的です。
日々の1on1面談で心のモヤモヤを早期にキャッチ
若手社員の早期離職を防ぐためには、日々の1on1面談が非常に効果的です。1on1面談は単なる業務報告ではなく、部下の悩みやモチベーションの変化を察知する重要なコミュニケーションの場です。

面談では、若手の不満を聞き出し、改善していきましょう。
特に若手は職場での不安や不満を周囲に打ち明けづらい傾向があり、日常的な会話の中で本音を引き出すことがポイントになります。週1回の短い面談でも「最近どう?」「困っていることはない?」というカジュアルな問いかけが大きな効果を発揮します。
マネージャ側も「評価」ではなく「対話」を重視し、聞き役に徹することで、若手は安心して本音を話すようになります。こうした日々の積み重ねが早期離職の予防につながり、エンゲージメント向上にも効果があります。
パルスサーベイの活用で離職リスクを見える化
若手の離職兆候を早期に察知するには、パルスサーベイの活用が有効です。パルスサーベイとは、数問の簡単なアンケートを週1回程度の頻度で実施し、従業員のコンディションやモチベーションの変化をリアルタイムで把握する仕組みです。
特に若手社員は言葉で不満を表現しづらく、気づいた時には手遅れというケースが多いため、定期的な数値化が重要です。
離職リスクが高いとされると以下のような項目を定期的にチェックし、問題があれば即座にフォローアップできる環境を整えます。
- ストレス
- 孤独感
- 成長実感の欠如
問題があれば即座にフォローアップできる環境を整えます。サーベイ結果はチーム単位でも可視化できるため、マネジメント層も現場の課題を把握しやすくなります。小さな変化に素早く対応することが、若手の定着率向上につながります。
配属・オンボーディングでミスマッチを防ぐには
若手の早期離職を防ぐためには、配属とオンボーディングの段階から工夫が必要です。まず、配属時のミスマッチを避けるためには、本人の希望や適性を正確に把握することが欠かせません。
一方的な企業都合での配属は、早期離職の大きな原因となります。また、配属後のオンボーディングも重要です。入社直後のフォローアップが手薄だと、若手は孤独感や不安感を募らせやすくなります。
そこで、初期の数ヶ月間は以下のような機能を活用し、「あなたの成長を支援している」というメッセージを繰り返し伝えることが効果的です。
- 定期的な面談
- サーベイ
- メンター制度
業務の目的や成長ロードマップを明示することも、早期の「やりがい」形成につながります。配属・初期育成は離職防止の重要な第一歩です。
成長実感を高めるキャリア支援とフィードバック
若手社員の定着には、「成長できている実感」を持たせることが極めて重要です。日々の業務の中で成長実感を得ることができれば、多少の不満や壁があっても離職にはつながりにくくなります。
効果的な取り組みの一つが、定期的なキャリア面談やスキルの可視化です。半年や四半期ごとに現時点のスキルや実績を確認し、次のステップを明示すると、若手は「自分は評価されている」「成長できている」と感じやすくなります。
また、日常のフィードバックも大切です。ポジティブな声かけや具体的なフィードバックを積み重ねることで、若手のモチベーションは向上します。特に目標に対する達成度や成長ポイントを定量化して伝えることが、成長実感を高め、長期定着につながります。

ポジティブな声掛けは大切です!
現場の負担を減らし、離職防止を実現する「みんなのマネージャ」とは
若手の離職防止には、現場マネジメントの質を高めることが不可欠ですが、現場のマネージャーに過度な負担をかけると逆効果になることもあります。そこで注目されているのが、現場のマネジメント負荷を減らしつつ、エンゲージメント向上を実現できる「みんなのマネージャ」です。
| みんなのマネージャの機能 | 日々のパルスサーベイによるリアルタイムな従業員心理の把握と、「AIによる的確なフィードバック支援」 |
心理的安全性を高め、コミュニケーションの質を改善し、若手の不満や悩みを早期に可視化できます。結果としてマネジメントの属人化を防ぎつつ、組織全体の離職率低下を実現します。負担軽減と若手定着を両立できる仕組みとして、多くの企業で導入が進んでいます。
サーベイとAIフィードバックで若手の不満を早期把握
「みんなのマネージャ」では、従業員一人ひとりの心理状態を可視化できる週次サーベイが特徴です。若手は悩みを言語化するのが苦手な場合も多く、サーベイを通じて匿名性が確保された形で本音を拾い上げられます。
さらに、回答結果はAIが自動的に分析し、離職リスクが高い従業員をピックアップ。マネージャは個別対応が必要なメンバーをすぐに把握できます。
加えて、AIが最適なフィードバック例や声かけの内容まで提案してくれるため、経験の浅いマネージャでも効果的なフォローが可能です。この仕組みによって、見落としがちな若手の小さな不満や兆候にも早期対応でき、結果として離職率低下に直結します。

みんなのマネージャは、離職率を下げるためにも使える有能なツールです。

離職率を下げたい企業の人はぜひ使ってみてください!
フィードバックの質が揃い、心理的安全性も向上
現場のマネジメントにおいて、課題となりやすいのが「フィードバックの質のバラつき」です。特に経験が浅いマネージャでは、若手とのコミュニケーションが自己流になりがちで、逆に若手の不満を増幅させてしまうこともあります。
「みんなのマネージャ」では、AIがフィードバック内容を提案するため、マネージャーごとの対応の差を無くすことが可能です。さらに、1on1面談の進め方や声かけの具体例も提示されるため、誰でも一定水準の質で若手に寄り添うことができます。
この結果、若手が安心して本音を話せる「心理的安全性」が高まり、不満の蓄積が未然に防がれます。職場に安心感が生まれることで、離職防止はもちろん、職場全体の雰囲気も大きく改善されます。
店舗・現場のマネジメント負担軽減の仕組み
「みんなのマネージャ」が選ばれる理由の一つが、現場のマネジメント負担を軽減できる点です。特に多忙な店舗マネージャーや現場責任者は、日々の業務だけでも手一杯になりがちで、メンバーケアまで手が回らないという悩みを抱えています。
本サービスでは以下のような機能を一元的にカバー。
- サーベイ回答の分析
- フォローが必要なメンバーのフラグ立て
- AIによるフィードバック、行動提案
マネージャーはダッシュボードを見るだけで、誰にどのような対応をすればいいのかが明確になります。結果として、マネジメントの工数は削減され、かつ対応の質は向上。
業務効率と離職率改善の両立が可能になります。負担が減ることでマネージャー自身のモチベーションも維持され、現場全体の健全化にもつながります。

誰にどのような対応をすればいいのかが明確になるのは有難いですね。
まとめ:若手の退職ショックを防ぎ、組織を強くするために
若手社員の退職は、単なる人員不足ではなく、企業の成長力やブランド価値にも大きな影響を与えます。特に以下のようななど、若手ならではの離職要因を放置すると、企業の将来にも悪影響が及びます。
- テキスト入社後のリアリティショック
- 成長実感の欠如
- 人間関係の問題
ですが、以下のようなフォローを行えば、こうした離職リスクは大きく減少させることができます。
- 日々の1on1面談
- パルスサーベイ
- キャリア支援を通じた定期フォロー
「みんなのマネージャ」を活用すれば、現場の負担を増やすことなく、従業員の本音を早期にキャッチし、心理的安全性の高い職場を実現できます。
若手の離職を防ぎ、定着率を高めることは、組織全体の安定と成長の鍵です。今こそ、離職防止の仕組みを整え、強い組織作りを目指しましょう。

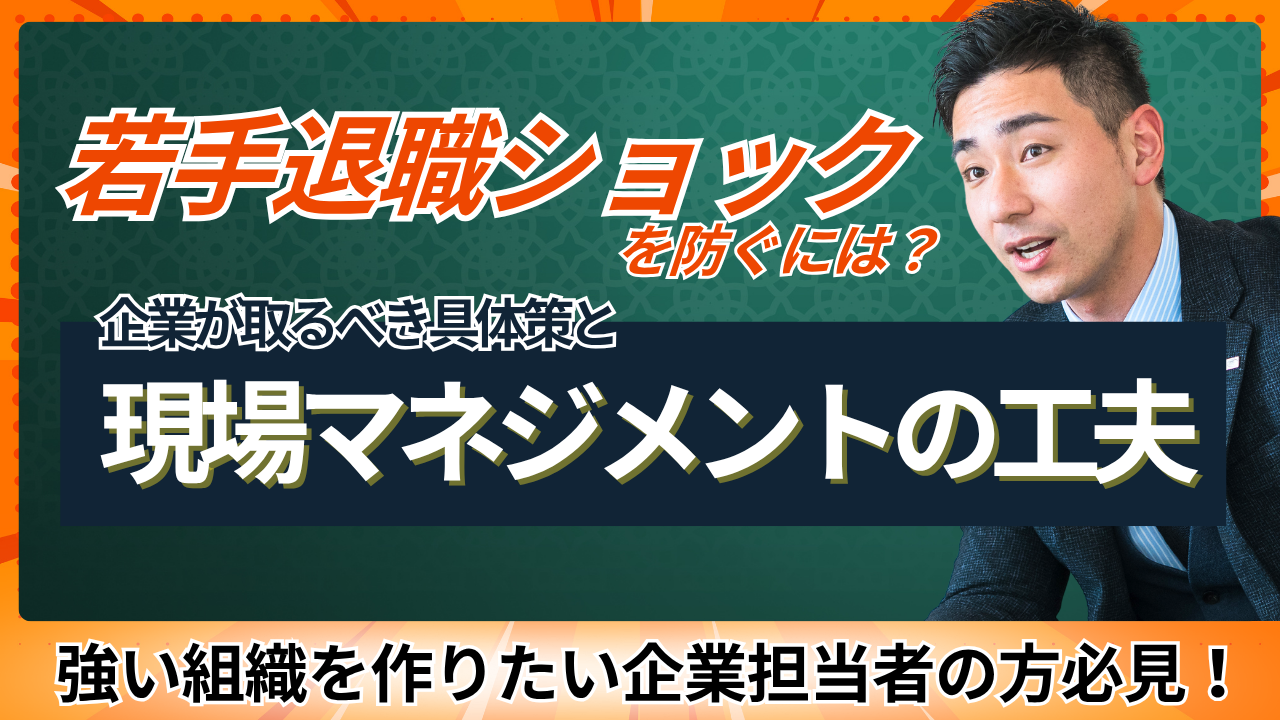
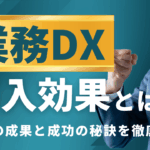

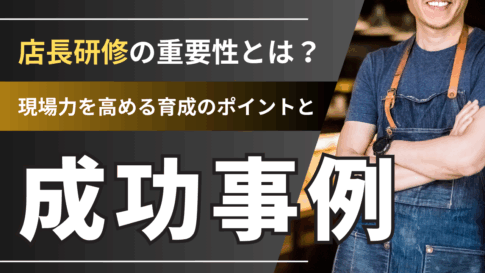


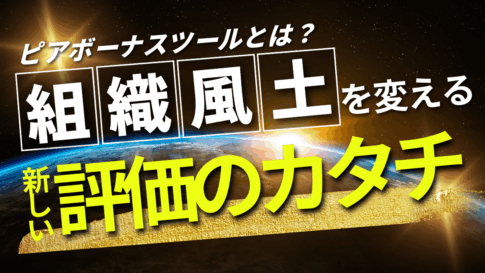
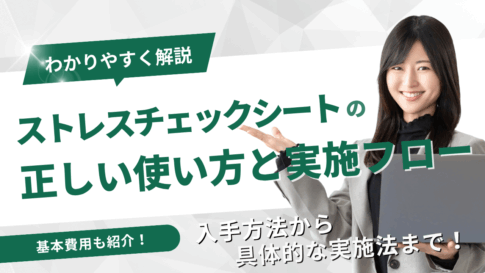
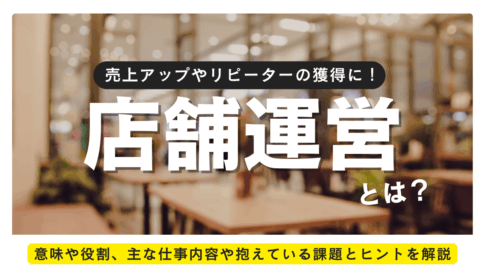
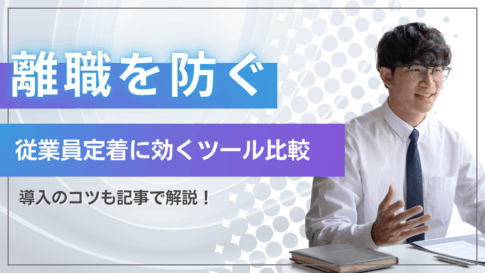
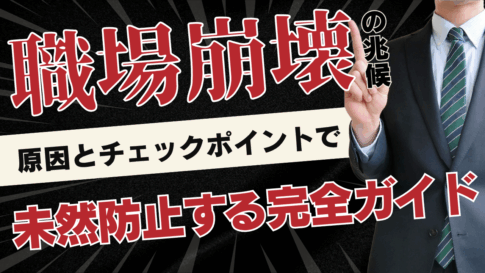



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。