
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
人事評価のタイミングになると、社員のモチベーションが下がる——
そんな声を聞いたことはありませんか?
本来、評価制度は社員の努力を認め、成長を後押しする仕組みであるべきです。
しかし、運用次第では逆にやる気を奪ってしまうこともあります。
本記事では、人事評価でやる気をなくす原因を明らかにし、企業やマネージャーが今すぐ取り組める5つの対策をご紹介します。あわせて、信頼・納得・成長を支えるツール「みんなのマネージャ」の活用方法も解説します。
評価制度を見直し、社員のパフォーマンスとエンゲージメントを高めるヒントをつかみましょう。
- 人事評価が社員のやる気をなくす理由
- 社員のやる気を高めるための5つの実践的対策
- 離職率改善に効果的なツールの活用法
人事評価でやる気をなくすのはなぜか?
人事評価は本来、社員の成長を支える制度です。しかし、運用を誤ると、逆に社員がやる気をなくす要因となり、場合によっては離職の引き金になることもあります。
この章では、人事評価で社員がやる気をなくす5つの要因を見ていきましょう。
評価基準が不透明・不公平だと感じる
評価制度に関する不信感は、往々にして評価基準の不透明さに起因します。
以下のようなケースと対策を見直すことで、納得感を高める第一歩となります。
| よくある問題 | 具体例 | 対策のポイント |
|---|---|---|
| 評価基準が共有されていない | 「何を評価されているのかわからない」 | 評価シートを事前配布し、目標設定と連動させる |
| 評価者によって判断がぶれる | 「同じ行動でも上司によって評価が違う」 | 評価項目の統一+評価者研修の実施 |
| 成果しか見られていない | 「努力しても評価に反映されない」 | プロセスや行動指標も評価に含める |
これらは、一言でいえば評価の基準が社員にとって納得できるものでないということです。

評価や基準の明確化は、社員の信頼を築く第一歩です。

自分が何を評価されるのかが分かれば、もっと頑張ろうと思えますよね。
明確で一貫性のある評価制度を構築しましょう。
成果ばかりが重視され、努力が無視される
営業の売上金額に代表されるような目に見える成果だけが評価対象になると、努力や過程が評価されないという不満が生まれます。
特にチームでの支援や、地道な準備、改善提案などは数値化が難しく、見落とされがちです。
努力しても認められないという体験は、「どうせ頑張っても意味がない」という無力感につながります。
その結果、社員は挑戦や工夫を避けるようになり、組織の活力も低下してしまいます。
評価には、プロセスや取り組み姿勢を含める視点が不可欠です。

プロセスの評価も重要で、成長を感じるための基盤です。
フィードバックがない、もしくは的外れ
人事評価の場で、具体的なフィードバックがなければ、社員は「何が良かったのか」「どこを改善すべきか」が分かりません。
また、フィードバックの内容ややり方にも注意する必要があります。
否定的なフィードバックばかりの場合は社員のモチベーションを著しく損なうケースがありますし、面接辞退が形式的になってしまうと真剣に受け止められなくなることがあります。

具体的なフィードバックは成長のカギ。面談の質を上げることが重要です。
フィードバックを意義のあるものにするためには、建設的かつ社員にとって納得感のある内容であることが重要です。

自分が何を評価されるのかが分かれば、もっと頑張ろうと思えますよね。
評価者への信頼が持てない
評価制度が適切に整備されていても、それを運用する「評価者」が信頼されていなければ、社員は評価結果に納得できません。
例えば、社員が上司との関係性を希薄だと感じている場合や、上司が感情や好みによって評価していると感じたりしている場合などです。

信頼関係がないと、制度自体が機能しません。
そして、社員が評価者を信頼できない場合、人事制度全体の信用にも直結します。
両者間で信頼関係を構築するためには、上司が日常的にコミュニケーションを取り、部下の業務や課題を正しく把握する必要があります
評価と処遇が結びついていない
社員がやる気をもって働くには、評価と処遇が一致している必要があります。
評価がどれだけ高くても、昇給や昇進などの処遇に反映されない場合、社員は「評価されても意味がない」と感じるものです。
また、処遇との関係については説明が必要です。説明なく処遇が決まっているように見える場合、社員が不公平感を抱くリスクが高まります。
評価と処遇(報酬)の連動性が見えることで、社員の納得感ややる気維持につながるのです。
人事評価でやる気をなくさないための5つの対策
離職率改善の取り組みを行うために活用したい情報や対策を、実際の事例をもとに当記事では3つご紹介します。
要となるのは、社員や従業員の離職理由を正確に把握し、課題に対して適切な対策を講じることです。
| やる気を失う原因 | 主な課題 | 有効な対策 |
|---|---|---|
| 評価基準が不透明 | 納得感が得られず、不満が溜まる | 基準の明文化と事前共有 |
| 努力・過程が評価されない | 数値偏重で無力感が生まれる | プロセス評価の導入 |
| 的外れなフィードバック | 成長の指針を見失い、改善意欲が低下 | 前向きで具体的なフィードバックの実施 |
| 評価者が信頼されていない | 評価の信用が失われる | 評価者の教育+360度評価の活用 |
| 評価と処遇が連動していない | モチベーションの維持が困難になる | 処遇との連動設計と説明責任の徹底 |
評価基準を明確にし、事前に共有する
評価制度の納得感を高めるには、基準の明文化とその事前共有が重要です。「何を期待され、どう行動すれば評価されるのか」が明確であれば、社員は目標をもって行動できます。

共通認識ができると、目標に向かって進みやすくなります。

基準の明文化は、納得感を生むための基本です。
評価基準を決定する際、上司だけでなく社員ともすり合わせを行い、共通認識にしておくことが理想的です。
OKRやMBOなど、数値以外の目標も含めた設定を行うと、成果だけに偏らない多面的な評価が実現できます。
努力やプロセスも評価対象に含める
目に見える成果以外にも、過程や姿勢を評価することは社員のモチベーション維持に効果的です。
例えば、日々の改善提案、後輩育成への貢献、業務改善の試行錯誤などが数字に表れにくい項目です。
すぐに効果が目に見える訳ではないかもしれませんが、中長期的には大きく会社の業績に貢献しうる可能性があります。
数字に表れにくい点を評価に組み込むことで、社員の行動に前向きな意味を持たせ、挑戦を後押しする組織文化を育むことができます。

過程評価することで、社員の成長を促進します。
具体的で前向きなフィードバックを行う
フィードバックは評価の結果通知ではなく、次の成長の起点であるべきです。具体的で前向きなフィードバックは、社員に自己成長の方向性を示し、行動変容を促すきっかけになりやすいです。

面談での前向きな言葉が次の挑戦につながります。
例えば改善点を伝える際に、強みも一緒に伝えると、強みを伸ばしながら弱点を克服できる可能性を高められます。
定期的な1on1の場を活用することで、フィードバックの質と量の両面を高めることができます。
- 「このやり方はとてもよかった。さらにこうすると、もっとよくなる」
- 「この部分の工夫に気づけたのは成長の証拠です」
- 「改善点もありますが、前回より大きく前進しています」
評価者の教育と360度評価の導入
評価者が公正で信頼できる存在であるためには、評価者の教育や仕組み作りが重要です。
評価者の教育制度・仕組み作りの例としては、評価者向け研修やマネジメント支援などがあります。さらに評価の透明性を高めるための効果的な手法の一つが、360度評価の導入です。
360度評価とは、役職やチームの垣根を取り払い、社員と上司や同僚同士が相互に評価する制度のことです。360度評価の導入により、同僚や部下からの視点による評価が加わるため、評価の公平性や客観性が高まります。
結果として、評価の属人化が防止され、社員一人ひとりの評価に対する納得感が高まります。

360度評価は多様な視点を取り入れることで、評価のバイアスや属人化を防止します。
評価と処遇を連動させ、納得感を高める
高評価を受けても報酬の不一致により社員がやる気をなくしている場合は、処遇を連動させることにより納得感を高められます。
評価による昇給、昇進、インセンティブが明確に設定されていることで、社員は「頑張った結果が報われる」と実感できるでしょう。
ただし、評価と処遇の連動には透明性が必要です。なぜ、その処遇になったのかを説明できるようにしておきましょう。
みんなのマネージャで実現するやる気をなくさない評価
人事評価の課題を改善するうえで、ツールの力を活用することも有効な選択肢です。
そこで注目されているのが従業員のモチベーションやエンゲージメントをリアルタイムで可視化できる「みんなのマネージャ」です。
この章では、「みんなのマネージャ」について詳しく解説します。
心理的安全性を高める実名・透明アンケート
「みんなのマネージャ」では、実名での週次アンケートにより、従業員が率直な気持ちを伝えられる仕組みを採用しています。
定期的な回答で小さな変化や兆候を捉え、早期にフォローが可能です。1人1アカウント制なので、匿名性よりも信頼関係を前提とした心理的安全性の高いコミュニケーションが実現できます。

アンケート調査を始めてから、社内のコミュニケーションがスムーズになった気がします。ちょっとした変化も拾ってもらえるようになり、安心感があります。
AIと専門家によるパーソナライズされたフィードバック支援
「みんなのマネージャ」は、AIによるフィードバック支援機能を搭載しています。
フィードバック支援機能により、従業員ごとの状態に応じて、適切なフィードバックの内容や伝え方が提示されます。
フィードバック支援は、メンタルヘルスやコーチングの専門家が監修しているため、評価者のスキルや経験に頼らず、質の高いフィードバックが可能になります。
フィードバック支援機能を上手く活用することで、評価の属人化を防ぎつつ、社員一人ひとりに適した支援を届けられるということです。

的確なフィードバックを受けられたら、より前向きに業務に取り組めますね。
スキル評価+ご褒美設計でモチベーションを維持
「みんなのマネージャ」のオプション機能として、スキル評価機能が提供されています。
スキル評価機能とは、業務ごとの習熟度を可視化し、一定基準を満たした際に時給アップや表彰などのご褒美を連動させられる機能のことです。
あらかじめスキル評価として基準を明文化することで、社員は「頑張りが評価・処遇につながる」ということを実感でき、モチベーションの維持・向上につながります。スキル評価機能においては、自己評価と他者評価を平均化できることも、評価の客観性の観点において重要です。
| スキル評価項目 | 評価基準の例 | 処遇・ご褒美の設計例 |
| 社内ツールの活用能力 | 業務フローを見ながらミスなく操作できる | 時給+50円、バッジ付与 |
| チーム貢献・後輩指導 | 月1回以上のOJT実施とレポート提出 | Slackで称賛+社内ポイント進呈 |
| 改善提案の質と採用率 | 月1件以上が社内に実装される | 表彰+報奨金の支給(1提案500円など) |
1on1支援やタイムライン機能で信頼あるマネジメントを実現
「みんなのマネージャ」は、1on1の質を高めるサポートや、タイムラインでの状態変化の見える化など、日常的なマネジメントを支える機能も充実しています。
評価結果だけでなく、その背景やプロセスを可視化しながら、上司と部下が信頼関係を築けるような環境を提供しています。
- 評価基準の見直し
- プロセス評価を含めた制度設計
- フィードバックの質を上げる
- 評価教育+360度評価の導入
- 処遇と連動したインセンティブの仕組みづくり
まとめ
人事評価は、本来なら社員のモチベーションを高め、成長を後押しする強力な手段です。しかし運用を誤ると、かえってやる気を損ない、離職の原因にもなりかねません。

評価制度の見直しは、単なる制度改革ではなく、“組織文化のアップデート”です。小さな一歩からはじめましょう。
この記事では、「なぜ人事評価でやる気をなくすのか」という5つの原因と、それを防ぐための5つの対策を解説しました。
信頼・納得・成長を支える評価制度を実現するツールとして「みんなのマネージャ」のようなツールを活用することも効果的です。
人事評価に課題を感じている方は、まずは評価の透明性と信頼性の確保から始めてみてはいかがでしょうか。

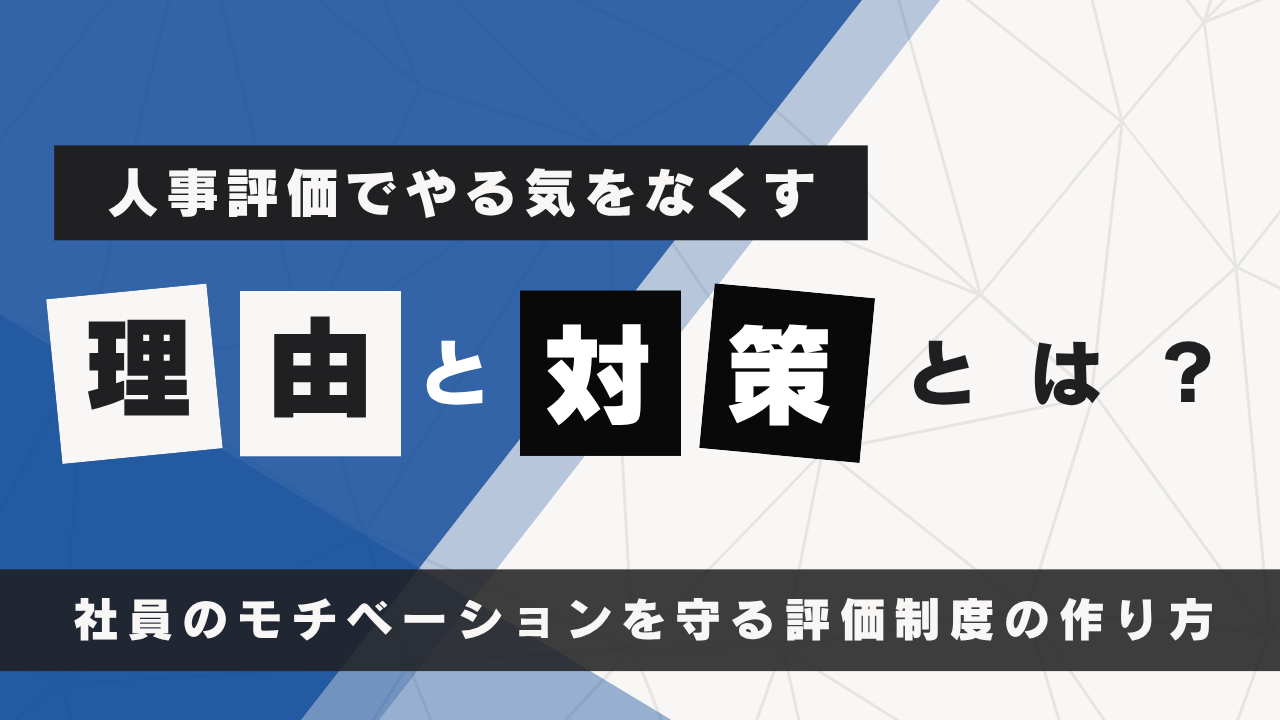

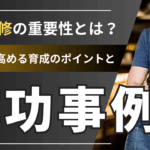

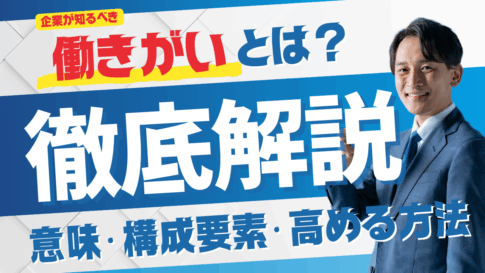
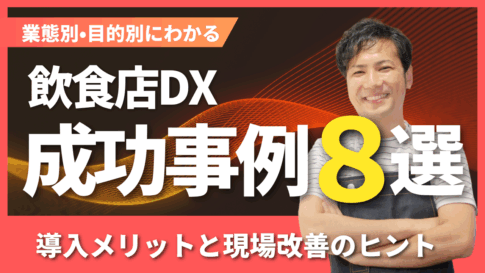
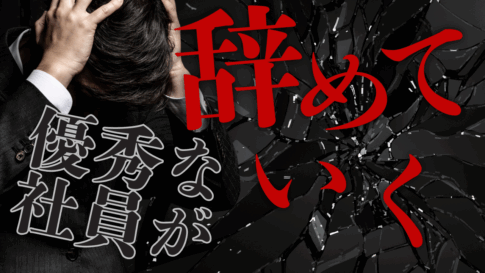

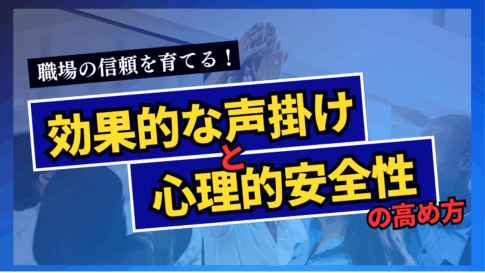
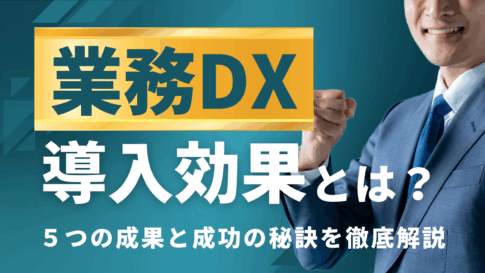




組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。