
組織人事コンサルタント(ジュニアアソシエイト)
上智大学 総合人間科学部卒
IT系広告代理店での営業経験を経て、現在は人事領域の実務を現場で学びながら、キャリアコンサルタント資格の取得を目指している。
ヒアリング力と素直な吸収力に定評があり、1on1設計やフィードバック支援などに携わるほか、離職防止ツールの導入プロジェクトでも活躍中。丁寧な対話と観察力を強みに、実務を通じて成長を重ねている若手コンサルタント。
趣味は朝活と読書。日々の気づきを記録する習慣を大切にしながら、仕事と生活のバランスを大事にしている。
「最近、職場の雰囲気が重たい」「メンバーが本音を言わなくなった」――そんな変化を感じていませんか?それはもしかすると、「心理的安全性」が低下しているサインかもしれません。
心理的安全性とは、職場で自分の考えや気持ちを安心して表現できる状態を指し、チームのパフォーマンスや離職率にも大きな影響を与えます。
本記事では、心理的安全性が低い職場に共通する特徴とその原因を明らかにしながら、今日からできる改善策を具体的にご紹介します。安心して働ける職場をつくるヒントを、ぜひ見つけてください。

社長
心理的安全性は、Googleの研究でも高業績チームの共通項として注目されている概念です。
- 心理性安全性が低い職場に見られる典型的な特徴とその背景
- 心理的安全性の低下がもたらす組織全体への悪影響
- 職場の心理的安全性を高めるためにとるべき具体的なアプローチ
- 心理的安全性を仕組みとして根付かせる方法とツールの活用法
心理的安全性が低い職場の特徴
心理的安全性が低い職場には、いくつか共通する特徴があります。
こうした職場では、従業員が自分の意見を自由に言えず、上司や同僚との関係にも緊張感があり、失敗や課題を正直に伝えることが難しくなります。
結果としてチーム全体のパフォーマンスが低下し、職場の雰囲気が悪化していくという悪循環が生まれます。

あー、何か言ったら変な空気になりそう…って思っちゃう職場、わかります。

それは心理的安全性の典型的なサインですね。
発言の萎縮は、イノベーションの芽を摘むことにもつながります。
本章では、実際に心理的安全性が損なわれている職場でよく見られる具体的な特徴を、5つの観点から整理して紹介します。
発言・相談しづらい雰囲気
心理的安全性が低い職場では、従業員が自分の意見や疑問を口にすることに不安を感じます。「こんなことを言ったら評価が下がるのでは」「周りに迷惑をかけるのでは」といった心理的ブレーキがかかり、発言そのものを控えるようになるのです。
- 評価への悪影響への不安
- 周囲への迷惑をかける恐れ
- 批判や否定されることへの恐怖
- 自分の意見に自信が持てない状況
特に会議の場では、上司や一部の声の大きい社員だけが話し、他のメンバーは沈黙することが日常化している場合があります。
このような空気が続くと、現場の課題やアイデアが表に出ず、組織の成長機会を失うことにつながります。

発言の萎縮は創造性の損失と直結します。
心理的安全性は組織の成長エンジンとも言えますね。
ミスを報告しづらい・責任追及型の文化
心理的安全性が低い職場では、失敗をしたときに「怒られる」「責められる」といった恐怖感が先立ち、ミスの報告が遅れる、あるいは隠蔽されることさえあります。
この背景には、ミスを個人の責任として厳しく追及する文化や、謝罪ばかりを求めるコミュニケーションがあります。

ミスを伝えるだけでビクビクするのって、本当に疲れるんですよね…
本来、ミスは早期に共有されることで再発防止や改善に繋がるものです。
しかし、報告しづらい環境では、同じミスが繰り返されやすく、組織としての学習機会が失われます。
結果として現場の信頼関係も損なわれ、萎縮した職場風土が定着してしまいます。
上司や同僚に対する不信感・無関心
心理的安全性が低い職場では、上司や同僚との人間関係に信頼や安心感がありません。
上司が部下の意見を聞かず一方的に指示を出す、同僚同士が協力し合わず成果の奪い合いになるといった状況が続くと、社員は「この人たちと一緒に働いても守られない」と感じるようになります。
| 信頼関係の欠如を示す行動 | 具体例 |
| 上司の一方的な指示 | 部下の意見を聞かずに決定を下す |
| 成果の奪い合い | 同僚の功績を横取りする |
| 無関心な態度 | 困っている人に声をかけない |
| 見て見ぬふり | 落ち込んでいる同僚を放置する |

成果を横取りするような行為は、チームの信頼残高を著しく損ねます。評価制度にも関係します。
また、困っている人に声をかけない、誰かが落ち込んでいても見て見ぬふりをするなど、チーム内に無関心な空気が広がります。
このような関係性では安心して働くことができず、コミュニケーションの断絶や孤立感の増加にもつながります。
評価やフィードバックが一方的である
評価制度やフィードバックの運用が一方的な職場では、従業員は自身の行動や成果について納得感を持ちづらくなります。
たとえば、上司の主観や好みによって評価が決まったり、改善点ばかりを指摘されるようなフィードバックが繰り返されたりすると、従業員は「どう努力しても報われない」と感じ、モチベーションが下がります。
また、双方向の対話がなく、相談や自己表現の機会もないと、組織への信頼や貢献意欲が低下します。公正で納得感のある評価と、相互理解を前提としたフィードバックが欠かせません。

がんばっても意味ないかも…って気持ち、静かにやる気を削がれますよね。
コミュニケーションが希薄・雑談がない
心理的安全性が低い職場では、業務連絡以外のコミュニケーションが極端に少なくなりがちです。雑談やちょっとした声かけがなくなると、職場全体がギスギスした雰囲気になり、人間関係が表面的になっていきます。
- 雑談や何気ない会話の減少
- 互いの理解不足の増加
- 誤解やトラブルの発生
- 職場への信頼感のさらなる低下
また、互いの状況や気持ちを理解し合う機会が減ることで、誤解やトラブルが起こりやすくなり、職場への信頼感がさらに低下します。
心理的な安全を確保するためには、あえて雑談の時間やリラックスできる場づくりを意識的に行うことが必要です。
信頼は日々の何気ない会話から育まれるのです。
心理的安全性が低くなる原因とは?
心理的安全性が損なわれてしまう職場には、単なる「雰囲気の悪さ」だけではなく、構造的・文化的な原因が存在しています。
多くの場合、それは長年の慣習や管理職のマネジメント手法、制度設計の欠陥から発生しており、個人の努力だけでは改善が難しいケースも少なくありません。
この章では、心理的安全性がなぜ低下するのか、その背景にある典型的な原因を4つの視点から分析していきます。
年功序列・上下関係が強い文化
組織内に年功序列や強い上下関係の文化が根付いていると、若手社員や部下は「立場上、意見を言ってはいけない」と感じやすくなります。
特に、日本企業に多く見られるような「上司の指示は絶対」「忖度が求められる」風土では、反論や提案がしづらくなり、会議や日常の業務でも沈黙が常態化します。
- 若手社員の意見表明の萎縮
- 反論や提案の機会の減少
- 会議での沈黙の常態化
- 新しい視点やアイデアの排除
このような文化は、新しい視点や柔軟なアイデアの排除につながり、組織の創造性や適応力を大きく損ねることになります。
職位に関係なく、率直な意見交換ができる風通しの良い環境が必要です。
評価制度が不透明
心理的安全性が低下する大きな要因の一つに、評価制度の不透明さがあります。
従業員が「何を評価されているのか分からない」「評価が偏っている」と感じると、不安や不信感が募り、仕事に対する積極性が失われます。
また、評価基準が曖昧なまま運用されていると、上司の主観に依存した判断が横行しやすくなり、公平性が損なわれます。
こうした状況では、挑戦や改善提案を避けるようになり、組織としての学習や成長が止まってしまいます。評価制度の見直しと、フィードバックの透明化が求められます。
マネジメントスキルのばらつき
組織内のマネージャーごとにマネジメントのスキルや姿勢に大きな差があると、部下の心理的安全性に直接的な影響が生じます。
あるチームでは意見が言いやすく、別のチームでは発言がタブーというような状態があると、組織全体の文化が統一されず、混乱や不平等感が生まれます。
| マネジメントスキルの差 | 影響 |
| チーム間での対応の違い | 組織文化の不統一 |
| 属人的なマネジメント | 特定社員への過度な負担 |
| 経験と勘に頼った指導 | 不公平な状況の発生 |
また、経験や勘に頼った属人的なマネジメントが続くと、特定の社員にだけ過度な負担がかかるなどの不公平な状況が発生しやすくなります。
組織として一貫したマネジメントレベルを保つためには、指導者に対する教育や仕組みの導入が欠かせません。
忙しすぎてケアできない現場
慢性的な人手不足や業務量の過多により、現場の管理職やメンバー同士が互いを気遣う余裕を失っているケースも、心理的安全性の低下につながります。「
忙しいから」「今はそれどころではない」という状態が続くと、声をかける、話を聞くといった基本的なコミュニケーションが後回しになり、個々が孤立しやすくなります。
また、ケアが不足することで小さな不安や不満が蓄積し、やがて離職やメンタル不調といった深刻な問題に発展する可能性もあります。まずは現場の負担を可視化し、対話の時間を意識的に確保することが重要です。
心理的安全性が低い職場で起きる悪影響
心理的安全性が低い職場環境は、単なる「居心地の悪さ」だけで済まされません。
その影響は、従業員の心身の健康、チームの生産性、さらには企業全体の業績や社会的信用にも及びます。職場の空気や人間関係が良くないと感じているとき、それが放置されればどのようなリスクに発展するのか。
この章では、心理的安全性の欠如が引き起こす代表的な3つの悪影響を整理して解説します。
離職率の増加・採用コストの悪化
心理的安全性の低い職場では、「もうここでは頑張れない」と感じた従業員が離職を選びやすくなります。表面的には大きなトラブルがなくても、日々の小さなストレスや孤立感が積み重なった結果、退職という形で表出するのです。
- 若手・中堅層の早期離職による人材損失
- 再採用・教育にかかるコスト増加
- 定着率の低さによる採用活動の困難化
- 優秀な人材確保の難航
特に若手社員や中堅層の早期離職は企業にとって大きな損失であり、再採用や教育にかかるコストも無視できません。
さらに、定着率の低さが社外にも伝われば、採用活動自体が難航し、優秀な人材の確保が困難になります。安全性の高い職場づくりは、長期的な人材戦略の要でもあります。
業務効率の低下とチーム力の喪失
心理的安全性が低いと、従業員は「余計なことは言わない方がいい」と思い込み、提案や改善意見を出さなくなります。
その結果、非効率な業務プロセスが放置されたり、問題が表面化するのが遅れたりして、全体の生産性が低下します。
また、助け合いの風土が育たず、チームワークも弱体化します。
例えば、困っている同僚に手を差し伸べることが「余計なお世話」と見なされるような環境では、互いをサポートする姿勢が失われ、チームとしての一体感が失われていきます。
これは組織全体の成果にも直結する深刻な課題です。
メンタル不調者の増加・隠蔽リスク
心理的に安全でない職場では、従業員がストレスを感じていても相談できず、心の不調を抱えたまま働き続けるケースが増加します。
無理をして業務を続けるうちに、うつ病やバーンアウトといった深刻なメンタル不調につながることも少なくありません。
| メンタル不調の隠蔽リスク | 問題の詳細 |
| 相談できない環境 | ストレスを抱えたまま業務継続 |
| 周囲の気づき不足 | 管理職・同僚の対応遅れ |
| 自己責任の風土 | 問題の隠蔽傾向 |
| リスクマネジメント不全 | 企業全体への影響拡大 |
また、そうした状態が表に出にくい環境では、管理職や同僚も気づかず、対応が遅れてしまいます。さらに問題なのは、メンタル不調や業務ミスが「自己責任」とされる風土です。
このような職場では、問題が隠蔽されやすく、企業としてのリスクマネジメントにも大きな影響を及ぼします。

「誰にも言えない」って思ったときが、いちばん危ないんですよね…。
心理的安全性を高めるためにできること
心理的安全性が低い職場を改善するには、「空気を変える」だけでなく、具体的な行動や仕組みを通じて、安心して働ける環境をつくることが求められます。そのためには、組織としてのルールや運用の見直しだけでなく、現場のマネージャーやメンバーそれぞれが意識を変え、実践を積み重ねる必要があります。
この章では、実際に職場の心理的安全性を高めるために効果的とされる施策を5つ紹介し、どのように現場に落とし込めばよいのかを考察します。
小さな声を拾う1on1の定期化
1on1ミーティングは、心理的安全性を高めるための強力なツールです。
特に定期的かつ継続的に行うことで、メンバーは「安心して話せる場所がある」と感じやすくなります。
業務の進捗確認だけでなく、悩みや気になること、今後のキャリアなど、本人が自然に話したくなるテーマを引き出すような対話が重要です。
- 定期的・継続的な実施
- 業務以外の話題も含める対話
- マネージャーの聞き手としての姿勢
- アドバイスより共感・承認を重視

1on1は、指導の場ではなく安心して話せる場として設計することが重要です

確かにちゃんと聞いてくれるってだけで、心がふっと軽くなるんですよね。
マネージャーは聞き手に徹し、アドバイスよりも共感や承認を意識した関わり方を心がけることで、信頼関係が深まります。
1on1は、気づきや課題の早期発見にもつながる貴重な機会となります。
フィードバック文化を見直す
心理的安全性を高めるには、フィードバックの方法や伝え方を見直すことが欠かせません。
否定的な表現や曖昧な指摘ばかりのフィードバックは、受け手にとってストレスとなり、安心して働くことができなくなります。
効果的なフィードバックは、「行動」に焦点を当て、具体的かつ肯定的な内容を含むことがポイントです。
また、フィードバックは一方通行ではなく、相手の話を聞き、対話を通じてすり合わせるプロセスが重要です。
このような文化が根付くことで、従業員同士が互いに学び合い、成長を後押しする関係性が構築されていきます。
感謝と承認の習慣化
心理的安全性が高い職場では、日常的に「ありがとう」や「助かったよ」といった感謝や承認の言葉が交わされています。
こうしたポジティブなコミュニケーションは、信頼関係を深め、従業員の自信ややる気を育む重要な要素です。
| 感謝と承認の実践方法 | 具体例 |
| 朝礼での共有 | ありがとうメッセージの発表 |
| チャットツール活用 | 感謝の気持ちの投稿 |
| 日常の声かけ | 「助かったよ」の一言 |
| 成果の承認 | 具体的な行動への評価 |
一方で、忙しい現場では感謝の気持ちが後回しになりがちで、「できて当たり前」と見なされることも少なくありません。だからこそ、意識的に感謝や労いの言葉を伝える文化をつくることが大切です。
たとえば、朝礼やチャットツールを活用して「ありがとうメッセージ」を共有するなど、簡単な工夫から始められます。
安全な発言機会の創出(仕組みで作る)
心理的安全性を高めるには、「誰もが安心して話せる場」を制度として設けることが有効です。例えば、アイデア出しの会議で「否定禁止ルール」を設ける、質問や意見を匿名で投稿できるツールを活用する、ミスをシェアする場をつくるなど、意見を引き出すための仕掛けを組織として整備することが重要です。
こうした仕組みがあることで、「発言しても大丈夫」という共通認識が広がり、沈黙が常態化していた職場にも少しずつ変化が生まれます。継続的に実践することで、現場の雰囲気も自然と柔らかくなっていきます。

ちゃんと仕組みにしてくれると、気分次第で変わるっていう不安がなくて安心できますよね。
「みんなのマネージャ」で仕組み化する方法
心理的安全性を高める取り組みを現場に根付かせるには、属人的な努力に頼るのではなく、システムとして定着させることがカギです。そこで注目されているのが、エンゲージメントサーベイツール「みんなのマネージャ」です。
- 週次パルスサーベイによる従業員状態の可視化
- ミス・不満の早期発見システム
- AIによる自動フィードバック提案
- 行動を促すアクションリスト機能
本ツールでは、従業員の状態を週次で可視化できるパルスサーベイ機能により、ミスや不満が表面化する前に早期発見が可能です。
また、AIによる自動フィードバック提案や、行動を促すアクションリスト機能により、マネージャーの対応が属人化せず、質が標準化されます。
安心して本音を伝えられる環境を、テクノロジーの力で日常に組み込めるのが「みんなのマネージャ」の大きな強みです。
まとめ
心理的安全性が低い職場では、発言しづらい雰囲気や評価の不透明さ、信頼関係の欠如といった問題が積み重なり、結果として離職や業績低下といった重大なリスクにつながります。
一方で、こうした環境は個人の努力だけで変えることは難しく、組織全体としての意識改革と仕組みづくりが必要です。
今回ご紹介したように、1on1やフィードバックの改善、感謝の習慣化など、小さな取り組みを積み重ねることで、心理的安全性を着実に高めることができます。
そして、それを継続的に支える仕組みとして「みんなのマネージャ」の導入は非常に効果的です。
従業員の声に耳を傾け、安心して働ける職場を実現することが、組織の持続的な成長にも直結していきます。

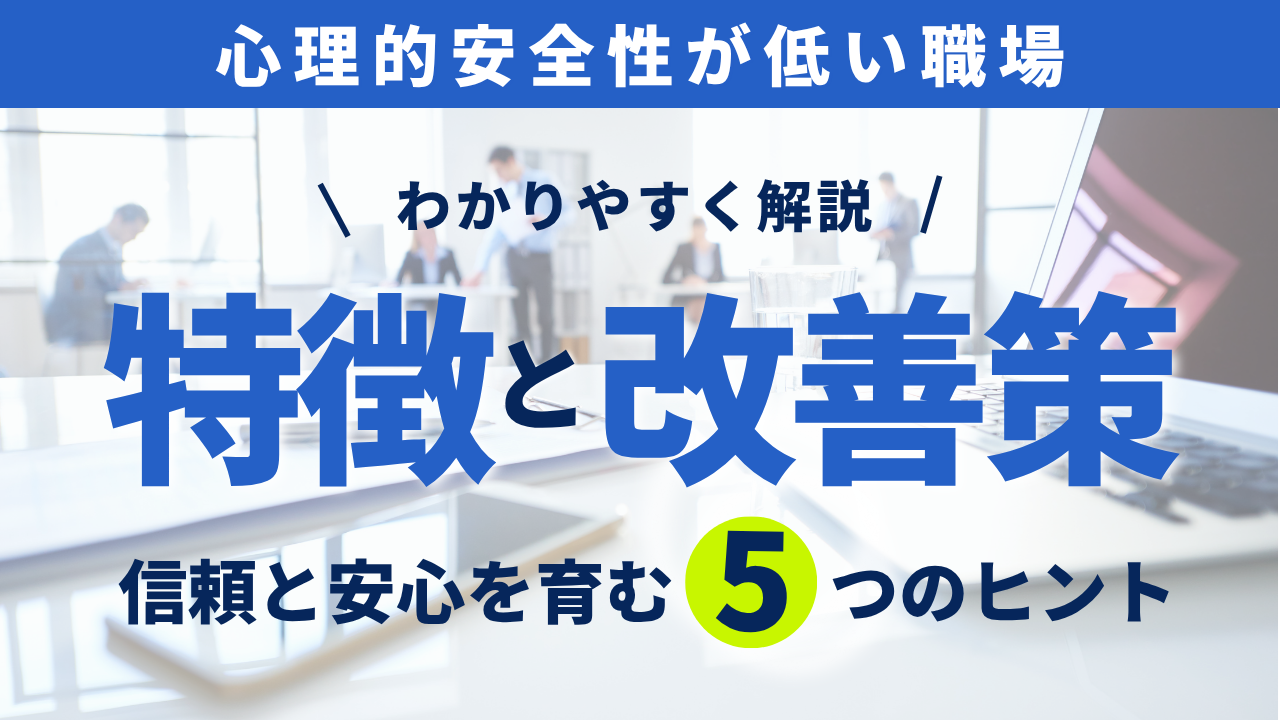
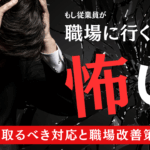
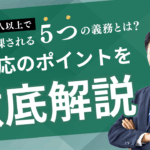
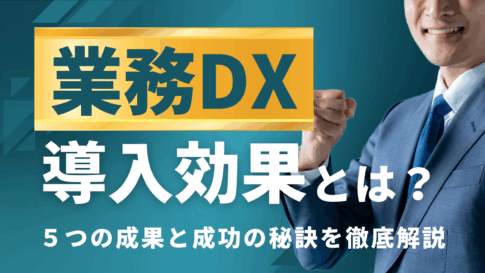

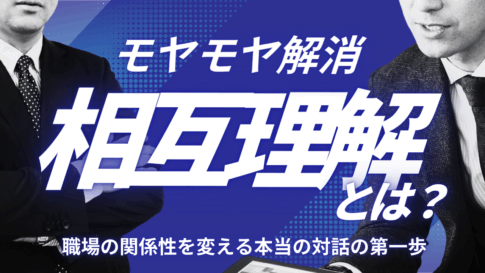
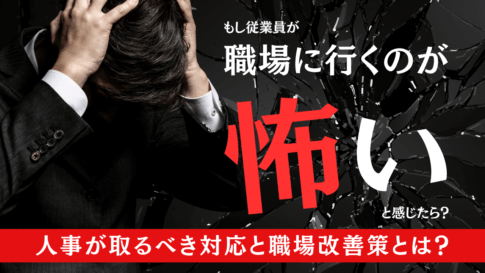
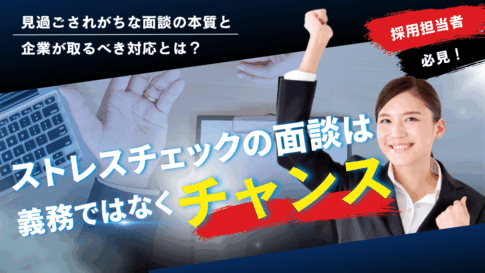
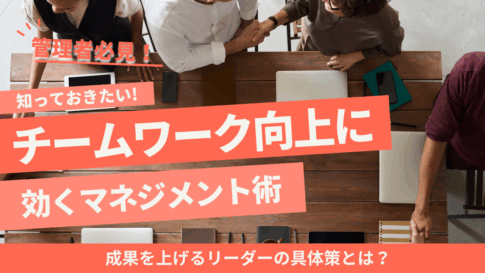
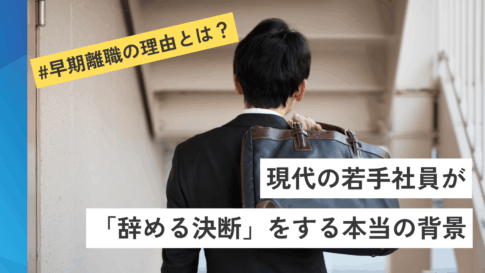
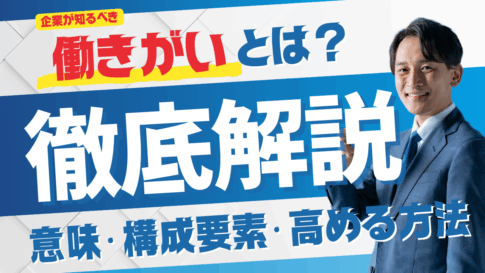



組織人事コンサルタント
早稲田大学政治経済学部卒
国家資格キャリアコンサルタント・産業カウンセラー
企業の離職防止や定着率改善を専門とし、制度設計にとどまらず、社員一人ひとりの「内発的動機づけ」に着目した支援を信条とする。
データ分析と現場ヒアリングを軸に、経営層・マネージャー双方への支援を提供。現場感と理論を兼ね備えた落ち着きある語り口と、信頼感ある立ち振る舞いが特徴。
私生活では筋トレや読書を通じて自己研鑽を重ねる一方、家族との時間も大切にしている。